特集
懐かしのテープやフロッピー、CD/DVD、そしてUSBメモリに至るまで。外部記録メディアの変遷
2025年2月14日 06:14
ここでは本編の番外編として、メインストリームになり損ねてしまった外部記録メディアについて紹介しています。
デジタルカセット
AKIBA PC Hotline!より引用
カセットテープのところで書いたように、基本カセットテープI/F(インターフェイス)は極めてアナログ的に利用された。MZ-80シリーズにもいくつかあるが、たとえば1981年4月に発売されたMZ-80Bのケースで言えば、記録速度は2,000bpsと結構高速であった。
さらに、再生/録音/停止/巻き戻しに加え、頭出しまでプログラム側から管理可能だったので、カセットを入れさえすれば後は人間が直接操作しなくても(=再生ボタンを押したり停止ボタンを押したりしなくても)操作できたが、ほとんどのケースは外に接続したカセットデッキを人間が操作する必要があった。
そうしたケースがほとんどの中でティアック(TEAC)が発売したデジタルカセットは、形状こそカセットテープなものの、テープ自体はティアックが提供する独自の物が必要で、記録密度は1,600bpi、記録速度は15ips、転送速度は24,000bpsとかなり高速であった。
【お詫びと訂正】初出時に転送速度を間違って掲載しておりました。お詫びして訂正させていただきます。
このMT-2はNECのCompo BS/80にオプションとして内蔵できたほか、外付けで接続も可能(こちらはPROLINE-100という名称)だった。テープ1本あたりの最大容量は760KBとFD(Floppy Disk)に匹敵するものだった。ちなみに筆者も稼働する実物にお目にかかったことがある。
……と書いたら読者より「Compo BS/80の内蔵ドライブはMT-2ではなく1,200bpsのカセットドライブで、差額は4万円だ」というご指摘をいただいた。どうも記憶違いをしていたらしい。お詫びして訂正したい。
ちなみに筆者が見た稼働する実物は、COMPO 80/BSに外付けで動作しているMT-2ドライブであった。
そんなMT-2やPROLINE-100だが、普及したとは言い難かった。なにせPROLINE-100の価格は9万5,000円(発売当時)。当初こそFDDよりも安価だったが、すぐにFDDのほうが安価になった。
あとMT-2/PROLINE-100は標準I/Fがなく、CPUバスに直結するという乱暴な構成なので、接続できる機種が限られた。
ちなみにPROLINE-100は6502/6800向けの構成だったので、8080向けとしてPROLINE-200という機種があったという情報もあるのだが、筆者は確認できていない。
MT-2はティアックの情報によれば2018年4月に完売したそうだが、マーケットとしては大きなシェアを取ることは一度もないままだったと記憶している。
FDに負けたさまざまな磁気記録型メディア
FDおよびFDD(Floppy Disk Drive)は比較的改変が容易ということもあって、独自の規格の物が多数存在する。筆者が知っている(≠使ったことがある)だけで4/3.8/3.25/3/2.8/2.5/2インチの寸法の物があり、このうち2.8インチはQuick Diskという名称でシャープのMZシリーズやMSXに採用されていたが、どれも独自規格ということもあって長続きはしなかった。
2ED FD
同様に、1.44MB容量の2HD FDの容量を増やす試みも成功しなかった。最初に出て来たのは2.88MBの容量を持つ2ED(Extra high Density)で、3.5インチFDと同じ寸法ながら容量が2倍というものだ。
2EDは1990年頃に発表されたが、1997年1月末の秋葉原での調査ではまだ3.25インチ 2EDが1枚980円で販売されていたそうだから、この頃まではFDも販売されていたのは間違いない。
ただ肝心のドライブのほうはほとんど流通しなかった。1994年に発売されたThinkPad 755にオプションで2ED FDDが用意されたほか、1990~1993年に発売されていたNeXTstationは、筐体の左側面に2ED FDDが1ドライブ搭載されている。
ただ筆者の知っている例はこの程度で、自作マーケットに2ED FDDが流れてくることはなかったし、そのほかのメーカーが積極的に2ED FDDを搭載したという話も聞かない。
SuperDisk
1996年に、松下寿とImationは共同でLS-120という、その名の通り容量120MBのFDDと対応FDを発売、翌1997年にSuperDiskに改称された。
このSuperDiskの顛末はこちらの記事に纏まっているので繰り返さない。2000年には容量を240MBに倍増したものも登場した(FDD/FDともに120MBのものとは互換性はない。ただ240MBのFDDで120MBのFDDの読み書きは可能)。
この240MBのFDDには、通常の3.5インチ 2HD FDの容量を32MBに拡大できるという謎のFD32MBという機能も搭載された。なのだが、そこまでしても確たるシェアを確保するには至らず、消えていってしまった(筆者の家のどこかに、1台だけ120MBのUSB接続のSuperDiskのFDDがあるはずなのだが、発見に至らず)。
HiFD
1997年にはソニーと富士フイルムが共同でHiFDという名称の200MB FDD(とFD)を発表するが、製品そのものの市場投入は2000年までずれ込んだ。本体との接続はパラレルポートであった。
富士フイルムはこれに加え、スマートメディアとPCカードまで搭載したトリプルドライブであるFinePix Platform HA-700なる製品を3月から発売予定だったが、延期されたのちに理由不明で発売中止になってしまった。
代わりに同年11月5日にZipを搭載したHA-770が発売される。秋葉原の店頭でドライブ150台が販売され、即完売なんてニュースもあったが、結局HiFDは市場に大量に流れることなく消えてしまった。
UHC FDD
同じように消えてしまったものにUHC(Ultra High Capacity) FDDがある。これはミツミ電機とSwan Instrumentsが共同開発した容量120MBの規格で、1996年9月に生産計画が発表され、1997年春に発売が開始されるというアナウンスもあったのだが、発売されたという話は遂に聞くことがないまま終わったように思う。
発売元になる予定だった亜土電子工業は1999年にCSKの子会社となり、Swan Instrumentsもその後の行方が不明なままである。仮に市場出荷されていたとしてもさほど取れたシェアは大きくなかっただろうし、実際には出荷される前になくなった可能性もある。とりあえず筆者は実物を見たことは一度もない。
Pro-FD
同じく実物を見たことがないものには、Pro-FDがある。TechMonitorの1998年11月15日の記事によれば、Samsung Electronicsが発表したそうで、容量は123MBで2HDおよび2DDのFDと互換性がある、という話であるがこれもこの記事だけの話で、サンプルの写真すら見たことがない。
it Drive
もう一つit Driveもあった。こちらはCaleb Technologyが1997年に発表した製品で、米国ではUHD144という名称で販売されていた。UHDはUltra High Densityの略で、容量は最大144MBである。
こちらも筆者は見たことがないのだが、故元麻布春男氏が製品比較とベンチマークまでなさっておられ、あとこんな記事やこんな記事もあったので、ある程度の数量が流通していたのは間違いなさそうだ。
そんなit Driveであるが、こちらはCaleb Technologyが2002年早々に破産して、そのまま消えてしまった。
ここまでは既存のFDと互換性のある、あるいは互換性はないがFDの延長にあったメディアであるが、まったく違う格好の物もあった。
SyQuest SQ306
まず最初はSyQuestを紹介したい。同社はShugart氏がShugart Associatesを退職してSeagate Technologyを創業した際の創業メンバーの1人であるSyed Iftikar氏が1981年に創業したメーカーである。
最初の製品であるSyQuest SQ306は容量6MBのリムーバブルメディアである。1982年当時としては、HDDと同等の容量とアクセス速度でありながら、メディアを交換可能という画期的な製品であった。
これに続き、1986年には容量15MBの「SQ319RD」ドライブと「SQ300」カートリッジを、次いで容量44MBの「SQ555」ドライブと「SQ400」カートリッジを発表する。
このSyQuestのリムーバブルメディアは、ちょうど1987年にMacintosh IIが発売され、この上でDTP(DeskTop Publishing:コンピュータ画面上で印刷物の生成を行なう)のマーケットが立ち上がったタイミングをうまく掴んだ。
この当時の事だからDTPソフトはAldus PageMakerが唯一のものであるが、さすがに初代Macintoshの512×384pixelではまともに作業するには画面が狭すぎた。
ところがMacintosh IIでは大画面やマルチモニターが利用可能となり、版下までの生成をMacintoshで行なうことが可能になった。それは良いのだが、その版下データは当然かなりの容量になるため、これを印刷所にどう届けるか?という問題が出てきた。
まだインターネットなんぞない時代だし、FDだとウン十枚になる。最終的には版下データを収めたSCSI HDDを、送ると途中で壊れそうなのでハンドキャリーで持っていくとかいう騒ぎになったわけだが、言うまでもなく大きいし重い。
こうした用途に44MBのSQ555/SQ400は非常に適しており、米国におけるDTP向けマーケットのほとんどをSyQuestが抑えることに成功する。
1988年の売上は2,000万ドルだったが、1990年には8,000万ドルまで伸ばした。この1990年に同社はドライブを15万台、カートリッジを70万個売り上げている。1991年には容量を倍増させたSQ5110ドライブとSQ800カートリッジを、1994年には容量200MBのSQ5200CとSQ2000カートリッジをそれぞれ投入する。
Bernoulli Disk
出典:2009 Evil saltine, File:Bernoulli230.jpg,CC BY 3.0
ただ1990年が同社のピークであった。というのは後述するIomegaが同じマーケットに参入してきたからで、IomegaのBernoulliドライブがSyQuestのシェアを奪い始める。
また仏Nomai Inc.がSyQuest互換カートリッジの販売を始め、Iomegaは1993年にこの互換カートリッジの取り扱いを始めたことで、両社は本格的に競合することになる。
Zip
そのIomegaが1994年に低価格のZipドライブを投入したことを受け、SyQuestは1995年に3.5インチサイズのカートリッジを持つEZ135(容量135MB)をまず投入、その後は容量230MBのEZ230、容量1.5GBのSQ1500、容量1GBながらより低価格なSparQ、最後には容量4.7GBのQuest driveを発表するが、失ったシェアを取り戻すことはできないまま、1998年11月3日に破産した。
これに先立ちIftikar氏は1996年に経営悪化の責任を取る形で退任していたが、氏が次に興したのがCastlewood Systemsで、COMDEX/Fall 98では2.2GBのORB Driveというリムーバブルメディアの新製品をデモしていた。
ただ量産に入ったところ、製造工程のトラブルにより製造した35万台のORB Driveのリコールが必要ということが判明、結局製品発売前に会社ごと消えることになってしまった。同社はこれに続き5.7GBの製品も開発中だったが、全部幻と化してしまった。
そのSyQuestを追い詰めたのがIomegaである。1980年創業の同社、元々はBernoulli Diskと、これを利用できるBernoulli Boxを開発していた。
ベルヌーイの法則から取られたこのDisk、要するにヘッドとディスクの間の流速を下げることで、ヘッドがディスクにクラッシュしないという仕組みを持ち込んだことからこの名前が付けられたが、実際にはしばしばクラッシュしたというのがなんともはや。
それでもいろいろトラブルを克服して1984年にはBernoulli Box A220とBernoulli Diskを発売している。容量は5/10/20MBで、当時のHDDの代替を狙ったものだ。
1988年には第2世代製品が登場。こちらはまず20/35/44MBのものがリリースされ、最終的には230MBまで容量を拡大している。
このあたりでSyQuestで追撃の準備が整った格好だが、1992年あたりに市場の飽和もあって業績は再悪化。そこで市場調査を行なったところ、「容量は少なくてもいいから低価格のメディアが必要」という結果が出たそうだ。
これを受け、同社はBernoulli Diskを捨て、まったく新しいメディアとしてZipの登場である。こちらはドライブとメディア、どちらも結構安価でそのわりにアクセスは高速だった。当初リリースされたのは外付けのタイプで、
まずはパラレル、次いでUSB接続であったが、後には3.5インチドライブサイズの内蔵用(接続方法はATAPI)ドライブも登場し、これを組み込んだBTOマシンなども存在した。
SyQuestの製品、あるいはIomegaでもBernoulli Diskはまったくと言っていいほど日本国内では見かけなかったが、Zipは国内でも広く流通した。同社はこれに続き、容量1GB(のちに2GB)のJaz、PC向けのテープドライブであるDitto、超小型ドライブであるClik!などを相次いで発売。
また倒産したSyQuestの資産を丸ごと買収するなど勢いに乗っていたが、USBメモリの登場で急速にシェアを失い、2008年にEMCに買収されて消えることになった。
MicroDrive
広義に磁気記録メディアに含まれるものとしては、1999年にIBMが発表したMicroDriveも含まれるかもしれない。I/FはCompact Flash Type 2準拠ということで、理論上はそのままCompact Flashの代わりに利用できた。
当初は340MBだったが、その後512MB/1GB、2/4GB、6GBときて最終的には8GBまで容量を伸ばした。
もっともこのMicroDrive、確かに信号こそCompactFlash Type 2互換ながら、中に小型のプラッタが格納さてモーターで駆動しているため、消費電力はCompact Flash Type 2の規定をぶっちぎっており、なので現実問題としてMicroDriveに対応したCompact Flash Type 2対応機器でしか使えない、という非互換性があった。
筆者も(なぜか)所有していたが、まともに動かない機器のほうが多かった。あとHDDだから耐衝撃性にも乏しく、そういう意味でも外部記録メディアというにはちょっと脆弱であり、フラッシュメモリの大容量化に負けて消えてしまった。
光磁気記録メディアいろいろ
日本でSyQuestのSQ400とかIomegaのBernoulli Diskが入ってこなかった理由はいくつか考えられるが、すでに光磁気記録メディアが結構流通していたから、というのは1つの要因ではあるだろう。
MO
その代表格がMO(magneto-optical)ディスクである。いわゆる光磁気ディスクというもので、1990年後半にはエンタープライズ向けに8インチや5.25インチのものが利用されていた(昔はさらに大きいサイズの物もあったらしいのだが、筆者は見たことがない)。
8インチはさすがに廃れてしまったが、5.25インチのディスクはまだAmazonで販売されていたし、ドライブの方もAmazon USで販売されていた。ただこれらはPC向けの外部記録メディアというよりは、企業における重要データのバックアップ用といった位置づけで、あまり一般的とは言えなかった。
一般的なのは3.5インチサイズのもので、まず最初は128MBのものが登場したのだが、これの登場時期が今一つ分からない。Google BooksでPC Magazineのバックナンバーの広告を調べると、1994年1月11日号に初めてMOドライブの広告が掲載された模様だ。
この時は799ドルとちょいお高めであった。日本での流通開始時期は不明だが、多分そう変わらなかったように思う。この後、日本では急速にMOの普及が進む。
普及と言ってもドライブ単価はそれなりに高かったからZipに比べるとそんなに多くはなかったが、2年後の1996年3月12日号では230MBのFujitsu DynaMO 230が$499になったとされているなど、ドライブの低価格化も進んでいたから、結構手頃であった。
筆者もバックアップやデータ交換用にMOドライブを多用していた。こちらの記事によれば1999年には日本で高いシェアを誇っていたとあり、実際筆者もこの意見に同意する。
もっとも2000年に入ると先に書いたようにUSBメモリの急速な普及もあって、次第にニーズが減ってきたのも事実である。2000年代後半になるとほぼ新製品が絶えた中、2011年11月にロジテックがWeb販売限定で1.3GBまでに対応するMOドライブを発売。
これがいよいよ最後か、と思ったらまだニーズがあったようで、2013年にも640MB対応ドライブを発売したが、これがおそらく最後の新製品のドライブの発売と思われる。
MD
もう一つ、普及に至らず消えていったのがMDである。元々は音楽用として1991年に発表され、1992年から製品が市場に出て来た。これはこれで結構便利で、筆者も取材の録音をカセットテープからMDに切り替えたりしたのだが、これはあくまで音楽用の話である。
データ交換用としては1993年にMD DATAという規格(というか、名称)が定められ、1995年頃からドライブやメディアも登場した。外付けタイプ以外に3.5インチドライブベイ内蔵タイプのMDM-111も存在した。容量は140MBであるが、実は別にMD DATAでなく音楽用のMDであってもフォーマットし直せばMD DATAとして使えるということで、メディアの入手性はMOに比べるとずっと高かった。
【お詫びと訂正】初出時に「Data MD」としておりましたが、正しくは「MD DATA」となります。お詫びして訂正させていただきます。
ちなみにPCの周辺機器だけでなく、デジタルカメラのストレージとしても検討されており、シャープは1996年のエレクトロニクスショーで参考展示を行なっているし、ソニーは1997年にDSC-MD1を発表している。
ということでソニーを中心に結構普及に向けて努力はしたのだが、思ったようにはMD DATAは普及しなかった。これは国内だけでなく海外も同じであった。
理由の1つはZipとモロにタイミングがぶつかったことだろう。容量もそう大差なく、価格はZipのほうが安いとあれば、それはMD DATAには苦しい戦いになるのは仕方がない。
実際メリットと言われても、Zip Driveで時々起きていたClick of death(Zip Driveにアクセスに行くと「カンカン」というクリック音が鳴るだけで一切アクセスできなくなる現象。Zip Driveと、その時装着していたカートリッジの両方がお亡くなりになる)がMD DATAでは発生しなかった程度しか思いつかない。
MD陣営もそのまま手をこまねいていたわけではなく、1996年には容量を650MBに増やしたMD DATA2を発表したが、製品化は遅れて1999年11月まで延びることになった。しかもメディアはともかくドライブのほうはビデオカメラであるDCM-M1のみが発売され、PCの周辺機器としてのドライブは発表されなかったため、MD DATAと言いつつ映像記録用としての使われ方のみであった。
ソニーはこの後、MDを改良したHi-MDと呼ばれる規格を2004年に発表、データ用として使うと1GBの記録が可能だったが、先のMOと同じくこの頃には光磁気メディアはUSBメモリなどに駆逐されてしまっており、もうPC用の外部記録メディアとして使われることはなかった。
PDとDVD-RAM、HD DVD
まずPDからいこう。PDはPhase-change Discの略(Phase-change Dualの略という説もあり)で、相変化を利用した記録メディアであり、松下が1995年に開発した。当初登場したLF-1002というドライブはSCSI接続で、容量650MBのPDと4倍速CD-ROMドライブの兼用という構成になっていた。
筆者も長らくこのPDは使っており、当時のCD-Rに比べると信頼性が高く書き込みの失敗もなかったが、アクセス速度はお世辞にも高速とは言えなかった(特にランダムアクセスは猛烈に待たされた)。
それでもバックアップ用としては優秀であり、容量も当時のMOに比べると大きいということで、一部のユーザー(含筆者)には支持されたが、それ以上にはシェアが広がらなかったように記憶している。そうこうしている間にMOの容量も追い付いてきて、最後には追い越された格好だ。
小型のPDドライブの発売などはあったほか、CD-Rの書き込み機能を追加したドライブも登場したが、PDそのものの容量増加とか高速化といった更新は遂に行なわれないままであった。
DVD-RAM
その代わりと言っては何だが、1997年に標準化されたのがDVD-RAMである。これはDVD Forumで標準化が完了しており、1997年のV1.0は片面2.6GB、2000年のV2.0は片面4.7GBになって、ほかのDVD±R/RW規格と肩を並べることになった。
ただ制御方式がDVD±R/RWとまったく異なる関係で、通常のDVDドライブなどでは読み出しすら不可能で、DVD-RAMドライブが必要というあたりがこの製品の扱いを難しくした。
PC向けとしては、PDとDVD-RAM(+CD+DVD)を扱えるLF-D101が1998年に発売されているが、非常に限られたシェアしか取れなかったのは無理もないところだろう。
HD DVD
最後がHD DVDである。これはBDに対抗する形で東芝とNECが立ち上げた規格である。BD対抗なのでこちらも容量は大きく、片面1層で15GB、2層で30GBなほか、Version 2.0では1層あたり17GBにして3層で51GBの容量を持つ規格も標準化された。
またメディアの種類としては以下の4種類が定義されている。
- HD DVD-ROM : 読み取り専用
- HD DVD-R : 1回書き込み可能
- HD DVD-RW : 複数回の書き込み/消去が可能
- HD DVD-RAM : PC向け、複数回の書き込み/消去が可能
また2006年にはXBox 360用のHD DVDドライブも発売された。
なのだが、ご存じの通りBDとの標準規格争いに敗れ、2008年に東芝が全面撤退。この時点でメディアとしての命運は絶たれた。実際この時点でHD DVDのドライブは映像の録画/再生用のものしか市販されておらず、PCにつないで書き込みをできるものは皆無だった。
ちなみにXBox 360用のHD DVDドライブはWindows 7では使える(ただし対応する再生ソフトが必要)ということで、結構買ったユーザーはいたと思うが、今となってはDVD-ROMドライブとしてしか使えない。そういう意味でも、PC用の外部記録メディアになる前に終わってしまったメディア、として良いかと思う。
フラッシュメディア
いわゆるメモリカードの類で、CF(Compact Flash)/CFExpress、スマートメディア、メモリースティック、xD Picture、SDカード/MMCカード/miniSD/microSDあたりが日本で利用されていた主なところかと思う。
これらはPCの外部記録メディアというよりは、デジカメだったりビデオカメラだったりの記録メディアという意味合いが強く、こちらもさまざまな変遷を経て昨今はSDカードやmicroSDカードが広範に使われている。
このSD Cardの歴史は以前こちらに書いたし、PCの外部記憶メディアという今回の趣旨からメモリカード類はちょっと外れる気がするので内容は割愛させていただく。


































![[Amazon限定ブランド]CCL い・ろ・は・すラベルレス 2LPET ×8本 ミネラルウォーター 無味 製品画像:2位](https://m.media-amazon.com/images/I/41h0MHfvhkL._SL160_.jpg)







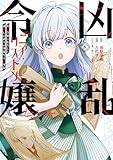







![【中古】 SONY VAIO VPCL128FJ 大容量HDD搭載 Core 2 Quad Windows10 Home ブルーレイ 液晶一体型 保証付 [93773] 製品画像:6位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/risemark/cabinet/pic/937b/93773.jpg?_ex=128x128)







![IOデータ 240Hz対応ゲーミングモニター KHGD242UDB GigaCrysta [23.8型 /フルHD(1920×1080) /ワイド] ブラック 製品画像:3位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/r-kojima/cabinet/n0000001297/4957180177496_1.jpg?_ex=128x128)
![【エントリーと合わせてポイント14倍★2/19 20:00〜】iiyama ProLite XUB3493WQSU-B6 [34型 IPS方式パネル ノングレア液晶] ウルトラワイドディスプレイ 34インチ モニター UWQHD(3440 x 1440)解像度 昇降 イイヤマ<新品> 製品画像:2位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/mousecomputer/cabinet/8_iiyama/xub3493wqsu-b6.jpg?_ex=128x128)

![若手弁護士・パラリーガル必携 通知書書式百選 [ 第一東京弁護士会 若手会員委員会 通知書研究部会 ] 製品画像:30位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/5926/9784788295926.jpg?_ex=128x128)
![いつのまにか頭がよくなる! マインクラフト なぞなぞ222連発! [ 神楽 つな ] 製品画像:29位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/0605/9784049150605_1_11.jpg?_ex=128x128)
![矢吹健太朗画業25周年記念イラスト集 Digital Art Collection High Light (愛蔵版コミックス) [ 矢吹 健太朗 ] 製品画像:28位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/6088/9784087926088_1_5.jpg?_ex=128x128)
![ONE PIECE 114 (ジャンプコミックス) [ 尾田 栄一郎 ] 製品画像:27位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/0191/9784088850191.gif?_ex=128x128)
![[古探 716] 古典探究 漢文編 [令和5年度改訂] 高校用 文部科学省検定済教科書 筑摩書房 製品画像:26位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/learners/cabinet/12119609/img20250825_10523785.jpg?_ex=128x128)
![[古探 715] 古典探究 古文編 [令和5年度改訂] 高校用 文部科学省検定済教科書 筑摩書房 製品画像:25位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/learners/cabinet/12119609/img20250825_10585560.jpg?_ex=128x128)
![真訳シェイクスピア四大悲劇 ハムレット・オセロー・リア王・マクベス [ ウィリアム・シェイクスピア ] 製品画像:24位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/8299/9784309208299_1_4.jpg?_ex=128x128)
![真訳 シェイクスピア傑作選 ロミオとジュリエット・夏の夜の夢・お気に召すまま・十二夜・冬物語・テンペスト [ ウィリアム・シェイクスピア ] 製品画像:23位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/9159/9784309209159_1_19.jpg?_ex=128x128)
![頭がよくなる! マインクラフトで絵さがしBOOK [ マイクラ職人組合 ] 製品画像:22位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/9253/9784299059253_1_3.jpg?_ex=128x128)
