大河原克行の「パソコン業界、東奔西走」
Windows 10から大きく変化したWindows 11のアクセシビリティ機能
2021年11月17日 07:00
Windows 11は、アクセシビリティを重視した形で、開発が進められた。アクセシビリティ機能の大きな進化は、Windows 11の隠れた特徴の1つだといっていい。開発段階においては、障碍のある人たちと共同で、デザインや設計に取り組んだだけでなく、Trusted Tester という適合性テストやユーザビリティテストなどのプロセスを採用して、アクセシビリティ機能の進化を実現してきた。新しいアクセシビリティ機能を設計した米Microsoft本社のインプット&アクセシビリティチームが、その取り組みについて語った。
障碍のある人にもない人にも快適な体験を提供
2021年10月5日に一般公開されたWindows 11では、Windowsがこれまでに10億人以上のユーザーが利用してきた、世界で最も普及したPC用OSであることを踏まえながら、ユーザー1人1人が大切なことに集中でき、愛されるエクスペリエンスを創り出すことを目指し、ユーザー中心のデザインを採用することに力を注いできたという。
そして、全世界10億人というユーザーのなかには、障碍がある人たちが含まれ、これらの人たちが、よりアクセスしやすいWindowsエクスペリエンスの実現を目指すことは避けては通れない要素だったといえる。
Microsoft Windowsシニアプロダクトデザインマネージャーのジウォン・チョイ(Jiwon Choi)氏は、「Windows 11のアクセシビリティ機能は、2つのプロダクトチームが連携して開発した点がユニークである。まずは、ダイバーシティを理解した上で必要なニーズを明らかにすることから作業を開始し、その上で、様々な能力、好み、姿勢、健康状態などを理解した上で、すべてのWindows 11ユーザーが生産性を発揮できる支援ツールと、最新の入力体験を提供できるようにした」と語る。
ここでいう2つのプロダクトチームのうちの1つは、障碍のあるユーザーのための設計を行うアクセシビリティチームだ。このチームでは、特有のニーズとして認識される可能性がある多様な能力や好みを把握する役割を担った。もう1つは、Windowsの最新の入力エクスペリエンスを担当するチームで、音声入力を使ってコンテンツを作成したり、指を使ってタイピングやタッチ操作を行なったり、ペンを使って絵を描き、Windows OSと対話するための機能を担当した。
「この2つの分野をサポートすることで、様々な能力や好み、姿勢を持っているすべての Windows 11ユーザーの生産性を高められるようになる」とする。
インクルーシブデザインの原則に則る
また、MicrosoftのWindows開発チームは、障碍のある人にも、障碍がない人にも、効率的で、楽しく、快適な体験を提供することを開発目標に掲げ、様々な能力、ニーズ、嗜好を持つ人々を尊重し、インスピレーションを得るという「インクルーシブデザイン」の原則に基づいて、Windows11の開発を行なった。
Microsoftが打ち出したインクルーシブデザインの原則では、排他的要素を見つけ出し、それを新たなデザインや、インクルーシブなデザインを創り出す機会として活用する「排他的要素を認識する」、プロセスの初期段階から人を中心に考え、多様な視点から見る「多様性から学ぶ」、障碍のある人のために設計することで、結果的に多くの人々に利益をもたらすデザインを創り出す「1人のためが、多くの人の解決に」という3つの要素で構成する。
Microsoft Windowsインプット&アクセシビリティ デザイナーのジョン・ポーター(John Porter)氏は、「これらの原則の多くは、アシスタント技術やアクセシビリティツールを、OSの一部に感じられることに繋がっている。ユーザーのニーズや、好みに関係なく、Windowsらしく、Windowsが本来使用されるべき方法で使用されているように感じられるようにしている」と述べる。
Windows 11では、ナレーター機能や拡大鏡、字幕機能、音声認識機能といったこれまでのWindowsに搭載されてきたアクセシビリティ機能を引き続き搭載しているほか、パートナーが提供するアクセシビリティ技術もサポートし、CART(コミュニケーション アクセス リアルタイム トランスレーション)サービス機能やスピーチコマンド機能なども体験できるようにしている。
「直感的で、速くアクセスでき、統合されたアクセシビリティ機能が欲しいという声があり、それを実現するために、開発チームは、様々なアクセシビリティツールを試してきた。これまでには、テクノロジーと体験のミスマッチという部分も一部にはあったが、タイピングやタッチ、ペンで描くといったインプット体験をより進化させ、さらに、アイトラッキングでの操作も進化させている。だが、ここでは、これまでのWindowsの操作性と変わらないようにすることも大切な要素であった」とする。
デスクトップやスタートメニュー、検索、タスクバー、設定など多くの機能は、これまで使い慣れてきたものと違和感なく感じてもらえるようにする一方、テクノロジーとのミスマッチの部分も改善した。
実は、これまでのWindows 10 のハイコントラストテーマでは、弱視や光に敏感な人たちに向けて、テキスト、背景、画面上の要素をできるだけ区別しやすくできるように設計した。だが、ユーザーからは、「このテーマには疎外感を抱く」、「あまりにも無骨なツールだ」といった声が挙がり、開発チームにも「やりすぎた」という反省があったという。コントラストを高めることは必要だったが、それほど極端なコントラストにする必要はなかったからだ。
Windows 11のコントラストテーマでは、視覚障碍のある人たちが、デザインプロセスの最初の段階から参加し、専門家としての意見や実際の体験に基づいて、カラーコントラストのデザインに意見をし、それを反映して完成させた。
わかりやすさを追求して名称を変更
また、Windows 11のアクセシビリティ機能は、様々なところで利用できるようにする点にもこだわったという。Microsoft Windowsシニアインプット&アクセシビリティデザイナーのジュリア・カールソン(Julia Carlson)氏は、「新たなアクセシビリティ機能は、Windows 11にデフォルトで搭載し、ログイン前やロック状態から使えるようになっている。また、アクセシビリティツールは、Windows11の全ての機能で使えるようにした。新たな機能を開発する際には、必ずアクセシビリティツールが機能するようにしており、様々なツールで期待していた行動、振る舞いが行なえるようにしている。それと同時に、ユーザー自らがカスタマイズできるようになっている点も特徴である」と語る。
視覚障碍者が、ナレーター機能などを使って自分でデバイスを設定しなおすといった利用を可能にしているのはその一例だ。
さらにカールソン氏は、アクセシビリティの設定ページの名称を、これまでは、「簡単操作」としていたが、それが汎用的すぎて分かりにくかったことから、「アクセシビリティ」に名称を変更するとともに、アイコンも変更。アクセシビリティの設定ページのメニューも刷新して、ナビゲートを容易にし、ツールを発見しやすくしたことも強調した。
「アクセシビリティのアイコンには、“人”の形を採用したほか、アクセシビリティの設定ページは、視覚や聴覚、操作といった項目に分けて、操作できるようにした。同時に、メニューから機能のオン/オフを、簡単に設定できることを重視した」とする。
音声入力は言語学習にも効果?
では、アクセシビリティという観点から、Windows11のいくつかの機能を見てみよう。
1つ目は、Windows Voice Typing(音声入力)である。これは、最先端のAI技術を駆使して音声を認識。テキストを書き起こして、自動的に句読点まで打ってくれる機能だ。
Microsoftのポーター氏は、「この機能は、ゼロから設計した新たなものである」と前置きし、「移動が制限されている人や、タイピングができない環境にある人、タイピングするよりも話すことを好む人たちが、音声によってコンテンツを作成でき、多くの人が発信できるように支援できる。音声入力によって、タイピングに支障がある人が、他のユーザーと同じくらいの速さでコンテンツを作成できるこができる、クールなエクスペリエンスを実現し、多様性をサポートする機能の1つとして重要なものになる」と語る。
重度の関節炎や反復性ストレス傷害、脳性麻痺など、さまざまな運動障碍のある人だけでなく、言語を学んでいる人々、音声入力が好きな人などにもVoice Typingを活用してもらいたいとする。
「インクルーシブデザインの原則で定めた、1人のための解決方法を見つけることが、多くの人のために拡散するという精神に基づいた機能の1つ」とも語る。
穏やかさや静寂にこだわったWindows 11のサウンド
2つ目は、サウンドである。
ポーター氏は、「Windows 11のサウンドは、穏やかさや静寂さにこだわり、誰もが楽しめる落ち着いたサウンドスケープ(音景)を実現した。スタートアップのサウンド再生も同様の考え方でデザインしており、すべての人に楽しんでもらえるようにしている」という。
視覚障碍者にとっては、Windowsが発生する音は重要な意味を持つ。強烈に感じたり、圧倒されたりすることなく伝え、音にストレスを感じないことは、アクセシビリティという観点からは大切な要素だ。
「サウンドは、Windows 11のデザインの中でも重要な役割を果たしている。多くの人が好むような音はなにか、ということを追求したほか、ユーザー自身が、サウンドテーマをチューニングできるようになっている」とする。
視覚障碍者や神経多様性のあるユーザーが、サウンドに関するニーズや好みに独特のニュアンスがあることにも配慮したという。
ユーザーからのフィードバックの結果、難聴の人が聞こえるようにするためには、250Hz~8,000Hzの音域を横断する必要があること、全盲の人がログイン情報を入力するタイミングを知るためには、ロック画面が表示された時点で起動音が鳴ると便利であることなどの声を反映。PCの準備が整ったことを知らせる新しいWindowsの起動音に加えて、より多くのユーザーに親しんでもらえる耳に優しく、有用な情報を示すサウンドを提供することにこだわったという。例えば、画面のコントラストを変えることができるライトテーマとダークテーマでは、異なるサウンドを用意している。
水生、砂漠、夕暮れ、夜空のコントラストテーマ
3つ目は、コントラストテーマである。
コントラストテーマは、Windows 10ではハイコントラストテーマと呼ばれていたもので、光に敏感な人や、長時間作業する人は、カラーフィルターに新たに用意されたダークテーマや、再構築されたハイコントラストテーマなどの美しいカラーテーマを選択することを勧めている。新しいコントラストテーマは、見た目が美しく、カスタマイズ可能なカラーの組み合わせで、アプリやコンテンツが見やすくなるようなものも用意したという。
MicrosoftWindowsインプット&アクセシビリティデザイナーのナタシア・シルバ(Natassia Silva)氏は、「光に敏感な人でも、色が識別できるようにしている。目の状態や神経問題、角膜に障害がある人にも適用できる。ここでも障碍者との緊密な連携によって要望を聞き、光の感度に敏感な人たちのニーズも満たすように設計した」という。
コントラストテーマのプレビューでは、水生、砂漠、夕暮れ、夜空の4種類を用意。これらの名称もフレンドリーなものにする工夫をした。また、カラーフィルターでは、色覚障害フィルターやグレースケール、反転なども用意。ユーザーの好みや見やすさなどの観点から、画面の色を変更できるようにしている。
モダン アクセシビリティ プラットフォームを提供
一方、Windows 11 では、Azure Virtual Desktop (AVD)においても、パートナーが提供するアクセシビリティ技術が実行できるようにしている。また、Windows 11のナレーター機能を使って、OfficeにRAIL(Remote Application Integrated Locally)でアクセスできるようにもしている。これは、視覚に障碍がある人でも、必要に応じてAzure上にホストされたOfficeなどのアプリケーションにアクセスできることに繋がる。
さらに、Windows 11では、Windows Subsystem for Linux (WSL)により、アプリのシステム要件を満たすデバイス上では、geditなどのLinux GUIアプリをサポートするが、ここでもアクセシビリティ対応を実現。視覚に障碍のある人が、サポート対象のスクリーンリーダーを使って、WSL内でWindowsが利用できる。
なお、Microsoftでは、アクセシビリティ技術を持つ企業とともに、「モダン アクセシビリティ プラットフォーム」を共同開発。ナレーターのような技術も、変更なしに様々なアプリケーションで使用でき、データなどにもアクセスすることが可能になっている。
障碍者の声を聞き、機能を進化させたWindows 11
Windows 11のアクセシビリティ機能は、障碍者との連携によって、進化を遂げた点が大きな特徴だ。
Microsoftのシルバ氏は、「障碍者コミュニティには、“私たちのことを、抜きに決めないで”というスローガンがある。これは、80年代の南アフリカの障碍者権利運動に端を発したものであり、障碍がある人々が、製品や政策に積極的に参加することの重要性を訴えている。設計チームは、この概念に従うことを大切にした。デザイナーとしての自分の専門性を謙虚に受け止め、ニーズや好み、これまでの生活経験に関しては、ユーザー自身こそが真の専門家であることを認識し、障碍者に向き合った」と語り、実際、2019年には、南アフリカの障碍者団体が訪問。あらゆる人の話を様々な角度から聞き、それを製品にしっかりと反映させていくことに力を注いだという
「障害者団体の人たちから多くの声を聞いた。直接会って、一緒にブレインストーミングを行ない、アクセシビリティの設計はどうあるべきか、どこに困ったいる点があるのか、といったことを語ってもらった。その声を、デザイナーや開発者に届けられるようにし、障碍者からのアドバイスを反映。検証するだけでなく、開発プロセスのなかにまで入ってもらい、高いレベルのカスタマーエンゲージメントを実現した」と、その経緯を語る。
ユーザーの声を聞き、そこから生まれた要望を、既存のアクセシビリティ機能の改善や、新たな機能として追加したのが、Windows 11におけるアクセシビリティ機能の進化のベースとなっている。
「パンデミックの時代になり、世界に出て行くのが難しくなっている今こそ、このようなエンゲージメントが大切である。様々な方法を組み合わせることで、それが実現できるようになる」と、Microsoftのシルバ氏は語る。
アクセシビリティ機能の進化は、障碍者を含む世界中のWindowsユーザーにとって、新たなエンゲージメントを実現することに貢献しそうだ。












![[Amazon限定ブランド]CCL い・ろ・は・すラベルレス 2LPET ×8本 ミネラルウォーター 無味 製品画像:2位](https://m.media-amazon.com/images/I/41h0MHfvhkL._SL160_.jpg)








![【中古】 Acer Aspire Timeline X AS3830T-F54D Core i5 2450M Windows7世代のPC 均一 電源投入可 HDMI ジャンクPC 送料無料 [94590] 製品画像:26位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/risemark/cabinet/pic/945b/94590.jpg?_ex=128x128)


















![液晶ディスプレイ アイ・オー・データ DI-D242SA-F [100Hz対応 フリースタイルスタンド ワイド液晶ディスプレイ 23.8型] 製品画像:5位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/etre/cabinet/itemimage35/1292998.jpg?_ex=128x128)
![【エントリーと合わせてポイント14倍★2/19 20:00〜】iiyama G-MASTER GB2471HSU-B1 [ 23.8型 FAST IPS方式ゲーミング液晶 ] 液晶ディスプレイ モニター フルHD(1,920×1,080)23.8インチ 240Hz 応答速度 0.3ms(MPRT)昇降・ピボット機能 スタンド 製品画像:4位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/mousecomputer/cabinet/8_iiyama/gb2471hsu-b1.jpg?_ex=128x128)


![デコピンのとくべつないちにち (単行本 608) [ 大谷 翔平 ] 製品画像:30位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/9368/9784591189368.jpg?_ex=128x128)
![INI Viva la vita [ ISAC ] 製品画像:29位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/0034/9784065420034_1_4.jpg?_ex=128x128)
![SODA (ソーダ) 2026年5月号 [雑誌] 製品画像:28位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/0562/4912158030562.gif?_ex=128x128)

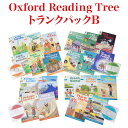

![REAL TRUCKS 9(トラック魂 特別編集) [ トラック魂 編集部 ] 製品画像:24位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/8254/9784865428254.gif?_ex=128x128)

![夏目友人帳 33 (花とゆめコミックス) [ 緑川 ゆき ] 製品画像:22位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/noimage_01.gif?_ex=128x128)
