笠原一輝のユビキタス情報局
ソニー出身の鈴木国正氏がインテルを退任。VAIO切り離し時の決断や日本のITへの期待を語る
2025年3月14日 09:53
Intelの日本法人となるインテル株式会社(以下IJKK)の代表取締役社長、代表取締役会長を歴任してきた鈴木国正氏がIJKKを3月末で退任することが明らかになった。
鈴木氏はソニー出身で、VAIO事業本部長、ソニー・コンピュータエンタテインメント(SCEI)副社長、ソニーモバイルコミュニケーションズ 社長 兼 CEOなどの要職をソニーで歴任した後、2018年11月にIJKKの社長に就任した。
それまでIJKKのトップは社内昇格ないしは、米国のエグゼクティブが兼任するという体制だったが、近年では初めて外部からの招聘でトップとなったのが鈴木氏だった。それから約6年が経過し、昨年大野誠氏に社長の座を譲ったあと会長に就任していた。
そうした鈴木氏に、約30年のソニー時代、6年半IJKK時代というビジネスパーソンとしてのキャリアを振り返っていただき、鈴木氏がソニー役員時代に決断したVAIO切り離しについての想いや、そしてこれからのIJKKや日本のITに期待することについて伺ってきた。
PCメーカーからの景色と、Intelからの景色の違いは「エンドユーザーに直接接しているかどうか」
――鈴木氏はソニー時代にもVAIO事業本部長など、ITに関わることが多かったと理解しているが、そうしたソニー時代のキャリアを振り返ってほしい。
鈴木氏(以下敬称略) 1984年にソニーに入社し、その後海外事業の立ちあげに関わってきた。サウジアラビア、アルゼンチン、米国などの子会社の立ちあげや成長に関わり、1999年頃にVAIO事業に参画した。
その後、米国子会社の社長をやったあと、2008年に日本に帰ってきて役員になりVAIOの事業本部長、ソニー・コンピュータエンタテインメント(SCEI)副社長に就任し、そしてソニーモバイルコミュニケーションズ 社長 兼 CEOとなった。その意味では事業部に関わっているときには、IT関連の事業をずっとやってきたとは言える。
――その後Intelに入って、IJKKの社長に就任された。PCメーカーのトップ(事業本部長)とサプライヤー側になるIntelの日本法人社長という両方のトップを務められたのは鈴木氏以外に誰もいないが、その両方から見た景色の違いはどういうものか教えてほしい。
鈴木 最大の違いはエンドユーザーに対して直接に接しているか、そうではないかだ。PCメーカーはエンドユーザーと直接やり取りをしていて、エンドユーザーがほしいものは何かを理解している。そのため、VAIOは、デザイン性、長時間バッテリ駆動、小型化などに注力して、PCのユーザー体験を改善していくことをけん引していたと自負している。
それに対して、半導体の側に来てみると高性能、プロセス技術、そしてそれを組み合わせて提供するプラットフォーム戦略などで進んでいく。それがお客さまであるPCメーカーのニーズと合致したときにすばらしい製品ができるということを実感した。VAIO時代にも、Intelが低消費電力の製品をリリースしたときに、VAIOが新しいデザイン、小型化などを実現し、それがエンドユーザーに評価された。
もう一つ重要なことは、PCのビジネスも変化し続けているということだ。以前は、PCメーカーがいて、そこに半導体を供給するIntelのような会社があるというシンプルな構造だった。
しかし、この20年でPCビジネスは高度に発展を遂げている。PCメーカーがいて、製品を実際に製造するODMメーカーがいて、そこにIntelのような半導体メーカー、そしてロジスティックや販売パートナー……とサプライチェーン全体が複雑になり、より高度になると同時に、半導体メーカーから直接顧客に接している、
PCメーカーとの距離は広がっている。だからこそ、サプライチェーン全体で「どのような最終製品を作るのか」ということを共有する必要があるし、そうしたPCメーカーの「想い」をIntelとしてもきちんと吸い上げていくことが大事だと考えている。
従来のようなバトンリレーではなく、スクラム型で製品を作り上げていく、そうしたことが可能になり、それぞれのレイヤー(PCメーカー、ODM、半導体メーカーなど)で競争が起きて、より良いモノを作れる環境を整えていく、それが大事だと考えている。
日本のためのIntelと、Intelのための日本という複眼の視点が必要なIntel日本法人の半導体戦略
――IJKKの社長、会長を務めたこの6年半を振り返って、最も良かったこと、あるいはその逆につらかったことを振り返ってほしい。
鈴木 基本的に楽観的なほうなのでつらかったことというのはあまり思いつかないが、大変だったという意味では、私がIntelに入ってすぐに発生した半導体の不足のころは、お客さまからも厳しいお声をいただいたりしていた。
また、その後のコロナ禍では、半導体一般が足りなくなってきたことが話題になり、自動車、扇風機や給湯器が作れないということが話題になった。そこで実感したことは、Intelという会社は社会的に期待されている社会性がある企業であり、お客さまに期待されている企業であるということだ。
そこで、私達がこの6年半でやってきたことは、日本のDX(Digital Transformation、デジタル変革)を推進していくことだ。特にIJKKでは、DcX(Data Centric Transformation)という造語を作り、データの利活用を通じてデジタル変革を促すということを訴求してきた。
DcXでは日本のビジネスリーダーに対して、データを利活用していくことこそがDXで最も重要なことであるとアピールしてきた。これはIJKKとしては新しい取り組みで、すぐに「我々の新しい半導体を買ってください」ということではなく、データを中心において活用していくことがビジネスをデジタル変革していく上でもっとも重要なことなのですと啓発していく取り組みだった。
それを推進していくことで、最終的にデータセンターやクラウドの重要性をビジネスリーダーの方に理解していただき、その結果として我々のお客さまであるサーバーベンダーのビジネスが活性化されたのはよかったと考えている。
――経産省を中心に25年の壁(筆者注 : コロナ禍にデータを利活用していない企業は25年に崖を迎えるという経産省のキャンペーン)という取り組みが行なわれたが、本年はその25年だ。25年の壁は来たのか、来なかったのか?
鈴木 経産省が使われた「25年の崖」という言葉そのものは刺激的だが、ビジネスリーダーの意識を変えるということには大きく貢献したと評価している。
ただし、本当の意味でDcXが進んだのかと問われるなら、それはまだ入り口に立っただけという形だと思う。この先に、大きな機会があって、それを着実に実行し実際に日本の国際競争力を引き上げられたのかが問われると思う。
我々としても、2年前から経済同友会で「企業のDX推進委員会」という取り組みを行なっている。伊藤穰一氏(千葉工業大学学長)、上野山勝也氏(PKSHA Technology創業者・代表取締役)と一緒に3人で、少しでも日本のDXが前に進むような取り組みを行なっている。
PCのAI化を促進するAI PCも、そうしたDXの一環だと我々は捉えている。今はまずハードウェアであるNPUがPCに搭載されている段階で、今後より多くのことがビジネスシーンでできるようになるアプリケーションソフトウェアが登場していくことになる。
それにより、企業のDXが進展していくと我々は強く信じており、Intelとしてエコシステムのパートナーと協力して作り上げていくことが大事だと考えている。
――半導体メーカーとしてのIntelは、日本には工場は持っていないが、日本にはウェハメーカーや後工程の素材を提供するような素材メーカーが多数あり、かつグローバルな市場でも大きな市場シェアを持っている。
鈴木 おっしゃる通り、日本には素材系のメーカー、そして製造装置系のメーカーという点で、Intelにとって重要なエコシステムパートナー企業が多数ある。私がIJKKのトップとして社内で使ってきたのが「Intel for Japan」(筆者意訳 : 日本のためになるIntel)、「Japan for Intel」(筆者意訳 : Intel本社に貢献できる日本のパートナー)という言葉で、日本の中でのIntelの役割、そしてIntelにとっての日本の役割ということを常に考えてきた。
そこで、日本のパートナー各社と一緒に日本の政府や産業界に対して半導体戦略の加速を働きかけたりしてきた。私の後任として社長になった大野(筆者注 : 大野誠氏、昨年IJKKの代表取締役社長に就任した)が中心になってさまざまな取り組みを行なってきており、その成果の1つとしてSATAS(Semiconductor Assembly Test Automation and Standardization Research Association、半導体後工程自動化・標準化競合組合)をパートナー各社と一緒に設立し、私が理事長を務めている。他にも先日の記者会見で大野が説明したと思うが、産業技術総合研究所(産総研)や理化学研究所(理研)との取り組みも加速させている。
――後任の社長が大野氏になったのもそうした流れがあったということか?
鈴木 そうしたことも影響していると思う。これまで彼が私と一緒にそうした取り組みを一緒にやってきたので、安心してバトンを渡せるし、本社からの信頼も厚い。そうした意味でこれからのIJKKを背負っていく人材として最適だ。
キャリアを通じて唯一つらかったことは、2014年にVAIOをソニーから切り離した決断
――鈴木氏は、ソニー時代には、VAIO、プレイステーション、そしてXperiaというデバイス事業に関わってきて、IJKKの社長・会長を務めるなどの経歴をお持ちだ。ずっとIT産業を見てきた鈴木氏の目から見て、IT産業のこの30年で最も印象的な出来事はなにか?
鈴木 「デジタルディバイド」という言葉に代表されるような「ディバイド」(英語でディバイドは分割するという意味の動詞で、日本語で使われるときには複数のグループに階層化されるという意味になる、デジタルディバイドならデジタルを使いこなせる層と、使いこなせない層に階層化が進んでいるという意味で使われる)という言葉が出てきたことが一番印象的なことだった。
90年代に登場したインターネット、そして00年代にはモバイル……さまざまな新しいテクノロジが登場するたびにそれを使いこなせている層とそうではない層の分断が発生した。今はそれがビジネスの現場で発生している。データやAIを使いこなせている企業とそうではない企業の差は大きくなっている。それをいかに小さくすることを可能にするか、それがIntelなどのIT企業にとって重要になっていると感じている。
PC産業もある意味でディバイドが進んだ産業だった。先ほど申し上げたように、PCメーカーだけで成り立っていた時代から、ODMメーカーで製造するようになり……とプレーヤーが増えていき、サプライチェーンはより長くなっていた。しかし、2010年代に日本のPCメーカーはそのサプライチェーンの中から脱落していったというのが歴史だ。
私はキャリアの中で常にポジティブに考えてきたが、唯一つらかった決断を強いられたのは、ソニーからVAIO事業を切り離す決断をしたときだ。そのとき私は、ソニーの執行役EVPだったが、それを決めたのはすごく厳しい決断だった。しかし、PC産業全体の流れを考えたときには、それが必要な決断だったと今でも思っている。
――そのVAIOも含めて、NECから切り離されたNEC PC、富士通から切り離されたFCCL(富士通クライアントコンピューティング)、そして東芝から切り離されたDynabookと、新しいオーナーの元で今でも特色のあるPCメーカーとして運営されている。その意味では必要な決断だったということではないか?
鈴木 おっしゃる通りだと思う。Intel日本法人のトップとしては、グローバルのトップ5メーカーなども含めてすべてのPCメーカーのビジネスが成功してほしいと願っているし、公正な競争が行なわれてほしいと願っている。一人の日本人としては、そうした日本ローカルのPCメーカーがこれからも特色のある製品を作って、日本のユーザーに製品を提供していくことが長く続けてほしいと願っている。
――ディバイドという意味では、今の話題はAIを使いこなせている人とそうではない人の差がさかんに言われるようになっている。また、日本の企業は米国などの他の地域の企業に比べてAIへの取り組みが遅いという指摘もある
鈴木 AIのディバイドはすでに起き始めている。日本の企業には日本の企業の取り組みが必要で、すでに多くの企業が独自のファウンデーションモデルに取り組んでいることはいいことだと考えている。そうしたAIでディバイドが起きないようにすることが、日本のIT関係者の義務だと私は考えている。
AIでディバイドされる側にならないように日本に必要なことはIT人材の育成
――Intelは2021年にIDM 2.0の方針を明らかにし、Intel Foundryというファウンドリーサービスを立ちあげることを発表し、そこからファウンドリービジネスの実現に向かって走り続けてきた。本年はその最初のプロセスノードになるIntel 18Aが本格的に立ち上がる年になる
鈴木 IntelがこれまでIDM 2.0として推進してきた方針は間違っていないと私は考えている。今のIntelは「AI Everywhere」(筆者意訳 : どこにもAI)とファウンドリーという2つの大きな軸があり、実のところどちらもAIを実現するためのものなのだ。
我々はNVIDIAがAI事業で成功したことをリスペクトしているが、しかし今後健全にAIが発展していくためにAIがNVIDIAの半導体でだけ処理されているような状況は健全ではない。そこにIntelもしっかりと役割を担っていき、AIを活用した社会の発展に貢献していく必要がある。
また、製造に関しても同じようなことが言える。今はTSMCという、Intelにとって強力なパートナー(筆者注 : Core Ultraシリーズ2の大部分はTSMC製のダイが利用されている)でもあり、ファウンドリーという意味では強力なライバルがいる。そこでしっかりとIntelがお客さま(のファブレス半導体メーカー)に選択されなければならないし、AIを演算する半導体がIntelのファウンドリーで作られて世の中に出ていく、そうしたことが今後実現していくと考えている。
――これからのIJKKはどうなっていく、あるいはどうなって言ってほしいと考えているか?
鈴木 やはりAIへの対応、それから半導体のサプライチェーンの中で日本の存在感を高めていってほしいということだ。AIのファウンデーションモデルの開発でも日本独自のモデルの開発が進んでいるが、そうしたことを今後も推進しAI Everywhereを本当の意味で実現していってほしい。
また、半導体製造に関してはSATASのような取り組みを加速して、日本の半導体産業の存在感を高めていってほしい。そしてそれはIntelの半導体ビジネスにとっても大きなメリットをもたらすものだと私は信じている。
――日本のITにとってこれからの課題は?
鈴木 現状深刻なのは、IT人材の不足と、スキルギャップ(筆者注 : 求められるスキルと、今の人材が持っているスキルとのギャップ)だ。経産省の試算では、2030年までにITエンジニアが約80万人足りなくなるとされている。リスキリング(筆者注 : 新しい職につくために必要なスキルを獲得すること)を含めて、そうしたIT人材をどう育てて行くのか、それが今の日本のITにとって求められている大きな課題だ。
今後日本のITが発展していくためには、強力な指導力を持つリーダーが必要だと考えている。私がソニー時代には、Apple創業者のスティーブ・ジョブス氏、ホンハイ創業者のテリー・ゴー氏、そしてNVIDIA創業者のジェンスン・フアン氏など、カリスマと言われるようなリーダーと渡り合ってきた。
彼らは本当に強いリーダーシップを持ち、迫力を持って仕事をしている。日本にもそうしたカリスマと渡り合えるようなリーダーが必要だと考えており、そうしたリーダーになるためにどうしたらいいのかをこれからリーダーになっていく人たちにシェアしていくことが重要だ。
――3月末でIJKKの会長を退任されてからは何をされる予定か?
鈴木 経済同友会での「企業のDX推進委員会」の取り組みや、SATASの理事長職などはインテルを退任した後も続ける計画だ。そうした取り組みにより、引き続きインテルや日本の半導体産業のために働いていきたいと考えている。
また、アポロ・グローバル・マネジメントというプライベート・エクイティ(非公開株式)や投資を行なう投資会社のシニアアドバイザーを1月から始めているほか、JTBの社外取締役、リコーの監査役、日本バレーボール協会の理事(非常勤)も行なっており、これまでの自分の経験を生かして産業界や社会に貢献していきたい。

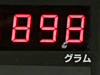













![[Amazon限定ブランド]CCL い・ろ・は・すラベルレス 2LPET ×8本 ミネラルウォーター 無味 製品画像:1位](https://m.media-amazon.com/images/I/41h0MHfvhkL._SL160_.jpg)



![【Amazon.co.jp限定】 伊藤園 磨かれて、澄みきった日本の水 2L 8本 ラベルレス [ ケース ] [ 水 ] [ 軟水 ] [ ペットボトル ] [ 箱買い ] [ ストック ] [ 水分補給 ] 製品画像:5位](https://m.media-amazon.com/images/I/41n0o65dSkL._SL160_.jpg)

































![ベビーブック 2026年 4月号 [雑誌] 製品画像:29位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/0463/4912010110463_1_2.jpg?_ex=128x128)


![MBA 2030年の基礎知識100 [ グロービス ] 製品画像:26位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/3352/9784569853352_1_4.jpg?_ex=128x128)
![【楽天ブックス限定特典】INI 2nd写真集 「Viva la vita」(限定カバー+ランダムトレカ1枚(全11種)) [ ISAC/Shuhei Tsunekawa ] 製品画像:25位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/1108/9784065431108_1_3.jpg?_ex=128x128)
![木挽町のあだ討ち (新潮文庫) [ 永井 紗耶子 ] 製品画像:24位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/8835/9784101028835_1_10.jpg?_ex=128x128)
![[新品]角川まんが学習シリーズ 日本の歴史 5大特典つき全16巻+別巻5冊セット 製品画像:23位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/mangazenkan/cabinet/syncip_0061/j1140408635_01.jpg?_ex=128x128)
![ロジカル・シンキング 論理的な思考と構成のスキル (Best solution) [ 照屋華子 ] 製品画像:22位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/1129/9784492531129.jpg?_ex=128x128)
![LEE (リー) 2026年 4月号 [雑誌] 製品画像:21位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/0469/4912013810469_1_3.jpg?_ex=128x128)