福田昭のセミコン業界最前線
FET発明100周年とAI時代の展望。VLSIシンポジウム2025、京都でスタート
2025年6月9日 06:12
半導体のデバイス・プロセス技術と集積回路技術に関する最先端の研究開発成果を披露する国際学会「VLSIシンポジウム(2025 IEEE Symposium on VLSI Technology and Circuits:VLSI 2025)」が、今年(2025年)も8日に始まった。開催地は京都府京都市、会場は「リーガロイヤルホテル京都」である。
ここ十数年、VLSIシンポジウムは西暦の奇数年に京都府京都市(リーガロイヤルホテル京都)、偶数年に米国ハワイ州ホノルル(Hilton Hawaiian Village)を開催地としてきた。同シンポジウムの関係者はこの交互開催を「京都開催」、「ハワイ開催」と呼んで区別してきた。コロナ禍による2020年と2021年のバーチャル開催を経て2022年にはハワイ開催、2023年には京都開催が復活した。今年はコロナ禍以降では2回目の京都開催となる。
コロナ禍によって生み出された「オンデマンド」、あるいは「オンライン」などと呼ばれるリモートでの参加枠は、今年も設けられる。ただし参加登録料金は現地参加とオンライン参加で変わらない。また現地参加者もオンラインで公開された講演ビデオを視聴できる。
日曜のワークショップは特別企画「FET発明100周年」を実施
2025年の開催テーマは「Cultivating the VLSI Garden: From Seeds of Innovation to Thriving Growth(VLSIガーデンの育成:革新の種から繁栄する成長へ)」である。半導体集積回路の進化を牽引してきた微細化はすでに行き詰まりつつあることから、3次元集積化や新材料、新アーキテクチャなどが新たな牽引役候補となりつつある。VLSIシンポジウムが将来の繁栄をもたらす、革新の種を見つける場になることを期待する。
シンポジウムの全体的なスケジュールは以下のようになっている。基本的には曜日によって予定が決まる。始まりは日曜である。8日と9日がプレイベント、10日~12日がメインイベント(技術講演会:テクニカルカンファレンス)と進む。火曜と水曜の午前には基調講演が実施される。
8日にはスペシャル・ワークショップ1件、レギュラー・ワークショップ12件が開催される。「スペシャル」は午後1時~午後7時までと時間がかなり長い。「FET発明100周年」をテーマに議論する。
「100周年」という表現に違和感を覚える読者は少なくないだろう。一般的には、トランジスタは1947年にベル研究所の研究者チームが発明したとされているからだ。しかし事実はいささか異なる。オーストリア-ハプスブルグ帝国の物理学者ユリウス・エドガー・リリエンフェルド(Julius Edgar Lilienfeld)が1925年にカナダ、1926年に米国で電界効果トランジスタ(FET)の特許を申請していた。リリエンフェルドはFETに関する学術論文を発表しなかったことと、試作品の製造が困難であったことから、この発明はほとんど知られずにいた。
ベル研究所によるトランジスタの発明以降、リリエンフェルドの業績が発掘され、再評価された。1989年には米国物理学会が「リリエンフェルド賞(Julius Edgar Lilienfeld Prize)」を創設し、毎年1回、受賞者を選出している。
レギュラー・ワークショップは3つの時間枠に分かれる。午後1時~午後3時に2件が同時並行で、午後3時30分~午後6時に5件が同時並行で、午後7時~午後9時30分に5件が同時並行で実施される。
9日のショートコースは「AIづくし」
9日はショートコース(技術講座)を予定する。共通のテーマに基づいた複数の講演で構成される。共通テーマはデバイス・プロセス技術側で1つ(番号はSC1)、回路技術側で1つ(番号はSC2)あり、両者が同時並行で進行する。
デバイス・プロセス技術側の共通テーマは「Key VLSI Technologies in the AI Era(AI時代のカギとなるVLSI技術)」である。午前8時25分から午後4時30分までの予定時間で、合計で8件の講演を実施する。
回路技術側の共通テーマは「Circuits and Systems for AI and Computing (AIおよびコンピューティング向けの回路とシステム)」である。午前8時25分から午後5時25分までの予定時間で、合計で9件の講演を実施する。
月曜日夜のデモセッションにはワークショップの一部も参加
9日の夕方から夜には、恒例のデモセッション兼レセプションが実施される。10日以降に発表予定の研究成果を一部の有志がひと足早く、テーブルトップ形式で概要を展示する。今回は技術講演だけでなく、ワークショップの3件がデモセッションに加わった。
プレナリーセッションでは「DRAM」、「AI向けVLSI」、「AI向け半導体設計」、「エッジAI」の講演を予定
続く10日と11日の午前にはプレナリーセッションが実施される。それぞれ2件ずつの基調講演を用意した。いずれも招待講演である。
10日は、「Driving Innovation in DRAM Technology-Towards a Sustainable Future(持続可能な未来に向けてDRAM技術の革新を駆動する)」のタイトルでSK hynixのSeon Yong Cha氏が、続いて「Innovate VLSI for AI Growth(AIの成長に向けた革新的なVLSI)」と題してNVIDIAのJohn Y. Chen氏が講演する。
11日は、「Enabling Generative AI: Innovations and Challenges in Semiconductor Design Technologies(生成AIの実現:半導体設計技術における革新と課題)」のタイトルでMedia Tek USAのKou-Hung Lawrence Loh氏が、続いて「The evolution of edge AI: contextual awareness and generative intelligence(エッジAI革命:コンテキスト認識とインテリジェンス生成)」と題してSTMicroelectronicsのAlessandro Cremonesi氏が講演する。
パネル討論では技術側が環境問題、回路側が技術者育成を議論
10日以降のサブイベントにも触れよう。10日の夜にはパネル討論会(イブニングパネルディスカッション)を予定する。技術(テクノロジー)側の討論テーマは「What can semiconductor industry do for greener society?(半導体産業が環境により優しい社会のためにできることは何か)」である。回路側の討論テーマは「Practical Circuits & Technology Training:Academia vs. Industry – Where Do We Learn the Most?(実用的な回路と製造のトレーニング:アカデミア対企業-最も良く学べるのはどちらなのか)」であり、技術側と回路側では趣のかなり異なるテーマが並んだ。
投稿論文数は過去最高の前年ハワイ開催を再び更新
ここからは投稿論文と採択論文の傾向を説明しよう。投稿論文の件数(レイトニュースを除く)は2010年以降、2023年までは500件~600件で推移してきた。ところが前年(2024年)のハワイ開催で突然、前年比40%増、件数にして259件増の897件と激増し、過去最高を一気に更新した。
今年の京都開催も勢いが衰えない。投稿論文の件数は合計898件と前年ハワイ開催の897件をわずかに超え、過去最高を2年連続で更新した。
採択論文数は250件、採択率は27.8%である。前年はそれぞれ232件、26%だったので、今年はいずれもわずかに上昇したことが分かる。それでも2023年以前の平均34%に比べ、依然として門戸は狭い。
投稿数では中国がダントツ、採択数では北米と韓国が僅差でトップ2に
地域別に投稿論文数(レイトニュースを含む)を見ていくと、中国(香港とマカオを含む)が298件と最も多く、全体の3分の1近く(32.4%)を占める。次いで韓国が174件、北米(米国とカナダ)が161件、台湾が104件と続く。
国・地域別の採択論文数では、北米(米国とカナダ)が56件(採択率34.8%)、わずか1件差で韓国が55件(同31.6%)でトップ2を占める。第3位は50件(採択率16.8%)の中国である。それから欧州が36件(採択率41.4%)、台湾が23件(同22.1%)、日本が22件(同47.8%)となっている。
過去20年の国・地域別論文数推移を見ていくと、中国が投稿論文を2024年に急増させていることが分かる。採択論文でも中国の増加が目立つ。韓国は2020年以降、投稿の件数を徐々に増やしてきた。そのことが採択件数の増加傾向につながったように見える。
ショートコースと技術講演会の前売りが完売
参加登録の状況は主催者にとってうれしい悲鳴となりつつある。7日の時点で、9日のショートコースと10日~12日の技術講演会は予定枠を売り切ってしまい、公式Webサイトでは参加登録をクローズした。これはオンサイトでの追加登録が不可能なったことを意味する。個人的な経験で申し訳ないが、国際学会で完売を理由に現地登録を休止した例を知らない。混乱を避けるために現地登録を休止したことが、新たな混乱を呼んでしまうのではないかと、いささか心配だ。
現地参加ではなく、リモートのオンライン(オンデマンド)登録も一時的に停止しており、こちらは16日に再開する予定だという。
激増した投稿論文数と低下した採択率を受け、発表論文の品質はかなり高そうだ。次回以降のレポートでは、技術分野と回路分野の注目論文(ハイライト論文)をご報告したい。






























![[Amazon限定ブランド]CCL い・ろ・は・すラベルレス 2LPET ×8本 ミネラルウォーター 無味 製品画像:1位](https://m.media-amazon.com/images/I/41h0MHfvhkL._SL160_.jpg)



![【Amazon.co.jp限定】 伊藤園 磨かれて、澄みきった日本の水 2L 8本 ラベルレス [ ケース ] [ 水 ] [ 軟水 ] [ ペットボトル ] [ 箱買い ] [ ストック ] [ 水分補給 ] 製品画像:5位](https://m.media-amazon.com/images/I/41n0o65dSkL._SL160_.jpg)
























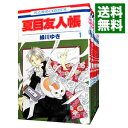
![予約の取れないセラピストの骨格小顔バンド [ 三木まゆ美 ] 製品画像:29位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/8296/9784865938296_1_16.jpg?_ex=128x128)
![ROCKIN'ON JAPAN (ロッキング・オン・ジャパン) 2026年 5月号 [雑誌] 製品画像:28位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/0561/4912097970561.gif?_ex=128x128)
![青天 [ 若林 正恭 ] 製品画像:27位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/0665/9784163920665_1_10.jpg?_ex=128x128)


![STORY (ストーリィ) 2026年 4月号 [雑誌] 製品画像:24位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/0464/4912054830464_1_2.jpg?_ex=128x128)
![ANIMATION WORKS「LUPIN THE IIIRD」シリーズ公式コンプリートブック [ MdN編集部 ] 製品画像:23位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/8389/9784295208389_1_2.jpg?_ex=128x128)
![だぶるぷれい 7【電子書籍】[ ムラタコウジ ] 製品画像:22位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rakutenkobo-ebooks/cabinet/1782/2000019711782.jpg?_ex=128x128)
![Numero TOKYO (ヌメロ・トウキョウ)4月号増刊 2026年 4月号 [雑誌] 製品画像:21位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/0466/4912172000466_1_2.jpg?_ex=128x128)