笠原一輝のユビキタス情報局
諸君らが愛してくれたVAIO Zに第12世代搭載製品はない、なぜだ?
2022年6月14日 10:58
「SX14が速いからさ……」とVAIOの関係者が言ったかどうかは定かではないが、実のところそれがVAIO Zの2022年モデルが登場しない理由の1つになっている。
VAIOから第12世代インテルCoreプロセッサ(以下第12世代Core)を搭載した2022年モデルのモバイルノートシリーズが発表された。今回発表されたのはVAIO SX14(VJS145)、VAIO SX12(VJS125)というVAIOの14型、12.5型のディスプレイを搭載し、最小構成では1kgを切るようなモバイルノートPCだ。発表概要などに関しては既報をご参照いただきたい。
しかし、その新しいラインナップの中には、VAIOがこれまでハイエンドとして販売してきたVAIO Zが製品ラインナップとしては用意されていない。VAIO株式会社 開発本部プロダクトセンター センター長 黒崎大輔氏は「第12世代Coreを搭載したVAIO Zは計画されていない」と述べ、VAIO Zの第12世代Core搭載製品は計画がないことを明らかにした。
その背景には、VAIO SX14が一部VAIO Zを上回るような機能を搭載しているなどしており、VAIO SX14だけでハイエンドまでカバーできるという状況が発生していること、さらには2022年モデルのVAIO SX14が、従来モデルのSX14はもちろんのこと、VAIO Zをも性能で上回っていることがある。
第12世代Core搭載のSX14とSX12が登場。一方VAIO Zの第12世代は計画なし
VAIOからVAIO SX14(VJS145)、VAIO SX12(VJS125)の2つの2022年モデルが発表された。といっても先代から製品名は同じで、どちらも14型ディスプレイ(4K UHDないしはフルHD)、12.5型ディスプレイ(フルHD)を搭載しているという基本的な骨格も変わりなく、SoCが第11世代Coreから第12世代Coreへと進化したことが大きな特徴となっている。
そうしたVAIO SX14、VAIO SX12の製品についての詳細は別途掲載されている発表記事をお読みいただくとして、ここでは同時に明らかになった、VAIO Zの第12世代搭載製品の計画がないという点について、いろいろと考えていきたい。
VAIO Zは2021年2月に発表されたVAIOのハイエンドノートPCで、いわゆるTiger Lake-H35と呼ばれてきた第11世代Core H35を搭載していることが最大の特徴となっている。第11世代Core H35は、もともとゲーミングPC向けとしてIntelが発表した製品で、下位グレードになる第11世代Core(UP3)に比べてCPUコア数は同じだが、ベースTDP(Thermal Design Power、熱設計消費電力)が28Wから35Wに引き上げられており、その分だけ高いクロック周波数で動くのが大きな違いとなっている。
本来第11世代Core H35はゲーミングPCに搭載され、単体GPU(dGPU)と組み合わせて利用することが前提になっていた。ゲーミングPCの中でも薄型のノートPC向けに用意されていたのが第11世代Core H35なのだ。
VAIO Zではその特性を逆手にとって、dGPUは搭載しないで、熱設計の機構(具体的にはヒートパイプの材質や構造、ファンの数など)に工夫を施すことで、PL2(Turbo Boost時に最大消費するターゲット電力)では64Wにも達するような大電力を流せるように設計し、第11世代Core(UP3)を搭載した製品よりも高い性能を実現した。それが最大の特徴となっていた。
そうしたVAIO Zだが、VAIO株式会社 開発本部プロダクトセンター センター長 黒崎大輔氏は「第12世代Coreを搭載したVAIO Zは計画されていない」と述べ、第12世代Coreを搭載したVAIO Zは計画がないと明らかにした。つまり、今後VAIO Zは徐々にフェードアウトしていき、VAIOが販売する製品のハイエンドは、VAIO SX14および、VAIO SX12がそれに該当することになる。
2021年秋の段階でもVAIO Zを一部上回っていたVAIO SX14。Zに対しての弱点を補強
実は2021年10月にVAIO SX14およびVAIO SX12の2021年型モデルを発表した段階で、すでにVAIO ZとVAIO SX14が機能的にオーバーラップしており、後から発表されたVAIO SX14の方がVAIO Zよりも機能が高いという逆転現象が発生していた。VAIO自身、VAIO Zの技術はSX14やSX12に波及していくものだと説明しており、それが現実になったということでもある。
その代表例は、VAIO SX14のディスプレイだ。4K UHD(3,840x2,160ドット)およびフルHD(1,920x1,080ドット)のパネルが選べる(CTOモデル選択時)のは同じだが、VAIO SX14はインセルタッチでペン(AES)対応のフルHDを選ぶことができるという点でVAIO Zを上回っていた。一方で、これはVAIO Zの方は意図的に外されている(デザインや軽量さを優先しているため)。
また、Gigabit EthernetやUSB Standard-A(いわゆるUSB-A)端子などが用意されており、ビジネスパーソンにとってはまだまだあった方がうれしい端子があるといった点でVAIO Zを上回っていた。
その反面、VAIO Zの方が明確に上回っていた部分もあった。それが、熱設計周りと、セルラーモデム(携帯電話回線を利用したWANのこと)だ。
具体的には、たとえば熱設計では、CPUファンがSX14の方は1つ、VAIO Zの方は2つになっており、そもそも廃熱能力はVAIO Zが勝っていると考えることができる。また、セルラーモデムはVAIO Zの明確なアドバンテージで、VAIO Zは5Gに標準対応していたが、SX14(2021年モデル)はLTEまでの対応となっており、5Gの高速通信はできなかった。
今回のSX14、SX12で注目なのはそうした、VAIO Zに比べて弱点になっていた2つのうち、セルラーモデムに関しては、CTOモデルでかつ「ALL BLACK EDITION」限定という制限は付くものの、5Gを選べるようになった(というよりも、ALL BLACK EDITIONは5Gしか選べない)。
そのSX14/SX12 ALL BLACK EDITIONに搭載されているセルラーモデムはデバイスマネージャで確認すると「Telit SDX55 PCIe EP modem」と表示されており、「Qualcomm Snapdragon X55 5G modem」を搭載したTelit社のFN98xシリーズを採用しているとみられている。おそらくVAIO Zに搭載されている5Gに対応したモデムと同じと考えてよいだろう。
このため、SX14でもALL BLACK EDITIONを選択し、モデムを5Gにすれば、この点でVAIO Zと機能差はなくなることになる。
第12世代Core Pシリーズに強化されたSX14は、第11世代Core H35のVAIO Zを性能で上回る
モデムの弱点はALL BLACK EDITION限定で解消しているとはいえ、熱設計に関してはVAIO Zの方が上じゃないか、というご指摘が飛んでくるだろうが、それはその通りだ。VAIO Zの熱設計はデュアルファン(SXシリーズはシングルファン)で、より高いPL2で留まるように設定されており、同じアーキテクチャのCPUであれば、VAIO ZとVAIO SX14を比較すれば、VAIO Zの方が高い性能を発揮するのは間違いない。
しかし、新しいVAIO SX14はCPUが第12世代Coreにアップグレードされた。それが製品の性能にどういう影響を与えているかが重要になってくる。
3つの製品のCPUを比較してみると、以下のようになる。なお、本紙の読者には改めて説明する必要はないと思うが、同じ世代のCPUでもグレードによって細かなスペックが異なるので、それぞれの製品の最上位グレードのCPUを紹介している(なお、厳密に言うとVAIO Zには2021年10月に追加されたVJZ142という製品があり、そちらにはさらに高速なCPUが採用されているが、今回は発売時のVJZ141の最上位グレードを取り上げている)。
| 【表1】VAIO SX14(VJS145)、VAIO Z(VJZ141)、VAIO SX14(VJS144)のCPU比較 | |||
|---|---|---|---|
| SX14(VJS145) 2022年夏モデル | VAIO Z(VJZ141) 2021年春モデル | VAIO SX14(VJS144) 2021年秋モデル | |
| SoC世代 | 第12世代 | 第11世代 | 第11世代 |
| 開発コードネーム | Alder Lake-P | Tiger Lake-H35 | Tiger Lake-UP3 |
| グレード | Core i7-1280P | Core i7-11375H | Core i7-1195G7 |
| CPUコア数 | 14コア | 4コア | 4コア |
| Pコア(相当) | 6コア | 4コア | 4コア |
| Eコア | 8コア | - | - |
| L3キャッシュ | 24MB | 12MB | 12MB |
| ブースト時最大周波数 | 4.8GHz | 5GHz | 5GHz |
| GPU | Iris Xe(96EU) | Iris Xe(96EU) | Iris Xe(96EU) |
| ベースパワー/TDPup(PL1) | 28W | 35W | 28W |
| 最大ターボパワー(PL2) | 64W | 64W | 64W |
こうしてみると、新しいVAIO SX14に採用されているCore i7-1280Pはアーキテクチャ的にも大きなジャンプアップであることがよく分かる。
第12世代CoreでIntelは「パフォーマンス・ハイブリッド・アーキテクチャ」と呼ばれる、2つの種類のCPUコアが存在する新世代のCPUを採用している。従来型のCoreプロセッサで採用されていたレイテンシ重視のPコア(パフォーマンス・コア)と、効率重視で大量のデータを一度に処理するような処理に向いているEコア(エフィシェンシー・コア)という2つのCPUを内包している。
新しいVAIO SX14に採用されているCore i7-1280Pでは、Pコアが6コア、Eコアが8コアになっている。従来の第11世代Coreを搭載したVAIO Zや2021年モデルのVAIO SX14はいずれもPコアが4コア相当なので、Pコアが2コア分とEコアが8コア増えていると考えられる。このため、特にマルチスレッド時にはその性能が大きく向上することになる。
では実際にベンチマークを利用して、3つのシステムを比較してみよう。今回はシステム全体の性能(メモリやストレージなどの性能を含む)ベンチマークではなく、CPUの違いを見ていくので、主にCPUに負荷をかけるテストになるCinebench R23を利用した。結果は以下の通りだ。
これを見て分かるように、新しいVAIO SX14はシングルスレッドでもVAIO Zを上回っており、特にマルチスレッド時には約30%の性能向上が認められる。これだけ性能が上がっていれば、VAIO Zのユーザーがより性能を得る乗り換え先、あるいはVAIO Zの代わりにSX14の購入を検討しているユーザーにとっては十分と言っていいだろう。
なお、先代のSX14から今回の新SX14への上がり幅はもっと大きく、72%もの性能向上になっている。これはGen to Genと呼ばれる1世代間の性能向上としてはかなり大きなジャンプだ。
ただ、よりフェアに言うのであれば、もし仮にVAIO Zの熱設計(たとえばデュアルファン)でSX14を設計していたら、もう少し性能が上がった可能性は高い。というのも、Cinebench R23というベンチマークテストは10分間で何回かテストを繰り返し、その中で一番低いスコアを性能としている。つまり、CPUの熱が増えて徐々に性能が低下するという現代のCPUの特性を上手く捉えるようになっている。
Core i7-1280Pを搭載した新しいVAIO SX14では、マルチスレッドのスコアは当初は約12,000と、最終結果の8,606よりも高いスコアをたたき出しており、徐々に10,000付近、9,000付近と下がっていき、最終的に8,606というスコアになった。その意味では、もう少し廃熱性能が優れていれば、さらにスコアが上がる可能性がある。
その可能性は否定できないが、VAIO SX14が10万円台からなのに対して、VAIO Zは20万円台からという価格設定だったことを考えれば、それはそれで妥当な判断というところではないだろうか。
技術的に考えれば、第12世代Core HなVAIO Z実現のハードルはPL2が115Wに引き上げられていること
最後に、マーケティングや商品としてのバリュー(有り体に言えば売れるかどうか)などの議論は抜きにして、技術的に考えてなぜ第12世代Coreを搭載したVAIO Zが難しいのかを筆者なりに考えてみたい。
VAIO Zが技術的に成り立たなくなった理由は2つあると考えている。1つはIntelのノートPC向けCPUのラインナップのうち、上位2つのTDPについて、45W(Core H45)だったのが55W(Core HX)、そしてVAIO Zに搭載していた35W(Core H35)が45W(Core H)へと、それぞれ枠が1つずつ上に引き上げられたことだ。
| 【表2】第11世代Core H35、第12世代Core Pシリーズ、第12世代Core HシリーズのTDP(PL1)、PL2 | |||
|---|---|---|---|
| 第11世代Core H35 | 第12世代Core Pシリーズ | 第12世代Core Hシリーズ | |
| TDP(ほぼPL1) | 35W | 28W | 45W |
| PL2 | 64W | 64W | 115W |
この影響は、特にTurbo Boost時の最大電力の値となるPL2に大きな影響を与えている。第11世代Core H35ではPL2は64Wの設定になっていた。それに対して、第12世代Core HではPL2は115Wへと大きく引き上げられている。
これは第12世代Core HがゲーミングPC向けを想定にしているためで、dGPUを搭載するようなゲーミングノートPCでは、GPUに供給する分の電力がある。GPUを使っていないときにそれをCPUに回せることなどを考えれば、特に問題のないスペックだと言える。
しかし、VAIO ZのようなモバイルノートPCでは、電源回路はそこまでの電力量を供給するような仕様になっていない。実際、VAIO Zでは最大64Wの電力を供給するようになっており、CPUの冷却に余裕がある場合には5GHzまでクロックを引き上げる。その後マザーボード上のセンサーなどにより規定の温度以下であれば、CPUをできるだけ高いクロックで動作させ、徐々にTDPで規定されているベースクロックまで下がって動作する。
仮に、VAIO Zの第12世代Core版をCore H45でフルに性能が出るように設計すると考えると、PL2を115Wに設定する必要があり、電源回路もそれだけの電力を流せるように設計する必要がある。
もし64Wのままであれば、PL2がそもそも64Wになっている第12世代Core Pシリーズ(SX14に搭載されているシリーズ)と同じになってしまい、性能は大して変わらないということになってしまう。特にPシリーズの最上位グレードCore i7-1280Pは、第12世代Core Hと同じ14コア(Pコア:6コア、Eコア:8コア)の構成で、性能差はPL2の設定に依存することが大きいからだ。
そこで、そうならないようにPL2を115Wに引き上げるとすると、2つの問題が発生する。1つはそれに合わせて放熱機構を大きくしないといけないこと、もう1つが電源周りの設定をそれに合わせて強化しないといけないことだ。
当然基板の電源部分が大きくなり、基板のサイズを変えたりする必要があるし、そもそも付属している65WのACアダプタ(USB Type-C、UBS PD)では電力をまかないきれなくなる。現行のVAIO Zでもフルパワー時には足りない分をバッテリからもらっているぐらいだから、仮に第12世代Core H搭載VAIO Zを設計すると考えると、USB PD 3.0に対応した100Wを超えるUSB Type-CのACアダプタが必要になり、こちらも大きくなってモバイル性が損なわれることになる。
技術的に考えると、こうした足かせがあるため、VAIO Z+第12世代Core Hというのは技術的にも、SX14が第12世代Core Pシリーズを採用して性能を伸ばしているという現実を前に商品性的にも、実現が難しかった、そういうことではないだろうか。
だが、これまでVAIOはそうしたハードルを乗り越えて、そう来たか! という製品をリリースしてきたPCメーカーだ。その意味で、次世代ではそうした技術的な足かせなどを乗り越えて、VAIO Zの復活希望! ということで、この記事のまとめとしたい。
















![[Amazon限定ブランド]CCL い・ろ・は・すラベルレス 2LPET ×8本 ミネラルウォーター 無味 製品画像:1位](https://m.media-amazon.com/images/I/41h0MHfvhkL._SL160_.jpg)



![【Amazon.co.jp限定】 伊藤園 磨かれて、澄みきった日本の水 2L 8本 ラベルレス [ ケース ] [ 水 ] [ 軟水 ] [ ペットボトル ] [ 箱買い ] [ ストック ] [ 水分補給 ] 製品画像:5位](https://m.media-amazon.com/images/I/41n0o65dSkL._SL160_.jpg)
















![DELL OptiPlex 7090 SFF (Win11x64) 中古 Core i7-2.5GHz(11700)/メモリ16GB/HDD1TB/DVDマルチ [C:並品] 製品画像:3位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/usedpc/cabinet/url1/5726315c.jpg?_ex=128x128)






![【❤最安挑戦❤+LINEクーポン】新発売 [1+1年保証] モニター 100Hz 21.5インチ 23.8インチ 27インチ pcモニター 1ms応答 パソコン モニター 1920*1080 FHD ゲーミングモニター 非光沢 VA 角度調整 VESA Freesync pc/switch/ps4/ps5/xbox スピーカー内蔵 製品画像:9位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/qifeng/cabinet/10653721/10653722/imgrc0112340482.jpg?_ex=128x128)
![WINTEN モバイルモニター 15.6インチ テレワーク/デュアルモニター/サブモニターに最適!ゲーミング 1080P FHD IPSパネル 軽量 薄型 非光沢 カバー付 ミニPC Switch iPhone Type-C/HDMI接続 [1年保証] WT-156H2-BS 5523 製品画像:8位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/win10/cabinet/monitor/imgrc0112809238.jpg?_ex=128x128)
![ASUS|エイスース PCモニター Eye Care ブラック VA24DQLB [23.8型 /フルHD(1920×1080) /ワイド /75Hz] 製品画像:7位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/biccamera/cabinet/product/6626/00000009413787_a01.jpg?_ex=128x128)



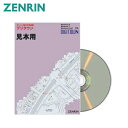

![彗星起源感覚 市川春子イラストレーションブック2 [ 市川 春子 ] 製品画像:28位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/4858/9784065424858_1_3.jpg?_ex=128x128)
![BLUE GIANT MOMENTUM(7) (ビッグ コミックス) [ 石塚 真一 ] 製品画像:27位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/8536/9784098638536_1_20.jpg?_ex=128x128)
![『街道をゆく』全43巻+夜話 3大特典付き 完全予約販売BOXセット [ 司馬遼太郎 ] 製品画像:26位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/1188/9784022681188_1_3.jpg?_ex=128x128)
![[新品]ジョジョの奇妙な冒険 [新書版] (1-63巻 全巻) 全巻セット 製品画像:25位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/mangazenkan/cabinet/syncip_0003/si-01_01.jpg?_ex=128x128)
![【楽天ブックス限定デジタル特典】「修学旅行で仲良くないグループに入りました」ドラマ公式ビジュアルブック(公式ビジュアルブック撮影裏側動画配信データ - 2人きりの修学旅行編) [ ABC ] 製品画像:24位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/8092/9784046858092_1_3.jpg?_ex=128x128)
![【楽天ブックス限定グッズ】堀夏喜 1st写真集『LIVING FOR』(オリジナルキーホルダー) [ 堀 夏喜(FANTASTICS) ] 製品画像:23位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/7242/2100014637242_1_2.jpg?_ex=128x128)
![隔週刊 水曜どうでしょうDVDコレクション 2026年 3/31号 [雑誌] 製品画像:22位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/0361/4912301750361.gif?_ex=128x128)
![【楽天ブックス限定抽選特典】【クレジットカード決済限定】CANDY TUNE 3rd Anniversary写真集(仮)(オンラインラッキードロー抽選権) [ CANDY TUNE ] 製品画像:21位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/2708/2100014832708_1_2.jpg?_ex=128x128)