笠原一輝のユビキタス情報局
TDPが上がった第12世代Core HXは、ノートPCの新しいデザインポイントを実現する
2022年5月16日 09:14
Intelは5月10日(現地時間、日本時間5月11日)に、同社がAlder Lake-HXの開発コードネームで開発してきた第12世代Core HXプロセッサ(以下第12世代Core HX)を発表した。
第12世代Core HXは、従来はデスクトップPCだけに投入されてきた16コア(Pコア×8+Eコア×8)で24スレッド(Pコア:16スレッド、Eコア:8スレッド)の構成を、ノートPC向けのBGAパッケージに変更し、TDPを55Wに設定することで、以前から提供してきた第12世代Core Hプロセッサ(以下第12世代Core H)に比べてより高い性能を発揮するようにした製品となる。Intelは第12世代Core HXを、モバイルワークステーション向けやハイエンドなゲーミングノートPC向けと位置づけている。
そうした第12世代Core HXや、今後のノートPC向けの製品開発の方向性などに関して、ノートPC向けの製品を担当しているモバイル製品マーケティング 上席部長 ダン・ロジャース氏にお話しを伺ってきた。
モバイルワークステーション、ハイエンドゲーマー向けの製品となる第12世代Core HX
冒頭でも紹介した通り、Intelは5月10日(日本時間5月11日)に、米国テキサス州ダラスで開催した「Vision 2022」において、第12世代Coreプロセッサの製品としては「最後のシリーズ」(上級副社長 兼 クライアントコンピューティング事業本部 事業本部長 ミッシェル・ジョンストン・ホルトス氏)として第12世代Core HXを発表した。
Intelは昨年(2022年)の10月にデスクトップPC向けとなる第12世代Coreプロセッサ Sシリーズ(以下第12世代Core S)を発表し、1月にはゲーミングPC向けとなる第12世代Core H、2月には薄型ノートPC向けの第12世代Coreプロセッサ Pシリーズ(以下第12世代Core P)と第12世代Coreプロセッサ Uシリーズ(以下第12世代Core U)を順次リリースしてきた。ホルトス氏の言葉を借りれば今回発表された第12世代Core HXは第12世代としては最後の製品で、第12世代の各製品シリーズは出そろったことになる。
このことを言い換えれば、今年の後半にリリースされる予定であることが明らかにされている次世代デスクトップ向けCPU「Raptor Lake」はもう第12世代ではないということをIntelが公式に認めたということでもある。
| 第12世代Core Sシリーズ | 第12世代Core HXシリーズ | 第12世代Core Hシリーズ | 第12世代Core Pシリーズ | 第12世代Core Uシリーズ | |
|---|---|---|---|---|---|
| ターゲット市場 | デスクトップPC | モバイルワークステーション/ゲーミングPC | ゲーミングPC/コンテンツクリエーション | 薄型ノートPC | 超薄型ノートPC/タブレット |
| パッケージ | LGA+PCH | BGA+PCH | BGA(1チップ) | BGA(1チップ) | BGA(1チップ) |
| TDP(PL1) | 125W | 55W | 45W | 28W | 15W/9W |
| マックスターボブースト(PL2) | 241W | 157W | 115W | 64W | 55W/29W |
モバイル製品マーケティング 上席部長 ダン・ロジャース氏は、第12世代Core HXに関して「ターゲットとしているのはハイエンドゲーマーやクリエイターとなる。たとえば3Dモデリングのソフトウェアを利用しているユーザーなどはもっと処理能力を欲しがっているし、ハイエンドゲーマーは言うまでもない。そうしたユーザー向けにさらなる高性能をお届けする製品、それがCore HXになる」と述べ、第12世代CoreのノートPC向け製品に新しいデザインポイントとより高い性能を実現するための製品になると説明した。
第12世代Core HXのTDPが55Wに引き上げられているのはOEMメーカーの自由度を高めるため
第12世代Core HXが追加されたことで、第12世代Coreの熱設計の観点でのデザインポイントは5つになった。それにより、前世代の第11世代Coreのデザインポイント数の5つに戻った。ただし、Hシリーズは、第11世代では45W(2チップ)と35W(1チップ)という構成だったのに、第12世代では55W(HX、2チップ)と45W(H、1チップ)という構成になり、それぞれTDP(Thermal Design Power、熱設計消費電力)の値が10W引き上げられている。
| 第11世代 | 第12世代 | |
|---|---|---|
| 開発コードネーム | Tiger Lake | Alder Lake |
| 55W | - | HXシリーズ(BGA+PCH) |
| 45W | Hシリーズ(BGA+PCH) | Hシリーズ(BGA) |
| 35W | Hシリーズ(UP3) | - |
| 28W | Uシリーズ(UP3) | Pシリーズ(BGA) |
| 15W | Uシリーズ(UP3)/Uシリーズ(UP4) | Uシリーズ(BGA) |
| 9W | Uシリーズ(UP4) | Uシリーズ(BGA) |
こうしたデザインポイントの変更に関してロジャース氏は「TDPの定義は非常に複雑だが、我々としてはOEMメーカーの選択肢を増やすというのが基本的な考え方だ。このため、今回の製品では55Wという新しいデザインポイントを提供している。それによりノートPCメーカーは、ラインナップを増やすことが可能になり、新しいカテゴリの製品に取り組むことができる」と述べ、Core HXで新しい55WというTDPの枠を導入したのは、ノートPCメーカーに高性能なノートPCを作ることを可能にするためだと説明した。
よくTDPの枠を引き上げたから、バッテリ駆動時間は短くなっているに違いないという指摘を見るのだが、それは大きな誤解だ(CPUがノートPCのバッテリ駆動時間に与える影響を示す指標としては、「平均消費電力」という別の指標がある)。TDPというのは、ピーク時の消費電力ではないし、平均消費電力でもない。
TDPとはCPUメーカーがスペックとして規定しているベースクロックで動作させるために、そのベースクロックで動作している時に発生する熱に相当する消費電力の値のことだ。CPUがベースクロックで動作している時に、そのTDP相当の電力をかけて発生する熱を、ノートPC側の放熱機構が処理する(=CPUの温度を規定温度内に留める)という設計をノートPCメーカーが行なう時に、参照するスペックがTDPであって、消費電力そのものではないのだ。
実際のところ、現代のCPUは、Intelで言えば「Turbo Boost Technology」のように、CPUが規定温度以下であればベースクロックよりも高いクロックで動くように設計されているので、たとえば2GHzのベースクロックのCPUがターボモードの3GHzで動作していれば、CPUの消費電力はTDPよりも高くなっている(IntelのCPUではそのターボ時のピーク電力のことをPL2やマックスターボパワーといい、Core HXでは157Wになっている)。TDPというのはあくまで熱設計時に設計上参照すべき仕様であって、それをもって消費電力が多い、少ないということを議論する数値ではないのだ。
今回の第12世代Core HXではTDP(≓PL1)も、そしてマックスターボパワー(=PL2)も引き上げられており、ノートPCメーカーの設計によってはPL2近くで長く留まったりすることが可能なように設計にもできるようになっている(その場合には電源回路や放熱などを、標準設計よりも高負荷に耐えうるように設計することが必要になる)。もちろんより高度な放熱機構や電源回路はそれだけスペースを取ることになるが、それでもとにかく高性能をというユーザーが多いのが、モバイルワークステーションやハイエンドゲーミングPCのユーザーだ。そうした新しいノートPCの設計を可能にするのが今回発表された第12世代Core HXの大きな意味なのだ。
実際、今回Visionで展示された第12世代Core HX搭載のノートPCはいずれも、やや大型のディスプレイを搭載した製品になっており、熱設計に関しても、かなり巨大なCPUクーラーなどを搭載した製品ばかりだ。
つまり、ニーズとしてはデストップPCの代替(デスクトップリプレースメント)のモバイルワークステーションやゲーミングノートPCというのが、各ノートPCメーカーのターゲットということになり、そうしたデスクトップPC級の性能が必要だけど、無理すれば持ち歩けるノートPCが欲しい、そうしたユーザー向けのノートPCがCore HX搭載のノートPCだということができるだろう。
第12世代はパフォーマンス・ハイブリッド、平均消費電力の削減は将来世代で実現へ
今回発表された第12世代Core HXに限った話ではないが、開発コードネーム「Alder Lake」がつけられている第12世代Coreは、Intelがハイブリッド・アーキテクチャと呼んでいる、低レイテンシで高クロック動作を実現する性能重視のPコア(パフォーマンスコア)と、低消費電力でコア数を稼げる効率重視のEコア(エフィシェンシーコア)という2つの種類のCPUコアから構成されている。
ハイブリッド・アーキテクチャそのものは、別にAlder Lakeで初めて導入されたものではない(第10世代Coreのバリエーションとして投入されたLakefieldで導入済み)し、ArmアーキテクチャのCPUでは「big.LITTLE」という名称でおなじみのアーキテクチャだ。高性能で動作する時にはIntelで言うところのPコアで動作し、アイドル時にはIntelで言うところのEコアに切り替えて動作することで、低消費電力を実現してバッテリ駆動時間を延ばす仕組みになっている。平均消費電力と呼ばれる、システムの電源を入れてから切るまでにCPUが消費する電力の平均を下げることで、バッテリ駆動時間を延ばす、それが狙いになる。
では第12世代Coreではどうかというと、第12世代Coreの平均消費電力は、1つ前の世代でハイブリッド・アーキテクチャには未対応となる第11世代Core(Tiger Lake)とほぼ同じで、その観点では大きな強化にはなっていないという。
ロジャース氏は「我々は第12世代Coreのアーキテクチャを設計する時に、ハイブリッド・アーキテクチャを性能重視のためと位置づけた。そのため、バッテリ駆動時間という観点では第12世代は第11世代とほぼ変わらないレベルになっているが、パフォーマンスに関しては大きく向上している」と説明する。
あくまで、今の世代の「パフォーマンス・ハイブリッド・アーキテクチャ」と位置づけてハイブリッド・アーキテクチャは、性能を上げるための手法だというのがIntelの立場なのだ。
では、将来的にハイブリッド・アーキテクチャはそうした使い方のみなのかと言えば、ロジャース氏によれば将来はバッテリ駆動時間を延ばす方向に使う可能性も検討していると示唆した。「ハイブリッド・アーキテクチャにはさまざまな可能性がある。将来の世代ではそれをバッテリ駆動時間に利用する可能性はある」と述べ、どの世代になるかなど具体的なことは明言しなかったが、将来の世代ではハイブリッド・アーキテクチャを、平均消費電力を下げる、つまりはバッテリ駆動時間を延ばす方向に使う可能性もあるとした。
Intelは今回のVision 2022の展示会場で、第12世代Coreの次世代製品となるMeteor Lakeの実物を展示した。しかし、その詳細に関しては特に語らず、今年の2月に発表されたMeteor Lakeの内容から特にアップデートはなかった。
ロジャース氏がいう平均消費電力を下げる方向にハイブリッド・アーキテクチャを使うのは次世代のMeteor Lakeなのか、その次のArrow Lakeなのか、3世代先のLunar Lakeなのかは分からないが、高性能でかつ長時間バッテリ駆動のノートPCが欲しいと思う1ユーザーとして、そうした方向に進むことに期待したいところだ。

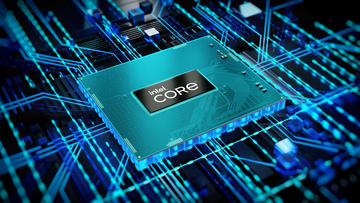











![[Amazon限定ブランド]CCL い・ろ・は・すラベルレス 2LPET ×8本 ミネラルウォーター 無味 製品画像:2位](https://m.media-amazon.com/images/I/41h0MHfvhkL._SL160_.jpg)











![NEC|エヌイーシー ノートパソコン LAVIE SOL(S1355/LAP) フェアリーパープル PC-S1355LAP [13.3型 /Windows11 Home /intel Core i5 /メモリ:16GB /SSD:512GB /Office Home and Business /2025年秋冬モデル] 製品画像:1位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/biccamera/cabinet/product/14696/00000014542232_a01.jpg?_ex=128x128)







![紫雲寺家の子供たち 9【電子書籍】[ 宮島礼吏 ] 製品画像:30位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rakutenkobo-ebooks/cabinet/8892/2000019768892.jpg?_ex=128x128)
![おやおや、おやさい (福音館の劇場版シリーズ) [ 石津ちひろ ] 製品画像:29位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/0391/9784834080391_1_3.jpg?_ex=128x128)
![もりのおふろ (福音館の劇場版シリーズ) [ 西村敏雄 ] 製品画像:28位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/4838/9784834024838_1_3.jpg?_ex=128x128)
![芸術新潮 2026年 3月号 [雑誌] 製品画像:27位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/0364/4912033050364_1_2.jpg?_ex=128x128)
![晴れ晴れ日和 8【電子書籍】[ 吉村佳 ] 製品画像:26位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rakutenkobo-ebooks/cabinet/0341/2000019730341.jpg?_ex=128x128)
![リビルドワールド 15【電子書籍】[ 綾村 切人 ] 製品画像:25位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rakutenkobo-ebooks/cabinet/0638/2000019730638.jpg?_ex=128x128)
![無職転生 〜異世界行ったら本気だす〜 24【電子書籍】[ フジカワ ユカ ] 製品画像:24位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rakutenkobo-ebooks/cabinet/6100/2000019696100.jpg?_ex=128x128)
![オタク同僚と偽装結婚した結果、毎日がメッチャ楽しいんだけど!(4)【電子書籍】[ 七十 ななそ ] 製品画像:23位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rakutenkobo-ebooks/cabinet/0656/2000019730656.jpg?_ex=128x128)
![青天 [ 若林 正恭 ] 製品画像:22位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/0665/9784163920665_1_10.jpg?_ex=128x128)
![チラチラ(6)【電子書籍】[ 小窓際 ] 製品画像:21位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rakutenkobo-ebooks/cabinet/1686/2000019711686.jpg?_ex=128x128)