Hothotレビュー

ミドルレンジだが質感が大きく向上した「Google Pixel 6a」
2022年7月22日 02:00
Googleは、最新ミドルレンジスマートフォン「Pixel 6a」を7月28日に発売する。製品自体は、5月11日(現地時間)に米国で開催された「Google I/O 2022」において発表済みで、日本でのGoogleストアでの直販価格は5万3,900円、auおよびソフトバンクからも発売されることが発表されている。予約開始は既に開始されており、発売は7月28日を予定。今回いち早く実機を試用する機会を得たので、ハード面を中心に紹介する。
アルミフレームと背面ガラスの採用で質感が大きく向上
Pixel aシリーズは、同世代のPixelシリーズに搭載されるカメラをはじめとした各種機能をほぼそのまま受け継ぎつつ、比較的安価な価格で販売されるミドルレンジモデル、という位置付けのシリーズだ。それについてはPixel 6aも変わっていない。主なスペックは、表1にまとめたとおりだ。
| Pixel 6aの主な仕様 | |
|---|---|
| SoC | Google Tensor |
| メモリ | 6GB |
| 内蔵ストレージ | 128GB |
| セキュリティチップ | Titan M2 |
| OS | Android 12 |
| 更新 | 5年間のPixelアップデート(Androidアップデート3年、セキュリティアップデート5年) |
| ディスプレイ | 6.1型有機EL、1,080×2,400ドット、アスペクト比20:9、HDR、リフレッシュレート最大60Hz |
| 背面カメラ | 超広角:F値2.2、画角114度、1,200万画素センサー(ピクセルピッチ1.25μm) 広角:F値1.7、画角77度、1,220万画素 1/2.55型センサー(ピクセルピッチ1.4μm)、光学式手ブレ補正 |
| 前面カメラ | F値2.0、画角84度、800万画素センサー(ピクセルピッチ1.12μm) |
| モバイル通信 | 5G Sub-6:n1/2/3/5/7/8/12/20/25/28/30/38/40/41/48/66/71/77/78 4G LTE:B1/2/3/4/5/7/8/12/13/14/17/18/19/20/25/26/28/29/30/38/39/40/41/42/48/66/71 3G:1/2/4/5/6/8/19 GSM:850/900/1,800/1,900MHz |
| 対応SIM | nanoSIM+eSIM |
| 無線LAN | IEEE 802.11ax(Wi-Fi 6) |
| Bluetooth | Bluetooth v5.2 |
| センサー | 近接センサー、環境光センサー、加速度センサー、ジャイロセンサー、磁力計、気圧計 |
| おサイフケータイ | 対応 |
| 防水・防塵 | IP67 |
| 生体認証性能 | ディスプレイ埋め込み型指紋認証センサー |
| 外部ポート | USB Type-C |
| バッテリ容量 | 標準4,410mAh |
| サイズ(幅×奥行き×高さ) | 71.8×152.2×8.9mm |
| 重量 | 178g |
| カラー | Sage、Chalk、Charcoal |
ところで、Pixel 6aでは従来までのPixel aシリーズからかなり大きく変わっている部分がある。それは外観だ。
従来のPixel aシリーズは、コストダウンのために樹脂の筐体を採用するなど、見た目にやや安っぽい印象があった。昨年(2021年)登場したPixel 5a 5Gでは、樹脂筐体ではなく金属製ユニボディとなったものの、基本的なデザインコンセプトはそれ以前のPixel aシリーズから大きく変わっておらず、金属製ながらあまり高級感が感じられなかったのも事実だ。
それに対しPixel 6aは、Pixel 6シリーズと同じように、側面にアルミフレーム、背面に強化ガラスを採用することで、質感が大きく高められている。実機を手に取ってみても、従来までのPixel aシリーズのような安っぽさは全くといっていいほど感じられない。なお、アルミフレームには再生アルミニウムを採用しているという。
また、本体デザインもPixel 6シリーズとほぼ同等のものとなっている。
筐体の角は、従来のPixel aシリーズでは、比較的大きいなだらかなカーブとなっていたのに対し、Pixel 6aはPixel 6シリーズ同様に比較的小さなカーブとなり、全体的に直線的なイメージが強くなった。さらに、背面のカメラユニットは、Pixel 6シリーズ同様の左右側面まで達する帯状の突起にカメラを配置する「Pixelカメラバー」を採用している。
これらによってPixel 6aは、質感やデザインはPixel 6シリーズとほぼ同等となり、ミドルレンジモデルながら高品質なスマートフォンという印象を強く感じられるようになっている。これは、見た目や質感を重視する人にとって、かなり大きな進化点と言っていいだろう。
なお、背面ガラスは、Pixel 6シリーズでは米Corning製強化ガラスのGorilla Glass 6またはGorilla Glass Victusを採用しているのに対し、Pixel 6aではGorilla Glass 3を採用。この違いはコストダウンの影響と考えられるが、それでもスマートフォンとして十分な強度を備えており、ミドルレンジモデルと考えても十分納得できる。
カラーは、Sage Green、Chalk White、Charcoalの3色をラインナップ。カメラバーの上下でわずかに色合いが変えられている点もPixel 6シリーズ同様だ。今回試用したのはグレーを基調とするCharcoalだったが、落ち着いた印象で、背面ガラスによって光沢感があり、手に持ったときのツルツルとした感触と合わせて、申し分ない質感と感じた。
Pixel 5a 5Gと比べ、サイズは小さく重量も軽くなった
サイズは、71.8×152.2×8.9mm(幅×奥行き×高さ)。Pixel 5a 5Gは73.2×156.2×8.8mm(同)だったため、厚さこそ0.1mm増えているが、幅が1.4mm、奥行きが4mm短くなっている。双方を並べてみると、ひとまわり小さくなったという印象で、比較的ボディはコンパクトとなっている。
今回は手元にPixel 6がなかったため、Pixel 6 Proとも比較してみたが、かなり大型ボディのPixel 6 Proとの比較ではPixel 6aのコンパクトさがより際立つ。筆者は比較的手が大きいこともあるが、実際に手にしてみても、片手で楽に持って操作できるという印象だった。
以前のPixelシリーズは、よりコンパクトなモデルもあったため、Pixel 6aが特別コンパクトとは言えないだろう。それでも、このところ大型化が顕著となっているスマートフォンの中では比較的コンパクトな部類で、手の小さな人でも比較的扱いやすいはずだ。
また、重量が比較的軽い点も嬉しい部分。Pixel 6aの重量は公称178g。実測の重量もSIM非装着で177.9gと、公称とほぼ同じだった。筐体サイズが小型化していることもあるが、Pixel 5a 5Gの重量が183gだったため、Pixel 6aは5g軽くなった計算。手にすると、その差はほとんど感じられなかったものの、重量が210gのPixel 6 Proと持ち比べてみると、その差は歴然。近年は、重量が200gを超えるスマートフォンも珍しくないとはいえ、やはり重量は軽い方がありがたいのは間違いなく、Pixel 6aの軽さも大きな魅力となるはずだ。
アスペクト比20:9の6.1型有機ELパネルを採用
ディスプレイは、アスペクト比20.9、表示解像度1,080×2,400ドットの6.1型有機ELパネルを採用している。4辺狭額ベゼル仕様となるが、Pixel 6シリーズ同様に上部中央に前面カメラ用のパンチホールが空けられている。また、ディスプレイ表面のガラスには、背面ガラス同様に米Corning製強化ガラス、Gorilla Glass 3を採用している。
Pixel 4a 5Gはディスプレイサイズが6.34型だったため、Pixel 6aではわずかながらサイズが小さくなっている。筐体が小型化しているのは、ディスプレイサイズが小さくなったことも影響していると言える。
コントラスト比は100万:1以上、HDR表示にも対応と、有機ELパネルらしい優れた表示性能を備えている。実際に写真や映像を表示してみても、非常に鮮やかに表示される。これなら、さまざまなコンテンツを申し分ないの発色で楽しめるだろう。
なお、リフレッシュレートは60Hz対応となっており、Pixel 6やPixel 6 Proのように90Hzや120Hzといった高リフレッシュレート表示は非対応。このあたりはコストダウンによるものと考えていいだろう。
背面カメラの仕様が一部落とされている
カメラの仕様は、Pixel 6シリーズと同等とはなっておらず、背面カメラの仕様が一部落とされている。
背面カメラは、広角レンズと超広角レンズの2眼仕様となる点と、超広角レンズ側の仕様はF値2.2、画角が114度のレンズと、1,200万画素センサー(ピクセルピッチ1.25μm)との組み合わせとなる点はPixel 6と同じとなる。
それに対し広角レンズの仕様は、Pixel 6ではF値1.85、画角が82度で光学手ブレ補正機能を備えるレンズと、5,000万画素の1/1.31型(ピクセルピッチ1.2μm)Octa PD Quad Bayerセンサーとの組み合わせだったが、Pixel 6aではF値1.7、画角が77度で光学手ブレ補正機能を備えるレンズと、1,220万画素の1/2.55型センサー(ピクセルピッチ1.4μm)の組み合わせに変更されている。つまり、広角レンズ側は画角がやや広くなるとともに、撮像素子がやや小さくなり、画素数が落とされているわけだ。
このPixel 6a背面カメラの広角レンズ側の仕様は、Pixel 4やPixel 4a/5a 5Gとほぼ同じだ。これも、コストダウンの影響によるものと考えていいだろう。コスト的にPixel 6と同等の背面カメラを搭載するのは難しかったのかもしれないが、Pixel 6のカメラから仕様が落とされている点は少々残念だ。
また、撮影機能も一部省かれている。夜景モードやポートレートモード、4K/60FPS動画撮影、1/8倍およ1/4倍のスローモーション動画撮影、タイムラプスなどは用意されているものの、Pixel 6に搭載されていたモーションモードが省かれている。このあたりは、広角レンズ側の仕様変更による影響と思われる。
なお、前面カメラはF値2.0、画角84度のレンズに、ピクセルピッチ1.12μmの800万画素センサーの組み合わせでパンフォーカス仕様となっており、こちらはPixel 6と同じだ。
このように、背面カメラや撮影機能に一部変更が見られるものの、実際の写真のクオリティは申し分ないものとなっている。等倍まで拡大すると、細部などやや解像度の甘さが見られる部分もあるが、Pixelシリーズでおなじみの、非常に明るく撮影できる夜景モードなども十分満足できるものとなっている。少なくとも、ミドルレンジスマートフォンで撮影できる写真と考えると、十分満足できるクオリティと言える。
新たに“カモフラージュモード”を追加
Pixel 6aでは、カメラ関連で新たな機能が追加されている。それは「カモフラージュモード」というものだ。
カモフラージュモードは、写真に写り込んだ人などをAI処理で削除して目立たなくする「消しゴムマジック」の派生機能で、文字通り写真に写り込んだものを目立たなくするための機能だ。消しゴムマジック同様に、撮影後の編集機能から呼び出して利用する。
例えば、記念写真を撮影したり、風景写真を撮影したときなど、背景に派手な色の物体が写り込んで目障り、という場合などに、その目障りな物体をAI処理で目立たない色合いに自動修正してくれる。消しゴムマジックのように、写り込んだ物体を削除するわけではないが、色合いを修正するだけでも、かなり雰囲気を高めることができる。
カモフラージュモードの利用手順は次の通り。撮影した写真をフォトアプリで表示し、下部の編集ボタンをタップ。次に、「ツール」から「消しゴムマジック」を選択し、「カモフラージュ」を選択。そして、不要な部分をなぞるか、指で○印を付けると、AI処理で物体を認識し、その周囲の背景に溶け込むような色合いに修正される。消しゴムマジックのように、修正する部分をAIが自動選択し提案される場合もある。
実際に、猫を写した写真で試してみたが、元の写真では後方に赤い洗面器やバッグが写り込んでやや目障りだが、カモフラージュモードで修正するとそれらが背景に溶け込む色に修正され、より猫が浮かび上がる写真となった。
修正前と後、どちらがいいかは見る人の印象によって変わるとは思うが、個人的にはなかなか使える機能と感じた。
SoCにはPixel 6シリーズと同じGoogle Tensorを採用し、AI機能も充実
主なスペックは、冒頭の表1にまとめたとおりだが、SoCはPixel 6シリーズと同様に、GoogleオリジナルSoCのGoogle Tensorを採用している。セキュリティチップのTitan M2も搭載しており、このあたりの仕様はPixel 6シリーズと全く同じだ。ただし、RAMは6GB、内蔵ストレージは128GBと、Pixel 6シリーズよりも抑えられている。外部ストレージとしてmicroSDが利用できない点はPixel 6と同じだ。
SoCにGoogle Tensorを採用しているため、Pixel 6とほぼ同等のAI関連機能も利用できる。例えば、翻訳アプリを利用した自然言語のリアルタイム翻訳や、チャット、メッセージなどのリアルタイム翻訳、ライブ配信動画の自動字幕起こし、録音アプリを利用した音声の自動文字起こしなどが行なえる。これらは事前に翻訳用のデータをダウンロードしておけば、オフラインでも利用可能だ。
モバイル通信は、5G Sub-6対応(対応バンドは表1のとおり)。対応SIMは、nanoSIMとeSIMに対応しており、双方の同時利用も可能。
無線LANは、IEEE 802.11ax準拠。ハードウェアとしては6GHz帯域を利用するWi-Fi 6Eもサポートしているが、日本ではWi-Fi 6Eの利用認可が下りていないため、現時点では利用不可能となっている。BluetoothはBluetooth 5.2準拠。
生体認証機能は、Pixel 6同様にディスプレイ埋め込み型指紋認証センサーを採用。ただ、Pixel 6に比べてやや認証速度が遅い印象だ。
防水防塵性能はIP67準拠。また、おサイフケータイもサポートしている。センサー類は、近接センサー、環境光センサー、加速度センサー、ジャイロメーター、磁力計、気圧計を搭載。OSはAndroid 12で、5年間のアップデートも保証されている。
物理ボタンは、左側面に電源ボタンとボリュームボタンを用意。ポートは、下部側面にUSB 3.1 Gen1準拠のUSB Type-Cを用意するのみで、オーディオジャックは非搭載。
内蔵バッテリ容量は4,410mAhで、公称で24時間以上の駆動が可能とのこと。今回、ディスプレイ輝度を50%に設定し、SIM装着、無線LANに接続した状態でフルHD動画の連続再生してみたところ、9時間経過で48%の容量消費を確認した。そのまま計測を続けると、18時間を超える駆動が可能だったはず。これなら、よほど高負荷のアプリを連続使用しない限り、1日でバッテリが尽きることはなさそうだ。
製品の付属品はインストラクションカード、USB Type-Cケーブル、USB変換アダプタ、SIMピンで、ACアダプタは付属しない。
オプションとして専用カバーを用意。Pixel 6シリーズ用の専用カバーとほぼ同じものとなっており、背面をしっかりカバーしてくれる。ただ重量はやや重く、専用カバーを装着した状態での重量は実測で209.2gと200gを超える。できれば、カバーはもう少し軽いとありがたいと感じる。
完成度の高いミドルレンジスマートフォンとしてお勧め
今回は、発売に先駈けての試用ということで、ベンチマークテストは実行できなかった。ただ、実際に使ってみたところでは、SoCにGoogle Tensorを採用していることもあり、非常にキビキビと動作し、快適に利用できた。搭載RAMがやや少ないものの、ベンチマークテストではPixel 6とほぼ同等のスコアが得られるものと思われる。おそらく、性能面での不安は全くないと言っていいだろう。
カメラ機能がPixel 6からやや後退している点は少々残念ではあるが、その点を考慮してもPixel 6シリーズと同じSoCを搭載することによる優れた基本性能やAI関連機能、コンパクトで軽く質感に優れる筐体など、ミドルレンジスマートフォンとして完成度は十分に高いと感じる。しかも、5万3,900円という価格は、かなり魅力的だ。
以上から、比較的安価な価格で最新のPixelシリーズを手に入れたいと思っている人や、高性能なミドルレンジスマートフォンが欲しいと思っている人にお勧めしたい。










![[Amazon限定ブランド]CCL い・ろ・は・すラベルレス 2LPET ×8本 ミネラルウォーター 無味 製品画像:1位](https://m.media-amazon.com/images/I/41h0MHfvhkL._SL160_.jpg)



![【Amazon.co.jp限定】 伊藤園 磨かれて、澄みきった日本の水 2L 8本 ラベルレス [ ケース ] [ 水 ] [ 軟水 ] [ ペットボトル ] [ 箱買い ] [ ストック ] [ 水分補給 ] 製品画像:5位](https://m.media-amazon.com/images/I/41n0o65dSkL._SL160_.jpg)







![【中古】 NEC VersaPro PC-VK23TGVGU SSD搭載 Core i5 6200U Windows11 Home Wi-Fi 長期保証 [94838] 製品画像:20位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/risemark/cabinet/pic/948a/94838.jpg?_ex=128x128)




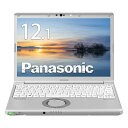



![DELL OptiPlex 7090 SFF (Win11x64) 中古 Core i7-2.5GHz(11700)/メモリ16GB/HDD1TB/DVDマルチ [C:並品] 製品画像:3位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/usedpc/cabinet/url1/5726315c.jpg?_ex=128x128)





![【❤最安挑戦❤+LINEクーポン】新発売 [1+1年保証] モニター 100Hz 21.5インチ 23.8インチ 27インチ pcモニター 1ms応答 パソコン モニター 1920*1080 FHD ゲーミングモニター 非光沢 VA 角度調整 VESA Freesync pc/switch/ps4/ps5/xbox スピーカー内蔵 製品画像:13位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/qifeng/cabinet/10653721/10653722/imgrc0112340482.jpg?_ex=128x128)






![【楽天ブックス限定抽選特典】【クレジットカード決済限定】CANDY TUNE 3rd Anniversary写真集(仮)(オンラインラッキードロー抽選権) [ CANDY TUNE ] 製品画像:30位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/2708/2100014832708_1_2.jpg?_ex=128x128)
![臨床医のためのライフハック 「診療・研究・教育」がガラッと変わる時間術 [ 中島 啓 ] 製品画像:29位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/2435/9784260062435.jpg?_ex=128x128)


![【楽天ブックス限定特典】乃木坂46川崎桜 1st写真集『エチュード』(限定カバー) [ 川崎桜 ] 製品画像:26位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/1009/2100014821009_1_3.jpg?_ex=128x128)
![きのう何食べた?(25)【電子書籍】[ よしながふみ ] 製品画像:25位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rakutenkobo-ebooks/cabinet/0973/2000019710973.jpg?_ex=128x128)
![太郎 DON’T ESCAPE!【特典ペーパー付】【電子書籍】[ mememe ] 製品画像:24位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rakutenkobo-ebooks/cabinet/2467/2000019272467.jpg?_ex=128x128)
![古語大鑑 第3巻 し~て [ 築島 裕 ] 製品画像:23位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/0075/9784130800075_1_11.jpg?_ex=128x128)
![青天 [ 若林 正恭 ] 製品画像:22位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/0665/9784163920665_1_10.jpg?_ex=128x128)
![書簡型小説「二人称」 ヨルシカ [ n-buna ] 製品画像:21位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/6341/9784065416341_1_3.jpg?_ex=128x128)