山田祥平のRe:config.sys
ASUSが本気で取りに来た薄型軽量PC市場
2025年2月8日 06:34
「日本市場にはすべての項目が“ちょうどイイ”ノートPCが必要だ」。だからこそ最先端の技術を凝縮してゼロから開発されたというASUSの新ノートPC。ASUSはこの製品に日本市場向けの限定ネーミングとしてSORAという名前を特別に用意した。そして、Zenbook SORAが誕生し、歩き始めた。
1Kg未満の薄軽市場でトップシェアを目指すASUS
ASUS JAPANのノートPCプロダクトマネージャーLeon Chen氏(システムビジネスグループ コンシューマービジネス事業部)は切り出した。それが冒頭の台詞だ。2025年2月上旬に開催された同社の新製品発表会のプレゼンテーションはこの台詞で始まった。
2025年は出荷される製品の3割がCopilot+ PCになるだろうと同社は考えているそうだ。そんな中で同社は薄型軽量PC市場でのトップシェアを目指す。そのミッションを果たすべくZenbook SORAが生まれた。1Kg未満のセグメントで市場をリードし、AIを活用してユーザーのタスクをサポートしようというわけだ。
そもそもZenbookは日本の禅をヒントに生まれたブランディングで、禅の哲学として美しさと性能の調和をめざしてきた。そしてその新たな付加価値として目指すのが1Kg未満の薄軽だ。
同社は日本市場におけるノートPCの使用実態を調べ、東京近郊の通勤通学平均時間が1時間42分に及ぶことを知った。その道中では、PCに加えて電源アダプタやケーブル類など多くの周辺機器を持ち歩く。カバンはノートPCの厚みで圧迫される。ラッシュによる混雑もある。
なのにそのノートPCは、バッテリが丸一日持たない。だからこそ今、軽さ、薄さ、十分な駆動時間を備えたPCが求められているはずだと判断したらしい。
そして、最軽量モデルで899gの薄軽を誇るノートが生まれた。それがSORAだ。
SORAの中で最も重い製品でも980gと1kgを切っている。筐体の最薄部は13.4mmだ。セラミックとアルミニウムを融合したセラルミナム素材を使った高い洗練感を持つボディで、これまた日本市場の調査結果に基づいた本体カラーとしてニュートラルな2色のカラーが用意された。ザブリスキーベージュとアイスランドグレーだ。似たような中間色だが似ているようで趣向が違う。強い主張は感じないが、美しさに加えて「粋」を感じる。
バッテリ重量と駆動時間はトレードオフ
ハードウェアとしてのSORAは980gの上位製品「RA」がSnapdragon X Elite X1E-78-100を、899gの製品「QA」がSnapdragon X X1-26-100を搭載している。どちらの製品もArmアーキテクチャで45TOPSのNPUを持つ。つまり、Microsoftの提唱するCopilot+ PCの要件を満たしている。
スペックを見ると、RAは光沢パネルの有機EL、QAは非光沢パネルの液晶ディスプレイで、双方ともにアスペクト比は16:10だ。重量980gのRAは70Wh、899gのQAは48Whのバッテリを搭載している。
日本における軽量ノートPCとしてはFCCLの製品が群を抜いていることで知られている。ASUSとしても本当は世界最軽量のCopilot+ PCを名乗りたかったに違いない。
だが、発表会の約2週間前となる1月16日の午後、ASUSから今回の新製品を指すキーワードとしての「最軽量Copilot+ PC」を「超軽量Copilot+PC」へ修正するとの連絡があった。ちょうどこの日、FCCLから848gのCopilot+ PC「FMV Note U」が発表されたからだ。搭載するバッテリの容量は64Whだ。
結局のところ、バッテリ駆動時間を確保するためにはバッテリ容量を増やすのが最も簡単だ。だが、ペナルティとして重量がかさむ。
個人的には800gを超えるノートPCはむしろ重いとさえ感じる。ムサシとして約634gの世界最軽量を実現した「FMV Zero」のとんでもない軽さを体感で知ってしまっているからだ。だが、その搭載バッテリは31Whしかない。それでも1時間程度の記者会見を2件、ハシゴして使うには十分な駆動時間を確保できる。それでいいという使い方なら不満はない。
長時間のバッテリ駆動時間が必要な場合は、別途モバイルバッテリなどを外付けするわけで、その重量を加味すれば相当の重量増になってしまう。だったら最初から多少の重量を覚悟しても大容量のバッテリが内蔵されている方がいいという判断も正しいはずだ。ASUSの言う「ちょうどイイ」というのはそういうことなのだろう。
Arm版のWindowsに感じるストレス
今回は、発売前のRAを3週間ほど使うことができた。何も問題はない。実にキレイにまとまったPCに仕上がっている。だが、個人的な理由で操作のストレスを感じる。
ちなみにCopilot+ PCは手元にMicrosoftのSurface Laptopがある。発売から1年弱の製品だが、そこで感じたのと同じストレスを最新のSORAにも感じる。
Snapdragonプロセッサ、つまりArmアーキテクチャを採用したWindowsは、普通に使う限りにおいて特に困ることはないのだが、やはり、IMEが限定されるというのはつらい。ジャストシステムのATOKは個人的に何十年にも渡って愛用してきた日本語入力環境なので、Microsoft IMEでは入力の効率が落ちるのだ。
ATOKにArm版はないが、インストールはできて、32bitアプリ上なら入力もできる。だったら32bit版のChromeを入れればWebブラウザ上でもATOKが使えるかも……という淡い期待をしてもみたのだが、32bit版ChromeはArm版Windowsをサポートしていないことが判明して企画倒れに終わった。Webブラウザで日本語入力をする機会はかなり多いだけにショックだった。
ATOKでないと困るのは、Windows標準のIMEでは入力に際するキー割り当てをATOKとまったく同一にすることができないからだ。試してみたがGoogle日本語入力も同様で思い通りにはならなかった。でも、日常的に標準の日本語IMEに慣れ親しんでいるユーザーには何も問題はないだろう。
Arm版のWindowsを使うためには乗り越えなければならない多少のハードルを覚悟しなければならない。だが、そんなことに悩むユーザーはわずかだろうし、当然、そのことがASUSのSORAの評価を下げる理由にはならないはずだ。
「ちょうどイイ」を模索
今にして思えば、Windowsというのは、どんなハードウェアでもその差異を吸収し、各種のソフトウェア、ペリフェラルを動かせるようにする環境だった。その前にはMS-DOSがあったが、Windowsには驚いた。海外製のアプリを海外通販で取り寄せて、PCー9800シリーズで稼働する日本語版のWindowsで難なく動かせたときには本当にびっくりした。今でこそ当たり前だがそういう時代もあったのだ。
まさか、40年近くたって、そういうことを改めて考えなければならなくなるとは思わなかった。でも、それが時代の変わり目ということでもある。そのハードウェアの違いに苦しみながらも、その差異が解消されていくことで適材適所のハードウェア環境が使い分けられるようになっていく。
今回のASUS SORAがノートPCの新しい使い方を提案する背景として、そんな要素もあわせて考えながら、プロセッサのアーキテクチャの違いと、その環境を生かしたAI活用におけるPCの「ちょうどイイ」を模索してみたい。












![[Amazon限定ブランド]CCL い・ろ・は・すラベルレス 2LPET ×8本 ミネラルウォーター 無味 製品画像:1位](https://m.media-amazon.com/images/I/41h0MHfvhkL._SL160_.jpg)



![【Amazon.co.jp限定】 伊藤園 磨かれて、澄みきった日本の水 2L 8本 ラベルレス [ ケース ] [ 水 ] [ 軟水 ] [ ペットボトル ] [ 箱買い ] [ ストック ] [ 水分補給 ] 製品画像:5位](https://m.media-amazon.com/images/I/41n0o65dSkL._SL160_.jpg)
























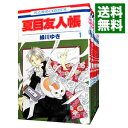
![予約の取れないセラピストの骨格小顔バンド [ 三木まゆ美 ] 製品画像:29位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/8296/9784865938296_1_16.jpg?_ex=128x128)
![ROCKIN'ON JAPAN (ロッキング・オン・ジャパン) 2026年 5月号 [雑誌] 製品画像:28位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/0561/4912097970561.gif?_ex=128x128)
![青天 [ 若林 正恭 ] 製品画像:27位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/0665/9784163920665_1_10.jpg?_ex=128x128)


![STORY (ストーリィ) 2026年 4月号 [雑誌] 製品画像:24位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/0464/4912054830464_1_2.jpg?_ex=128x128)
![ANIMATION WORKS「LUPIN THE IIIRD」シリーズ公式コンプリートブック [ MdN編集部 ] 製品画像:23位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/8389/9784295208389_1_2.jpg?_ex=128x128)
![だぶるぷれい 7【電子書籍】[ ムラタコウジ ] 製品画像:22位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rakutenkobo-ebooks/cabinet/1782/2000019711782.jpg?_ex=128x128)
![Numero TOKYO (ヌメロ・トウキョウ)4月号増刊 2026年 4月号 [雑誌] 製品画像:21位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/0466/4912172000466_1_2.jpg?_ex=128x128)