Hothotレビュー

GeForce搭載ハイエンド2in1「Surface Book 2」を検証
~性能を求めるユーザーに唯一無二の存在
2017年12月2日 11:00
日本マイクロソフトは、クリエイターなどハイエンドユーザーをターゲットとした着脱式2in1の新モデル「Surface Book 2」を発売した。
第8世代Core i7やGeForce GTX 1050を採用するモデルを用意するなど性能面を進化させるとともに、使いやすさも高められている。今回、Surface Book 2の最上位モデルを試用する機会を得たので、ハードウェア面を中心に紹介する。すでに発売済みで、直販価格は200,664円から。
基本的なデザインは従来モデルを踏襲
まずは、Surface Book 2の外観を見ていこう。
Surface Book 2は、キーボードに装着してクラムシェルノートとして、ディスプレイ部を外してタブレットPCとして利用できる、いわゆる着脱式の2in1 PCだ。
本体の基本的なデザインコンセプトは、従来モデルのSurface Bookシリーズとほぼ同じ。キーボード後方に蛇腹状の独特なデザインで、スムーズな開閉が行なえるヒンジ「Dynamic Fulcrum Hinge」を備える点や、閉じたときにヒンジ付近にすき間ができる点、ディスプレイ部を前後逆向きにヒンジに装着し、スタンド型の閲覧モードや、たたむことでペン入力を快適に行なえる角度を実現するスタジオモードといった複数のモードで利用できる点も、しっかり受け継がれている。
ディスプレイ部を単体で見ると、背面にキックスタンドは備えず、側面部は垂直に切り落とされているため、タブレットPCのSurfaceシリーズとはやや印象が異なる。それでも、直線的でフラットな板状の筐体デザインや、シルバーの筐体カラー、天板のWindowsロゴ以外に目立つ装飾がなく落ち着いた印象を受けるといった点からは、Surfaceシリーズらしさが十分に感じられる。
筐体素材には、従来モデル同様にマグネシウム合金を採用。マット調の加工が施されている点も同様だ。
ディスプレイ部の着脱機構には、従来モデル同様の「Muscle Wire」機構を採用。キーボードのDeleteキー左に、Muscle Wireのロック解除ボタンが用意されており、このボタンを押すことでMuscle Wireロックが解除され、ディスプレイ部を取り外せるようになる。
また、ヒンジ部の金属突起にディスプレイ部下部の溝を合わせて装着すると、Muscle Wireでしっかりとロックされる。ロックされた状態では、ディスプレイ部のみを持って持ち上げても、キーボードが外れるといった不安さは一切なく、非常に強力にロックされていることがわかる。
ところで、従来モデルではクラムシェルPCモードでのディスプレイのぐらつきがかなり大きいという大きな欠点があったが、Surface Book 2ではそのぐらつきがかなり解消されている。
Surface Book 2では、Muscle Wireロックを構成する金属突起を大きくするなどの仕様変更によって、従来モデルの問題を改善。実際に、ディスプレイを前後に揺らしてみても、わずかに揺れる程度で、従来モデルのように、やや強くキーボードを叩いているだけでディスプレイが揺れるといったことはほぼなくなった。
なお、ディスプレイの開く角度は、従来モデルとほぼ同じで、125度程度までとなっている。これは、ディスプレイ部がどうしても重くなってしまう着脱式2in1の宿命でもあるが、Surface Book 2ではキーボード側の重量が比較的重いこともあるので、できればもう少し深い角度まで開けるとよかったように思う。
本体サイズは、搭載CPUによってわずかに違いがあるが、今回試用したCore i7搭載モデルの、キーボード装着時のサイズは312×232×15~23mm(幅×奥行き×高さ)。これは、従来モデルとまったく同じサイズとなっている。
重量は、キーボード込みで1,642gからとなっている。実測では、キーボード込みで1,633g、ディスプレイ部単体で717gだった。実際に手にしてみても、13型クラスのノートPCとしてはやや重いという印象を受ける。とはいえ、Surface Book 2自体、モバイルノートPCに近い位置づけの製品ではなく、ゲーミングノートPCに匹敵するスペックを搭載していることを考えると、十分満足できる軽さを実現していると言っていいだろう。
第8世代Core i7やGeForce GTX 1050を採用するなど、性能が大きく向上
Surface Book 2は、クリエイターなどのハイエンドユーザーをターゲットとしていることもあって、スペック面の充実も大きな特徴となっている。
CPUには2コア4スレッド処理対応の第7世代Core i5-7300Uを搭載する下位モデルと、4コア8スレッド処理対応の第8世代Core i7-8650Uを搭載する上位モデルの、2モデルをラインナップ。
また、メインメモリはLPDDR3-1866ながら、最小8GB、最大16GBまで搭載可能で、内蔵ストレージも最大1TBのPCIe SSDを搭載可能。メモリ、内蔵ストレージともに、ハイエンドモデルらしく余裕がある点はうれしい。
Core i7-8650Uの上位モデルの特徴となるのが、キーボード側にディスクリートGPUとしてGeForce GTX 1050(ビデオメモリはGDDR5が2GB)を搭載する点だ。
従来モデルではGeForce GTX 965Mを搭載していたが、GeForce GTX 1050に強化されたことで、3D描画能力も大きく高められている。GeForceシリーズということで、カジュアルなゲームであれば対応できるため、クリエイティブな用途だけでなく、ゲーミングPCとしても十分活用できるだろう。
Windows Mixed Reality Ultraの要件も満たしているので、Windows Mixed Realityヘッドセットも最大限に活用できる。
なお、今回試用したモデルは、CPUがCore i7-8650U、メモリが16GB、内蔵ストレージが1TBのPCIe SSDと最強スペックのものだった。直販価格は397,224円となる、非常に贅沢なモデルだが、どの程度のパワーを備えているのだろうか。そこで今回は、先にベンチマークテストの結果を紹介していく。
利用したベンチマークソフトは、Futuremarkの「PCMark 10 v1.0.1403」、「PCMark 8 v2.7.613」、「3DMark Professional Edition v2.4.3819」、Maxonの「CINEBENCH R15.0」、スクウェア・エニックスの「ファイナルファンタジーXIV: 紅蓮のリベレーター ベンチマーク」の5種類で、キーボード装着時とディスプレイ部単体の双方でテストを行なった。
残念ながら、従来モデルを用意できなかったので、従来モデルとの比較は紹介できないが、4コア8スレッド処理に対応するCore i5-8250U搭載の富士通「LIFEBOOK UH75/B3」の結果を比較用として掲載する。
| Surface Book 2 | Surface Book 2 ディスプレイ部のみ | LIFEBOOK UH75/B3 | |
|---|---|---|---|
| CPU | Core i7-8650U(1.90/4.20GHz) | Core i7-8650U(1.90/4.20GHz) | Core i5-8250U(1.60/3.40GHz) |
| GPU | GeForce GTX 1050(2GB) | Intel UHD Graphics 620 | |
| メモリ | LPDDR3-1866 SDRAM 16GB | DDR4-2400 SDRAM 4GB | |
| ストレージ | 1TB SSD(PCIe) | 128GB SSD(SATA) | |
| OS | Windows 10 Pro 64bit | Windows 10 Home 64bit | |
| Surface Book 2 | Surface Book 2 ディスプレイ部のみ | LIFEBOOK UH75/B3 | |
|---|---|---|---|
| PCMark 10 v1.0.1403 | PCMark 10 v1.0.1275 | ||
| PCMark 10 Score | 4,089 | 3,617 | 3,240 |
| Essentials | 7,689 | 7,870 | 6,814 |
| App Start-up Score | 10,044 | 9,991 | 8,541 |
| Video Conferencing Score | 6,795 | 7,149 | 5,977 |
| Web Browsing Score | 6,663 | 6,827 | 6,198 |
| Productivity | 5,860 | 6,219 | 5,769 |
| Spreadsheets Score | 7,650 | 8,163 | 7,073 |
| Writing Score | 4,490 | 4,849 | 4,706 |
| Digital Content Creation | 4,120 | 2,595 | 2,591 |
| Photo Editing Score | 4,260 | 3,330 | 3,137 |
| Rendering and Visualization Score | 4,198 | 1,496 | 1,782 |
| Video Editting Score | 3,912 | 3,510 | 3,112 |
| PCMark 8 v2.7.613 | |||
| Home Accelarated 3.0 | 3,596 | 3,448 | 3,456 |
| Creative accelarated 3.0 | 5,125 | 4,769 | 4,444 |
| Work accelarated 2.0 | 4,451 | 3,771 | 4,574 |
| Storage | 5,061 | 5,030 | 4,866 |
| CINEBENCH R15.0 | |||
| OpenGL (fps) | 86.74 | 53.32 | 39.12 |
| CPU | 672 | 679 | 534 |
| CPU (Single Core) | 173 | 177 | 144 |
| 3DMark Professional Edition v2.4.3819 | |||
| Cloud Gate | 17,571 | 5,188 | 6,971 |
| Graphics Score | 29,421 | 5,808 | 7,455 |
| Physics Score | 7,292 | 3,779 | 5,683 |
| Sky Diver | 16,155 | 3,890 | - |
| Graphics Score | 18,900 | 3,666 | - |
| Physics Score | 8,922 | 6,184 | - |
| Combined score | 18,509 | 3,545 | - |
| Time Spy | 1,794 | 369 | - |
| Graphics Score | 1,647 | 322 | - |
| CPU Score | 3,643 | 2,193 | - |
| ファイナルファンタジーXIV: 紅蓮のリベレーター ベンチマーク | |||
| 1,280×720ドット 標準品質(ノートPC) | - | 4,057 | 2,358 |
| 1,920×1,080ドット 標準品質(ノートPC) | - | 2,244 | 1,324 |
| 1,280×720ドット 標準品質(最高品質) | 10,634 | - | |
| 1,920×1,080ドット 標準品質(最高品質) | 6,208 | - | |
結果を見ると、ディスクリートGPUが利用可能となるキーボード装着時の性能はなかなかのもので、ディスプレイ部単体や、Core i5-8250U搭載のLIFEBOOK UH75/B3の結果と比較しても、多くの項目でスコアが上回っている。
とくに大きな違いとなっているのが、ディスクリートGPUが活用されるテストや、3Dグラフィックスのテストの結果で、いずれもほかを大きく引き離している。GeForce GTX 1050を搭載しているため、この結果も当然ではあるが、やはりディスクリートGPUの存在は非常に大きいと言える。
ただ、一部テストでは、キーボード装着時よりもディスプレイ部単体時のほうが結果が優れている部分もある。基本的にベンチマークテストは3回計測するようにしているが、いずれの結果でも同様であった。
今回のテストでは、キーボード装着時にはクラムシェルモードで、ディスプレイ部単体はデスクの上に置いてテストを行なったが、テスト時には、ディスプレイの天板側が比較的高温になることも確認しているので、放熱の違いが影響している可能性が高いと思われる。
おそらく、ディスプレイ部単体では、熱がデスクに伝わって、より放熱性能が高まり、わずかではあるが結果が高まったのだろう。もちろん、スコアに差があると言っても、体感できるほどの差とは言えないため、実際に利用する上で気にする必要はなさそうだ。
ただ、テストの結果よりも気になった部分が2つほどある。1つは、ディスクリートGPUが高負荷になったときの空冷ファンの動作音。キーボード側の後方にディスクリートGPUの熱を放出する排気口があるが、高負荷時にはかなり大きめの動作音と風切り音が耳に届き、ややうるさいと感じる。
とはいえ、これについては、ハイエンドスペックということと、薄型軽量の筐体ということを考えると、仕方のない部分とも言えるだろう。なお、低負荷時にはファンの動作音も非常に小さくなり、十分な静かさとなる。
もう1つのほうは少々いただけない。それは、ディスクリートGPUがフルに動作する高負荷時には、ACアダプタを接続していてもバッテリが消費される場面があったという点だ。これは、ディスクリートGPUがフルに動作する場合には、付属ACアダプタの出力(95W)では電力が足りないことが原因だろう。
バッテリがみるみる減っていくというわけではないが、ACアダプタを接続していても高負荷が続くとバッテリが減ってしまうというのは、やはり気持ちがいいものではない。フル稼働時でも余裕を持って電力を供給できるACアダプタを付属してもらいたかった。
従来同用アスペクト比3:2の13.5型PixelSenseディスプレイを採用
ディスプレイには、アスペクト比3:2、表示解像度3,000×2,000ドットの13.5型PixelSenseディスプレイを採用している。パネル自体は従来モデルと同じと思われ、コントラスト比も1,600:1と同じとなっている。
具体的な発色性能などは公開されていないものの、クリエイターをターゲットとしたハイエンドモデルらしく、非常に鮮やか、かつ自然な発色が実現されている。十分な高解像度表示のため、表示できる情報量が多い点も、プロ向けのアプリケーションを利用する場合の優位点となるだろう。ただ、パネル表面は光沢仕様となっているため、やや外光の映り込みが多い点は気になった。
パネル表面には10点マルチタッチ対応のタッチパネルを搭載。また、オプションのスタイラスペン「Surface ペン」によるペン入力や、ダイヤル型の操作デバイス「Surface Dial」による操作が可能。
Surfaceペンは、Surface Pro新モデルでサポートされた、筆圧検知4,096段階、傾き検知にも対応する新モデルに対応。液晶パネルとタッチパネルはダイレクトボンディングとなっているため、ペン先と液晶とのギャップも最小限で、非常に軽快かつ緻密なペン入力が行なえる。
キーボードの仕様は従来モデルとほぼ同じ
キーボードは、従来モデル同様に、キーの間隔が開いたアイソレーションタイプのものを採用している。キーピッチは約19mmフルピッチで、キーストロークは約1.6mm。キー配列や、フラットなキーボード面、キーボードバックライトの搭載など、キーボードの仕様は従来モデルと同等となっている。
キータッチはやや柔らかめだが、クリック感がしっかりと感じられるので、打鍵感は非常に良好。タブレットタイプのSurfaceシリーズのカバー型キーボードに比べると、当然ながら圧倒的に扱いやすいと感じる。
また、キーボード手前のタッチパッドも従来モデル同様で、クリックボタン一体型のものを採用。パッド面積が十分に広く、ジェスチャー操作にも対応しているので、こちらも申し分ない使い勝手を実現している。個人的には、クリック操作時のコツコツという音がやや大きい点が気になったが、全体的な利便性は十分満足できると感じる。
USB PD 3.0対応のUSB Type-Cポートを新たに用意
Surface Book 2に用意される外部ポートは、基本的にキーボード側に集約されている。
キーボード側左側面には、USB 3.0(3.1 Gen1)×2ポートとUHS-II対応SDカードスロットを備え、右側面にはオーディオジャックとUSB 3.0対応USB Type-C×1、付属のACアダプタやオプションのSurfaceドックを装着する独自コネクタ「Surface Connect」を備える。従来モデルではMini DisplayPortを備えていたが、Surface Book 2ではUSB Type-Cへと変更されている。
USB Type-Cポートは、USB 3.1 Gen2やThunderbolt3には非対応だが、DisplayPort出力(DisplayPort Alt Mode)をサポートしており、最大4K/60Hz出力が可能。USB Type-C HDMI変換アダプタなどを利用したHDMI出力なども可能だ。
また、USB Power Delivery(PD) 3.0をサポートしている点も特徴の1つ。電力供給は基本的に付属ACアダプタをSurface Connectに接続して行なうことになるが、USB PD対応ACアダプタによる給電も可能となっている。
今回、実際に最大出力が46WのUSB PD対応ACアダプタを利用して確認してみたところ、接続時に供給電力が足りない旨の警告メッセージが表示されたものの、電力供給およびバッテリの充電が可能なことを確認した。より大出力のUSB PD ACアダプタがあれば、この警告も出なくなると思われる。
Surfaceシリーズは、独自形状のコネクタ採用のACアダプタを利用しているため、ACアダプタの汎用性が低い、大きく重いACアダプタを持ち歩かないといけない、といった欠点があった。
しかし、Surface Book 2ではその欠点が解消されたと言っていい。今後は、携帯性重視のタブレット型Surfaceシリーズでも、USB PD対応USB Type-Cポートの採用を進めてもらいたいと思う。
それに対し、ディスプレイ部には下部側面にSurface Connectを備えるだけで、それ以外のポートは一切用意されない。この部分は従来モデルから変わっていないが、できればディスプレイ側にもUSBポートなどの外部ポートを用意してもらいたかった。
カメラは、天板側にオートフォーカス対応の800万画素カメラ、ディスプレイ上部に500万画素のカメラを搭載。ディスプレイ上部には顔認証用の赤外線カメラも搭載しており、Windows Helloを利用し顔認証でのログオンが可能だ。
無線機能は、IEEE 802.11ac準拠の無線LAN(速度は最大867Mbps)とBluetooth 4.1を標準搭載。センサー類は、環境光センサー、加速度センサー、ジャイロスコープ、地磁気センサーを搭載する。
付属のACアダプタは、出力が95Wと大きいということもあって、サイズがやや大きく、付属電源ケーブル込みの重量も実測で387.5gと重い。ただ、5V/1.5A出力対応のUSB充電ポートが用意されており、スマートフォンなどの充電に活用できる点はうれしい部分だ。
実測で14時間超の連続駆動を確認
ベンチマークテストの結果は先に紹介しているので、ここではバッテリ駆動時間を見ていくことにする。
Surface Book 2は、ディスプレイ側とキーボード側それぞれにバッテリを内蔵している。それぞれのバッテリ容量は非公開だが、トータルの容量は70Whと公表している。そして、ディスプレイ部単体で最大5時間、キーボードとドッキングさせた状態で最大17時間の連続動画再生が可能とされている。
それに対し、Windowsの省電力設定を「バランス」、電源モードを「(バッテリ)推奨」、バックライト輝度を50%に設定し、無線LANを有効にした状態で、BBenchでキー入力とWeb巡回にチェックを入れて計測したところ、ディスプレイ部単体では約3時間33分、キーボードとドッキングさせた状態では約14時間44分だった。公称の駆動時間に比べるとやや短かったものの、テスト条件を考えると、まずまず納得の範囲だ。
もちろん、ディスクリートGPUを利用する高負荷な作業を続けた場合には、駆動時間はかなり短くなると思うが、これだけの駆動時間があれば、電源の取れない外出先でも比較的重い作業を安心して利用できるはずだ。
高性能な軽量ノートを探しているプロのクリエイターにおすすめ
Surface Book 2は、CPUに第8世代Core i7-8650U、GPUにGeForce GTX 1050を搭載するモデルが追加され、従来モデルから性能が大きく強化された。
外観などデザイン面は従来モデルからほぼ変更はないが、ディスプレイ部のぐらつきが少なくなるなどの改善も見られ、スペック以外での進化も施されている。こういった進化によって、クリエイター向けのPCとして魅力が大きく向上している。
重量は、実測で1,633gと、モバイルPCとして考えるとやや重いものの、このスペックのハイエンドノートPCとして考えると十分に軽く、高性能なノートPCを気軽に持ち運んで使いたいという人にも魅力があるだろう。
また、GPUにGeForce GTX 1050を採用しているため、ゲーミングPCとしても十分に活用できるはずだ。
問題となるのは、やはり価格だろう。
Core i7-8650U搭載モデルは、今回の試用機と同じ仕様で397,224円、メモリが8GB、内蔵ストレージが256GBの最小スペックでも262,224円(いずれも直販価格)となる。
もちろん、着脱式の2in1仕様となっている点や、タッチパネルを搭載し、高性能なスタイラスペンが利用できるといった特徴を考えると、仕方がないが、2in1仕様やタッチ、スタイラスペンが不要という人にとっては、かなり高いと感じるだろう。そう考えると、万人にはおすすめしづらいのも事実だ。
それでも、タッチ操作、高性能なスタイラスペンの利用ができ、その上でハイエンドに匹敵する性能を備え、軽量で楽に持ち運べるPCを探している人にとって、これ以上ない製品なのは間違いない。価格に納得できるなら、映像や画像クリエイターにとって、現時点で最善の選択肢となるだろう。










![[Amazon限定ブランド]CCL い・ろ・は・すラベルレス 2LPET ×8本 ミネラルウォーター 無味 製品画像:2位](https://m.media-amazon.com/images/I/41h0MHfvhkL._SL160_.jpg)







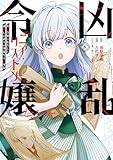


![良品 フルHD 15.6インチ Lenovo ThinkPad L15 Gen3 Type-21C4 / Office付きWindows11/ 10コア 卓越性能 第12世代Core i5-1235u/ 8GB [16GBメモリー選択可能]/ 爆速NVMe式256GB-SSD/ カメラ/ 無線Wi-Fi6/ Win11ノートパソコン 中古パソコン 中古PC 即日発送 税込送料無料 製品画像:28位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/pc-one/cabinet/11670319/11768356/11768363/lenovo11-xxx-1.jpg?_ex=128x128)
![【中古美品】SONY VAIO ProPK22 VJPK2280000 ハイスペックモバイルノートPC Office Win11 Office 第12世代 [Core i5 1235U メモリ16GB SSD256GB 無線 14型 Bluetooth ] 製品画像:27位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/whatfun-pc/cabinet/38/vjpk22_r.jpg?_ex=128x128)





【ノートパソコン】【送料無料】 製品画像:21位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/e-cutestyle/cabinet/noimg.jpg?_ex=128x128)




















![パラコード・ワークス ひも結び完全ガイドブック [ 辻岡 ピギー ] 製品画像:30位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/9372/9784766139372_1_4.jpg?_ex=128x128)

![暁のヨナ【通常版】 47【電子書籍】[ 草凪みずほ ] 製品画像:28位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rakutenkobo-ebooks/cabinet/7161/2000019737161.jpg?_ex=128x128)
![都市伝説解体センター 全篇解体書 (Vジャンプブックス) [ Vジャンプ編集部 ] 製品画像:27位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/8371/9784087798371.gif?_ex=128x128)
![青天 [ 若林 正恭 ] 製品画像:26位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/0665/9784163920665_1_10.jpg?_ex=128x128)
![がん・放射線療法 改訂第8版 [ 大西 洋 ] 製品画像:25位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/0493/9784055200493_1_4.jpg?_ex=128x128)
![きのう何食べた?(25)【電子書籍】[ よしながふみ ] 製品画像:24位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rakutenkobo-ebooks/cabinet/0973/2000019710973.jpg?_ex=128x128)
![おともだちえほん はじめての「よのなかルールブック」 [ 高濱正伸 ] 製品画像:23位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/1540/9784284001540_1_3.jpg?_ex=128x128)
![【楽天ブックス限定デジタル特典】QuizKnock10周年スペシャルブック 十字路(ロケ撮影メイキング映像 ダウンロード) [ QuizKnock ] 製品画像:22位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/9436/9784048979436_1_9.jpg?_ex=128x128)
![こども語彙力クイズ366 1日3分で頭がよくなる! [ 高濱正伸 ] 製品画像:21位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/1519/9784284001519_1_3.jpg?_ex=128x128)