大河原克行の「パソコン業界、東奔西走」
島根富士通でレノボPCを生産する日がやってくる?こだわりが詰まったFMV Note Cの生産ラインを初公開
2025年2月17日 06:01
島根富士通が、同社の長期ビジョン「SFJ Next 30」において、2050年に累計生産1億台を目指す新たな指針を発表した。
それに向けて、2030年度には基板実装ラインの100%自動化、組立工程における65%の自動化を計画。さらに、2030年度までに製造コストで2分の1、ラインリダクションで4分の1、物流リードタイムで6分の1など、意欲的な計画を打ち出した。
2025年1月に累計生産台数5,000万台に到達した島根富士通が、次の新たな目標に踏み出すことになる。その目標の中には、レノボブランドのPCを、島根富士通が生産する可能性が含まれるものとなる。
島根県出雲市の島根富士通を訪れ、新たな目標について聞くとともに、2025年1月から出荷を開始したFMV Note Cの生産ラインを取材した。
累計生産5,000万台を達成した国内最大のPC工場
島根富士通は、富士通クライアントコンピューティング(FCCL)の生産子会社であり、2025年1月20日に、PCの累計生産台数が5,000万台に到達した。国内のPC生産拠点としては初めてとなる。
島根富士通は、1989年12月に設立。1990年10月から富士通初のPC専門工場として操業しており、34年4カ月で5,000万台に到達したことになる。
今回、新たに公表した累計生産1億台の目標は、今後25年間で5,000万台を生産するという長期的な視点に立ったもので、生産能力をさらに拡大するとともに、グローバル向けPCの生産にも踏み出すという、これまでにはない島根富士通の新たな決意を示したものになる。
島根富士通の神門明社長は、「2050年に1億台という目標を新たに掲げた。そして、今後3年間で、累計生産6,000万台を達成したい」と意気込む。
「変動力」と「逆境力」も強みに
島根富士通は、2021年8月に、長期ビジョンである「SFJ(島根富士通) Next 30」を、対外的に発表した。
同社が長期的視点での方針を発表したのは、このときが設立以来初めてであり、2020年10月に30周年の節目を迎えたこと、2020年度には過去最高の240万台の年間生産を達成したこと(現時点でも過去最高実績)、2021年5月に福島県伊達市の富士通アイソテックで行なっていたデスクトップPCの生産を島根富士通に完全移管し、国内でのPC生産を島根富士通に一本化するといった節目を迎えたことなどを背景に、神門社長が打ち出したものだった。
当初は、具体的な指標は示さず、従来から培ってきた「現場力」、「技術力」、「創造力」に加えて、環境の変化に追随する「変動力」、逆境を乗り越えて糧にする「逆境力」を、島根富士通の新たな強みとして掲げ、変化に強く、しなやかな工場へと進化することを方針に掲げた。
神門社長は、「島根富士通は、これまでに6人の社長がバトンをつないできた。歴代社長が打ち出した国内生産ならではの強み、開発との緊密な連携によるコストダウンへの取り組み、人と機械の協調生産への進化、生産革新に対するこだわりなどが、今へとつながっている」と、これまでの進化の歴史を振り返る。
2003年から「ものづくり革新活動」を開始し、2005年からはトヨタ生産方式を導入して、ジャストインタイム、自働化、平準化による生産革新を実施し、その成果をもとに、島根富士通生産方式(FJPS)へと進化。
2008年からは、組み立てから梱包までの一気通貫ラインを構築し、さらに、ロボットや自動搬送車などの導入を加速させてきた。現在では、1台単位での混流生産の実現や、最短で中2日で出荷する製造リードタイムを実現。BTO比率は約95%で、5万種類の組み合わせに対応することができる。島根県出身者の従業員比率は99%で、人材定着率は98%という高さも特徴だ。
現在、プリント基板製造ラインは24時間体制で稼働。10ラインが稼働し、0.4×0.2mmという最小部品の実装を含めて、年間36億ショットの部品実装を行なっている。
また、組立ラインはノートPCで20ライン、デスクトップPCで3ラインが稼働。最大で年間300万台の生産が可能だ。さらに、35台のAGVが稼働し、9つのルートで部品や完成品の自動搬送を行なっている。
神門社長は、「30年間培ってきた現場力、技術力、創造力に、変動力および逆境力を加え、最先端のスマートファクトリーの構築を目指している。世界のトレンドに追随するためにはさらなる加速が必要である」と、今後の進化にも意欲を見せる。
また、島根富士通の宮下浩之執行役員常務は「特にここ3年間で、自前の治具やロボットの導入がかなり進展している。しかも自動化のために機械を導入するだけでなく、機械同士やロボットとの間を補完したり、つないだりするような仕組みを、自分たちで開発するケースが増加している。島根富士通にとって、最良の生産方法を実現するには、外部から機械やロボットを調達するだけでなく、自ら機械を開発する必要があり、さらにデータを活用し、踏み込んだ形で改良する必要がある。内製率を高め、保全も自らが行なえるようにしている」とする。
島根富士通では、2024年4月に、神門社長の肝入りで、「ものづくりセンター」を設置。この組織が、宮下執行役員常務が指摘する現場改善の原動力となっている。長年のものづくり経験者をリーダーに据える一方で、若手社員を中心に議論を進めているのも特徴だ。
神門社長は、「今一度、モノづくりの基礎を徹底させ、現場の改善を図るための組織として設置とた。新たな機器を導入したり、デジタルを活用したりといったことだけでは、モノづくりは進化しない。単独のシステムを導入するだけでなく、機械同士が連携し、全体最適化を図り、モノづくりのブラッシュアップに取り組んでいる。それが、今の成果につながっている」と、手応えに自信を見せた。
その一方で、データ活用は今後の課題と位置付ける。
神門社長は、「2年前にデータ分析基盤を構築し、データを蓄積し始めている。そのうち活用したいデータが70~80あるが、現時点で活用できているのは3分の1程度。今は品質データが中心であり、リアルタイムに可視化できるようにしているが、これからは可視化したデータをどう使いこなすかといった点に力を注ぎたい」とする。
「SFJ Next 30」で掲げた新たな指標とは
2025年2月13日に、島根富士通で行なわれた累計生産5,000万台の記念式典で挨拶した神門社長は、その中で、2030年の具体的な指標を初めて明らかにした。
1つ目は、プリント基板製造ラインにおいて、2024年度に達成した79%の自動化率を、2030年に100%に引き上げるという「完全自動化」の目標だ。
これまでは、基板投入から両面実装、最終検査工程までを自動化していたが、自動倉庫を活用した工程内の搬送業務の自動化、生産設備の機種切り替え作業の無人化、AIを活用した設備不調の事前予知によるトラブルの未然防止、完成したプリント板の組立ラインへの自動ダイレクト供給を目指す。
「完全自動化に向けて、徹底的な省人化を図る。また、変種変容の小ロット生産に柔軟に追随するために、AMR(自走式ロボット)を導入し、搬送をすべて自動化する。段取り替えも無人化し、完成した基板は在庫せずに、組立ラインにダイレクトに供給して、製造リードタイムの短縮も図る。さらに、設備のコンディションを最適化するために、デジタルデータとAIを活用した予知保全システムを構築し、設備の稼働率向上や製造品質の向上を図る」(神門社長)という。
2つ目は、組立ラインの進化だ。人と機械の協調生産を加速し、2024年度には24%だった自動化率を、2030年には65%にまで高めることになる。
ここでは、1台単位にセットした組立部材をラインに自動供給するほか、アシストロボットによる人の作業の支援を推進する。組立ラインには、製造指示に併せて柔軟に可変するフレキシブルラインを導入し、メガネ型ウェアラブルモニターへの作業指示の表示、ロボットを活用した試験ラインや梱包ラインの完全自動化を図る。
「生産量に応じて、人、設備、場所が、自在に変化するフレキシブルラインを構築する。ライン内では人の作業をサポートするアシストロボットや、共通性が高い試験や梱包工程におけるロボットの導入によって、ラインで必要とするコア人員数は半分以下にする。変種変容に自在に対応するには、オーダー情報から必要なライン数を自律的に判断し、1台単位でセット供給ができるようにしていく」という。
そして、3つ目が、物流における省力化および効率化である。2024年度には40%の自動化率を、2030年には80%にまで高める。
AGF(無人自動フォークリフト)によるパレットの積み込みや荷下ろしの自動化、製造ラインへの部材搬送の天井搬送の実現、オーダー情報に基づいた自動ピッキングを行なうほか、自動倉庫の導入による部品の入出庫や在庫管理のスマート化、AIでの部品受け入れ検査の自動化も計画している。AGV(無人搬送車)に加えて、AMRの導入も検討していくことになる。
「部品の入荷から完成した製品の出荷まで、運搬作業のすべてを無人化することを考えている。人の作業に関しては、負荷低減を目的とした省力化整備を同時に導入していく。自動倉庫の導入より、空間を活用した収容率の拡大、入出庫の自動化、在庫管理のデジタル化を行ない、変種変容のモノづくりに最適なスマートで、フレキシブルな倉庫システムを構築していく」と述べた。
その上で、神門社長は、「キーワードは、オートメーション、フレキシビリティ、ジャストインタイムの3つ。単なる自動化ではなく、知能を持った自律化へと進化させる。今後の環境変化に対応するためには、効率性と柔軟性を持ち、迅速に変化に追随できる製造ラインの構築が必要である。必要なときに、必要なものを、必要なだけ生産し、お客様の要望に、すばやく、的確に対応できる仕組みを構築する」と述べた。
今後5年で製造コストを2分の1に
今回新たな指標として発表したのが、2030年度までに製造コストを2分の1、ラインリダクション率で4分の1、物流リードタイムでは6分の1といった意欲的な目標である。これは先に触れた3つの目標とも連動したものになる。
製造コストの2分の1は、自動化とデジタル化によって実現することになるという。
「基板実装ラインでは、自動化によって、5年間で120人を80人に削減し、設備投資と相殺し、約20人分の人件費の削減を達成している。さらに自動化を推進することで、基板実装ラインの人員数を半減させ、人は付加価値の高い作業にシフトすることになる。一方で、組立ラインの自動化は開発部門との連携によって、自動化を推進していく。まずは検査、梱包などを自動化し、現在、10人で作業しているコア人員を5人以下にしたい」とする。
また、ラインリダクション率を4分の1とする目標については、「今は、細かい作業も人に頼っている部分がある。カメラを使って作業を確認しているが、開発部門との連携で、自動化できる部分を自動化することで、品質を高めることができる」と語る。
そして、物流リードタイムの短縮においては、基板実装ラインでの自動倉庫の導入とともに、組立ラインにおいても、自動倉庫の導入する計画を初めて明らかにした。現在、人が巡回し、デジタルピッキング方式によって、正しい部品を調達し、それを人手あるいは、搬送ロボットによって、組立ラインに供給している仕組みを進化。自動倉庫からの自動ピッキングと、1台ごとのセット供給を実現するという。
宮下執行役員常務は、「出庫に関しては、すでにパレタイズロボットを導入し、自動化を図っている。部品の入庫、ピッキング、部品のラインへの供給などの自動化については、2025年度から徐々にやり始めることになる。2030年度には自動倉庫とアームロボットの組み合わせによって、自動化率を80%に高めたい」とする。
神門社長も、「他社を凌駕するパフォーマンスを目指して、自動化、デジタル化の活動を積極化し、2030年度の削減目標の達成につなげる」と意欲を見せた。
島根富士通でレノボブランドのPCを生産か?
冒頭に触れたように、島根富士通が、長期的な指標として新たに掲げたのが、2050年に累計生産1億台という目標だ。さらに、3年後には累計生産で6,000万台という目標も掲げて見せた。
これは極めて大きな目標となる。たとえば、4,000万台から5,000万台までの1,000万台の生産には、5年7カ月の期間を要していたが、3年間で100,0万台という数値の上乗せは、その半分強の期間で達成するという目標になるからだ。
現時点で、島根富士通の年間生産能力は最大で300万台であり、これまでの過去最高生産台数が年間240万台。目標を達成するには従来とは次元が異なる生産体制を敷くという姿勢の表れと受け取ることができる。
しかも市場環境を捉えると、2025年度までは、Windows 10のEOS特需があるものの、その後は一気に需要が冷え込むと見られていることや、今後2年間で約1,000万台の新たな需要が見込まれるGIGAスクール構想第2期において、商談を担当する富士通では、GIGA全体の10%程度しか見込まれないWindows PCだけを取り扱うことに決めており、GIGAスクールによる出荷量の拡大はほぼ見込めないと言っていい。
つまり、2026年度以降は生産台数が低下する中で、過去最高を更新し続けるという目標を掲げたことになり、その計画は、あまりにも高いハードルだと言わざるを得ない。
そして今回、島根富士通が打ち出した1億台の目標についても、描かれた累計生産台数推移の成長曲線が、2030年度以降にまるでギアが1つ上がったようなカーブを描いているのである。
では、なぜこれだけ強気の姿勢を打ち出すことができるのだろうか。
今回の取材で、神門社長はこれまでになかった新たな構想を打ち出した。それは、グローバルに展開することを意味するものだった。
神門社長は、「レノボグループの一員として、グローバル展開ができないかということを考えている」と明かす。
FCCLは、すでに海外市場から撤退しており、2025年1月に発表したFMVのブランドリニューアルにおいても、新たなコンセプトの1つに、「日本のお客様を見つめ、コンピューティングテクノロジーで日本の暮らしを応援すること」を掲げ、日本市場にフォーカスすることを強調している。
また、Fujitsuブランドの法人向けPCの販売を担当している富士通も、PC事業についてはすでに海外市場から撤退している。
つまり、今後需要縮小が見込まれる日本市場だけをフォーカスしたFCCLのPCだけでは、生産台数の拡大は見込めないのは明らかで、この意欲的な目標を達成するには、グローバルで展開する、他ブランドのPCの生産を請け負うことが必須となるのだ。
神門社長は、「レノボブランドのPCを生産するかどうかはまだ見えていない」と言葉を濁すが、「レノボグループは全世界で年間5,000万台、6,000万台のPCを販売している。そこにMADE IN JAPANの高付加価値を提供できるかどうかといったことを、私自身の個人的な思いとして期待している」と述べる。
そして神門社長は、「島根富士通は、2025年1月に累計生産5,000万台に到達したが、これは通過点に過ぎない。次の未来に向けて進化する」と、力強く宣言する。
次の未来に向けて、ギアを1つ上げることができるのか。そしてどんな戦略転換を行なうのか。累計生産5,000万台の達成を迎えた2025年を起点にした、これから数年が、島根富士通の今後の成長に向けて、重要な意味を持つことになりそうだ。
初公開となったFMV Note Cの組立ライン
今回の取材では、2025年1月16日に発表したFMV Note Cの組立ラインを初めて外部に公開した。
FMV Note Cは、若年層をターゲットにしたノートPCで、若手社員で構成したFMV From Zero Projectを2022年に発足。若手の感性を生かして開発したのが特徴だ。富士通クライアントコンピューティングの大隈健史社長は、「2025年1月に実施したFMVのブランドリニューアルを象徴する製品」と位置付け、まさに戦略的商品と言える存在だ。
では、写真を通じて、FMV Note Cの組立ラインを追ってみよう。FMV Note Cならではの工程もあり、生産へのこだわりが見てとれる。
デスクトップPCなどの工程も公開
一方で、デスクトップPCの生産工程などについても公開した。こちらの様子も写真で紹介する。


















































































![[Amazon限定ブランド]CCL い・ろ・は・すラベルレス 2LPET ×8本 ミネラルウォーター 無味 製品画像:2位](https://m.media-amazon.com/images/I/41h0MHfvhkL._SL160_.jpg)


















![【中古】 ASUS EeeTop PC ET2002 Atom 330 1.6GHz Windows7モデル 液晶一体型 均一 BIOS表示可 HDMI ジャンク 送料無料 [91056] 製品画像:8位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/risemark/cabinet/pic/910b/91056.jpg?_ex=128x128)



![【3年保証】HP PRODESK 600 G5 [新品SSD] SSD256GB メモリ8GB Core i5 Windows 11 Pro 中古 返品 送料無料 中古デスクトップパソコン 中古パソコン デスクトップパソコン デスクトップ PC OFFICE付き 製品画像:4位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_gold/pcwrap/goods/4bo250011_1.jpg?_ex=128x128)











![【エントリーで最大2万ポイント当たる|2/25まで】 DELL|デル PCモニター Dell 27 Plus ホワイト S2725DSM-R [27型 /WQHD(2560×1440) /ワイド /144Hz] 製品画像:4位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/biccamera/cabinet/product/15031/00000014663194_a01.jpg?_ex=128x128)

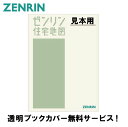

![REAL TRUCKS 9(トラック魂 特別編集) [ トラック魂 編集部 ] 製品画像:28位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/8254/9784865428254.gif?_ex=128x128)
![ドラゴンクエストの生みの親 堀井雄二 新学習まんが人物館 (小学館版 学習まんが人物館) [ 堀井 雄二 ] 製品画像:27位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/2073/9784092702073_1_50.jpg?_ex=128x128)
![[新品]進撃の巨人 (1-34巻 全巻) 全巻セット 製品画像:26位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/mangazenkan/cabinet/syncip_0020/si-506_02.jpg?_ex=128x128)
![【楽天ブックス限定特典】コアラ沼への招待状(豪華オリジナルシール1枚) [ 早川 卓志 ] 製品画像:25位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/8236/2100014838236.gif?_ex=128x128)
![超かぐや姫!(1) (ファミ通文庫) [ スタジオクロマト・スタジオコロリド ] 製品画像:24位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/7348/9784047387348_1_23.jpg?_ex=128x128)

![看護師・看護学生のためのレビューブック 2027 [ 岡庭 豊 ] 製品画像:22位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/9698/9784896329698_1_3.jpg?_ex=128x128)
![ルイ・ボナパルトのブリュメール18日 (講談社学術文庫) [ カール・マルクス ] 製品画像:21位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/3464/9784065193464_1_22.jpg?_ex=128x128)