大河原克行の「パソコン業界、東奔西走」
“モダンPC”訴求で個人向けPC市場活性化を狙う日本マイクロソフト
2019年5月8日 06:00
国内PC市場は、法人向けPCは2桁増の高い成長しているものの、個人向けPC市場は、ようやく長い低迷から抜け出しはじめたところだ。市場低迷が長期化した背景には、個人向けPCの購入サイクルの長期化や、学生のPC離れなどが指摘されている。そうしたなか、日本マイクロソフトが、「モダンPC」の訴求で成果をあげてはじめている。
モダンPCは、Windows 10の機能を最大限活用したPCで、これによって、PCの新たな魅力を訴求。同時に、10数年ぶりに、日本マイクロソフトとインテルが共同でキャンペーンを行なうなど、業界を巻き込むかたちで、買い替えサイクルの短縮に取り組んでいる。
一方で、3月から実施した新大学生を対象にしたプロモーションでは、「大学生に、ノートPCはいらない。」という異例のメッセージが話題を集めた。日本マイクロソフト 執行役員常務 コンシューマー&デバイス事業本部長の檜山太郎氏に、個人向けPC需要拡大の切り札に位置づける「モダンPC」の取り組みについて聞いた。
――2018年度下期から、ようやく個人向けPC市場が回復基調に転じました。法人向けPC市場に比べて、需要低迷が長期化した理由はなんでしょうか。
檜山氏(以下、敬称略) 個人向けPC市場は、2014年4月のWindows XPのサポート終了に伴う特需以降、前年割れが続いてきました。法人向けPCは、2020年1月のWindows 7のサポート終了に伴う買い替え需要が前倒しで進んでいることや、働き方改革などを追い風にして、すでに前年比2桁成長を続けています。しかし、ご指摘のように、個人向けPC市場は、2018年度下期から、ようやく回復しはじめたところです。
個人向けPCの需要低迷から抜け出せなかった理由はいくつかありますが、その1つに買い替えサイクルが長期化している点が挙げられます。内閣府が2019年4月に発表した「消費動向調査」によると、PCの平均使用年数は7年となっています。
10年前の2009年の調査では、5.3年であったことと比較しても、長期化していますし、主要先進国における買い替えサイクルが3~5年となっていることに比較しても、平均使用年数の長さが際立ちます。日本での買い替えサイクルの長期化は、Microsoft本社でも課題の1つと捉えています。
さらに、この状況を分析すると、首都圏に関しては、3~5年の買い替えサイクルとなっており、欧米の先進国と同じサイクルになっているものの、地方においては、9~10年という買い替えサイクルになっていることがわかりました。
しかも、地方で使われているPCは、海外の人たちから、「弁当箱」と称されるかたちのノートPCが中心になっています。15型クラスの液晶ディスプレイを搭載し、HDDや光学ドライブを搭載したノートPCであり、PCとして必要とされるインターフェイスはひととおり搭載しており、重量は2kg以上。家のなかだけの移動やほぼ固定して利用するといった使い方が中心となっています。
量販店では、これらのノートPCが購入しやすい価格で販売されており、地方の量販店では、こうした製品ばかりを展示しているケースが見られます。もちろん、こうしたPCの存在を否定するわけではありませんし、これが日本のユーザーのニーズに合致した製品であることはよく理解しています。
しかし、10年前のPCのままですと、Windows 10が提供する最新の機能が使えず、いまのPCの魅力を活かすことができません。最新のPCの魅力を知らないため、メールをしたり、検索をしたり、ちょっと文書を書くために、動くPCが1台あればいいということになり、それが買い替えサイクルを長期化させ、個人向けPC市場の低迷につながっていると見ています。
一昔前のPCよりも大きく利便性が向上している「モダンPC」
――5年前や10年前のPCにはない、Windows 10の機能とはなんですか。
檜山 Windows 10搭載の最新PCでは、AIの機能を活用して、さまざまな使い方ができます。たとえば、PCのなかに大量の写真が保存されていた場合にも、AIによる顔認識機能を使って、お父さんが写っている写真、子供が写っている写真を、瞬時に分類して表示するといった使い方も可能です。
また、Windows 10で動作するOffice 2019の翻訳機能は、60カ国語以上に対応しており、わからない単語をWebで調べて、ワード文書のなかにカット&ペーストして入れるといった作業も不要になります。膨大な資料を外国語へ翻訳する場合にも最適です。日本マイクロソフトでは、こうした最新の機能を利用できるPCを「モダンPC」呼んでいます。
――モダンPCの定義を教えてください。
檜山 モダンPCは、「機能性と美しさを備えた安心快適なPC」を指しています。薄型、軽量と長時間バッテリ駆動を実現したPCや、タブレットにもなる2in1型の構造により、モバイル利用にも最適化したりといった特徴のほか、SSDやeMMCの搭載によって、高速に起動したり、衝撃に強く持ち運びにも安心といったPCを指します。
さらに、タッチやペン、顔認証や指紋認証などの最新機能を搭載し、直感的な操作や高いセキュリティを実現しています。そして、Windows 10の機能を最大限に利用するために、最新のIntel Coreプロセッサを搭載し、Office 2019を搭載していることも、モダンPCの条件の1つです。
モダンPCは、国内ではPCメーカー13社から、100機種以上が発売されており、世界最軽量の約698gを実現し、SSDによる高速起動を実現した「富士通 LIFEBOOK UH-X/C3」、カバンに収まるコンパクトサイズながら、約 11.7 時間の長時間駆動を実現したNECパーソナルコンピュータの「LAVIE Note Mobile NM550/MAG」、dynabook30周年モデルと位置づけられる「Dynabook G8(P1G8JPBL)」、クラス最高水準の性能を実現した13.3型ノートPC「デル XPS 13」、回転するタッチディスプレイを搭載し、用途や姿勢に合わせた自由なスタイルでの使用を可能にした「HP Spectre x360 13」、コンパクト筐体ながら持ち歩きに必要な強度を実現した360°回転式コンパクト2in1モバイルPCの「パナソニック レッツノート RZ8(CF-RZ8BDFQR)」、11.9mmのスリムボディを実現した「レノボ Yoga S730」、そして、長時間のバッテリを実現し、タッチ操作やペン入力にも対応した「Microsoft Surface Laptop 2」などが、モダンPCの代表的な製品と言えます。
日本マイクロソフトでは、「モダンPC」のステッカーを用意して、量販店店頭での展示のさいに、どれがモダンPCであるかがわかるようにしています。モダンPCの魅力を知っていただくことで、長年使用していたPCを、最新の環境に移行することのメリットなどを理解していただけたらと考えています。
Windows 7のサポート終了によって、仕方なくPCを買い替えるのではなく、新たなPCによって、より創造性を発揮してもらったり、効率性を高めてもらったりといったように、生活や仕事を変え、楽しく利用してもらえる環境を提案したいと考えています。
――100機種以上のモダンPCがあるとのことですが、実際に販売構成比はどれぐらいですか。
檜山 まだ低く、4割弱といったところです。ただ、首都圏では半数以上にまで比率が上昇している一方で、地方ではかなり低い状況なのが実態です。じつは、アジアでは、個人向けPCのほぼ100%がモダンPCという国もあるほどです。
私は、日本のPC業界にとっても、モダンPCの比率を高めることが、個人向けPCの買い替えサイクルの短縮につながり、業界の活性化にもつながると考えています。実際、モダンPCの購入者は、友達にPCを紹介する人が5倍に上昇し、次も同じメーカーのPCを購入したいという人が、40%も上昇するなど、PCメーカーにとってもプラス効果があります。
最新のPCを使ってもらえないと、PC本来の魅力が伝わらず、どんどんPCから離れていくことになります。日本のPC業界の活性化という点でも、モダンPCの比率を高めることが重要ですし、Windowsのエコシステムを最大限に活用するためにもモダンPCは重要です。
そして、日本の国際競争力の向上や、学生や社会人のクリエイティテビティを刺激したり、家族やシニアが生活を楽しむためにも、モダンPCがはたす役割は大きいと考えています。小学生だった子供が就職するときには、いまの職業の65%がなくなっていると言われており、新たに生まれる仕事の多くが、ITやクラウド関連に付随する職種になると見られています。
モダンPCは、そうした子供たちの未来に向けた環境を整えるという意味もあります。小学生が10年後に社会に出たときに必要とされる資質はなにかということを考えた場合、家にある古いPCでは、それをサポートできません。
欧米や日本でも、すでに働き方が「協働」へと変化してきています。従来のコミュニケーションの取り方は、パワポを使ってプレゼンテーションをしたり、メールでやりとりをしたりといった手法であり、メッセージアウト型のコミュニケーションが中心でした。私たちも、そのための教育を受けてきました。
しかし、いまでは、自分の意見だけでなく、相手も意見も聞きながら、問題意識を共有し、創造力を持って課題を解決していく仕事の仕方が増えており、将来の働き方もその方向に向かうことになるでしょう。
日本マイクロソフト社内では、Teamsを導入し、これによって、双方向型のコミュニケーションで仕事をしています。意見の上に意見を重ねていって、結論を導くというやり方もその1つです。こうしたコミュニケーションの仕方を学ぶ必要があり、そのためのツールが最新のPCに搭載されています。
さらに、いつでも、どこでも、という環境で働いたり、学んだりすることが前提となるのであれば、それに最適なPCが必要です。そこにも、携帯性に優れ、バッテリ駆動時間が長いといった特徴を持つモダンPCが役割をはたします。
こうした狙いからもわかるように、モダンPCの提案は、Windows 7のサポート終了に向けた買い替え提案ではなく、長期的な視点で取り組んでいくものになります。
――地方では、クルマでの移動が多いですし、日本人特有のなんでも入っているものがほしいという要望もあります。地方では、モダンPCまでは必要がないという考え方もありますが。
檜山 ただ、10年前のPCでは、PCの使い方が限定的になってしまいます。また、選択肢を提案できていないため、本当に自分に最適なPCを選ぶことができていたのか、そのための情報が提供できていたのかという課題もあります。結果として、モダンPCではないPCを購入してしまったという人もいるのではないでしょうか。
かつては、首都圏で売れた新たなPCが、次には、地方で売れるという流れがありました。しかし、いつかのタイミングから、その流れがなくなってきました。約2年前に調査したときに、首都圏で売れているPCと、地方で売れているPCには大きな差があり、売れ筋の機種が乖離していることを知りました。首都圏では、こんな使われ方をしており、それによってこれだけのメリットを生んでいるということや、そうした使い方が格好いいというような魅力が、地方に訴求しきれていないという反省があります。そこで、いくつかの取り組みを開始しました。
日本マイクロソフトによるPC訴求のための2つの施策
――具体的には、どんな取り組みですか。
檜山 1つは、「NEW BUDDY」というキャンペーンです。これは、昨年(2018年)の年末商戦向けに展開したキャンペーンで、「家族」に対して、モダンPCを訴求するものとしました。30~40代の家族や、15歳までの子供を持つ家族をメインターゲットにして、一家に1台、最先端のPCがあるとどんなことができるかといったことを訴求しました。
ここでは、モダンPCの機能を紹介するよりも、活用シナリオを前面に打ち出し、大量の写真を顔認識で検索して、アルバムを簡単に作れたり、動画作成やライブ配信が手軽に行なえたり、3D画像を扱うことができることで、どんな楽しみ方ができるのかといったことを提案しています。
じつは、このキャンペーンは、日本マイクロソフトとインテルと共同で行ないましたが、2社が共同キャンペーンを行なったのは、10数年ぶりになります。
もちろん、イベントなどを共同で行なうことはありましたが、キャンペーンのプランニング段階から共同ではじめ、同じターゲットに向けて、同じクリエイティブを使ったキャンペーンを行なうのは、本当に久しぶりです。もしかしたら、2001年のWindows XPの発売以来かもしれません(笑)。
個人向けPC市場の低迷、買い替えサイクルの長期化、首都圏と地方都市との売れ筋の乖離、先進国との比較によるモダン化の遅れといったことに対する危機感を共通認識として持ったことが背景にあります。キャンペーンのサイトには、久しぶりに、MicrosoftのロゴとIntelのロゴが並んで表示されました(笑)。
そして、2つ目が「ENTER!」というキャンペーンです。
――「ENTER!」は、どんなキャンペーンですか。
檜山 これは、日本マイクロソフトのほかに、ASUS、NECパーソナルコンピュータ、dynabook、デル、日本HP、パナソニック、富士通クライアントコンピューティング、レノボ・ジャパンの8社のPCメーカーとともに共同で行なっているモダンPCのキャンペーンです。
2月8日から5月12日までの期間で行なっています。「好奇心に、飛び込め。」をキーワードに、大学に入学した学生、社会人デビューする人、子供と一緒に新たな学びをスタートする人、新しい趣味や習い事をはじめるアクティブシニアなど、入学、就職、入社、転職、結婚、出産、趣味、定年、退職といったライフステージの変化において、幅広い層の人たちの新しいチャレンジを、モダンPCを活用することで、もっと楽しく、簡単にするための活用シナリオを提案するものになります。
キャンペーンサイトでは、ENTERボタンをデザインしたものを採用しており、モダンPCのENTERボタンを押して、新たな世界に飛び込んでほしいという意味を込めています。
これまでは、PCメーカー各社ごとに、それぞれの意図を持ったかたちでキャンペーンを行なってきたのですが、そうした取り組みでは、個人向けPC市場の低迷から脱却できないままでした。そこで、各社の協力のもと、PC業界全体が同じメッセージで、強力に訴求するキャンペーンを行なうことにしました。
最初は、PCメーカー各社も、自らの特徴を訴求できる独自のキャンペーンを実施したいという要望が多かったのですが、ここ数年の需要低迷に危機感を持っており、この取り組みに賛同をしていただきました。さらに、量販店にも協力をあおぎ、ここでも同じメッセージで展開してもらうことにしました。
量販店も独自の展示方法やメッセージを重視するなかで、エディオン、ケーズデンキ、ジョーシン、ビックカメラ、ヤマダ電機、ヨドバシカメラ、Amazon.co.jpの各社が足並みをそろえたかたちで訴求を行ないました。量販店の間にも、業界全体を盛り上げていきたいという思いが背景にあったと言えます。量販店における取り組みの1つとして、主要店舗において、4月以降、モダンPCコレクションという売り場を設けて、モダンPCを比較しやすくしたり、使い方に沿った購入がしやすいようにしました。
日本マイクロソフトでは、全国27店舗で専用の什器を使ったWindows PCだけを展示した売り場づくりを行なってきましたが、これを6月末までに400店舗にまで拡大し、モダンPCコレクションの名称を使って、モダン PCの集合展示を行ないます。「どこになにがあるかわからない」、「ほしい製品が見つからない、比較ができない」 、「製品の特長がわからない、違いはなにか」といったお客様の声を反映した売り場としています。
そして、この「ENTER!」キャンペーンには、「NEW BUDDY」キャンペーンに続き、インテルに参加してもらっています。
――一方で、今年(2019年)春に実施した大学生向けプロモーションが、ちょっとした話題になっていますね。
檜山 3月1日から開始した新たに大学生を対象にしたこのプロモーションでは、「大学生に、ノートPCはいらない。」というメッセージが話題を集めました。昨年、同時期に実施したプロモーションに比べても、SNSへの書き込みは、18倍にもなりました。このメッセージに対して、「よくやった」という反応もありましたが、その一方では、「どうなのか」といった声もあったのも事実です。
このプロモーションでは、スマートフォンや学校の古いPCで、日常のさまざまなタスクを器用にこなしていく現役大学生の姿をテンポよく描きながら、「本当にノート PC はいらないのだろうか?」、あるいは「なにかになりたくて大学に入ったはずだ」といったことを、現役大学生でありながら、映像クリエイターとしても活躍する清水良広さんが問いかけ、新大学生に新たな気づきを与えるものとしました。
前半は、ノートPCがなくても、楽しい大学生活を送れることを示しながら、後半には、映像監督として清水さん自身が登場し、「Surface があれば、キミはなににだってなれる」と大学生を鼓舞し、「解き放て、創造力」という言葉を投げかけ、ノートPCがあれば、もっと楽しい大学生活を送れることを示しています。
このプロモーションをきっかけとして、大学時代を楽しんだり、有意義に過ごすためにはノートPCは必要であることや、社会に出たときのために、PCを使っておくことが大切であるといった声もあがっていました。こうしたSNSの反応を見ても、PCの必要性を提示できたいい機会になったと思っています。
ちなみに、このプロモーションにあわせて、Surface Pro 6にタイプカバーを付属したセットモデルを数量限定で販売したり、最大4万円をキャッシュバックする学生優待プログラムも用意しました。
――大学生のPC離れが指摘されていますが、それを解決する提案にもなりましたか。
檜山 確かに、政府のコメントでも大学生のPC離れが指摘されていますが、実際には、多くの大学生がPCを利用しています。日本マイクロソフトの今年3月の調査によると、「大学の課題・授業などのメモや資料作成において、PCとスマートフォンのどちらを使用しますか?」という質問に対して、スマートフォンのみの利用はわずか6%にとどまり、スマートフォンとの併用を含むPCの利用は85%に達しています。
しかも、そのうち、48%の学生がPCだけを利用していると回答しています。ただ、PCを使い倒しているのか、協働を前提にした新たな使い方ができているのかという点では、課題があるとも思っています。今回のプロモーションは、大学生のPC離れを解決するという切り口ではなく、大学生に対して、こんなPCの使い方をしてはどうか、といったことの提案になります。
――こうした一連のキャンペーンの成果はどうですか。
檜山 強い手応えを感じています。NEW BUDDYやENTER!のキャンペーンを通じて、モダンPCの構成比が一気に上昇しています。さらに、新大学生向けのプロモーションがはじまって以降、その勢いが加速しており、モダンPCの構成比は、市場全体で6割弱にまで高まっています。
そして、なんと言って、個人向けPC市場が前年実績を上回るかたちで推移しはじめたことが大きな成果です。とくに、地方における成長率が高くなっています。地方におけるモダンPCの展示も増加し、販売が増えています。
また、キャンペーンを開始して以降、来店して、PCを触る人が増えており、これまでにはなかったOneNoteを使って、ペンを体験する人も増えています。店頭デモのコンテンツを工夫した成果もあり、とくに、地方の店舗でさわってみるという動きが目立っています。
私は、Windows 7のサポート終了の駆け込み需要や、消費増税前の特需といった影響がまだ本格化していない段階において、モダンPCによるシナリオ提案によって、需要を喚起できたことに手応えを感じています。今後、この提案を継続することで、さらに勢いを加速したいですね。
「ENTER!」のキャンペーンは、5月12日で終了しますが、今年の夏商戦や年末商戦などのキャンペーンも、できれば、PCメーカーや量販店など、業界全体を巻き込んだかたちで行なっていきたいと思っています。オーストラリアでは広大な土地のなかに400店舗しかありませんが、日本では、地方だけでも2,000店以上の店舗があり、地方においてもPCを店頭で購入しやすい環境が整っています。その環境を活かしつつ、そこにデジタルを組み合わせることで、地方におけるPCの買い替えを促進したいと思っています。これは、今後の重要なテーマだと言えます。
――ゲーミングPCに関しては、キャンペーンとしての取り組みがありませんが。
檜山 量販店にはゲーミングPCのコーナーが増加し、ゲーマーの購入だけでなく、おしゃれであるとか、コストパフォーマンスが高いPCという観点で、一般ユーザーがゲーミングPCを購入する例が増えています。また、ゲーミングPCの専用ブランド以外の製品でも、GPUを搭載した製品が増加しており、こうした製品にも注目が集まっています。ここに、Microsoftが持つゲームのプラットフォームをどう訴求するかが、2019年7月以降の当社新年度の重要なテーマの1つになります。そして、ゲーミングPCもモダンPCの1つとして提案していくことになります。











![[Amazon限定ブランド]CCL い・ろ・は・すラベルレス 2LPET ×8本 ミネラルウォーター 無味 製品画像:2位](https://m.media-amazon.com/images/I/41h0MHfvhkL._SL160_.jpg)


























![INNOCN 25G1H [24.5型ゲーミングモニター/240Hz/Display Portx2、HDMIx2] 製品画像:22位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/etre/cabinet/itemimage33/1289757.jpg?_ex=128x128)
![フィリップス(ディスプレイ) 241S9A/11 [23.8型液晶ディスプレイ/1920×1080/HDMI、D-Sub/スピーカー:あり/5年間フル保証] 製品画像:21位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/etre/cabinet/itemimage26/1267243.jpg?_ex=128x128)




![ビブリア古書堂の事件手帖V ~扉子と謎めく夏~(5) (メディアワークス文庫) [ 三上 延 ] 製品画像:30位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/3247/9784049163247_1_4.jpg?_ex=128x128)
![きのう何食べた?(25) (モーニング KC) [ よしなが ふみ ] 製品画像:29位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/3165/9784065423165_1_2.jpg?_ex=128x128)

![世界最速のレベルアップ (9)【電子書籍】[ 鈴見 敦 ] 製品画像:27位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rakutenkobo-ebooks/cabinet/1042/2000019711042.jpg?_ex=128x128)
![異世界で土地を買って農場を作ろう (11) 【電子限定おまけ付き】【電子書籍】[ 岡沢六十四 ] 製品画像:26位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rakutenkobo-ebooks/cabinet/6928/2000019746928.jpg?_ex=128x128)
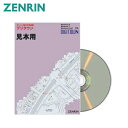
![WBC2026観戦ガイド [ 世界文化社 ] 製品画像:24位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/1130/9784418261130_1_3.jpg?_ex=128x128)
![anan(アンアン) 2026年 3月4日号 No.2485[エンタメの系譜2026]【電子書籍】[ anan編集部 ] 製品画像:23位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rakutenkobo-ebooks/cabinet/9578/2000019779578.jpg?_ex=128x128)

