大河原克行の「パソコン業界、東奔西走」
東芝の故・西田厚聰氏は東芝のPC事業に何を残したのか?
2017年12月28日 06:00
東芝の社長および会長を務めた西田厚聰氏が、2017年12月8日13時53分、急性心筋梗塞のため東京都内の病院で死去した。享年73歳。
葉巻を愛するヘビースモーカーで、取材中にも葉巻が切れることがなかった。その煙が気になって、いつもは取材後に行なう写真撮影を、取材前に行なったことがあった。写真撮影が終わった後は、気兼ねなく葉巻を吸ってもらい、背広も脱いでリラックスして取材を受けてもらった。いつもよりも饒舌だったような気がする。
読者にとって、西田氏のイメージは、晩年に起こった東芝不正会計問題の中心的人物というものだろう。
東芝の経営トップが、事業責任者や社員に対して、「チャレンジしてほしい」という言葉を使い、目標達成や利益拡大を強要したり、PC事業において、「Buy-Sell(バイセル)取引」という仕組みを通じて、組織的に利益をかさ上げし、不正な会計処理を行なったりといった事実が明るみになり、相談役だった西田厚聰氏、当時の社長であった田中久雄氏、副会長の佐々木則夫氏の歴代3社長が辞任するなど、あわせて8人の取締役が辞任。
その後、西田氏が社長時代に買収した原発事業のウェスチングハウスが大規模な減損を発表。これをきっかけに債務超過に陥り、土俵際とも言える状況で、経営再建に挑んでいるところだ。
経営再建のために、収益部門であったヘルスケア事業、家電事業、メモリ事業、テレビ事業の売却を決定。さらに、PC事業の売却にも踏み出そうとしている。
残るのはエレベータや鉄道などの社会インフラ事業のほか、エネルギー事業、ICTソリューション事業だが、どれも東芝の柱となるには迫力に欠けるとの指摘もある。
東芝を窮地に追い込んだ「戦犯」というイメージを、払しょくできないままに晩年を過ごしたのは残念だ。
西田氏の経歴は、東芝のなかでも異色だ。
1943年12月29日生まれ、三重県出身。つまり、ちょうど明日(29日)、74歳を迎えるところだった。西田氏は、東京大学大学院法学政治学研究科卒業後に、イランで東芝が合弁で設立した現地法人に入社。その2年後となる1975年に帰国して東芝に入社しているが、このときすでに31歳という年齢だった。2005年に東芝の社長に就任、2009年には会長に就き、2014年からは相談役に退いていた。
学生時代は政治哲学を学び、海外子会社からの入社。しかも、31歳という年齢での東芝入り。そこから社長に昇りつめたのは、もちろん前例がない経歴だ。
ちなみに、西田氏がイランで東芝現地法人に入社した背景には、学生時代に結婚したイラン人女性の妻の存在が避けられない。先に、イランの東芝現地法人に勤務していた妻の紹介で、西田氏は、同現地法人に入社したからだ。
東芝入社後の西田氏は、欧州や米国の現地法人を担当し、1995年6月にパソコン事業部長に就任した。まさにWindows 95が投入される直前のタイミングでの就任となった。
この間、西田氏の手腕は社内外から高い評価を得ていた。
欧州の現地法人に勤務していたときには、東芝のノートPCを欧州市場に定着させ、トップブランドへと引き上げる一方、1991年に起こった「コンパック・ショック」により、米国市場で低価格化が進んださいにも陣頭指揮を執り、米国のPC事業を立て直したのも西田氏だった。
東芝のPC事業は、日米欧の3極で事業を展開しており、ブランド価値を高めるという点で重要な欧州市場で存在感を発揮したり、もっとも競争が激しい米国市場で存在感を発揮し続けたりすることは、同社のPC事業の成長を左右する重要な要素であった。そこがほかの国内PCメーカーとは異なる東芝特有の部分であり、西田氏はその期待に十分応える実績を残した。
1996年には米国における市況低迷を背景にした在庫過剰問題が発生。そのさいにもパソコン事業部長ながらも、急遽米国に赴任し、その解決に当たるなど、火中に飛び込んでいく、行動派の人物でもあった。外から見ていると、PC事業のピンチの時に現れて、事業を立て直すというイメージすらあった。
西田氏は、かつての東芝がPC事業で成功した要因の1つに、「事業を開始した当初からグローバルを視野に入れていたこと」を挙げていた。「グローバル市場でいかに勝ち抜くかということを視野に入れて、危機感を持って事業に取り組んできたことが、東芝のPC事業における成長の原動力となっている」とする。
そして、日本マイクロソフトのあるOBは、こんな逸話も披露してくれたことがある。
「米Microsoftのビル・ゲイツやスティーブ・バルマーが来日すると、日本のPCメーカーの多くの幹部が面談をしても、社交辞令を英語で述べるに留まっていた。だが、日本では3人だけ、自らの意見を率直に述べ、英語で議論する人がいた。1人は、NECの戸坂馨氏(2007年逝去)、2人目は、ソニーの石田佳久氏(現シャープ副社長)、そして、東芝の西田厚聰氏だった」。
2005年6月27日には、前週に東芝社長に就任したばかりの西田氏が、米Microsoftのビル・ゲイツ会長を同席させた会見を行なってみせたが、このとき、ゲイツ会長が「東芝は、世界で最もタブレットPCを生産している企業。私も東芝のタブレットPCを使用している」と語っていたのが印象的だった。
西田氏は、まさに世界と戦っていたのだ。
西田氏の号令で、多くのユーザーの声を聞き、それを製品に反映させるという仕組みを採用したのも、西田氏がPC事業を統括していたころのことだ。
東芝では、数千人規模のユーザーを対象にヒアリングを定期的に行ない、東芝のPCのどこが良いのか、どこが悪いのか、使い勝手はどうかといったことを市場の声として収集。これをモノづくりに活かしていった。
SNSがない時代に、これだけの情報収集を行なうのは、かなりのこだわりがないと実行に移せない。これ以降の製品企画には、ユーザーの声が数多く反映されている。
また、2001年10月には、東京・青梅の青梅工場内に、開発センターを竣工。当時、デジタルメディアネットワークス社の社長として、PC、映像、磁気ディスク、通信などの技術者3千人を1カ所に集め、これらの技術を融合した製品の開発にも着手した。マルチメディア機能を搭載したノートPCの開発に拍車がかかったのも、これ以降のことだ。
こうした新たな仕掛けを、大胆に行なってきた点は評価されるものだろう。
そして、首位を維持することへのこだわりも強かった。東芝は、2000年まで、7年連続でノートPCの世界シェア1位を獲得していたが、2001年にデルに抜き去られ、2位になった。このとき、西田氏にインタビューしたことがあった。
西田氏は、「1位になれば、新たな市場を作るというリーダー戦略を推進できるが、2位になった途端、1位のフォロアー戦略に終始することになる。つまり、1位にならないと、リーダーとして、市場を開拓する製品を出すことはできない。1位と2位の差は、数字では僅差であったとしても、事業に与える差はきわめて大きい」と答えていた。
とくに、強調したのが、技術者のモチベーションが下がっているという課題だった。
「2位になった途端に、技術者が委縮してしまい、新しいものを出していく、という意欲が見られなくなった。あるいは、失敗を恐れているという感じが伝わってきた。これでは東芝の力を本当に発揮できる製品が出てこない。シェアはますます下がるだけである。技術者が生き生きとモノづくりができる環境が必要である」と、当時のインタビューでは語っていた。
このときに見せた首位への強いこだわりは、社長経営にもつながったのは明らかで、東芝の拡大路線は西田社長体制になってから急加速した。これは残念ながら、振り返れば、無謀な拡大路線となり、東芝全体の経営には悪い結果になったと言わざるを得ない。
2006年に東芝はウェスチングハウスを買収したが、当時、社長を務めていた西田氏は、追加出資を含め、ウェスチングハウス買収に6,600億円を投資した。
これは、その半分でも高いと言われる投資規模であったが、それにも関わらず、買収に踏み切ったのは、原子力を軸とした社会インフラ事業を成長戦略に掲げ、売上高で2桁成長という意欲的な成長を計画していたことが背景にあった。
2010年に、東芝のノートPC事業が25周年を迎えたときに、当時、東芝の会長を務めていた西田氏に、PC事業を振り返ったもらったことがあった。
経団連副会長などの要職にあった西田氏が、PC事業に関した内容だけで取材を受ける機会は、すでにその時点では極めて異例であったが、楽しそうにPC事業について語っていたことが思い出される。そのインタビュー内容は本誌で紹介している。
そのさいに、西田氏は、「私自身、PC事業で学んできたことを、企業経営に活かしてきた。私は、企業経営には、『イノベーションの乗数効果』が大切だという言い方をしているが、この言葉を使うことができるのは、私自身がPC事業で数多くの経験をしてきたことが背景にある。もし、PC事業を経験していなかったら『イノベーションの創出』、『イノベーションの拡大』といった言葉ぐらいで止まっていた」と語り、変化が激しいPC市場での経験が東芝の経営に生きていることを示した。
実際、西田氏はそれを行動に移している。
「2005年6月に東芝の社長に就任したときに、この乗数効果の考え方を社内に取り込めないかと考えた。また、私が経験し、蓄積したPC事業のノウハウを、あらゆる部門に移植しようということも考えた。すべての事業部門を廻り、そのなかで乗数効果の意味を説いて廻った」と語る。
PC事業の手法を用い、それを東芝全体の社員の意識改革につなげ、スピード経営を実現したという点では、良い成果が生まれた事例だといえるだろう。もちろん、それは、西田氏の指示によって、PC事業が不正会計の温床となったことで、帳消しどころか、評価はマイナスになっている点を付け加えておかなくてはならないのは残念だ。
じつは、この取材のさいに、PC事業での失敗についても聞いてみた。
開口一番、西田氏が語った最大の失敗は、「デスクトップPC市場に参入したこと」だった。
1996年ごろに、法人顧客の声を聞いた結果、「ノートPCとデスクトップPCを含めた一括商談ができれば、コストダウン効果があり、導入しやすい」という声が挙がっていたことがきっかけとなり、デスクトップPCを開発したが、これが失敗に終わった。
当時は、デスクトップPCの構成比が高い時代であり、東芝にデスクトップPCの開発を期待するのは、当然のことであった。西田氏は、「開発したデスクトップPCの仕様が、時代を先取りしすぎた」と反省するが、東芝の特徴が発揮しにくい領域の製品であったことは確かだろう。
東芝は、その後、一体型のPCを発売したこともあったが、これをデスクトップPCとは表現しなかった。それほど、東芝にとって、デスクトップPCの失敗は堪えている。東芝の魅力を発揮できない領域ということが徹底されている。
東芝のPC事業は、一時期は、年間2千万台規模の出荷を目指す事業へと拡大した。だが、現在の東芝のPC事業は年間約180万台に留まる。10分の1程度にまで減少しているのだ。
そして、外資系PCベンダーへの売却の可能性が報じられるなど、日本のPCメーカー再編が進むなか、東芝のPC事業の今後の先行きが注目されている。
西田氏は、過去のインタビューのなかで、東芝の将来のPC事業の姿について触れ、「大きな意味でPCと言えるものは、これからも生き残る。だが、PCの形が変わり、今のようなスタイルのPCではないものがたくさん出てきたり、PCという呼び方ができないものも増えてきたりする。そのなかで東芝は、技術面で、製品面でもリーダーとなるものを提供し続けていく。その姿は変わらない」とコメントしていたことを思い出す。
果たして、東芝のPC事業はこれからどうなるのか。西田氏が残した良い面と悪い面を成長の糧に変えられるかが注目される。










![[Amazon限定ブランド]CCL い・ろ・は・すラベルレス 2LPET ×8本 ミネラルウォーター 無味 製品画像:1位](https://m.media-amazon.com/images/I/41h0MHfvhkL._SL160_.jpg)



![【Amazon.co.jp限定】 伊藤園 磨かれて、澄みきった日本の水 2L 8本 ラベルレス [ ケース ] [ 水 ] [ 軟水 ] [ ペットボトル ] [ 箱買い ] [ ストック ] [ 水分補給 ] 製品画像:5位](https://m.media-amazon.com/images/I/41n0o65dSkL._SL160_.jpg)

















![【新品】トレーディングPC4 FX 株 デイトレ 仮想通貨 22型×4画面マルチモニタ トレパソNEW Office Windows11 無線キー・マウス 多画面 [Core i5 14400F 16GB 500GB ] :新品 製品画像:1位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/whatfun-pc/cabinet/20/tpnew4_r.jpg?_ex=128x128)
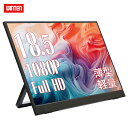
![【クーポン利用で★14,833円!】[五年保証] モニター 27インチ IPS (1920×1080/120Hz)|USB Type-C・HDMI接続対応|目疲れ配慮|スピーカー内蔵|Adaptive Sync|HDR10|sRGB110%|VESA対応|フレームレス |USB-Cケーブル付き (MF27X3A・ケーブル付属) Minifire 製品画像:12位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/minifire-direct/cabinet/120.jpg?_ex=128x128)




![液晶ディスプレイ アイ・オー・データ DI-CU271AB-F [4K対応 USB Type-C搭載 27型液晶ディスプレイ] 製品画像:7位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/etre/cabinet/itemimage24/1266247.jpg?_ex=128x128)






![ネットワーク図の描き方入門 分かりやすさ・見やすさのルールを学ぶ [ 萩原 学 ] 製品画像:27位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/7381/9784296207381_1_38.jpg?_ex=128x128)
![たのしい幼稚園 2026年 4月号 [雑誌] 製品画像:26位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/0461/4912010130461_1_2.jpg?_ex=128x128)
![JISハンドブック 3 非鉄(2026) [ 日本規格協会 ] 製品画像:25位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/1594/9784542191594_1_2.jpg?_ex=128x128)
![彗星起源感覚 市川春子イラストレーションブック2 [ 市川 春子 ] 製品画像:24位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/4858/9784065424858_1_3.jpg?_ex=128x128)
![JISハンドブック 2 鉄鋼 II 〔棒・形・板・帯/鋼管/線・二次製品/電気用材料〕(2026) [ 日本規格協会 ] 製品画像:23位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/1587/9784542191587_1_2.jpg?_ex=128x128)
![継母の心得3【電子書籍】[ ほおのきソラ ] 製品画像:22位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rakutenkobo-ebooks/cabinet/8330/2000019738330.jpg?_ex=128x128)
![JISハンドブック 6-2 配管 II(製品)(2026) [ 日本規格協会 ] 製品画像:21位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/1617/9784542191617_1_2.jpg?_ex=128x128)