Hothotレビュー

Core Ultra 7 165H搭載の最新NUC登場!高性能かつ静かなミニPC「ASUS NUC 14 Pro」
2024年6月25日 06:02
2020年くらいからデスクトップPC市場で存在感を強めているコンパクトな「ミニPC」の源流には、Intelの「NUC」(Next Unit of Computing)があると言ってよい。
NUC関連事業は2023年7月にASUSに移管されたが、これはミニPC市場の大幅な拡大によって、パイオニアとしての役割を終えたということもある。いちユーザーとしても、信頼性の高いIntelのNUC事業がそのままASUSに引き継がれ、新製品の投入や旧製品のサポートが継続されることは喜ばしいことだ。
今回紹介する「ASUS NUC 14 Pro」シリーズは、ASUSに事業移管後に最初に発売されるNUCの1つである。搭載CPUはノートPC向けで最新の「Core Ultra」シリーズで、第13世代Coreシリーズを搭載した「NUC 13 Pro」シリーズからは大きな性能向上が期待できそうだ。また、デザインや使い勝手なども細かく検証していこう。
従来のNUCシリーズを踏襲するデザイン、インターフェイスは多彩
ASUS NUC 14 Proシリーズでは、2.5インチベイを装備するやや厚みのある「Tall」タイプと、これを装備しない薄型の「Slim」タイプという2種類の筐体を用意する。
さらにそれぞれの筐体に対して、そのままPCとして利用できる「ASUS NUC 14 Pro Mini PC」シリーズと、ベアボーンPCの「ASUS NUC 14 Pro Kit」シリーズの2つをラインナップする。こうした構成は、IntelのNUC 13 Proシリーズでも同じだ。
今回はTallタイプのベアボーンPCに、メモリやSSD、Windows 11がインストールされた状態のモデルを試用した。CPUはCore Ultraシリーズの中でも上位モデルにあたる「Core Ultra 7 165H」、メモリはDDR5-5600 SO-DIMMの8GBモジュール×2で16GB、SSDは1TBという構成だった。
なお、このCore Ultra 7 165Hを搭載したベアボーンPCは未発売のモデルであり、現状では購入できない。ASUSの直販サイトや各種パーツショップでは、Core Ultra 7 155H、Core Ultra 5 125Hなどを搭載するモデルが購入できるので、すぐに入手したいならそちらを検討しよう。
| 【表1】ASUS NUC 14 Pro Kitのスペック | |
|---|---|
| OS | Windows 11 Pro |
| CPU | Core Ultra 7 165H(16コア22スレッド) |
| 搭載メモリ | DDR5-5600 SO-DIMM 8GB×2(空きスロットなし、最大96GB) |
| ストレージ | 1TB(PCI Express 4.0) |
| 拡張ベイ | PCI Express 4.0対応M.2スロット×2、2.5インチシャドー×1 |
| 通信機能 | Wi-Fi 6、Bluetooth 5.3 |
| 主なインターフェイス | 2.5Gigabit Ethernet、HDMI×2、Thunderbolt 4×2、USB 3.2 Type-C、USB 3.0×3、USB 2.0 |
| 本体サイズ | 117×112×54mm |
| 重量 | 570g |
Core Ultraシリーズでは、13世代Coreシリーズで採用されていた高性能コア(Performanceコア、Pコア)と高効率コア(Efficientコア、Eコア)に加え、省電力で動作する高効率コア(LowPower Eコア、LP-Eコア)を搭載する。こうした3種類のコアを状況に応じて使い分けることで、処理性能と省電力性を両立するという。
デザインは、IntelのNUC 13 Proシリーズをそのまま継承したようなイメージだ。幅や奥行き、高さなどのサイズ感も非常に似かよっており、以前レビューしたIntelのNUC 13 Proシリーズと比べても既視感がある。前面には小さくHDMIのロゴが入っているが、これもシンプルで目立たない。
片手の上に乗る程度のサイズ感は、昨今のミニPCとも似ている。また付属のACアダプタの出力は120Wまでで、本体と同様にコンパクトなので今回のASUS NUC 14 Proと一緒に持ち歩くのも容易だろう。ノートPC向けながらかなり高性能なCPUを搭載することもあり、120Wで足りるのかちょっと不安になったが、後述する消費電力のテストを見る限り、問題はなかった。
コンパクトな筐体ながら、インターフェイスは充実している。映像出力端子としてはHDMIを2基搭載するほか、高速データ通信にも対応するThunderbolt 4を2基装備する。いずれも4K解像度(3,840×2,160ドット)でリフレッシュレート60Hzの出力に対応しているため、大画面の4Kディスプレイを複数台接続してマルチディスプレイ環境を構築できる。
有線LANは2.5GBASE-T対応で、内蔵する無線LAN機能もWi-Fi 6対応。Thunderbolt 4のほかにも急速充電対応のUSB 3.2(20Gbps) Type-C、3基のUSB 3.0など、さまざまな高速データ通信ポートを備えており、USBハブを用意しなくても一通りの周辺機器は利用できるだろう。
このように外観やインターフェイス構成については、13世代Coreシリーズを搭載したIntelのNUC 13 Proシリーズを踏襲している。ASUSへの事業移管で、デザインや利用イメージが大きく変更する部分はない。今までのNUCを気に入って利用していたユーザーなら、安心して乗り換えられるはずだ。
新世代のCPUを搭載することで性能は大きく向上
気になる性能を見ていこう。本機が搭載するCore Ultra 7 165Hは、Hyper-Threading対応のPコアを6基、Eコアを8基、LP-Eコアを2基搭載し、合計で16コア22スレッドをサポートする高性能なCPUだ。また内蔵するGPUも、Core Ultraシリーズから「Intel Arc graphics」に変更されている。
今回はいくつかの標準的なベンチマークテストを行ない、1つ世代が古いIntelのNUC 13 Proと比較してみた。比較で使用した検証機では「Core i7-1360P」を搭載しており、これは性能重視のモバイルノートで搭載されることが多かったCPUだ。そうしたPCとの性能比較として考えるのもよいだろう。
| 【表2】検証機のCPUとGPU | |||
|---|---|---|---|
| CPU | コア/スレッド数 | 内蔵GPU | |
| ASUS NUC 14 Pro | Core Ultra 7 165H | 16コア/22スレッド | Intel Arc graphics |
| Intel NUC 13 Pro | Core i7-1360P | 12コア/16スレッド | Intel Iris Xe Graphics eligible |
Core i7-1360PのPコアは4基、Eコアは8基で、合計12コア16スレッドという構成になる。CPUの位置付けは近いが、Core i7-1360PはPコアが2基少ない上にLP-Eコアを搭載せず、内蔵GPUは1つ世代が古い「Intel Iris Xe Graphics eligible」となる。世代が進むことで、どの程度性能が向上するのかに注目したい。
まずは一般的なアプリの快適度をScoreで計測できる「PCMark 10 Extended」の結果だ。Scoreが大きいほど性能が高い。グラフを見れば分かる通り、おおむねすべての項目でASUS NUC 14 Pro Kitが勝利している。特に6,000台半ばという総合Scoreは、ビデオカードを装備しない構成のPCではなかなか見られないScoreであり、基本性能の高さが伺える。
次に3Dグラフィックスの描画性能を検証できる「3DMark」の結果をグラフにしてみた。すべてのテスト項目でASUS NUC 14 Pro Kitが勝利しており、内蔵GPUの性能は確実に向上していることが分かる。特にDirectX 12ベースの「Time Spy」では3,000台半ばというScoreを示しており、これはGeForce GTX 1650搭載のビデオカードを組み込んだ自作PCのScoreに近い。
CPUコア部分の性能を見るため、「TMPGEnc Video Mastering Works 7」で動画をエンコードする処理速度を計測した。処理にかかる時間が短いほど性能が高い。当然ながらコア/スレッド数が多いCore Ultra 7 165Hを搭載するASUS NUC 14 Pro Kitのほうが、すばやく処理できることが分かる。
以上のように基本的なベンチマークテストの結果を見る限り、世代が進むことで順当に性能が向上していることが分かる。特にGPU性能は、謳い文句通りの高い性能を示していることを考えると、PCゲームへの適性が気になるユーザーもいるだろう。
ここではさらに、比較的描画負荷の低い「レインボーシックス シージ」と、「ファイナルファンタジーXIV : 黄金のレガシー ベンチマーク」を実行し、実用的なフレームレートでプレイできるかどうかを検証した。
レインボーシックス シージのグラフィックス設定は、最も高い「最高」と下から2番目の「中」。解像度はフルHD(1,920×1,080ドット)とした。前述の通り比較的描画負荷の低いゲームなので、描画設定が最高の状態でも最低FPSは60を超えている。このクラスのゲームなら、問題なくプレイできそうだ。
ファイナルファンタジーXIV : 黄金のレガシー ベンチマークのグラフィックス設定は「高品質(デスクトップPC)」と「標準品質(デスクトップPC)」を試した。解像度はレインボーシックスと同様にフルHDとした。ちなみに最も高い「最高品質」では描画がかなりカクつき、プレイに支障が出た。
高品質(デスクトップPC)の評価は「普通」だったが、実際はぎこちなく感じる場面もそれなりにあり、快適かどうかはプレイスタイルにもよるだろう。標準品質(デスクトップPC)の評価は「やや快適」となり、動きが引っかかる場面はかなり減る。レポートでチェックできる平均FPSは60に届かないが、個人的にはそれなりに不満のないレベルかなとは感じた。
内部へのアクセスは容易で、軽作業時は非常に静か
今回試用したASUS NUC 14 Pro KitはベアボーンPCなので、本来はユーザーやショップブランドメーカーが、メモリやSSDを組み込む必要がある。そのため、筐体内部には簡単にアクセスできるようになっている。
底面のカバーはロック用のダイヤルとスライドロックで固定されているので、まずはこれを外そう。すると底面のロックが解除されて、パカッと底面のパネルが外れる。底面につながっているフレキケーブルを断線させないように慎重に外すと、メモリやSSDを組み込める状態になる。
基板上には2280サイズ用と2242サイズ用のM.2スロットが1基ずつ、そしてメモリスロットも2基装備する。試用機では2280サイズのM.2 SSDやDDR5 SO-DIMMメモリが装着済みだ。また2.5インチデバイス用のシャドウベイも用意されており、コンパクトながら拡張性はそれなりに確保されている。
最後に、CPU温度の状況と消費電力を見てみよう。LP-Eコアの搭載で、アイドル時や軽作業時の消費電力が大きく低下したということだが、こうした機能がどの程度影響しているのかは気になるところだ。
IntelのNUCシリーズは、NUC 13 Proシリーズまで含めて冷却重視の設計であり、ほかのミニPCと比べるとややファンの音は大きめだった(控えめ表現)。そうした歴史を考えると、ようやくというべきかやっとというべきか、動画再生やWebブラウズといった軽作業時の静音性は、他社のミニPCと同じくかなり静かになった印象がある。
今回は起動後10分間の平均的な温度を「アイドル時」、動画配信サイトの動画を1時間再生中の平均的な温度を「動画再生時」、PCゲームのプレイ時を想定した3DMarkのStressTest(Time Spy)実行中(約22分間)の平均的な温度を「3DMark時」、長時間負荷が続いたときを想定したCinebench R23実行中(約10分間)の平均的な温度を「Cinebench時」とした。
アイドル時や動画再生、Webブラウズなどといった軽作業時はほぼ43~50℃の範囲で動作した。ほとんどファンの音がしない状況ながらもこの温度は、なかなかすごい。3DMark時の温度は80℃を切っており、こちらも不安は感じない。テスト中のファンの音も控えめだった。
一方で連続的に負荷がかかるCinebench時では93℃まで上がり、ファンの音もかなりうるさくなる。当然ではあるが、動画のエンコードなど負荷のかかる作業を立て続けに行なうようなPCではない、ということだ。
消費電力も同じ条件で検証した。ノートPC向けCPUということもあって、アイドル時は10Wを切る9W前後とかなり低い。動画再生などの軽作業時は大体20Wといったところだった。3DMark時は最初に80W前後まで上がった後、グラフィックス描画中は大体65W前後で推移する。
連続的に高い負荷をかけ続けるCinebench時は95Wと高いが、それでもACアダプタの最大出力である120Wには届かないので心配はいらない。
サポートも含め安心して使えるミニPCの新しい選択肢
新CPUの搭載で、1世代前と比べると飛躍的と言ってよいほど性能が向上したASUS NUC 14 Proシリーズ。デザインテイストもシリーズの伝統を引き継いでおり、NUCのスタイルを好んで選択してきたユーザーはもちろん、サポート面なども含めて安心できるメーカー製のミニPCを購入したい、というユーザーにもおすすめできるモデルだ。
またASUSでは、従来モデルを引き継ぐ今回のASUS NUC 14 Proのほかに、アルミニウム製ボディで高級感を高めた上位モデル「ASUS NUC 14 Pro+」、外部GPUを搭載してゲーミング性能を高めた「ASUS ROG NUC」などを発表しており、NUCのラインナップはさらに大きく拡充される。こうしたNUCの新たな挑戦にも期待したい。











![[Amazon限定ブランド]CCL い・ろ・は・すラベルレス 2LPET ×8本 ミネラルウォーター 無味 製品画像:2位](https://m.media-amazon.com/images/I/41h0MHfvhkL._SL160_.jpg)
![【Amazon.co.jp限定】 伊藤園 磨かれて、澄みきった日本の水 2L 8本 ラベルレス [ ケース ] [ 水 ] [ 軟水 ] [ ペットボトル ] [ 箱買い ] [ ストック ] [ 水分補給 ] 製品画像:3位](https://m.media-amazon.com/images/I/41n0o65dSkL._SL160_.jpg)




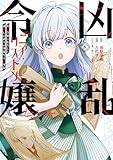




























![JN-V32FLFHD [液晶ディスプレイ/32型/1920×1080/ブラック] 製品画像:24位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/etre/cabinet/itemimage20/01255219_01.jpg?_ex=128x128)



![丸まった背中 曲がった腰・うつむいた首 何歳からでも自分で伸ばせる! 名医が教える最新1分体操大全 [ 石井賢 ] 製品画像:30位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/8619/9784866518619_1_3.jpg?_ex=128x128)
![12歳までに身につけたい「ことば」にする力 こども言語化大全 [ 山口拓朗 ] 製品画像:29位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/3904/9784478123904_1_2.jpg?_ex=128x128)
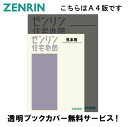
![令和8年度 年度別問題解説集 2級舗装施工管理 一般試験・応用試験 [ 森野 安信 ] 製品画像:27位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/5604/9784910965604.gif?_ex=128x128)
![転生したら第七王子だったので、気ままに魔術を極めます(22)【電子書籍】[ 石沢庸介 ] 製品画像:26位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rakutenkobo-ebooks/cabinet/5607/2000019605607.jpg?_ex=128x128)
![桃月なしこ2nd写真集 (仮) [ Takeo Dec. ] 製品画像:25位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/3904/9784065433904.gif?_ex=128x128)
![アイドルマスター シャイニーカラーズ 事務的光空記録 4 CD付特装版 (サンデーうぇぶりコミックス) [ 夜出 偶太郎 ] 製品画像:24位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/2355/9784099432355_1_54.jpg?_ex=128x128)
![北極星 僕たちはどう働くか [ 西野 亮廣 ] 製品画像:23位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/5583/9784344045583.jpg?_ex=128x128)
![JISハンドブック 49 化学分析(2026) [ 日本規格協会 ] 製品画像:22位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/1822/9784542191822_1_2.jpg?_ex=128x128)
