Hothotレビュー

「Xperia PRO-I」のカメラ性能、機能、使い勝手を徹底検証
2021年12月1日 06:45
ソニーは、Xperia PROシリーズSIMフリースマートフォン新モデル「Xperia PRO-I」を発表した。フラッグシップスマートフォン「Xperia 1 III」をベースとしつつ、1.0型イメージセンサーを採用するカメラを搭載することで、カメラ機能を大きく強化している点が最大の特徴だ。
今回、実機を試用する機会を得たので、特にカメラ回りを中心に見ていこうと思う。なお、試用機は開発中の評価機だったため、仕様や動作など製品版と異なる可能性がある点はご了承願いたい。発売は12月15日を予定しており、直販価格は19万8,000円。
重厚感のあるデザインだが、Xperia 1 IIIと比べてわずかに大きく重い
すでにXperia PRO-Iのニュース記事でも紹介しているので、ここでは簡単にXperia PRO-Iの仕様や外観を紹介する。
Xperia PRO-Iは、後ほど紹介するように背面カメラが大きく変更されているものの、それ以外の部分については、XperiaシリーズのフラッグシップモデルであるXperia 1 IIIのSIMフリーモデルとほぼ同等となっている。
Xperia PRO-Iの主な仕様は表1にまとめたとおりで、ほとんどがXperia 1 IIIのSIMフリーモデルと同等となっている。SoCがSnapdragon 888 5G、RAMが12GB、内蔵ストレージが512GB。5G通信はsub 6のみの対応となるが、nano SIM×2のデュアルSIM対応で、DSDS/DSDVをサポート。ディスプレイの仕様や内蔵バッテリ容量、IP65/68準拠の防水防塵仕様をサポートする点などもXperia 1 III SIMフリーモデルと同じ。おサイフケータイにも対応している。
| SoC | Snaodragon 888 5G |
|---|---|
| メモリ | 12GB |
| 内蔵ストレージ | 512GB |
| 外部ストレージ | microSD |
| OS | Android 11 |
| ディスプレイ | 6.5型有機EL、4K(1,640×3,840ドット)、アスペクト比21:9 HDR、リフレッシュレート最大120Hz |
| 背面カメラ | 超広角:16mm/F2.2、1/2.5型1,220万画素 広角:24mm/F2.0,F4.0 ZEISS Tessar、光学手ブレ補正、1.0型1,220万画素、 標準:50mm/F2.4、光学手ブレ補正、1/2.9型1,220万画素 3D iToF |
| 前面カメラ | 800万画素 |
| 5Gネットワーク | Sub-6 |
| 対応バンド | 5G:n3/n28/n77/n78/n79 4G:1/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/21/26/28/38/39/40/41/42 3G:1/5/6/8/19 GSM:850MHz/900MHz/1.8GHz/1.9GHz |
| 対応SIM | nano SIM×2(うち1つはmicroSDと排他) |
| オーディオ | フロントステレオスピーカー「フルステージステレオスピーカー」、3.5mmオーディオジャック Dolby Atmos対応、ハイレゾ音源/DSEE Ultimate対応/360 Reality Audioスピーカー再生/360 Spatial Sound |
| 防水・防塵 | IP6/8、IP6X |
| 生体認証機能 | 電源ボタン一体型指紋センサー |
| おサイフケータイ | 対応 |
| ワイヤレス充電 | 非対応 |
| 外部ポート | USB Type-C、3.5mmオーディオジャック |
| バッテリ容量 | 4,500mAh |
| サイズ(幅×奥行き×高さ) | 72×166×8.9mm |
| 重量 | 211g |
ただし、Xperia PRO-Iではワイヤレス充電機能が省かれている点。これは背面カメラの仕様変更に伴って非搭載となったそうだ。
物理ボタンは、右側面に集約。上部からボリュームボタン、指紋認証センサー一体型電源ボタン、ショートカットキー、シャッターボタンが並ぶ。このうちショートカットキーは、ユーザーが指定した任意のアプリを起動するためのボタンだ。標準では、後ほど紹介する動画撮影アプリ「Videography Pro」が割り当てられており、その他の任意アプリを指定できる。
仕様についてはXperia 1 III SIMフリーモデルとほぼ同等で、側面にメタルフレーム、背面にガラスを採用する点も変わっていないが、外観デザインは大きく変更されている。
特に大きく変わっているのが側面のデザインで、Xperia 1 IIIでは側面がほぼフラットだったのに対し、Xperia PRO-Iは細かな溝が掘られ、波形のようなデザインとなっている。これは、本体をしっかりグリップできるよう考慮してのものとのことだ。また、当然ながら背面カメラの仕様が大きく変わり、カメラの搭載位置も本体中央部に変更されていることから、背面の印象も大きく変わっている。
これは個人的な印象だが、特に側面のデザイン変更によってXperia PRO-Iのほうが重厚な印象が強い。Xperia PROシリーズのターゲット層を考えても、このデザインはマッチしていると感じる。
カラーは、フロストブラックのみとなる。側面のメタルフレーム、背面ガラスともに光沢感を抑えたすりガラス調のフロスト加工となっており、これも重厚感を高める要因となっているはずだ。
また、左側面にストラップホールが用意されている点も、Xperia 1 IIIにはない特徴だ。近年のスマートフォンでは本体にストラップホールを備えるものはほぼなく、ストラップを使いたい場合にはストラップホールを備えるケースを活用するしかない。しかしXperia PRO-Iは本体にストラップを装着して利用できるため、非常に安心感がある。合わせて、ネックストラップなどを活用することで本体をしっかりホールドできることにもなるため、より安定して撮影できることにも繋がる。
サイズは72×166×8.9mm(幅×奥行き×高さ)。Xperia 1 IIIのサイズが71×165×8.2mm(同)なので、Xperia PRO-Iのほうがわずかに大きくなっている。実際に双方を持ち比べても違いを感じるほどではないが、横に並べるとその違いがはっきりわかる。とはいえ、残念に感じるほど大きくなっているわけではないため、それほど気にはならないはずだ。
それに対し重量は約211gと200gを大きく超えている。Xperia 1 IIIから約25gの重量増となっており、実際に手にしてもかなりずっしり重く感じる。重量増は、カメラの大型化や筐体の大型化などが要因だが、できれば200g未満で抑えてもらいたかったようにも思う。なお実測の重量は210.2g(SIM非装着時)だった。
1.0型イメージセンサー採用の広角カメラを加えた4眼仕様のカメラを搭載
では、Xperia PRO-I最大の特徴となる、背面カメラを見ていこう。
Xperia PRO-Iの背面カメラは、超広角、広角、標準、3D iToFセンサーで構成される4眼仕様となっている。4眼仕様という点はXperia 1 IIIと同じだが、その中身は大きく変更されている。
大きく変わっているのが、その見た目と搭載位置だ。Xperia 1 IIIの背面カメラは背面の左上角に搭載しているのに対し、Xperia PRO-Iは本体中央上部に搭載。また、4眼のレンズを縦に並べて搭載している点はどちらも同じだが、Xperia PRO-Iは上から2番目の広角レンズ部がかなり大きく、カメラユニットから横だけでなく上にも大きく飛び出している。
このように広角レンズ部が大型化しているのは、1.0型と大型のイメージセンサーを採用しているからだ。イメージセンサーが大きくなると、必然的にレンズも大きくする必要があり、そのため広角レンズ部が大型化しているわけだ。これによって、カメラの存在感も大きく変わっている。
各レンズおよび撮像素子の仕様は次のとおり。いちばん上のレンズは16mm/F2.2超広角レンズで1/2.5型センサーとの組み合わせ。2番目は24mm広角レンズで1.0型センサーとの組み合わせ。3番目は3D iToFセンサー。4番目は50mm/F2.4標準レンズで1/2.9型センサーとの組み合わせとなる。各レンズのセンサーはいずれも有効画素数が約1,220万画素で統一されており、像面位相差AFに対応する点も同様だ。
ところで、一般的なスマートフォンカメラのレンズは樹脂レンズを採用しているのに対し、Xperia PRO-Iの広角レンズはガラスモールド非球面レンズを採用した「ZEISS Tessar」となる。加えて、通常は搭載されない物理的な絞り機構も搭載しており、F2.0とF4.0の2段階に絞りを切り替えられるようになっている。過去に同様の可変絞り機構を備えるカメラを搭載するスマートフォンは存在していたが、Xperiaシリーズとしてはこれが初だ。このような、ガラスモールド非球面レンズの採用や可変絞り機構といった、カメラに近い仕様を実現しているのは、もちろん1.0型イメージセンサーの性能を最大限活用するためだ。
搭載している1.0型イメージセンサーの画素ピッチは2.4μmと、一般的なスマートフォンに搭載されるセンサーに比べてかなり大きく、それぞれの画素がより多くの光を取り込める。より多くの光を取り込めることで、暗い場所でも明るく、ノイズが少なく、ダイナミックレンジの広い撮影が行なえることになる。その1.0型イメージセンサーを最大限活用するために、高品質なレンズや可変絞り機構を採用しているわけだ。
さらに、ソニーのデジタルカメラ「α」や「サイバーショット」に搭載される、画像処理用のフロントエンドLSIもXperiaとして初めて搭載している。
このように、1.0型イメージセンサーとガラスモールド非球面レンズ、可変絞り機構の採用、フロントエンドLSIの搭載などによって、これまでのスマートフォンカメラとは一線を画す高感度・低ノイズ性能、高ダイナミックレンジ、自然なボケ味などを実現している。
また、カメラ性能も高められている。
人や動物などの瞳を認識してピントを合わせる「リアルタイム瞳AF」と、動いている物体にピントを合わせ続ける「リアルタイムトラッキング」は、静止画だけでなく動画撮影時にも対応。合わせて、広角レンズ利用時には撮像エリアの約90%をカバーする総数315点の像面位相差検出AFセンサーが配置されることで、ほぼ画面全体でAFが動作する。
連写性能は、最大秒間60回のAF/AE演算によるAF/AE追従の最大秒間20コマ高速連写に対応。さらに、1.0型イメージセンサーからの高速読み出しが可能となったことで、高速に動く被写体を撮影する場合などに発生する「ローリングシャッター歪み」も抑えられている。
このほか、明暗差の大きなシーンで10枚以上の画像を自動で連続撮影して重ね合わせノイズを低減する「マルチショットNR」や、12bit RAW撮影などにも対応している。
スマートフォンとは思えないほど高品質な静止画が撮影できる
カメラアプリは、Xperia 1 IIIと同じ「Photography Pro」を採用。スマートフォンの標準カメラアプリに近いUIでの静止画・動画の撮影が可能な「BASIC」モードだけでなく、αやサイバーショットに近いUIでの撮影モードを用意。撮影モードは、BASIC、AUTO、プログラムオート、シャッタースピード優先、マニュアル、メモリーコールの6種類を用意。この点はXperia 1 IIIのPhotography Proと同じだが、Xperia PRO-IのPhotography Proでは、24mm広角レンズ利用時に絞りをF2.0とF4.0に切り替える機能が追加されている。
また、本体側面のシャッターボタンがより使いやすくなっている。Xperia 1 IIIよりもボタンが大型化されるとともに、ボタンの2段押しがより明確に判断できるようになっている。個人的には、半押しがやや軽すぎる気もするが、ボタンに軽く指を添えると半押しになってピントが合い、そこから押し込むとシャッターが切れる、というようにデジタルカメラらしい操作で撮影が可能。Photography ProではBASICモード以外は基本的に画面にシャッターボタンが表示されず、物理シャッターボタンでの撮影が基本となる。シャッターボタン自体が扱いやすいため、軽快な写真撮影が可能と感じた。
では、いくつか静止画の作例を紹介しよう。いずれの写真も、Photography Proの「AUTO」モードで撮影したものを無修正で掲載している。
まずはじめに、同じ場所から超広角、広角、標準の各レンズで撮影したものだ。各レンズの焦点距離に応じた画角で撮影できているが、いずれもほとんどゆがみなく撮影できている。
デジタルズームはレンズごとに行なえ、超広角レンズでは16~24mm、広角レンズでは24~50mm、標準レンズでは50~150mmの範囲でズームが行なえる。以下の写真は、標準レンズの最大望遠となる150mmで撮影したものだが、デジタルズームとはいえなかなかのクオリティで撮影できている。
ここからは、1.0型イメージセンサーを採用する24mm広角レンズで撮影した写真を紹介する。
まずは、F2.0とF4.0の違いを見てみよう。以下の写真は、花に最大限寄って撮影したものだが、F2.0とF4.0で背景のボケ具合や、花にピントが合っている範囲に違いが見られることがわかる。その差はそこまで大きくないとも言えるが、F2.0のほうがより手前の花が強調されている。反面、F4.0のほうは解像感に優れるように見える。背景のボケ味はどちらも自然で、このあたりはデジタル処理でボケ加工した場合との大きな違いを感じる。
こちらも、順光の明るい場所で撮影したものだ。こちらは近接撮影ではないため、いずれも背景はほとんどボケていない。また、クオリティも大きな違いはないが、F4.0で撮影したほうがF2.0の場合よりもわずかながら色や明暗の階調が良く再現されている。こういった点は、デジタルカメラで絞りを絞って撮影した場合と同じ傾向で、これがスマートフォンで撮影できるという点はなかなか魅力的と感じる。
こちらは、室内から天窓を撮影したものだが、いずれもコントラストも優れており、明るい場所が飛んだり、暗い場所が潰れることなく撮影できている。ただ、こちらもF4.0で撮影した方がわずかながら階調に優れているように感じる。
次に、太陽や木漏れ日をフレームに入れて撮影したものだ。それぞれ時間帯やF値に違いがあるが、いずれもそれほど盛大なゴーストやフレアは発生していない。太陽光が当たらない部分もしっかり描写されており、こちらもなかなかのクオリティで撮影できている。
こちらは、やや薄暗いレストランで撮影した写真だ。どちらもおいしそうだが、F2.0は手前のパンケーキが浮かび上がるような写真となっているのに対し、F4.0のほうは皿の縞模様までくっきり撮影できていることがわかる。
かなり薄暗いレストランで撮影。シャッタースピードはF2.0が1/25秒、F4.0が1/6秒。どちらも手持ちで撮影したが、光学手ブレ補正機能の効果でほとんどブレずに撮影できている。
次は夜景だ。今回はAUTOモードで撮影しているが、いずれも自動でHDRが有効となり、明るい場所だけでなく暗い場所もしっかり描写できている。現在のスマートフォンでは、いわゆるAI処理で明るさや色合いを補正するコンピュテーショナルフォトグラフィを活用した撮影が一般的となっており、夜景を鮮やかに撮影できる場合が多い。Xperia PRO-Iでもコンピュテーショナルフォトグラフィを活用している部分はあるが、不自然に明るく鮮やかな夜景写真ではなく、比較的自然な夜景写真が撮影できる点は、好印象だ。
最後に、ローリングシャッター歪みをチェックしてみた。こちらは、24mm広角レンズと50mm標準レンズを利用して、同じ場所から高速で走る電車を撮影した。画角が違うものの、24mm広角レンズで撮影した写真は電車の窓が歪むことなく撮影できているのに対し、50mm標準レンズで撮影した写真は窓などが斜めに歪んでいることがわかる。シャッタースピードの違いもあって、50mm標準レンズでは車体がブレている違いもあるが、これを見ても24mm広角レンズの1.0型イメージセンサーではローリングシャッター歪みがほぼ気にならないレベルで抑えられると言えそうだ。
以下に、他の作例も掲載するので、参考にしてもらいたい。
「Vlog Monitor」の利用で、背面カメラを利用した自撮りにも対応
Xperia PRO-Iでの動画撮影は、静止画撮影で利用するPhotography Proでの撮影と、動画撮影アプリとしてXperia 1 IIIにも用意されている「Cinematography Pro」に加えて、より手軽な動画撮影に特化したアプリ「Videography Pro」が新たに追加された。
Cinematography Proは、ソニーのプロ向けムービーカメラ同等のUIを再現し、プロ仕様の動画撮影機能を提供するが、多くの設定をマニュアルで行なう必要があり手軽な動画撮影には不向きだった。それに対しVideography Proは、細かな設定をマニュアルで行なうことも可能だが、基本的には設定をアプリ任せで高品質な動画が撮影できるように設計されているため、サッと取り出して動画を撮影するといった用途にも十分対応できる。
そのうえで、リアルタイム瞳AFやリアルタイムオブジェクトトラッキング、4K HDR 120fps撮影などに対応。もちろん、24mm広角レンズでの動画撮影時に、絞りをF2.0とF4.0で切り替えられる。Photography Proの簡易的な動画撮影機能では物足りないVloggerを意識した設計になっていると言っていいだろう。
実際にVideography Proを利用して、Xperia PRO-Iを手持ちでラフに動画を撮影してみたが、標準設定のままの撮影でも、露出やホワイトバランスが自動で最適に設定され、録画ボタンを押すだけで申し分ないクオリティの動画が撮影できた。画面のスライダーでスムーズなズーム動作ができるなど、操作性もなかなか優れている。
動画撮影時のリアルタイム瞳AFやリアルタイムオブジェクトトラッキングも、細かな設定不要で問題なく動作した。動く人や物体でもリアルタイムで正確にピントが合った状態で動画が撮影できるという点は、動画撮影を多用する人にとって大きな魅力となるだろう。
24mm広角レンズでの動画撮影時のローリングシャッター歪みがどの程度になるのか、という点も確認してみた。以下の動画は、走行する電車の車窓を撮影したものだ。目の前を高速に横切る電柱などはさすがに斜めに歪んでいるものの、その割合はそこまで大きくない。また、途中で別の列車とすれ違うが、その列車はほとんど歪んでいない。そのため、24mm広角レンズでの動画撮影でも、ローリングシャッター歪みがほとんど気にならないレベルに抑えられると言っていいだろう。
さらに、Vlogger向けの周辺機器も用意している。それが「Vlog Monitor」だ。
Vlog Monitorは、Xperia PRO-Iの背面カメラ、それも1.0型イメージセンサーを採用する24mm広角レンズを利用して自撮り撮影を可能とするための外部モニターだ。3.5型HD(1,280×720ドット)表示対応の液晶ディスプレイで、製品に同梱されるXperia PRO-I側面を挟んで固定するホルダーを利用してXperia PRO-I背面側に装着することで、背面カメラで撮影する場合のモニターとして利用できる。また、モニターにはマイク入力端子も用意され、外部マイクを装着して利用できる。
モニター部は背面に三脚ネジ穴が設けられているため、三脚ネジを備えるスイングアームなどに装着しての利用も可能。この他、ホルダーには上部にアクセサリーシュー、下部に三脚ネジ穴が用意されているため、上部にマイク、下部に三脚やシューティンググリップを装着して利用することも可能だ。ソニーのBluetooth対応シューティンググリップ「GP-VPT2BT」と組み合わせれば、シューティンググリップとしての利用はもちろん、Bluetooth接続で撮影のコントロールも可能となる。
実際に、Vlog MonitorとシューティンググリップのGP-VPT2BTを組み合わせて利用してみたが、確かに背面カメラを利用して自撮りする場合に非常に便利と感じる。ただ、Vlog Monitorを接続していると、撮影映像がVlog Monitor側のみに表示され、Vlog Monitorをオフにするか接続ケーブルを外さない限り切り替えもできないため、前方を撮影したい場合に映像を確認できなくなってしまう。また、Vlog Monitorはタッチ操作に対応せず、Videography Proの操作はXperia PRO-I側のディスプレイを利用しなければならない。操作については、Bluetooth接続のシューティンググリップを利用すればどうにかなるが、できればボタンのタップでモニター表示の切り替えを行なえるようにしてもらいたいと感じた。
なお、Vlog MonitorはXperia PRO-Iでのみ利用可能となっている。Xperia 1 IIIなどに接続しても全く認識せず利用できないため、注意したい。
ところで、Xperia PRO-Iでは、本体が高温になっても動画撮影を継続できる「撮影持続モード」が用意されている。実際に撮影持続モード有効にして4K/30fps動画を連続撮影してみたが、本体はかなり熱くなるものの、1時間を超えても発熱で撮影が止まることはなかった。
ただし、撮影持続モードを利用するには、Bluetooth対応シューティンググリップの利用が必須となる。Videography Proで撮影持続モードを設定しようとしても、通常は設定項目が表示されず、GP-VPT2BTを接続してはじめて設定項目が表示され、有効に切り替えられるようになっている。今回はGP-VPT2BTで試したが、その他のBluetooth対応シューティンググリップでも同様の動作になるのかは未確認。確実に撮影持続モードを利用したいなら、GP-VPT2BTの利用がベストだろう。
撮影には1.0型イメージセンサーの約60%の領域を利用
Xperia PRO-Iの背面広角レンズに採用されている1.0型イメージセンサーは、ソニーのデジタルカメラ「サイバーショット RX100VII」に採用されてるものとほぼ同等のものだ。このイメージセンサー採用の最大の理由は、もちろんカメラ性能を高めるためだ。
近年のXperiaでは、ソニーのデジタルカメラ「α」や「サイバーショット」の開発陣がXperiaのカメラ開発にも携わっており、カメラの品質や機能が大きく高められている。そういった中、よりαやサイバーショットに近いカメラ品質や機能を実現するために、1.0型イメージセンサーの採用に踏み切ったという。
ただ、Xperia PRO-Iのニュース記事でも紹介しているように、総画素数約2,100万画素の1.0型イメージセンサーを搭載してはいるが、静止画撮影時で約1,220万画素の領域のみの活用となっている。実際には、手ブレ補正などでより広い領域が利用されてはいるものの、静止画撮影で利用されるのはセンサー全体の約60%程度の領域。つまり、1.0型イメージセンサーの全体を活用する設計とはなっていないのだ。
この点についてソニーは、カメラとしての品質を高めるだけでなく、スマートフォンのカメラに求められるスピードなども両立するためと説明している。例えば、有効画素数を1,220万画素とすることでデータ量が減り、高速な処理が可能になっているという。これによって、先ほど紹介した静止画および動画でのリアルタイム瞳AFやリアルタイムトラッキングの実現、毎秒60回の演算でAF/AE追従の秒間20コマ高速連写といった機能を実現している。合わせて、広角レンズで撮影領域の約90%がAFエリアとなっているのも、1.0型イメージセンサーの約60%のみを利用するからこそ実現できているそうだ。
このほかにも、1.0型イメージセンサーの全領域を活用し、画質にもこだわった場合には、レンズやカメラユニット、ひいてはスマートフォン自体のサイズがより大きくなってしまう。そのため、カメラとしての品質やスピード、サイズなどのバランスを考慮してこういった仕様にしたのだと説明している。
確かに、1.0型イメージセンサーの全体を使わないことによって、様々なメリットがあるのは理解できる。また、搭載するイメージセンサーの全体を利用してないデジタルカメラも多く存在しており、こういったイメージセンサーの使い方が特殊というわけでもない。とはいえ、1.0型イメージセンサー搭載を強くアピールしていることを考えると、センサー全体を使ってないという点が引っかかるのも事実だ。1.0型イメージセンサーを搭載しているのは間違いないとしても、領域全体を使っていないなら、そのことをもっとしっかり説明すべきだと感じる。
PCとの直結ではデータ転送速度があまり速くない?
Xperia PRO-IのUSB Type-Cは、Xperiaシリーズ初のUSB 3.2 Gen2対応となっている。データ転送速度は10Gbpsで、高速なデータ転送が可能としている。そこで、USB 3.2 Gen2対応のPCのUSB端子と直結して、どれだけデータ転送速度が速いかチェックしてみた。
利用したPCは、富士通クライアントコンピューティングの「LIFEBOOK WU2/E3 5Gモデル」で、USB 3.2 Gen2対応のUSB Type-Cケーブルを利用し、LIFEBOOK WU2/E3 5GモデルのUSB 3.2 Gen2準拠USB Type-Cポート(Thunderbolt 4ポート)に接続。その状態でXperia PRO-IからLIFEBOOK WU2/E3 5Gモデルの内蔵SSDに、31個の動画ファイル、総容量約39.4GBのデータを一括転送する時間を計測した。
結果は、約4分52秒と、かなりの時間がかかってしまった。転送速度は約139MB/s程度で、USB 3.2 Gen2の速度が全く発揮されていない。これは、Thunderbolt 4との相性が悪いのかと思い、USB 3.2 Gen2対応USBポートを備える他のPCでも試してみたが、速度はほとんど変わらなかった。
そこで、試しにとSanDiskのUSB 3.2 Gen2対応ポータブルSSD「Extreme Portable SSD V2 2TB」を用意してXperia PRO-Iに直結し、同じデータを転送してみた。すると、約59秒で転送が完了した。転送速度は約687MB/sに達しており、これならUSB 3.2 Gen2の効果がしっかり発揮できていると言える。
PC直結時になぜ速度が遅くなるのか、理由は不明だ。ただ、USB 3.2 Gen2対応ポータブルSSDにはかなり高速にデータ転送できるため、撮影データを高速に転送したいなら、PC直結ではなく、USB 3.2 Gen2対応のポータブルSSDなどを用意し、そちらに転送したほうが良さそうだ。
価格をどう考えるかで魅力が変わってくる
今回、Xperia PRO-Iの試用機で、特にカメラ回りを中心にチェックしたが、カメラの完成度はほかのスマートフォンを圧倒するほどに優れている。Xperia PRO-Iのカメラ機能に注目している人も多いと思うが、その期待を裏切らないクオリティを実現していると十分に感じられた。
また、スマートフォンとして見ても、現役フラッグシップモデルであるXperia 1 IIIと同等の機能やスペックが備わっており、こちらも全く不満を感じることはないだろう。
ただ、気になる点があるのも事実だ。その1つが、1.0型イメージセンサーの全領域を利用していないという点だ。確かに、ソニーが説明するように全領域を利用しないことによるメリットが多くあることは理解できる。また、実際に撮影される写真や動画のクオリティも十分に優れている。それでも、1.0型イメージセンサー搭載を強調するだけでなく、センサーをどう使っているのかユーザーにわかりやすく説明すべきだろう。
19万8,000円という価格については、Xperia PRO-Iをどう捉えるかによって印象が大きく変わるだろう。例えば、Xperia PRO-Iのカメラに特に魅力を感じず、純粋なスマートフォンとして見る人からは、かなり割高と感じるだろう。ただ、Xperia PRO-Iのカメラに大いに注目する人からすると、Xperia PROシリーズ初代のXperia PROが24万9,800円だったことや、カメラ以外のスペックがほぼ同等のXperia 1 III SIMフリーモデルの価格が15万9,500円ということと合わせ、思ったほど高くないと感じるはずだ。
Xperia PRO-Iは、非常にニッチな製品であり、万人向けのスマートフォンではないことは確かだ。ただ、こういったニッチな製品を実際に作り上げ、発売するという姿勢からは、ソニーらしさが強く感じられる。そして、ニッチな製品を期待している人にとっては、間違いなく満足できる製品と言っていいだろう。
【12月3日訂正】記事初出時、製品名やカメラ、防水仕様といった記述に誤りがございました。お詫びして訂正します。










![[Amazon限定ブランド]CCL い・ろ・は・すラベルレス 2LPET ×8本 ミネラルウォーター 無味 製品画像:1位](https://m.media-amazon.com/images/I/41h0MHfvhkL._SL160_.jpg)



![【Amazon.co.jp限定】 伊藤園 磨かれて、澄みきった日本の水 2L 8本 ラベルレス [ ケース ] [ 水 ] [ 軟水 ] [ ペットボトル ] [ 箱買い ] [ ストック ] [ 水分補給 ] 製品画像:5位](https://m.media-amazon.com/images/I/41n0o65dSkL._SL160_.jpg)
















![DELL OptiPlex 7090 SFF (Win11x64) 中古 Core i7-2.5GHz(11700)/メモリ16GB/HDD1TB/DVDマルチ [C:並品] 製品画像:3位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/usedpc/cabinet/url1/5726315c.jpg?_ex=128x128)






![【❤最安挑戦❤+LINEクーポン】新発売 [1+1年保証] モニター 100Hz 21.5インチ 23.8インチ 27インチ pcモニター 1ms応答 パソコン モニター 1920*1080 FHD ゲーミングモニター 非光沢 VA 角度調整 VESA Freesync pc/switch/ps4/ps5/xbox スピーカー内蔵 製品画像:9位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/qifeng/cabinet/10653721/10653722/imgrc0112340482.jpg?_ex=128x128)
![WINTEN モバイルモニター 15.6インチ テレワーク/デュアルモニター/サブモニターに最適!ゲーミング 1080P FHD IPSパネル 軽量 薄型 非光沢 カバー付 ミニPC Switch iPhone Type-C/HDMI接続 [1年保証] WT-156H2-BS 5523 製品画像:8位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/win10/cabinet/monitor/imgrc0112809238.jpg?_ex=128x128)
![ASUS|エイスース PCモニター Eye Care ブラック VA24DQLB [23.8型 /フルHD(1920×1080) /ワイド /75Hz] 製品画像:7位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/biccamera/cabinet/product/6626/00000009413787_a01.jpg?_ex=128x128)



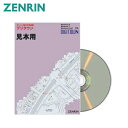

![彗星起源感覚 市川春子イラストレーションブック2 [ 市川 春子 ] 製品画像:28位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/4858/9784065424858_1_3.jpg?_ex=128x128)
![BLUE GIANT MOMENTUM(7) (ビッグ コミックス) [ 石塚 真一 ] 製品画像:27位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/8536/9784098638536_1_20.jpg?_ex=128x128)
![『街道をゆく』全43巻+夜話 3大特典付き 完全予約販売BOXセット [ 司馬遼太郎 ] 製品画像:26位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/1188/9784022681188_1_3.jpg?_ex=128x128)
![[新品]ジョジョの奇妙な冒険 [新書版] (1-63巻 全巻) 全巻セット 製品画像:25位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/mangazenkan/cabinet/syncip_0003/si-01_01.jpg?_ex=128x128)
![【楽天ブックス限定デジタル特典】「修学旅行で仲良くないグループに入りました」ドラマ公式ビジュアルブック(公式ビジュアルブック撮影裏側動画配信データ - 2人きりの修学旅行編) [ ABC ] 製品画像:24位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/8092/9784046858092_1_3.jpg?_ex=128x128)
![【楽天ブックス限定グッズ】堀夏喜 1st写真集『LIVING FOR』(オリジナルキーホルダー) [ 堀 夏喜(FANTASTICS) ] 製品画像:23位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/7242/2100014637242_1_2.jpg?_ex=128x128)
![隔週刊 水曜どうでしょうDVDコレクション 2026年 3/31号 [雑誌] 製品画像:22位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/0361/4912301750361.gif?_ex=128x128)
![【楽天ブックス限定抽選特典】【クレジットカード決済限定】CANDY TUNE 3rd Anniversary写真集(仮)(オンラインラッキードロー抽選権) [ CANDY TUNE ] 製品画像:21位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/2708/2100014832708_1_2.jpg?_ex=128x128)