特集
ぶっちゃけすぎてゴメン!変態UMPCを矢継ぎ早に出すGPD社長にいろいろ聞いた
2025年1月21日 09:28
ゲーム向けの「GPD WIN」シリーズからスタートし、ビジネス向けの「GPD Pocket」シリーズなど、10型以下のUMPC(Ultra Mobile PC)を多数輩出する企業として知られるGPD。今回、日本で代理店を務める天空の協力により、久々に社長であるWade氏にインタビューをする機会を得た。
そこで、2024年から展開している既存製品を振り返りつつ、2025年の新製品の展望をしてもらい、さらにはニッチ市場におけるビジネス戦略など、多岐にわたる話をWade氏に伺った。
GPD Pocket 3低価格モデル、GPD WIN Max2、GPD WIN4のマイナーチェンジ
インタビューでまず話題に上ったのは、8型液晶を搭載してダブルヒンジ機構により2in1スタイルを実現したビジネス向けの「GPD Pocket 3」の低価格版である。
もともとGPD Pocket 3の低価格モデルはPentium Silver N6000というJasper Lake世代CPUを搭載していたのだが、2024年モデルでは上位と同じTiger Lake世代のPentium Gold 7505を搭載し、USB4対応や内蔵グラフィックスの強化を図った。
ちなみにPentium Gold 7505はアーキテクチャ的には古いが、Intel N100よりも高速であり、Wade氏は「Pocket 3はビジネス用途を見据えた構成となっている。Pentium Gold 7505はUSB4対応と性能のバランスがよいのだが、他社ではまだ採用しているPCが少ない。その点での差別化を強みにしたい」とした。
続いては「GPD WIN Max2 2024」および「GPD WIN4 2024」のマイナーチェンジ(CPUアップグレード)版にあたる「GPD WIN Max2 2025」および「GPD WIN4 2025」だ。最新モデルでは、いずれもRyzen AI 9 HX 370またはRyzen 7 8840Uを搭載しているが、実はRyzen 7 8840U搭載モデルは2024モデルとは異なり、新設計の基板になっているという。
鋭い読者ならここで、「なぜ1機種でRyzen AI 300とRyzen 8000という2つの異なる世代のCPUを用意できるのか?」と疑問の思うことだろう。以下はGPD自身が公開している写真なのだが、Ryzen AI 300とRyzen 8000シリーズは当然ダイが異なれば、パッケージも異なる。1機種で2つのCPUのマザーボードをいちいち用意するのは、小ロットしか生産しないGPDにとってみれば不利なはず。2024モデルの基板をそのまま流用するのが筋ではないのか?
「最新モデルのRyzen 7 8840Uでは、Ryzen AI 9 HX 370と同じパッケージになっている。ピンが互換なので、共通のマザーボードで対応できる」とWade氏は種明かし。「当初採用したRyzen 7 8840Uは小型のパッケージだったのだが、Ryzen 7 7840Uとは異なり高負荷時に不安定になるといった課題があった。最新のRyzen 7 8840UはRyzen AI 300シリーズと同じ大きいパッケージに封止されているが、そうした不安定な問題もクリアになったように見える」という。つまり上記の写真に写っているRyzen 7 8840Uは旧モデルのものだったのだ。
実は、GPDがこれまで採用してきたRyzen 7 7840U/8840Uは、Ryzen 7 6800Uなどと互換性があり、フットプリントが小さい「FP7/FP7r2」パッケージのもの。しかしRyzen 7 7840U/8840Uには「FP8」パッケージ版もあり、このFP8はRyzen AI 300と互換となっているのだ。これによって同じ基板で対応できるようになった、ということだ。
ちなみに2025年第2四半期に、AMDは「Ryzen 200」と呼ばれるZen 4ベースのCPUコアを採用したRyzen AI 300シリーズの下位モデルを提供開始する予定だが、たとえばRyzen 7 250とRyzen 7 8840Uはスペックがほぼ共通である一方で、製品情報によればRyzen 200はFP8パッケージしかないようだ。つまり、AMDとしては今後FP8に移行させるのだろう。
GPD DUOは1世代だけで終わる“幻の製品”になる?
一方で2024年の“課題”として挙げられたのが、同社が2023年から構想し、ようやく実現した2画面のPC「GPD DUO」だ。この製品は筆者も日頃より家で愛用しており、深センに伺った際もGPD DUOだけを持っていったのだが、Wade氏は「GPD DUOは当初の構想から大きく外れてしまった」と反省を示した。
「GPD DUOは当初、11型の2画面を採用して1.3kg程度の軽量モバイルノートを目指していた。大学生などが持ち歩いて、どこでもプログラミング開発などができるような製品を実現したかった。GPD WIN Max2より少し重い程度で、十分に持ち運びに適していて、大手には用意されていないまったく新しいジャンルを切り開ける。しかし、開発途中でディスプレイ周りの問題が発生し、1.3kgを断念をせざる得なかった」と振り返る。
しかし、基板周りは既に設計していたため、この構想を完全に無駄にしないために、「ディスプレイを13.3型に切り替えて設計を完成させた」とも言う。Wade氏の過去の言葉を引用すれば、初代GPD Pocketのような“妥協した製品”になったのは否めないだろう。
では、その構想を「GPD DUO 2」などの新製品で実現する見込みはあるのか?と尋ねると、「GPD DUOのような製品は、2つディスプレイパネルがともにeDP(組み込み向けのDisplayPort規格)インターフェイスであるのが望ましい。つまり、MIPIからeDPの変換チップをなるべく使いたくない。このニーズを満たすパネルが、残念ながら今の市場にはない。今後、開発の優先度が高いのはGPD WIN 5やGPD WIN Max 3といった、従来を継承/発展させたモデルになる。GPD DUO 2は当面考えていない」とした。
GPD DUOを使えば分かるが、2画面がもたらす生産性の高さは破壊的であり、一度使い出したら元の環境には戻れないほど。そのGPD DUOが1代限りで終わりというのは筆者としては残念ではあるのだが、Wade氏の構想と乖離が進んでしまっては元も子もないというのは理解もできる。
GPD WIN Mini 2025の静かなるアップデート
続いての話題は、まだ日本で発売されていない「GPD Pocket 4」、「GPD WIN Mini 2025」についてだ。
既にGPD Pocket 4の特徴についてはレビューでお伝えしている通りだが、タブレット形態の時に電源ボタンや指紋センサーにアクセスできない問題を解消するといったブラッシュアップを図りつつ、銅製ヒートパイプやファンの強化により、対応するCPUの消費電力も従来の15~18Wレンジから28Wまで引き上げられ、Ryzen AI 9 HX 370の搭載を実現した。
また、モジュールによって機能を変更できる構造は踏襲するが、設計を刷新することで、Wade氏がどうしても実現したかったという4G LTEの対応を新たに果たせた。さらに凄く細かいところだが、ヒンジの改良によって液晶部と本体部の隙間が低減しているとのことだった。
一方で、GPD Pocket 3にあったペン入力はなくなったが、これは今回採用した8.8型のパネルがインセル型のタッチに対応しているものの、ペン入力が非対応となっているため。GPD社内では別途タッチセンサー/ペン対応デジタイザをつけて評価してみたものの、インセル型のタッチと干渉を起こしてしまい正常動作しなかったので除外したとのことだった。
ただ、このパネルメーカーではワコムAES対応のパネルをリリースしており、現在はそのラインナップ8.8型にも展開するかどうか評価しているとのこと。仮に製品化できれば、GPD Pocket 4のペン対応もあり得ると示唆した。
一方でGPD WIN Mini 2025だが、筐体は幅が4mm、厚みが1mmと微増となっている。しかしSSDスロットがM.2 2230からM.2 2280に変更され、ユーザーのSSDに対する拡張/交換の選択肢が大きく広がった。加えて熱密度も低減したので、放熱にも有利になっているとのことだった。
さらに、電源部分の放熱設計を一から見直し、新たにVRM部にも金属を加えてカバーするようにした。GPD WIN Mini 2024はデフォルトで15W、最大で20Wまで引き上げることが可能だったが、2025はデフォルトで24Wが設定され、最大35Wの熱処理ができるようになった。
【22日訂正】記事初出時、最大28Wとしておりましたが、正しくは35Wです。お詫びして訂正します。
また、従来のGPD WIN Mini 2024は別売りのグリップ(初回は同梱)が左右分離式で、なおかつドライバを用いて代替となる長いネジで留める方式だったが、仮に形態を変えながら使用する場合、ドライバや外した短いネジをなくさないようにするための収納を持ち運ぶ必要があり、単純に面倒が増えるだけだった。2025では左右一体型のはめ込み式に変更され、利便性が大きく向上している。
2025年はじっくり腰を据える年。長らく刷新がなかったあのモデルも予告!
最後にまだ姿を見せない、2025年に計画中の製品について語ってもらったが、どうやら新しいフォルムの製品を複数用意するようだ。
「2024年は既存モデルのCPU更新に追われた。こうしたアップデートは“受動的”であり、もっと革新的なアイデアを新製品に盛り込みたい我々にとって、正直物足りなかった。2025年は逆にCPUのアップグレードが少ないため、“能動的”に動くチャンス。我々にとってじっくり腰を据えて、アイデアを実現する機会となる」と瞳を輝かせた。
まずは、超小型UMPCとして人気を博し、法人や工場でも導入が進んだという「GPD MicroPC」の次世代機、「GPD MicroPC 2」を計画中のようだ。
「GPD MicroPCは特定の企業ユースやネットワークエンジニア向けという位置づけであるのは変わらない。GPD MicroPCはWindows 10搭載だったので、Windows 11に刷新するのがトピック。GPD Pocket 3よりもさらに小さく、コストを抑える必要があるため、Intel N250の採用を考えている。ただ、Gigabit Ethernetは保留するが、シリアルポートの搭載は見送る予定」だとする。なお、サイズは初代より少しだけ大きくなるようだ。
「続いてはGPD WIN 5。GPDにとって数字が1個進むということは、まったく新しい設計思想/設計思想の製品であるということ。今は詳細をまったく明かせないけど、ぜひ期待してほしい」と語る。
保守的かつ慎重なビジネススタイルは変えないGPD
近年、Valveの「Steam Deck」をはじめ、ASUSの「ROG Ally X」やLenovoの「Legion Go」、MSIの「Craw」シリーズなど、大手も参入してきているポータブルゲーミングPC市場。大手の参入で市場拡大が見込まれる……などと楽観視する人も少なくないようだが、Wade氏は「むしろ我々が狙っていたニッチな市場の競争が激しくなるだけで、我々にとって良い話ではない」ときっぱり否定する。
「そのためには2025年、我々は“平常心を保ち続け”ビジネスを回し続ける必要がある。利益ばかり追求せず、GPDらしいアイデアの製品開発を続け、大手PCメーカーではカバーしきれない細分化したニッチ市場への集中こそが、GPDの基本戦略だ。ユーザーの要望をきめ細かく吸い上げ、そのニーズを満たせる製品を出し続ける」。
GPDは創業当初より従業員が30人程度の小規模な企業であるが、今回訪れた際もほぼ同じ人数で、同じオフィスで仕事をしていた。先に訪れたAYANEOとは対照的だが、これにはWade氏が述べたGPDの保守的な基本戦略の踏襲が大きく影響しているのだろう。
「市場の拡大を目論む企業は多い。でも私の考えはこうだ。テストの点数を0点から60点まで引き上げるのは容易だが、90点を100点にするのは難しい。市場の拡大もそれに似ていて、切り開くの容易だが、拡大は困難だ。彼らは市場を拡大させるのに危機感や焦りを覚え、昼夜関係なく仕事し続けなければならないだろう。
でも先ほど述べたように、我々は常に平常心を保ち続けたまま、じっくり腰を据えてGPDらしい製品開発をしたい。そのため市場の拡大も考えていないし、会社の規模拡大も考えていない」。
競合が増えるUMPC市場であっても、ニッチな市場を狙う独自路線を堅持し、新しい設計思想を追い求めて、よりニッチな市場を狙うことで他社と差別化を図るGPD。今後登場する新製品がどのような進化を遂げるのか、引き続き注目していきたい。




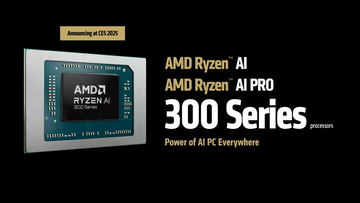




















![[Amazon限定ブランド]CCL い・ろ・は・すラベルレス 2LPET ×8本 ミネラルウォーター 無味 製品画像:1位](https://m.media-amazon.com/images/I/41h0MHfvhkL._SL160_.jpg)



![【Amazon.co.jp限定】 伊藤園 磨かれて、澄みきった日本の水 2L 8本 ラベルレス [ ケース ] [ 水 ] [ 軟水 ] [ ペットボトル ] [ 箱買い ] [ ストック ] [ 水分補給 ] 製品画像:5位](https://m.media-amazon.com/images/I/41n0o65dSkL._SL160_.jpg)



























![液晶ディスプレイ 27インチ ゲーミングモニター モニター ディスプレイ 液晶モニター ゲーミングモニター PCモニター 27型ワイド 1920×1080 VAパネル フルHD FHD 平面 非光沢 アイリスオーヤマ ILD-D27FHH-B ILD-D27FHT-B [安心延長保証対象] 製品画像:14位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/irisplaza-r/cabinet/11073544/12096888/imgrc0110088342.jpg?_ex=128x128)



![新日本海藻誌 日本産海藻類総覧 [ 吉田忠生 ] 製品画像:30位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/7536/75364049.jpg?_ex=128x128)
![決定版 西洋画家図鑑 [ 池上 英洋 ] 製品画像:29位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/1745/9784422701745_1_41.jpg?_ex=128x128)
![SPY×FAMILY 17 (ジャンプコミックス) [ 遠藤 達哉 ] 製品画像:28位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/0092/9784088850092_1_14.jpg?_ex=128x128)
![電池・電池材料の市場動向2026 (エレクトロニクス) [ シーエムシー出版編集部 ] 製品画像:27位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/8851/9784781318851_1_2.jpg?_ex=128x128)
![【楽天ブックス限定特典】山中柔太朗カレンダー2026.4-2027.3(通常版)(オリジナルフォトカード(スマホサイズ)) [ 山中柔太朗 ] 製品画像:26位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/9298/2100014739298_1_3.jpg?_ex=128x128)
![ザ・ファブル The third secret (4) (ヤンマガKCスペシャル) [ 南 勝久 ] 製品画像:25位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/2006/9784065432006.gif?_ex=128x128)
![ファイブスター物語 19 [ 永野 護 ] 製品画像:24位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/3336/9784041173336_1_2.jpg?_ex=128x128)
![世界一簡単! 70歳からのスマホの使いこなし術 [ 増田由紀 ] 製品画像:23位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/3529/9784776213529_1_2.jpg?_ex=128x128)
![[3月下旬より発送予定][新品]桜蘭高校ホスト部(1-18巻 全巻) 全巻セット [入荷予約] 製品画像:22位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/mangazenkan/cabinet/m-comic/comic0026/o-03.jpg?_ex=128x128)
![小学一年生 2026年 4月号 [雑誌] 製品画像:21位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/0466/4912010010466_1_2.jpg?_ex=128x128)