Ubuntu日和
【第52回】最新のUbuntuをRaspberry Pi 5で使おう!
2024年5月25日 06:18
先日リリースされたUbuntu 24.04 LTSでは、改めて「Raspberry Pi 5」への対応も行なわれた。今回はRaspberry Pi 5でUbuntuを使う方法を紹介しよう。
Raspberry Piは言わずと知れたArmプロセッサを搭載したシングルボードコンピューター(SBC)の代表格だ。世代を重ねるごとに性能(と価格)が向上し、今ではちょっとした小型のデスクトップPCとしても使えるまでの存在になっている。
その中でもRaspberry Pi 5は、カードサイズのフットプリントとHDMI/USB/NIC/GPIO/カメラといった各種ペリフェラルコネクタを備えた、Raspberry Piシリーズの最新版だ。Raspberry Pi 5そのものの詳細については、次の記事が参考になるだろう。
Raspberry Pi向けのOSと言えば「Raspberry Pi OS」が定番だが、実はUbuntuも昔からRaspberry Pi向けのイメージを配布している。実際に本連載でも、過去にも次の記事で「Raspberry Pi Zero 2 W」でUbuntuを動かす方法について紹介した。Raspberry Pi 5でも基本的な考え方/使い方はこの記事と大差がない。ただしデスクトップ版も十分実用的に使える点は、Zero 2とは異なるポイントだろう。
Ubuntuを使う利点については上記記事を参考にしてほしいが、おおまかに言うと「 最新のソフトウェアパッケージが使える(こともある) 」のと「 LTSによる長期サポート 」ぐらいだろう。あとはUbuntuユーザーなら、「 普段と同じ環境になる 」ことも利点としてあげられるかもしれない。
Ubuntu 24.04 LTSのインストール方法
基本的にはRaspberry Pi OSと同じく「[Raspberry Pi Imager][]」を使うことになる。Ubuntuならsnapパッケージとしてインストールすると良いだろう。
$ sudo snap install rpi-imager
あとはSuperキー(Windowsキー)を押して、「pi」とか「imager」とかで検索すればお馴染みのラズベリーのアイコンが登場するのでそれを起動しよう。
「デスクトップ版」と「サーバー版」が用意されているので好きな方を選んでほしい。サーバー用途で使うことが決まっているなら、余計なソフトウェアがインストールされていないサーバー版を使おう。ちにみにUbuntu 24.04 TLSからはArmの32bit版(armhf)のイメージは提供されなくなっている。Raspberry Pi 5でUbuntuを動かすのであれば、64bitイメージのみになる点に注意してほしい。
ちなみにRaspberry Pi 5サポートそのものは、Ubuntu 23.10でも行なわれている。ただし23.10のイメージはRaspberry Pi 5のサポートが不十分で、いろいろ動かない部分も多くある。今からインストールするのであれば、サポート期間も含めてUbuntu 24.04 LTSを選ぶことになるだろう。
またインストールメディアに関しては、Raspberry Pi 5だと最初からUSBブートにも対応しているため、USBメモリやUSB-SSDがおすすめだ。たとえば第41回で紹介した「SSD-PSTU3-BA」なんかは、サイズが小さくRaspberry Piに接続してもそこまで邪魔にならないのでおすすめだ。
ただし給電が5V/5Aに対応していない場合は、USBコンテクタへの電流は600mAに制限されるため、USBストレージの性能を十分に発揮できないかもしれない点には注意しておこう。また、後述するようにUSBブート時に確認メッセージが表示され電源ボタンを押す必要が出てくる。メッセージ自体は設定でスキップできるものの、そういう制約があることは覚えておこう。
もちろん引き続きmicroSDカードも使えるものの、どうしても速度や容量、耐久性に制約がある。特にUbuntuのデスクトップ版には向いていない部分も多いため、動作確認目的や、Ubuntu以外のストレージアクセスが少ないような用途などでない限りは使わないほうが良いだろう。
Raspberry Pi 5では、PCIe 2.0x1コネクタ経由のSSDからも起動できるため、そちらにインストールする方法もある。ただし現在のRaspberry Pi向けUbuntuイメージは、microSDやUSBストレージのように「インストール済みのイメージをターゲットストレージに書き込む」方式になるため、M.2 SSDにUbuntuをインストールしたい場合は、PCにM.2 SSDを接続するようなエンクロージャーが必要になる。もし手間を惜しまないなら、一度microSDカードかUSBストレージにUbuntuをインストールした上で、Raspberry Pi側でM.2 SSDにUbuntuのインストールイメージを書き込むという手もある。
microSDカード/USBストレージ/PCIe SSDのいずれの場合でも、Pi Imagerでデバイスを選択したあとの手順は同じだ。あとはRaspberry Piを起動するだけで良い。具体的には以下の機材が必要になる。
- 給電用のUSB-Cケーブル
- USB-Cに対応した5V/3A以上のACアダプターやモバイルバッテリー
- LANケーブルもしくはWi-Fi環境
- microHDMIケーブル
- microHDMIケーブルの先のHDMIディスプレイ
- USBに対応したマウスとキーボード
USBで起動した場合は、ディスプレイもしくはシリアルコンソールに次のようなメッセージが表示される。
USB boot requires high current (5 volt 5 amp) power supply.
To disable this check set usb_max_current_enable=1 in config.txt
or press the power button to temporarily enable usb_max_current_enable
and continue booting.
See https://rptl.io/rpi5-power-supply-info for more information
このメッセージが表示されたら、microSDカードスロットとUSB-Cコネクタの間にある電源ボタンを押そう。上記には「config.txtにusb_max_current_enable=1を書くか、電源ボタンを押すように」と書かれている。つまりconfig.txtを修正すればこのメッセージは出なくなる。Ubuntuのインストール完了後も再起動のたびに電源ボタンを操作したくない場合は、インストール後に「/boot/firmware/config.txt」を編集することになるだろう。
Pi ImagerからインストールできるRaspberry Pi向けのUbuntuは、いわゆる「プレインストールイメージ」と呼ばれるものであり、通常のインストールイメージとは構成が異なる。具体的にはルートファイルシステムに必要なソフトウェアはインストール済みで、初回起動時に環境設定やファイルシステムの自動調整を行ない、再起動してインストールが完了する仕組みとなっている。具体的には次の4ステップでインストール完了になる。撮影の都合でだいぶボケてしまっているが、雰囲気は感じ取ってもらえるだろう。
なお、インストール時に表示されるスライドショーの映像が崩れているが、これは既知の不具合だ。インストールそのものには影響しないので安心してほしい。無事にインストールが完了すれば、あとは再起動するだけだ。USBストレージを使う場合は、再起動後も上記のメッセージが出て、電源ボタンを押さなければならないことには注意しておこう。
日本語環境を構築する
Ubuntu 24.04 LTSのプレインストールイメージは、まだ多言語対応が完了していない。つまり、インストール時に「日本語」を選んでも、一部の日本語関連のパッケージがインストールされず、英語環境で起動してしまう。よって起動したらまずは、ソフトウェアを更新した上で、日本語対応を行なおう。
ソフトウェアの更新は「update-manager」で検索して「ソフトウェアの更新」を起動すれば良い。
あとは画面の指示に従って更新すれば完了だ。この時点で再起動するかどうか尋ねられるが、あとで手動で再起動することにしよう。
次に必要なパッケージをインストールするために、「言語サポート」を起動する。これはSuperキーを押して「language」と押せば表示される。もしくは設定ソフトウェアの「System」の「Region & Language」から「Manage Installed Languages」を選ぶ形でも良い。
あとは画面右上のインジケーター領域から歯車アイコンの設定ソフトウェアを起動し、「System」から「Region & Language」を選択する。その画面にある「Your Account」と「Login Screen」の「Laungage」を「日本語」に「Formats」を「日本」に変更しておこう。選択しただけだと表示は変わらないかもしれないが、ログインしなおせば(ソフトウェアの更新結果も反映するなら再起動すれば)、日本語環境の完成だ。おおよそのソフトウェアが期待通りに日本語で表示されることだろう。
なお、アプリセンターは日本語フォントが「豆腐」として表示される。これはアプリセンター側の不具合だ。おそらくSnapパッケージのフォント周りの問題だと思われるのだが、PCだと問題ないためarm64アーキテクチャ固有の話となる。残念ながら原因も回避策も不明なため、もしGUIからソフトウェアをインストールしたければ、CLIから「gnome-software」パッケージのインストールをおすすめする。
rpi-eeprom-updateとraspi-config
Raspberry Piでは、rpi-eeprom-updateコマンドを使うことで各種ファームウェアを更新できる。起動周りの問題や各種ハードウェアとの相性問題などは、新しいファームウェアで解消することも多い。たとえばRaspberry Pi 4の頃はUSBブートなどは新しいファームウェアに更新することで対応されていた。
rpi-eeprom-updateコマンドは最初からインストールされているため、更新したければ次のように実行しよう。
$ sudo rpi-eeprom-update
ただしこの更新方法は、rpi-eepromパッケージが更新されない限り、新しいファームウェアに更新できない。手動で最新版に更新したい場合は、Raspberry Piのドキュメントを参照して欲しい。基本的には最新のバイナリをダウンロードして、rpi-eeprom-updateコマンドを実行することになるだろう。
またRaspberry Piは伝統的に、いくつかの設定は「/boot/firmware/config.txt」によって変更できることになっている。手で直接変更しても良いが、変更用のツールである「raspi-config」コマンドが存在する。こちらは最初からインストールされていないため、必要であれば次のようにインストールする必要がある。
$ sudo apt install raspi-config
$ sudo raspi-config
ブートローダーのバージョンの確認などに使われるvggencmdも最初からインストールされている。このあたりの使い方はRaspberry Pi OSと同じだ。
カメラはまだ動かない
基本的にWi-FiやBluetooth、GPIO、HDMIといった周辺機器は問題なく動く。ただしカメラだけは、まだサポートしていない。これはUbuntu 23.10でも同様で、原因がまだ分かっていない状態である。
正直なところRaspberry Pi OSが十分に実用的な選択肢であるために、あえてUbuntuを使う理由は低くなりがちだ。特にペリフェラル周りは、上記のカメラのように「Raspberry Pi OSだと動くのに」ということも起こりうる。
ただし動かないのは「カメラなどの一部のソフトウェアだけ」とも言える。言い換えると、「ちょっとしたサーバー」や「ミニPC」程度の用途であれば、Ubuntuでも何の問題もなく利用できるのだ。つまりUbuntuの強みは、普段PCやWSLで使っている環境と同じにできるし、同じソフトウェアセットをそのまま利用可能なことになる。ここに意義を見いだせるなら、ぜひRaspberry Pi 4や5にUbuntuをインストールしてほしい。













![[Amazon限定ブランド]CCL い・ろ・は・すラベルレス 2LPET ×8本 ミネラルウォーター 無味 製品画像:1位](https://m.media-amazon.com/images/I/41h0MHfvhkL._SL160_.jpg)



![【Amazon.co.jp限定】 伊藤園 磨かれて、澄みきった日本の水 2L 8本 ラベルレス [ ケース ] [ 水 ] [ 軟水 ] [ ペットボトル ] [ 箱買い ] [ ストック ] [ 水分補給 ] 製品画像:5位](https://m.media-amazon.com/images/I/41n0o65dSkL._SL160_.jpg)










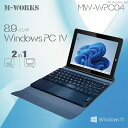













![IOデータ 275Hz&WQHD対応ゲーミングモニター KH-GDQ271UA GigaCrysta [27型 / WQHD(2560×1440) / ワイド] ブラック 製品画像:3位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/r-kojima/cabinet/n0000001586/4957180185699_1.jpg?_ex=128x128)


![山本ゆり iwakiの耐熱調理容器でおいしいレシピ モスグリーンver. (TJMOOK) [ 山本 ゆり ] 製品画像:30位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/3952/9784299073952_1_3.jpg?_ex=128x128)
![山本ゆり iwakiの耐熱調理容器でおいしいレシピ ダークグレーver. (TJMOOK) [ 山本 ゆり ] 製品画像:29位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/3914/9784299073914_1_3.jpg?_ex=128x128)
![Inspire Praise Bible Nlt, Filament Enabled (Hardcover Leatherlike, Purple) INSPIRE PRAISE BIBLE NLT FILAM [ New Living Translation ] 製品画像:28位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/7865/9781496487865_1_3.jpg?_ex=128x128)



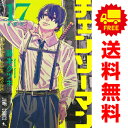

![継母の心得3【電子書籍】[ ほおのきソラ ] 製品画像:22位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rakutenkobo-ebooks/cabinet/8330/2000019738330.jpg?_ex=128x128)
