特集
知っ得!企業トップのAI活用法。日本マイクロソフト社長のCopilotの使い方がすごく勉強になる
2024年5月28日 06:28
日本マイクロソフトの津坂美樹社長は、生成AIである「Microsoft Copilot」を、自ら積極的に利用している経営者だ。2023年2月の社長就任時は、生成AIが国内に広がり始めたタイミングで、「日本マイクロソフトの社長に就任して最初にやったことは、生成AIを有料契約し、徹底的に使い始めたことだった」というほどに、生成AIの活用には前向きだ。
そして、生成AIを使いこなすには、「AIの筋トレ」が必要であると明言。それを自ら実践するとともに、ビジネスパーソンや開発者に対しても「AIの筋トレ」を勧める。
そこで今回は特別企画として、津坂社長が生成AIをどのように使いこなしているのかを探るため、一日の姿を追ってみた。これは、「AIの筋トレ」の実践方法とも言え、ビジネスパーソンにとって、生成AIの使いこなしのヒントになるはずだ。
一日の始まりはAIの呼び出しから
日本マイクロソフトの津坂美樹社長は、一日の始まりとともにCopilotを活用している。
津坂社長が、自宅で朝食をとりながら手にしているのはiPhoneだ。前夜から早朝にかけて送られてきたメールのチェックで一日の仕事が始まるが、このときすでにCopilotは津坂社長の作業をサポートしている。
日本の深夜でも米国本社は稼働している時間だ。早朝から多くのメールが送られてきているのは毎日のことである。津坂社長はCopilotに頼んで、優先度の高いメールをレコメンドし、表示してもらい、それをもとにメールを順番にチェックする。
さらに、長文のメールはサマリを表示し、必要な情報を短い時間に把握するといったことも行なっている。今日中に返信をしなければいけないメールは、Copilotが教えてくれる。
そして、グローバルチーム向けに英語でメールした内容は、Copilotで日本語化して、日本のチームと情報共有するといったことも行なう。
Copilotは朝食の時間にも、副操縦士として津坂社長の作業をしっかりとサポートしているのだ。
ミーティング前にCopilotで調査結果を分析
クルマで移動して出社すると、Copilotが活躍するデバイスは、津坂社長が日常利用しているノートPCのSurface Laptop 5に移る。
津坂社長が、東京・品川の日本マイクロソフト本社の社長室に入ると、すぐに最初のミーティングをスタートさせた。まずは、マーケティング担当者とのミーティングだ。
会議では、先月開催したイベントの調査結果を共有。担当者はFormsで集めた自由記述のコメントをCopilotで分析。Copilotは、良かった点の上位5項目と、課題となっている上位5項目を示し、それをもとにディスカッションが行なわれた。
短時間に課題を整理し、その成果を共有するとともに、次回のイベント開催に向けた議論を進めることができるわけだ。
次のミーティングは、今週末に迫った運輸業界の顧客へのプレゼンテーションの社内レビューだ。
チームはCopilotの助けで日英両言語のスライドを用意して、市場と社内のデータを組み合わせ、説得力のある内容の資料に仕立ててくれていた。津坂社長の要望も反映しながら、スライドを修正。Copilotを使って、顧客のコーポレートカラーを使ったり、フォントを統一したりといった細かい部分までブラッシュアップしたりすることができたという。
未出席のミーティングをCopilotで要約
ここで突然入ってきたのが、役員との緊急ミーティングだ。当初予定していた複数のミーティングには参加できなくなってしまったが、Teamsを利用して会議の内容を録画。Copilotで録音内容の要点を確認することにした。重要な部分や自分に関わる部分だけを抽出することで、効率的に会議の内容を把握できる。
津坂社長は、ミーティングの件数が集中しているときには、情報共有が主体となっている会議には出席せず、空いた時間を使ってあとから会議の要点を確認したり、節約した時間を別の会議の深いディスカッションに充てたりといったことを日常的に行なっているという。
スピーチのための話題をCopilotで収集
ランチタイムになると、津坂社長は再びiPhoneを取り出し、食事を取りながら、来月のイベントでのスピーチの準備を始めた。
Copilotに向かって、「出席者のグループに関連した驚くべきニュースを3つ教えて」、「出席者に最も注目が集まっているSNSのポストは?」などと尋ね、聴講者の心を掴めそうな話題を収集。スピーチに使えそうな話題を選んで、内容を構成していった。
かつては、担当者が聴講者の傾向を捉えた資料を揃え、それをもとにスピーチ内容を構成するというやり方だったが、津坂社長はCopilotを相棒に、自ら必要と思われる情報を収集する。担当者の作業時間を減らし、津坂社長自身もより理解を深めながら、最新の情報を取り入れて、スピーチの構成を考えている。
午後になると、品川本社を飛び出して顧客先に向かった。まずは、通信業界の客先へ訪問するというスケジュールが設定されている。
顧客の難質問をCopilotで事前予測
移動するクルマの中でも、津坂社長の手にはiPhoneが握られている。
自らが事前に用意してきた資料だけでなく、チームが用意してくれたドキュメントを再度確認。Copilotに対して、相手がしそうなタフな質問をいくつか予想してもらうという驚くべき使い方をして見せた。
客先に到着する最後の瞬間まで、準備に万全を尽くすのが津坂社長のやり方だが、そこにCopilotが準備の内容に幅と深みを持たせる役割を果たしているというわけだ。
訪問先では、Copilotのデモを行なったが、その際に、Microsoftが取り組む「責任あるAI」に対する姿勢を紹介。顧客は、生成AIに対する不安を持っていたそうだが、津坂社長の説明を聞き、Copilotの採用に前向きな返答が得られたという。
日々、津坂社長自らがCopilotを使い込んでいることが、自信を持って機能を紹介したり、説得力を持った「責任あるAI」の説明につながったりしていると言えよう。
初訪問の顧客をライバル関係なども含めてCopilotで情報収集
この日はいくつかの訪問先を回ったが、その中の1社は初めて会うことになる企業だった。
津坂社長は、準備のためにその企業の情報だけでなく、競合する2社が発表した最近のニュースをCopilotに検索してもらったほか、競合企業との比較表を作ってもらい、事前に分析を行なったという。
また、経営者のプロフィールや、市場に関するシンクタンクなどのレポートもまとめ、Copilotに要点を整理する作業を行なってもらっていた。
ここでは、Copilotとやり取りの応酬を行なっている。
たとえば、最初の質問は訪問する企業の経営理念やミッションに関するものだが、次にその回答をもとに、社長が打ち出した方針などについて質問。さらに、社長の人柄や趣味などのパーソナルな面についても質問するといったように、複数の質問を繰り返すことで深堀りし、情報を収集するといった具合だ。
社員への日本語・英語ビデオレターをCopilotで短時間に作成
品川本社のオフィスに帰社すると、オフィスでの終業時間まではわずかとなっていた。
津坂社長は、毎週金曜日に日本マイクロソフト全社員に向けて動画メッセージを配信しているが、この日は動画制作の日であった。
津坂社長の動画メッセージの特徴は、日本語と英語の2つのバージョンを用意していることだ。1つの映像に字幕を入れるのではなく、それぞれに収録するという手法を用いている。
Surface Laptop 5を起動させた津坂社長は、まずはCopilotを使って動画メッセージに使用する日英両方のドラフトを準備し、内容に差が出ないように整えた。
さらに、今回は海外や国内の出張先の写真を動画メッセージに挿入することを決定。Copilotと一緒になって説明用の画面をPowerPointで作り、動画の中に挿入することにした。
Copilotの支援を得て、短時間に完成度の高い動画メッセージを制作できたという。津坂社長は動画メッセージに使用するイラストや、講演の際に使用する画像にCopilotを使用することが多い。
2024年2月に東京・有明の東京ビッグサイトで開催した「Microsoft AI Tour – Tokyo」の基調講演の中でも、東京をイメージした画像を作成し、これを基調講演の中で公開して見せた。
同イベントは、世界13都市で開催したワールドツアーであったため、東京での開催を訴求する意味で画像を作成したという。大型スクリーンに映し出した「作品」の出来栄えについて津坂社長は「ちょっと富士山が大きかった」と語り、会場を沸かせた。
返信できていない重要なメールをCopilotに探してもらう
オフィスでの仕事を終えようとすると、返信をし忘れているメールをCopilotが教えてくれた。今日中に返信しなくてはならないメールをすべて完了させたところで、ちょうど終業時間を迎えた。
だが、津坂社長の仕事はまだ続いていた。
夕方から夜にかけて若いビジネスパーソン向けに、自分のキャリアを語る講演会にメインスピーカーとして登壇。デモンストレーションの場面では、Copilotに気の利いたジョークで助けてもらおうとしたが、それがおもしろくなさすぎて、逆に会場で受けてしまうという一幕もあった。
また、その後に行なわれた会食では、カジュアルな雰囲気の中で話題はゴルフに発展。Copilotが特定のホールの必勝法などについての情報を提供し、その場の雰囲気を盛り上げることに一役買ったという。
海外出張先の状況をCopilotで把握
ようやく帰路についた津坂社長だが、クルマの中では来週海外出張で訪れる3つの都市の状況を把握。各都市の天気予報や降水確率、帰国時に空港で買うといいお土産などの情報をCopilotに尋ねながら帰宅。荷造りの参考にしたという。
仕事をあらゆる角度からサポートしてくれるCopilotと過ごす津坂社長の1日が終わった。
AIを使いこなすには「AIの筋トレ」も必要
津坂社長の毎日は、このようにCopilotとともにあると言ってもいい。
津坂社長自身も「私にとってCopilotは100%必要なものになっている。もはやCopilotなしでは仕事ができない」とも語る。
今回紹介した使い方のほかにも、参加した会議の日本語の記事録を英語に変換して海外拠点に送るといった使い方や、会議そのものの精度を分析するといった用途にもCopilotを使用している。
「エンジニアでない私でも使えて、いつでも、どこでも、誰にでも、呼び出すことができるのがCopilotの特徴である。アシスタントとしての役割だけでなく、先生や同僚、部下というさまざまな立場になり、時には通訳者にもなって、業務を支援してくれる。CopilotはAIの民主化を実現するプラットフォームであり、すべての人をエンパワーし、多くのことを達成できるようにしてくれる」と語る。
ただ、津坂社長はCopilotを使いこなすには「AIの筋トレ」が必要だとする。
「最初のうちはなかなか言うことを聞いてくれなかったが、毎日使用していると、より良い結果が出るようになった。ある程度やったところで、AIの筋肉が付いたかなと思えるタイミングあった」という。
また、「ただ、さらに活用を進めると、またスキルが横ばいになっているなと感じる場面があった。しかしそれでも毎日毎日使い続け、Copilotと議論を繰り返すことで、AIの筋肉がさらに付いたと感じることができるようになった」とする。
生成AIそのものが進化を遂げている一方で、対話のために入力するプロンプトによって、回答内容や回答の質が変わるのが生成AIの特徴でもある。最適な回答を得るためにはノウハウの蓄積や、工夫した入力が必要であり、そのスキルを身に着けるために、「AIの筋トレ」が必要だという。
津坂社長も、当初は短いプロンプトの入力だったため、適切な回答が得られないことがあったようだが、最近ではプロンプトを長くして、より適切な回答が得られるようになったという。これも「AIの筋トレ」の成果だ。
生成AIは、多くの人が利用できるテクノロジであるという側面はあるものの、その一方で、使い方によって効果に差が出やすい特性もある。
それぞれの組織や個人が利用する際に、最も効果的な使い方ができるプロンプトやユースケース、ノウハウを蓄積し、それらを共有することで組織全体がより効果的に生成AIを利用できるようになる。
日本マイクロソフト社内でも、そうしたノウハウや工夫を共有する仕組みが構築されているという。
津坂社長は「2024年は生成AIをフル活用する年になる」と語る。そして、それを実践しているのが津坂社長自身である。津坂社長のように、毎日「AIの筋トレ」を実践している経営者と、そうでない経営者の差が、これから明確になってくるのかもしれない。










![[Amazon限定ブランド]CCL い・ろ・は・すラベルレス 2LPET ×8本 ミネラルウォーター 無味 製品画像:1位](https://m.media-amazon.com/images/I/41h0MHfvhkL._SL160_.jpg)



![【Amazon.co.jp限定】 伊藤園 磨かれて、澄みきった日本の水 2L 8本 ラベルレス [ ケース ] [ 水 ] [ 軟水 ] [ ペットボトル ] [ 箱買い ] [ ストック ] [ 水分補給 ] 製品画像:5位](https://m.media-amazon.com/images/I/41n0o65dSkL._SL160_.jpg)
























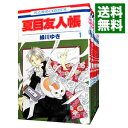
![予約の取れないセラピストの骨格小顔バンド [ 三木まゆ美 ] 製品画像:29位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/8296/9784865938296_1_16.jpg?_ex=128x128)
![ROCKIN'ON JAPAN (ロッキング・オン・ジャパン) 2026年 5月号 [雑誌] 製品画像:28位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/0561/4912097970561.gif?_ex=128x128)
![青天 [ 若林 正恭 ] 製品画像:27位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/0665/9784163920665_1_10.jpg?_ex=128x128)


![STORY (ストーリィ) 2026年 4月号 [雑誌] 製品画像:24位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/0464/4912054830464_1_2.jpg?_ex=128x128)
![ANIMATION WORKS「LUPIN THE IIIRD」シリーズ公式コンプリートブック [ MdN編集部 ] 製品画像:23位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/8389/9784295208389_1_2.jpg?_ex=128x128)
![だぶるぷれい 7【電子書籍】[ ムラタコウジ ] 製品画像:22位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rakutenkobo-ebooks/cabinet/1782/2000019711782.jpg?_ex=128x128)
![Numero TOKYO (ヌメロ・トウキョウ)4月号増刊 2026年 4月号 [雑誌] 製品画像:21位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/0466/4912172000466_1_2.jpg?_ex=128x128)