イベントレポート
抱くだけで心の乱れをチェックできる東芝のIoT機器や、AIが伴奏してくれるヤマハのピアノ
2018年3月19日 15:01
米国テキサス州オースティン市で3月9日~3月17日(現地時間)に開催された「SXSW Conference & Festivals」(サウスバイサウスウェスト・カンファレンス・アンド・フェスティバル)には、多数のスタートアップ企業や大企業のなかでも先端技術を開発する部門などが参加し、多数の新デバイスの展示や基調講演などが行なわれている。
音楽祭から発展して、ITスタートアップの祭典へと進化したSXSW
SXSWは、米国テキサス州オースティンで例年3月に開催されている展示会イベントとなる。元々は音楽祭として発展し、その後映画祭、さらにはインタラクティブと呼ばれるIT系のイベントが追加され、そこにIT系のスタートアップが多数参加するようになったという経緯で、IT系のイベントとしても注目を集めている。
IT系イベントとして伝統的なCESやIFAとの大きな違いは、SXSWにはスタートアップ企業が出展するのが一般的だったということだろう。たとえば、TwitterはSXSWで初めて注目を集めた企業だ。それに続けということでSXSWはスタートアップ企業が“夢を語る”イベントになり、投資会社なども注目して、1つの循環モデルとして成立していった。
現在では、多くのメディアが注目しているイベントに成長したこともあり、スタートアップ企業だけでなく、大手企業も開発中の技術やソリューションを展示するイベントとして活用されてきている。
地元オースティンに会社を置くDell、ソニー、パナソニックといった大企業も出展しており、VRやARなどの各種のソリューションを展示している。
ユニークなのは、SXSWの展示はメイン会場となるオースティンコンベンションセンターの会場だけでなく、オースティンのダウンタウン(中心街のこと)の街全体がある意味会場になっており、街にあるレストランなども貸し切って展示が行なわれている点だ。
CESやIFAがよりビジネス寄りの展示会であるのに対して、SXSWは音楽祭から発展したという歴史的な経緯もあって、よりお祭りに近いイベントになっている。このため、どこのブースに行っても、来場者にお酒が振る舞われていたり、バンドが生演奏していたりと、筆者が普段参加しているIT系のイベントとは大分趣が違っていた。
また、カンファレンスのメニューも充実しており、TESLAの創業者であるイーロン・マスク氏の講演なども行なわれていた。このように、スタートアップ界隈で話題の関係者が登壇するのもSXSWの特徴だ。
日本のお家芸「アナログ技術」を活用したセンサーを利用した展示が多数行なわれている
大企業のブースはメイン会場以外に設置されており、行くのにちょっと時間がかかるのがやっかいだが、行ってみると普段の展示会では見られないようなデモをしていたりしてなかなか興味深い。一報、資金的な余裕がない小さな企業は、オースティンコンベンションセンターの展示会場にブースを出している。
見ているだけでも楽しいのだが、こうした展示はちゃんと試作機を作ってデモしているところ、試作機なしでアイデアのみをアピールしているところというように大きく2種類に分けられる。
前者に関しては動くのを確認できて技術に関しても説明をしてくれる場合がほとんどなのだが、後者に関しては単にアイディアをアピールしているだけでどう実現するのと聞くと口ごもってしまうという例も少なくない。ただし、このあたりは、どの段階を必要とするのかによりけり(たとえば投資家なら後者が必要だろう)なので、一概にどちらが良い悪いということではない。
今年(2018年)のSXSWの展示を見ていて筆者が感じのは、どのデモでも鍵になっていたのは“センサー”だったということだ。この記事の後半で紹介するIoT機器もそうだが、ソニーでも、パナソニックでもデモの鍵になっていたのは人間の動きといったアナログな動きをデジタルに変換するモーションセンサーだった。
そのセンサーはデータを生み出し、それがクラウドに送られてひととおりまとめられれば「ビッグデータ」となり、それを元に深層学習を通して再びIoT側にフィードバックしていく、それが自動運転自動車を含むIoT機器の「エコシステム」だ。
日本のスタートアップもSXSWでは非常にがんばっており、経産省主導の下でSXSWの日本勢のブースはそれなりの大きさだった。すでに米国勢(Amazon、Google、Microsoft)が多大な投資を行なったあとで、正直これからクラウド側で日本メーカーが盛り返すのは難しいが、エッジ側のIoT機器にはまだチャンスがあると感じた。とくにセンサーは日本のお家芸と言えるアナログ技術の塊であり、そこを日本の部品メーカーなどがカバーできれば、存在感を出していくことは可能だろう。
東芝のMINDFULは抱くだけで呼吸の動きをチェックし、心の乱れなどを数値化
オースティンコンベンションセンターの展示会場には、東芝やヤマハと言った大手企業から、スタートアップまで大小多数のブースで賑わっている。とくに多いのは国別のブースで、日本メーカーが集まっているブース、中国メーカーのブース、メキシコメーカーが集まっているブースと、それぞれ国家主導でスタートアップを育てたいという思惑が感じられる構成だ。
日本メーカーが集まっているゾーンには注目の展示がいくつかあったが、東芝のブースでは「MINDFUL(マインドフル)」という名前のIoT機器が出展されていた。
MINDFULは呼吸センサーになっており、人間の呼吸の動きをチェックすることで、リラックスしているのか、緊張しているのかなどをチェックできるようになっている。
計測方法の詳細に関しては非公開だったが、内蔵されているセンサーがお腹までの距離などを測って、それによりどのように呼吸が行なわれているかを数値化しているという。写真のように、お腹の前に抱える感じで持っていると、呼吸の回数などを計測できる。
ヨガをやりながら呼吸が落ち着いているかを確認したり、日々正しく呼吸が行なわれているかなどを調べて病気の予防などにしたりといった使い方が考えられているとのことだった。
計測したデータはBluetooth経由でPCに送って処理しているという。将来的には、PCだけでなくスマートフォンなどにデータを送ることも可能になるようだ。
人間がコンピュータの伴奏に合わせるのではなく、AIが人間の演奏に合わせて伴奏
楽器メーカーのヤマハは、「Duet with YOO」と呼ばれるAIピアノのデモを行なった。ベースとなっているのは、同社の電子ピアノ「Clavinova(クラビノーバ)」で、MIDIデータを元にして鍵盤が自動で動きながら演奏してくれるというおなじみのシリーズだ。Duet with YOOではこれに深層学習AIを活用した演奏補助機能となっている。
具体的には、演奏者の演奏に合わせてAIが伴奏をつけるという機能になる。従来の自動演奏機能では、コンピュータやシーケンサーが自動演奏している音楽の上に、演奏者側が合わせて演奏する必要があった。つまり、コンピュータの自動演奏に合わせる演奏者側に、それなりの技術が要求されるものだったわけだ。
しかし、Duet with YOOではAIが演奏者に合わせて伴奏をつけてくれる。演奏者がゆっくり弾いた場合には伴奏もゆっくりになり、逆に速く弾いた場合には早くなるといった機能になる。
ピアノは幼稚園児時代オルガン教室に通い、以来数十年にわたって弾けた記憶がない筆者も実際にチャレンジしてみた。「キラキラ星」を弾いてみて慣れるまではとてもゆっくり弾いたのだが、それでもちゃんと伴奏で合わせてくれたし、逆に慣れてきて早く弾けるようになったら伴奏も早くなっているのが実感できた。
その伴奏を弾いているのは、そのピアノの横に設置されていたデスクトップPC上で動いているAI。なかをのぞいてみたら、GeForce GTX 1080と思われるビデオカードが2枚ささっており、それによりAIがユーザーのキー入力を検知して伴奏を調整しているという。筆者のように下手っぴでもAIが合わせてくれるので、演奏しているうちに楽しくなってくる。これはぜひとも将来的に導入してほしい機能だと感じた。
バンダイナムコの「PAC-CONNECT」や東大の浮遊アシストデバイス「LUNAVITY」
バンダイナムコは、同社の象徴とも言えるタイトルであるパックマンをベースにした新しいコンテンツを紹介。博報堂、Ars Electronica Futurelabらと共同でPACATHON(パッカソン)というパックマンベースの新しいコンテンツを開発しており、SXSWでその成果の一部を展示した。
たとえば、パックマンでこれまでなかった複数のプレイヤーが協力し合う機能を搭載した「PAC-CONNECT」を公開。通常のパックマンではパワーエサを食べるとモンスターを倒すことができるようになるが、PAC-CONNECTではパワーエサを食べた後に、ほかのプレイヤーと合流してつながるとミッションクリアとなる。つまり、ほかのプレイヤーと協力して初めてゲームをクリアできるのだ。
東京大学大学院情報学環 暦本研究室は、LUNAVITYという人間の物理的な能力を拡張するデバイスを出展した。
LUNAVITYは、背負っているデバイスの上部に16個のローターがついており、それを利用して人間の能力を超えたジャンプを可能にする。LUNAVITYを背負っておけばローターによる浮遊力のアシストを得ることができるので、階段で小気味よくジャンプして上ったり、本来の人間能力では飛び上がれないぐらいの高さに飛び上がることが可能になる。どんな感じかは、暦本研究室が公開しているビデオがあるので、参考にしてほしい。
ドラえもんのタケコプターのように、これをつけて人間が空を飛ぶという飛行デバイスではなくて、アシストデバイスという位置づけだ。現状ではバッテリに制限があるので、1日使い続けるなどは不可能で、バッテリで重くなってしまう分の浮遊力も必要になるため、効率が悪いという。その意味では将来的なバッテリ技術の革新に期待しているということだった。
そのほかにも以下のようなものが展示されていた。











![[Amazon限定ブランド]CCL い・ろ・は・すラベルレス 2LPET ×8本 ミネラルウォーター 無味 製品画像:2位](https://m.media-amazon.com/images/I/41h0MHfvhkL._SL160_.jpg)







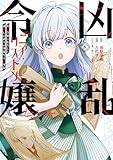





![【中古】送料無料[良品]Apple MacBook Air(M1, 2020)/ Apple M1 / メモリ8GB / SSD256GB / Windows11 / Office 2024品質保証あり 初期設定不要 無料サポート 製品画像:5位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/maclife/cabinet/10217568/imgrc0137080231.jpg?_ex=128x128)




![【中古】 SONY VAIO VPCL128FJ 大容量HDD搭載 Core 2 Quad Windows10 Home ブルーレイ 液晶一体型 保証付 [93773] 製品画像:6位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/risemark/cabinet/pic/937b/93773.jpg?_ex=128x128)








![【20%OFFクーポンあり!】[五年保証] モニター 27インチ IPS (1920×1080/120Hz)|USB Type-C・HDMI接続対応|目疲れ配慮|スピーカー内蔵|Adaptive Sync|HDR10|sRGB110%|VESA対応|フレームレス |USB-Cケーブル付き (MF27X3A・ケーブル付属) Minifire 製品画像:4位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/minifire-direct/cabinet/120.jpg?_ex=128x128)

【ECセンター】保証期間1週間 製品画像:2位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/janpara/cabinet/itemimg_tempostar/shop222_39/108159430-222_1.jpg?_ex=128x128)

![1冊ですべて身につくWordPress入門講座 [ Mana ] 製品画像:30位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/9405/9784815609405_1_6.jpg?_ex=128x128)

![青天【電子書籍】[ 若林正恭 ] 製品画像:28位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rakutenkobo-ebooks/cabinet/0144/2000019330144.jpg?_ex=128x128)

![Illustrator しっかり入門 増補改訂 第3版 [Mac & Windows対応] [ 高野 雅弘 ] 製品画像:26位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/4286/9784815624286_1_13.jpg?_ex=128x128)
![Photoshop しっかり入門 増補改訂 第3版 [Mac & Windows対応] [ まきの ゆみ ] 製品画像:25位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/4293/9784815624293_1_5.jpg?_ex=128x128)


![きらめきかわいいブック システムシール手帳特大号 (扶桑社ムック) [ サンリオ ] 製品画像:22位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/4392/9784594624392_1_3.jpg?_ex=128x128)
![1冊ですべて身につくHTML & CSSとWebデザイン入門講座[第2版] [ Mana ] 製品画像:21位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/8469/9784815618469_1_7.jpg?_ex=128x128)