やじうまミニレビュー
外見だけで仕様を判別できないケーブルは、テプラを貼り付けて管理!「テプラPRO」ブランドの専用ラベル2種類を試す
2024年5月16日 06:36
PCに使われるケーブルは、外見だけではスペックが判断できないこともしばしば。LANケーブルやUSB Type-Cケーブルのように、同じコネクタ形状でさまざまな仕様違いがあると、スペックの取り違えによって速度が出なかったり、特定の機能が利用できないといったトラブルが起こりやすい。
こうしたトラブルを防ぐには、ケーブルの仕様を記したラベルを、ケーブル本体に貼り付けておくのが手っ取り早い。やや手間はかかるが、これならば複数のメーカーの製品が混在していてもマイルールで統一できるし、見た目が揃うので複数のケーブルを併用していても比較的スッキリする。
こうした用途に使えるラベル製品を複数ラインナップしているのが、キングジムのラベルライター「テプラPRO」ブランドだ。専用機ではなく一般的なテプラを使えることから、初期コストもぐんと下がる。今回は一般家庭でも導入可能な2つのラベル製品を実際に試してみた。
裏面がシールになったセルフラミネートタイプ「ケーブル表示ラベル」
まず最初に紹介するのは、その名もズバリ「ケーブル表示ラベル」だ。幅24mmと36mmの2種類があるが、今回は24mmの「SV24KN」を購入した。実売価格は1,560円だ。
裏面がシールになっているのは、一般的なテプラのラベルと同様だが、一般的なラベルは全面が白になっているのに対し、本製品はラベルの上3分の1(幅8mm)が白い印字面、その下およそ3分の2(幅16mm)が透明なフィルムになっている。
この印字面にケーブルのスペックを印刷し、ケーブルをぐるりと巻くように貼り付けると、透明の部分が印字された部分を覆う格好になる。これにより、擦れによる印字の欠けを防止できるというわけだ。メーカーの「セルフラミネートタイプ」という表現は言い得て妙である。
ラベルはビニールに近い素材で伸縮性があるので、ケーブルの曲げにもある程度は対応できる。ただし過剰に曲げるとシワが残るので、ほどほどにしておきたい。
見た感じ、一般的なラベルもこれと同じことができそうに見えるが、ラベルの幅が足りないため、ケーブルの径をぐるりと一周できないことに加え、曲げるたびに端から剥がれてくるので、そこにホコリが付着するなど、見た目も汚くなりがちだ。その点本製品は、やはり専用品だけのことはある。
今回は長期間の耐久性まではチェックしておらず、何年にもわたって使った場合の劣化については不明だが、現在市販されているのは従来よりも伸縮性と隠蔽性を向上させたリニューアルモデルとのことで、3年以上前のAmazonの口コミに見られる曲げへの弱さなどは、ある程度対策されているものと考えられる。
粘着力は非常に強く、いったん貼ると剥がすのが困難なのは、利点でもあり欠点でもあるが、ケーブルの上から巻くという仕組み上、ケーブルの太さを問わず対応できるオールマイティさはなによりの強みだ。
熱風を吹きかけてフィットさせる「熱収縮チューブ」
もうひとつ紹介するのは、同じくテプラPROブランドの「熱収縮チューブ」だ。径が5mmまでと11mmまでの2種類がラインナップされているが、今回は11mmまでの「SU11S」を購入した。実売価格は1,450円だ。
これはあらかじめ筒状になったラベルに印字を行ない、ケーブルに通した後、ドライヤーで熱を加えて縮めることで、ケーブルにぴったり密着させるという製品だ。チューブマーカーなどと呼ばれる専用機でしかできない加工を、一般的なテプラでできてしまうのが特徴だ。実際の加工の様子は動画でチェックしてほしい。
この製品のメリットは、もともとがチューブになっていることから、剥がれる恐れがないこと。継ぎ目がないため見た目にも美しく、シワが発生しにくいのも利点だ。とにかく仕上がりの美しさを優先したい場合には、最良の選択肢だ。
気を付けたいのは、加工に用いるドライヤーは家庭用ではなく、工業用ドライヤーでなくてはならないこと。工業用ドライヤーは、家庭用のヘアドライヤーよりも高い温度に設定できるのが特徴で、本製品の収縮温度範囲(90~270℃)をカバーできる。家庭用ドライヤーは最大でも140℃程度なので、熱が足りないというわけだ。
今回試しに家庭用ヘアドライヤーも使ってみたが、やはり熱の関係か、縮み方がいびつになってしまった。従ってメーカーの推奨通りに工業用ドライヤーを用いるのがベターだが、本製品のためだけに実売数千円~1万円程度かかる工業用ドライヤーを購入するのは、さすがにためらう人も少なくないだろう。
もうひとつ、チューブ状であることから、LANケーブルのRJ45コネクタを付けたままでは通せないという、かなり致命的な問題がある。そのため用途は事実上、自分でコネクタを取り付ける自作LANケーブルなどに限られてしまう。
これがLANケーブルでなく、コネクタ径の小さいUSB Type-Cなどであれば通すことは可能なのだが、こちらはケーブルが細すぎて、チューブが縮みきらずにぶかぶかになってしまう(USBケーブルの径は3.5mm前後、本製品の対応直径は5.5~11mm)。このあたり、対応機種が非常にシビアで使いづらいのはマイナスだ。ある程度の知識と経験があって初めて使いこなせる製品と言えるだろう。
外見だけで仕様を判別できないケーブルの解決に
最後になったが、テプラ本体についても紹介しておこう。今回使用したのは「テプラ PRO」(SR-MK1)という、スマホからの操作に対応したモデルだ。文字の種類やフォントなどの制限が極めて少なく、かつ360dpiと高品質なのが特徴だ。ラベルの対応幅は24mmまでとなっている。
気を付けなくてはいけないのが、対応するスマホアプリで、「Hello」「TEPRA LINK 2」という、2種類のアプリが存在している。このうち「Hello」は家庭用のテンプレートの豊富さが売りのアプリで、今回の用途にはまったく向いていない。
もうひとつの「TEPRA LINK 2」も、UIが直感的でなく、文字の修正ひとつするだけでイライラさせられるのだが、今回のケーブルラベルのような実用的なラベルを作るのであれば、前述の「Hello」よりははるかにマシだ。ラベルのフォーマットを一度作ってしまえば、それを改変しながら出力すればよいからだ。
と、ラベル本体からアプリまでツッコミどころは数多くあるのだが、外見だけで仕様を判別できないケーブルが増えている昨今、ニーズが存在するのは間違いない。そろそろ本腰を入れてケーブルの整理をしなくては……と考えている方は、本稿を参考にしていただければ幸いだ。















![[Amazon限定ブランド]CCL い・ろ・は・すラベルレス 2LPET ×8本 ミネラルウォーター 無味 製品画像:2位](https://m.media-amazon.com/images/I/41h0MHfvhkL._SL160_.jpg)








![【中古】 富士通 LIFEBOOK AH AH54/D 大容量HDD搭載 Core i3 2310M Windows10 Home Wi-Fi 長期保証 [93932] 製品画像:15位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/risemark/cabinet/pic/939a/93932.jpg?_ex=128x128)








![新品 Inspiron 15 Ryzen 5 7530U・16GBメモリ・512GB SSD搭載モデル [カーボンブラック] 製品画像:6位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/pchome/cabinet/07387522/imgrc0099715364.jpg?_ex=128x128)



![【中古】LG電子 UltraGear 27GL650F-B [27インチ]【川崎駅前】保証期間1週間 製品画像:13位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/janpara/cabinet/itemimg_tempostar/shop236_39/236000772-236_1.jpg?_ex=128x128)




![黒/白2色 楽天1位!384冠!モニター 23.8インチ 27インチ 200Hz/180Hz/165Hz/100Hz ゲーミングモニター 1ms応答 pcモニター パソコン モニター 非光沢 VA チルト VESA Freesync スピーカー内蔵[1+1年保証] cocopar 製品画像:8位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/qifeng/cabinet/09826274/09826275/imgrc0105783334.jpg?_ex=128x128)



![I-O DATA|アイ・オー・データ ゲーミングモニター GigaCrysta ブラック KH-GDQ271UA [27型 /WQHD(2560×1440) /ワイド /275Hz] 製品画像:4位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/biccamera/cabinet/product/14386/00000014500746_a01.jpg?_ex=128x128)
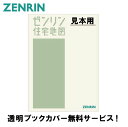
![影響力の武器[新版] 人を動かす七つの原理 [ ロバート・B・チャルディーニ ] 製品画像:29位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/4299/9784414304299_1_2.jpg?_ex=128x128)
![真の実力はギリギリまで隠していようと思う 9【電子書籍】[ 猫夜叉 ] 製品画像:28位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rakutenkobo-ebooks/cabinet/0549/2000019730549.jpg?_ex=128x128)
![【楽天ブックス限定特典】山中柔太朗カレンダー2026.4-2027.3(通常版)(オリジナルフォトカード(スマホサイズ)) [ 山中柔太朗 ] 製品画像:27位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/9298/2100014739298_1_3.jpg?_ex=128x128)

![【予約】[送料無料] 8bitゲーム ドラえもん&完全攻略ブック 40周年メモリアルBOX 製品画像:25位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/tc-books/cabinet/event01/imgrc0117078271.jpg?_ex=128x128)

![幼稚園 2026年 4月号 [雑誌] 製品画像:23位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/0468/4912010090468.gif?_ex=128x128)
![勝利の女神:NIKKE 公式設定資料集 [ ファミ通書籍編集部 ] 製品画像:22位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/7015/9784047337015_1_6.jpg?_ex=128x128)
![Harrison's Principles of Internal Medicine, Twenty-Second Edition (Vol.1 & Vol.2)【電子書籍】[ Joseph Loscalzo ] 製品画像:21位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rakutenkobo-ebooks/cabinet/6140/2000018326140.jpg?_ex=128x128)