福田昭のセミコン業界最前線
【インテル・トリニティの生涯】ゴードン・ムーア:インテルを最も長く愛し続けた男
2023年4月18日 06:21
インテルの創業と成長を支えた3名(トリニティ)
2023年3月24日(米国太平洋時間)、Intel(インテル)とGordon and Betty Moore Foundation(ゴードン・アンド・ベティ・ムーア財団)は共同で、インテルの共同創業者であるゴードン・ムーア(Gordon Moore)氏が94歳で他界したと発表した。ゴードン・アンド・ベティ・ムーア財団は、3月24日にムーア氏がハワイの自宅で家族に見守られながら、穏やかに息を引き取ったと発表文に付け加えた。
ゴードン・ムーア氏は、インテルの共同創業者として知られ、インテルの創業と成長を支えた3名の経営者、別名「インテル・トリニティ(Intel Trinity)」の1人として知られ、「ムーアの法則」の提唱者として知られる。
ちなみに「インテル・トリニティ」とはインテルの共同創業者であるロバート・ノイス(Robert Noyce)氏とゴードン・ムーア氏、それからインテルの社員第1号であるアンドリュー・グローブ(Andrew Grove)氏の3名を意味する(以降は一部を除き、人物名の敬称を略す)。シリコンバレーで長年にわたって新聞記者を勤めたマイケル・マローン(Michael Malone)氏の著作「The Intel Trinity: How Robert Noyce, Gordon Moore, and Andy Grove Built the World's Most Important Company(Harper Business、2014年7月発行)」により、米国では「インテル・トリニティ」の名称が広く知られるようになった(邦訳書籍は「インテル 世界で最も重要な会社の産業史」(文藝春秋、2015年発行)。
経営から退いた後も「ムーアの法則」でインテルの広報に貢献
「インテル・トリニティ」を構成する3名の中でノイスは1990年に62歳で急逝し、グローブは2016年に79歳で他界した。ムーアはトリニティの中では最も長く健康を維持し、1997年に経営の第一線から退いた後も、インテルの広報活動に大きく貢献した。
特に「ムーアの法則」の継続を旗印に掲げたインテルは、いくつかのイベントでムーアをたびたび活用した。たとえば2005年には「ムーアの法則40周年」を記念したいくつかのイベントに招かれた。10年後の2015年には「ムーアの法則50周年」を記念した複数イベントがあり、インテル公式ビデオ出演や「ニューヨークタイムズ」紙の著名ジャーナリスト(トム・フリードマン)によるインタビューなどをこなした。2018年にはインテル創立50周年の記念イベントでも「ムーアの法則」が担ぎ出された。
ただし2017年10月31日付けの本コラムで指摘したように、インテルが「ムーアの法則」を喧伝する過程で誤解の余地を生んでしまったことは否めない。経済性(低コスト化)よりも集積規模の拡大がいたずらに強調され、フェアチャイルドセミコンダクター(フェアチャイルド半導体)在籍時に発表した経験に基づく予測(経験則)であることは、ほとんど無視された。
ムーアが凄かったのは、1959年にフェアチャイルドセミコンダクター(フェアチャイルド半導体)でノイスがモノリシック集積回路を発明してから、わずか5年ほどでモノリシック集積回路の素子数拡大に関する経験則を見出したことだろう。特に「回路素子当たりの製造コストが最小になる集積規模(シリコンダイの素子数)が時間とともに指数関数的に増加しており、今後も続く」と指摘したことは彗眼の極みといえる。
米国ではなく、日本で初めて出版されたムーアの評伝
「インテル・トリニティ」を構成する3名の中で、ノイスの評伝とグローブの自伝および評伝は初めに米国で出版された。そのいくつかは、日本語に翻訳されて日本でも出版されている。著名企業インテルを代表する経営者なのだから、当然だろう。ところが筆者の知る限り、ムーアの評伝は米国ではなく、日本で初めて出版された。
それは日本経済新聞社の産業部記者を勤めていた玉置直司(たまき・ただし)氏が米国テキサス州ヒューストン支局に駐在していたときにムーアにインタビューした内容を基にした評伝「インテルとともに――ゴードン・ムーア 私の半導体人生――」(日本経済新聞社、1995年6月20日発行)である。インタビューの時期は1994年6月から12月まで。当時、ムーアはCEOをグローブに譲り、取締役会会長となっていた。
IBM PCのインテル製プロセッサ採用は大事件ではなかった
玉置記者(当時)の執筆によるムーアの評伝を読むと、興味深い記述がいくつかみられた。その中から3つのエピソードを以下に紹介しよう。なおページはすべて上記の初版本による。
最初は、メインフレームの最大手メーカーであるIBMが1970年代末にビジネス用PC事業を検討し、1981年8月に発売した最初の製品「IBM PC」にインテルの16bitマイクロプロセッサ「8088」を採用した件である(pp.96-100)。読者の多くがたぶんご存知であると思うが、インテルのマイクロプロセッサ事業が爆発的に成長して1990年代前半に世界最大の半導体メーカーになれたのは、IBMがPCにモトローラ製品(マイクロプロセッサ事業では当時最大の競合製品)ではなく、インテル製品を採用したことが大きく寄与した。IBM PCとその互換機(PC互換機)は、基本的にインテルのマイクロプロセッサを搭載した。
ところが当時は、マイクロプロセッサの大手ユーザーが1社増えた程度の認識だった。「私(ムーア)にしてもIBMのパソコンへのMPU搭載が決まった時は『ああ、大手の顧客がまた増えてよかった』という程度にしか考えなかった」(p.98)。インテルにとってIBMは、主力製品であるメインフレーム向けDRAMの最重要顧客であり、マイクロプロセッサはまだまだ主力製品ではなかった。IBMにしてもPCは新規事業であり、主力はあくまでメインフレーム事業だった。「パソコン革命なんて誰にとっても想像を超えた話だったのだ」(p.98)とムーアは述懐している。
製造子会社と前工程ラインの日本進出を諦めた理由
次は、インテルが日本に前工程ラインおよび製造子会社を設立することをかなり本気で検討していたことだ(pp.105~106)。1970年代~1980年代の日本市場はインテルにとって最重要海外市場の1つであり、創業3年目の1971年には、早くも日本に販売拠点を設立している。日本法人は1976年に設立された。販売とマーケティングの拠点は早くから日本に置かれた。製造拠点はどうだったのか。
「日本で半導体を製造したい時も何度かあった。15年前や20年前(筆者注:インタビュー時期(1994年後半)から1975年~1980年頃とみられる)には大変魅力的に思えたのだが、とうとうたどり着けなかった」(p.106)と延べ、最終的には断念した理由についても説明している。
「工場を初めて建設するときには管理職からエンジニア、一般の工員まですべて新規採用だ。外国企業が日本でこれをやるのは至難の業だ。新興の日本企業でも難しい……(中略)……大卒の優秀な人材はみな大企業か官庁に就職してしまうから、どうすれば優秀な人材を一度に大量に集めて工場をスタートできるかとうとうわからなかった」(p.106)。
テキサスインスツルメンツ(TI)が日本進出で選択した合弁会社方式(3年後に合弁相手の持ち株を買い取って100%子会社とする方式)は、当時のインテルのリソースでは困難だったという。
「日本で工場を買収することを考えたこともあったが、いろいろな事情でうまくいかなかった。今ではモノを作るにはコストがかかりすぎる国になってしまったから、もう工場を作ることはないだろう」(p.106)。
ゴードンは「ゴードンおじさん」という愛称でも知られるように、柔和で紳士的な振る舞いを崩さない。目立ちたがり屋のノイス、直情的なグローブとは対照を成す。フェアチャイルド半導体とTIがそれぞれ日本に製造子会社を設立しようとした1960年代に、日本の通商産業省(通産省)が彼らにどのような対応をしてきたか。フェアチャイルドは日本進出を断念してライセンス供与に切り換え、TIは3年におよぶ交渉を経て合弁方式の進出を1968年に果たした。ムーアがこれらの経緯を知らないはずがない。にもかかわらず、上記のような穏やかなコメントにとどめたところに、ムーアの人柄が窺える。
日本の半導体メーカーが引き起こした「人生最悪の思い出」
次は1985年のDRAM事業撤退に関するエピソードである。1970年代末に16Kbit DRAMの世代で、日本のDRAMメーカーは米国に技術開発で追いついた。次世代の64Kbit DRAMと次々世代の256Kbit DRAMの開発では、世界の先頭を走るようになった。この間、インテルは64Kbitと256KbitのDRAM開発で出遅れた。
それでもインテルには、紫外線消去型EPROM(UV-EPROM)があった。あまり知られていないことだが、創業から1980年代前半までインテルにとって最も利益率の高い製品はDRAMではなく、UV-EPROMだった。日本のDRAM攻勢を受けてインテルはDRAMの生産数量を減らした。ここまではインテルにとって不安はまだあまり大きくなかった。1983年はDRAM不足が続いたからだ。UV-EPROMは変わらず膨大な利益を生んでいた。
ところが1984年になるとDRAMが供給過剰になって値崩れを起こす。さらに日本のUV-EPROMメーカーが256Kbit品で価格競争を挑んできた。「84年の半ばから85年の初めのわずか9カ月間で(256Kbit UV-EPROMの)製品価格は30ドル強から3ドル弱にまで値下がりしてしまった」(p.113)。
そして運命の1985年が始まる。ムーアは「85年はインテルにとっても創業以来最悪の年になった。……(中略)……2万6000人いた従業員も、1万8000人以下に減らさざるを得なかった。全労働力の30%以上を解雇したことになる。8000人の解雇など、人生最悪の思い出だ」(p.113)と当時を振り返った。
試作品まで完成していた1Mbit CMOS DRAMチップ
前述のようにインテルは64Kbitと256KbitのDRAM開発で出遅れた。しかしDRAM市場が製品別では最大規模の市場に成長したことを受け、捲土重来を期して1Mbit CMOS DRAMを開発していた。「84年に市場が崩壊した頃に8個の社内サンプルが出来上がった。日本企業に十分対抗できると踏んでいた」(p.115)。
問題は量産投資の決断だった。インテルは創業以来「市場シェア20%以上」を規範としてきたようにみえる。市場で主導権を握るためには最低ラインのシェアであり、20%未満では参入している意味がないという考え方である。DRAM市場でも日本企業に対抗するためには、20%のシェアが必要だとムーアは考えた。20%のシェアを握るためには、2つの工場を建設しなければならない。「投資額は4億ドルだった。そこで私と社長のアンドリュー・グローブ氏は考え込んでしまった」(p.115)。
「パソコン(PC)はいよいよ普及期に入りつつあった。MPU事業の強化は待ったなしだった。こちらも巨額の投資は欠かせない」(p.115)。「DRAMは花形製品で、インテルは市場を開いたという自負もある。サンプルまでできている。難しい選択だった」(p.115)。
ムーア会長とグローブ社長は、「DRAM工場を着工するかどうか、最終的な話し合いをすることになった。グローブ社長は私に、「もし、あなたがインテルを経営するために外部からスカウトされてきた経営者だったとしたら、DRAMへの投資をするだろうか」と尋ねてきた。「いいやそうはしないだろう」。私はこう答えた。「私もそうだ」。グローブ氏もこう言い、インテルのDRAMからの撤退が決まった」(p.115~116)。
次回はロバート・ノイス氏を紹介
インテルがDRAM事業とEPROM事業から撤退し、マイクロプロセッサ事業に注力した結果は、ご存知の通りである。1992年には企業別の半導体売上高ランキングでトップとなり、昨年(2022年)までトップあるいは2位を堅持してきた。インテルの成功要因や経営戦略などに関しては数多くの書籍や文献などがあるので、ここではふれない。最後にムーア氏の年譜を掲載するとともに、改めて同氏の冥福を祈りたい。
そして「インテル・トリニティ」のシリーズでは次に、ロバート・ノイス氏の生涯について紹介する予定だ。ご期待されたい。

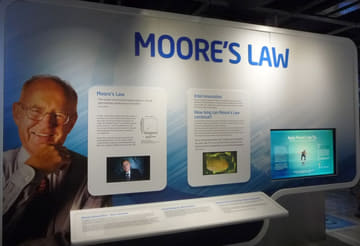








![[Amazon限定ブランド]CCL い・ろ・は・すラベルレス 2LPET ×8本 ミネラルウォーター 無味 製品画像:1位](https://m.media-amazon.com/images/I/41h0MHfvhkL._SL160_.jpg)


![【Amazon.co.jp限定】 伊藤園 磨かれて、澄みきった日本の水 2L 8本 ラベルレス [ ケース ] [ 水 ] [ 軟水 ] [ ペットボトル ] [ 箱買い ] [ ストック ] [ 水分補給 ] 製品画像:4位](https://m.media-amazon.com/images/I/41n0o65dSkL._SL160_.jpg)


































![[新品]ハイキュー!! (1-45巻 全巻) 全巻セット 製品画像:30位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/mangazenkan/cabinet/syncip_0020/ha-633_01.jpg?_ex=128x128)
![今日の治療薬2026 解説と便覧 [ 伊豆津宏二 ] 製品画像:29位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/3386/9784524273386_1_2.jpg?_ex=128x128)
![まいにちがたのしくなるおやくそく できるかな? [ ハ・ユジョン ] 製品画像:28位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/3577/9784478123577_1_2.jpg?_ex=128x128)

![はじめての世界名作えほん あかいえほんのおうち(1~40巻) (0) [ 中脇 初枝 ] 製品画像:26位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/8289/9784591918289_1_6.jpg?_ex=128x128)
![角川まんが学習シリーズ 世界の歴史 全20巻+別巻2冊定番セット [ 羽田 正 ] 製品画像:25位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/3703/9784041153703_1_16.jpg?_ex=128x128)
![COCO'S LOVE BOOK 2026年 2月号 [雑誌] 製品画像:24位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/0262/4912100300262_1_3.jpg?_ex=128x128)
![燻る骨の香り [ 千早 茜 ] 製品画像:23位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/noimage_01.gif?_ex=128x128)
![イヤーノート 2027 内科・外科編 [ 岡庭 豊 ] 製品画像:22位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/9681/9784896329681_1_4.jpg?_ex=128x128)
