山田祥平のRe:config.sys
USBケーブル、その長さと電力と帯域
2024年6月1日 06:11

かつてUSBケーブルが伝送できる主な要素はデータで、規格を遵守する限り、その給電能力は決して大きくはなかった。だが、USB Power Delivery(USB PD)規格の浸透によって近年はそれに電力が加わった。その結果、見かけは同じように見えるのに能力が異なるケーブルが登場して市場が混乱している。ここではパッケージから出したらそれでおしまいに近い状況をちょっと整理しておきたい。
EPRで100W超の大電力を扱うようになったUSB PD
両端がUSB Type-Cプラグを持つUSBケーブルに限定して話を進める。片側がUSB Type-Aのケーブルもあるが、それは話をさらにややこしくする。給電を担うUSB PDは両端USB Type-Cプラグのケーブルのための規格だ。
各種デバイスアクセサリー大手のベルキンが「Belkin Connect USB4 ケーブル、240W + 20Gbps」を発売した。100均の店頭でさえ、安心して使えそうなケーブルを容易に入手できるようになった今、1~2mのケーブルに4,000円近いコストをかけることにどれほどの意味があるのかと思うかもしれない。でも、この製品は相場が4,000~5,000円以上の240W対応USB4ケーブル市場において、3,800円程度を実現している。スペックをチェックすればなるほどとも思う。もちろんUSB-IFの公式認証を取得している。USB4は40Gbpsのデータ転送速度が理論値で、USB4 Ver.2.0で80Gbpsを実現しているが、このケーブルはそれを20Gbpsに抑えてコストダウンを実現しているようだ。
ケーブルの両端にeMarkerを実装し、電流や温度の状態をケーブルの両側でモニタリングすることで安全性を高めている。240Wという大電力に対応するケーブルなのだから、こうした実装があった方が安心して使える。過電流、過電圧、過熱などの異常を検知したら、すぐに電力供給を停止することができるという。接続されたデバイスが悪くなくても、ケーブルは保管状態や持ち運びなどによって劣化や損傷が生じていることもあり、それによる異常にも対応できるらしい。
USB PDは、スマホやノートPCなどで日常的に使われる電力を供給するための標準規格だ。安心安全に内蔵バッテリを充電するといったことをできるようにするため、USB-IFが定めたさまざまな仕様を遵守しなければUSB PD認証が通らない。
仕様によって決まる1つの要素が供給できる電力の上限だ。USB PD規格の現状では最大240Wまでの電力に対応している。ケーブルは対応する電力によって60W未満、60~100W未満、100W~240Wの対応に分かれている。100W超についてはEPR(Extended Power Range)として拡張されたUSB PDだ。規格上、240Wは最大48V×5Aと規定されている。
ケーブルの対応電力は3種類あるわけだが、それはケーブル自身が主張する。具体的には電力供給の前にプラグ部分に実装されたeMarkerチップに書き込まれた値が読み取られて、それを超える電力は伝送されないようになっている。ケーブルが何も主張しなければ60W未満にしか対応していないとみなされる。また、片側がUSB Type-Aプラグの場合はケーブルに56KΩの抵抗を実装するように規定し、それを検出すると、USB PDでの大きな電力での給電は行なわれない。
時はカネなり、スピード出すにはコストがかかる
ケーブルの能力を示すもう1つの要素はデータ伝送時の帯域幅だ。ケーブルは電力も運べばデータも運ぶ。廉価で入手できる多くのケーブルはUSB 2.0の60W未満の対応だ。ガジェットデバイスに同梱されているような両端USB Type-Cのケーブルはたいていそうだ。
USB 2.0は四半世紀前から使われている規格だが、その帯域幅は理論値で480Mbpsだ。圧縮技術でなんとかなっているBluetoothのデータレートが数Mbpsだということを考えれば480Mbpsはかなり大きいように感じる。だが、4K@60Hzの非圧縮画面出力を伝送してモニターに映し出すにしても1.5Gbps程度は必要だ。これは理論値480Mbpsの約3倍に相当する。
規格上、USB Type-Cケーブルを使った映像伝送にはUSB 3.0以降の対応が必要だ。USB 2.0は半二重の規格なので双方向通信のためには容量不足だという判断なのだろう。だから、USB 2.0ケーブルでは逆立ちしても映像出力はできないと考えておこう。
USB4の20Gbpsに対応したベルキンの新ケーブルは、USB4 Ver.2.0の80Gbpsには及ばなくても、これだけあれば日常の利用に困ることはまずなさそうだ。
もっともポータブルSSDなどを接続してのデータ伝送といったことをやりだすと20Gbps程度の帯域はアッというまにパンクする。20Gbpsではなく2.5GB/sと考えればそれなりのスピードでしかないと分かる。この値では最新のSSDの足かせになってしまうだろう。
スピードが必要な場合は迷わずThunderbolt 4ケーブルを選ぶべきだし、つなぐ相手もThunderbolt 4対応でなければならない。ベルキンもConnect Thunderblot 4 ケーブルを提供している。同じ2mで、今回の新製品と比べても倍近い価格の違いがあるが帯域幅も倍の40Gbpsとなる。まさに時はカネなりだ。
その長さと電力と帯域でケーブルを選ぶ
ケーブルの能力として目に見える要素には、その長さがある。よく見かけるケーブルの長さとしては50cm、80cm、1m、2mといったところだろうか。少なくとも両端がUSB Type-Cプラグのケーブルは規格上4mが最大伝送距離となっている。アクティブケーブルなどの特殊なものを使えば延長はできるが、話がややこしくなるのでここでは深く言及しないでおく。
PCと周辺機器を接続するときに、ざっくり1mでは足りないことは少なくない。たとえばモバイルモニター1つとってもサイズが大きなものだと1mのケーブルではレイアウトに支障が出るケースもある。その点、このケーブルは2mあるので自由度は高い。少なくとも2mを超えるケーブルは規格上USB 2.0までの対応だ。そこをガマンできれば長いケーブルが手に入るが、それでも4mまでだ。
結局のところ、あまりにも規格が複雑で、接続時に何かのトラブルに遭遇したときに、いったい何が悪いのかがよく分からないという状況になることが少なくない。そんなときに、信頼できるブランドのオールマイティなスペックの製品が手元にあれば安心だ。
規格ではUSB 2.0の両端USB Type-Cケーブル以外は、ベストエフォートでThunderbolt 3ケーブルとして機能してしまうし、対応スピードが分からないeMarkerのないケーブルでも、Gen1以上のケーブルならGen2として10Gbps対応とみなされる。そのくらい柔軟(やっかい?)な規格なので、トラブルが起きたときに何が悪いのかさっぱり検討がつかないようなことが起こる。トラブルの原因追求は時間の無駄でもある。だからこそ、リファレンスとなるパーツを手元においておくと心強い。
Thunderbolt 4対応の2mケーブルはオールマイティだが、かつEPR240W対応のものとなるとまだ少ない。ベルキンのラインアップでも100Wまでの対応製品しか見当たらないし、2mの製品はアクティブケーブルだ。今は、ゲーミングPCなどで100W超の電力供給を要求するPCを見かけるようになっているし、今後のオンデバイスAI処理のデマンドによって、一般的なビジネスPCでも100W超対応が求められるようになる可能性もある。
そういう意味では、今回のベルキンの新ケーブル「Belkin Connect USB4 ケーブル、240W + 20Gbps」は、ブランドとしても申し分なく、持っててよかったをもたらすオールマイティな製品といえそうだ。










![[Amazon限定ブランド]CCL い・ろ・は・すラベルレス 2LPET ×8本 ミネラルウォーター 無味 製品画像:1位](https://m.media-amazon.com/images/I/41h0MHfvhkL._SL160_.jpg)



![【Amazon.co.jp限定】 伊藤園 磨かれて、澄みきった日本の水 2L 8本 ラベルレス [ ケース ] [ 水 ] [ 軟水 ] [ ペットボトル ] [ 箱買い ] [ ストック ] [ 水分補給 ] 製品画像:5位](https://m.media-amazon.com/images/I/41n0o65dSkL._SL160_.jpg)







![【中古】 NEC VersaPro PC-VK23TGVGU SSD搭載 Core i5 6200U Windows11 Home Wi-Fi 長期保証 [94838] 製品画像:20位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/risemark/cabinet/pic/948a/94838.jpg?_ex=128x128)




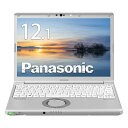



![DELL OptiPlex 7090 SFF (Win11x64) 中古 Core i7-2.5GHz(11700)/メモリ16GB/HDD1TB/DVDマルチ [C:並品] 製品画像:3位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/usedpc/cabinet/url1/5726315c.jpg?_ex=128x128)





![【❤最安挑戦❤+LINEクーポン】新発売 [1+1年保証] モニター 100Hz 21.5インチ 23.8インチ 27インチ pcモニター 1ms応答 パソコン モニター 1920*1080 FHD ゲーミングモニター 非光沢 VA 角度調整 VESA Freesync pc/switch/ps4/ps5/xbox スピーカー内蔵 製品画像:13位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/qifeng/cabinet/10653721/10653722/imgrc0112340482.jpg?_ex=128x128)






![【楽天ブックス限定抽選特典】【クレジットカード決済限定】CANDY TUNE 3rd Anniversary写真集(仮)(オンラインラッキードロー抽選権) [ CANDY TUNE ] 製品画像:30位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/2708/2100014832708_1_2.jpg?_ex=128x128)
![臨床医のためのライフハック 「診療・研究・教育」がガラッと変わる時間術 [ 中島 啓 ] 製品画像:29位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/2435/9784260062435.jpg?_ex=128x128)


![【楽天ブックス限定特典】乃木坂46川崎桜 1st写真集『エチュード』(限定カバー) [ 川崎桜 ] 製品画像:26位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/1009/2100014821009_1_3.jpg?_ex=128x128)
![きのう何食べた?(25)【電子書籍】[ よしながふみ ] 製品画像:25位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rakutenkobo-ebooks/cabinet/0973/2000019710973.jpg?_ex=128x128)
![太郎 DON’T ESCAPE!【特典ペーパー付】【電子書籍】[ mememe ] 製品画像:24位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rakutenkobo-ebooks/cabinet/2467/2000019272467.jpg?_ex=128x128)
![古語大鑑 第3巻 し~て [ 築島 裕 ] 製品画像:23位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/0075/9784130800075_1_11.jpg?_ex=128x128)
![青天 [ 若林 正恭 ] 製品画像:22位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/0665/9784163920665_1_10.jpg?_ex=128x128)
![書簡型小説「二人称」 ヨルシカ [ n-buna ] 製品画像:21位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/6341/9784065416341_1_3.jpg?_ex=128x128)