トピック
たった3年?いや、されど3年だ。最新ゲーミングノートはここまで進化している!
~日本エイサー「Predator Helios Neo 16」で旧世代からの進化っぷりを体感
- 提供:
- 日本エイサー株式会社
2024年5月20日 06:30
場所を取らずにPCゲームを楽しめるゲーミングノートが人気だ。最近のものはデスクトップPC級の性能を備えており、ノート型だからゲームを存分に楽しめない、なんてことがなくなったのが理由として大きい。
そして最新のゲーミングノートなら、重量級ゲームも余裕で楽しめるのはもちろん、競技性の高いタイトルにも対応可能なディスプレイ性能も備えていて死角なし。さらに、ビジネス向けノートPCのように、Web会議も快適にこなせるWebカメラとマイク、クリエイティブな作業やAI処理にも対応できる高い基本スペックも持っている。ゲームに限らず、PCならではの汎用性を高めているのが大きな特徴だ。
で、その今時のゲーミングノートが実際にどんなゲームをどれだけ快適に遊べるのか? ここでは旧世代のハイエンドモデルと比較しつつ、その進化の具合を見せていきたい。
実は最新世代のゲーミングノートは単純な性能だけでなく、筐体の薄型化など、外見の洗練も進んでおり、野暮ったさがなくなっているのも見逃せないところ。これまでゲーミングノートの導入に、いろいろな理由でためらいを感じていた人も、改めて最新のゲーミングノートってやつをしっかり見てほしい。
今回はCore i7-14700HXとGeForce RTX 4070 Laptop GPUを組み合わせた、日本エイサーの最新モデル「Predator Helios Neo 16」(型番: PHN16-72-N76Y47)を用意した。高性能パーツを載せていながらも、実売価格は22万円台半ば程度とお買い得感が高い。約3年前のゲーミングノート(Core i7-11800HとGeForce RTX 3070 Laptop GPU搭載)からどの程度進化しているのか検証していこう。
(1) 実はCPU性能も求められる最新ゲーム
(2) 軽量級から超重量級までゲーム性能を検証
(3) 画像生成などのAI性能を測定
(4) 大画面高機能なPredator Helios Neo 16
(5) 優秀なクーリングシステムで静音性も確保
実はCPU性能も求められる最新ゲーム
ゲームプレイにおいて一番重要になるのはGPUだが、最近の重量級ゲームではCPUパワーも求められるようになっている。そのため、CPUの性能もおろそかにできないのだ。
Predator Helios Neo 16に搭載されているCPUはIntelの第14世代「Core i7-14700HX」だ。パフォーマンス重視のPコアを8基、効率重視のEコアを12基と、異なるコアを組み合わせたハイブリッド・アーキテクチャを採用するCPUで、合計20コア28スレッドに達するメニーコア仕様だ。
Pコアは最大5.5GHzとクロックも高く、マルチコア性能、シングルコア性能どちらを求めるアプリにも強い。ちなみに、CPUの末尾に「HX」と付いているのは、Intelのノート向けではパフォーマンス重視の上位モデルである証拠。この時点で高い性能を持っていることは確定である。
比較用ゲーミングノートのNitro 5に搭載されているのは第11世代Coreの「Core i7-11800H」だ。8コア16スレッドで最大4.6GHzとノートPC向けとしては十分ハイスペック。末尾が「H」と付いているのは、HXほどではないがゲーミング向けのパフォーマンス重視モデルとなっている。
| Predator Helios Neo 16 | Nitro 5 | |
|---|---|---|
| CPU | Core i7-14700HX(20コア、28スレッド) | Core i7-11800H(8コア、16スレッド) |
| GPU | GeForce RTX 4070 Laptop GPU(GDDR6 8GB) | GeForce RTX 3070 Laptop GPU(GDDR6 8GB) |
| メモリ | DDR5-5600 16GB(8GB×2) | DDR4-3200 16GB(8GB×2) |
| OS | Windows 11 Home | |
最初に実行するベンチマークは、CPUパワーを測る「Cinebench 2024」だ。Predator Helios Neo 16には、動作モードとして「ターボ」、「パフォーマンス」、「バランス」、「静か」の4種類が用意されており、Cinebench 2024ではそれぞれのスコアを測定している。モードによって性能がどう変わるのかにも注目したい。
Cinebench 2024の結果を見ると、順当に「ターボモード」がもっとも高いスコアになった。Nitro 5に対して約2.3倍のスコアが出ており、20コア28スレッドの強さを存分に発揮した形だ。最新世代のアーキテクチャに加えて動作クロックが高いこともあって、シングルコアの性能も約1.4倍となっている。モード別に見ると「静か」にするとマルチ、シングルともガクッとスコアが落ちる。性能を抑えて静音性を重視するためだろう。
では、モード別で動作音はどう変わるのか。Predator Helios Neo 16の正面10cmの位置に騒音計を設置して、Cinebench 2024実行時の動作音を測定した。
「ターボ」だとそれなりに動作音が気になるレベルになる。CPUパワーを引き出すため仕方のないところだが、ヘッドフォンをしてゲームをするなら何ら問題ない。一方で、「静か」ではほとんどファンの音が気にならないレベルまで動作音は小さくなる。CPU性能は下がるが、家族が寝ている深夜やカフェなど静かに使いたい場面では役立つモードだ。
ちなみに、「バランス」は「ターボ」に対しては1割程度スコアは落ちるが、動作音はかなり減少する。性能も出しつつ動作音も抑えたい人にはピッタリ。まさにバランスのよいモードとなっている。
続いて、PCの基本性能を測定する「PCMark 10」と実際にAdobeの「Photoshop」と「Lightroom Classic」でさまざまな画像処理を実行する「Procyon Photo Editing Benchmark」を実行しよう。
PCMarkはどの項目も旧世代に対してしっかりスコアを伸ばしているが、クリエイティブ系の処理を行なうDigital Content Creationでは、約1.58倍もスコアアップと負荷の高い処理で大きな差を見せた。
Photo Editing Benchmarkも同様だ。特にLightroom Classicでの処理となるBatchProcessingでは、CPUパワーが影響しやすいこともあって差が大きく出ている。
軽量級から超重量級までゲーム性能を検証
実ゲームを使って今時のゲーミングノートの性能も調べていこう。
Predator Helios Neo 16のGPUはNVIDIA最新世代の「GeForce RTX 4070 Laptop GPU」。CUDAコア数は4,608基、メモリはGDDR6が8GB、メモリバス幅は128bitでノートPCの設計に合わせてブーストクロックは1,230から2,175MHz、カード電力は35~115Wで設定される。
Predator Helios Neo 16は、ブーストクロックが最大2,080MHz、グラフィックス電力はデフォルト80W、最大140Wとかなり高めの設定。GeForce RTX 4070 Laptop GPUの性能を十分引き出せる仕様と言ってよいだろう。
GeForce RTX 40シリーズは、ゲーム側の対応が必要となるものの、描画負荷を軽減するアップスケーラーとAIによるフレーム生成を組み合わせてフレームレートを大幅に向上させる「DLSS 3」に対応する。さらに、高圧縮&高画質の動画コーデック「AV1」へのハードウェアエンコードも利用可能と機能面で充実しているのも特徴だ。
比較用のNitro 5に搭載されているGPUは1世代前の「GeForce RTX 3070 Laptop GPU」。CUDAコア数は5,120基、メモリはGDDR6が8GB、メモリバス幅は256bitだ。スペックだけみるとGeForce RTX 4070 Laptop GPUを上回っているように見えるが、DLSS 3に対応できないなど機能面で世代の古さがある。アーキテクチャもRTX 40シリーズとは異なるので、そこあたりも含めて性能の違いに注目したい。
テストを実行するにあたり、比較用のNitro 5が画面比率16:9のフルHD(1,920×1,080ドット)なのでそれを基準にするが、Predator Helios Neo 16は画面比率が16:10のWQXGA(2,560×1,600ドット)を採用している。
当然ながらゲームをプレイするなら16:10比率の解像度にしたほうが見やすい。そのためフルHDに加えて16:10のWUXGA(1,920×1,200ドット)の結果も加えた。フルHDとWUXGA、わずか120ドットの差がフレームレートにどう影響するのかもチェックしてほしい。
Apex Legends/エルデンリング
まずは、DLSSなどアップスケーラーに対応しないタイトルとして定番FPSの「Apex Legends」と2024年6月21日にDLCの発売を控え、人気が再燃している「エルデンリング」を検証する。
Apex Legendsは、フルHDで平均258.5fps、WUXGAで平均248.2fpsと最高画質でも高いフレームレートを出した。Predator Helios Neo 16は240Hzの高リフレッシュレート液晶を採用しているが、それを生かし切れるだけのフレームレートになっている。アップスケーラーやフレーム生成を使わない“素”の性能でも、GeForce RTX 4070 Laptop GPUは十分高性能と言ってよいだろう。
エルデンリングは最大60fpsのゲームだ。そこに近ければ快適と言える。レイトレーシングを有効化するとかなり描画負荷は高くなるが、Predator Helios Neo 16ならフルHDでもWUXGAでも平均57fps台と十分スムーズなプレイが可能。DLCに対する備えもバッチリだ。
ドラゴンズドグマ2
続いて、DLSSに対応する重量級のゲームとして「ドラゴンズドグマ2」を試そう。
ドラゴンズドグマ2は、現状アップスケーラーだけのDLSS 2までの対応。それでもNitro 5よりも約1.7倍のフレームレートを達成。平均74fps台と快適なプレイの目安と言える平均60fspを大きく超えた。将来的にはフレーム生成が可能なDLSS 3に対応予定となっており、そうなればフレームレートの差はもっと大きくなるだろう。
ディアブロ4/サイバーパンク2077
次は、DLSS 3対応のゲームとして2024年3月26日のアップデートでレイトレーシング対応となった「ディアブロ4」と重量級のゲームの代表格「サイバーパンク2077」を用意した。
アップスケーラーとフレーム生成を組み合わせたDLSS 3の威力は大きい。DLSS 2までの対応でフレーム生成を利用できないGeForce RTX 3070 Laptop GPUを備えるNitro 5との差は非常に大きくなる。レイトレーシングをバリバリに効かせた状態では、Nitro 5だとどちらのゲームも平均60fpsに届かない。
その一方でPredator Helios Neo 16は、どちらも平均120fps以上を達成。レイトレーシングの美しさをなめらかな描画で楽しめる。たった1世代でも、GPUの性能と機能差が大きいことが分かる結果だ。
画像生成などのAI性能を測定
ここからは、AI処理も比較してみよう。さまざまな推論エンジンを使ってAI処理性能を測定する「Procyon AI Computer Vision Benchmark」、Stable Diffusionを使った画像生成速度を測定する「Procyon AI Image Generation Benchmark」、動画を高解像度化できる「Topaz Video AI Benchmark」を試した。
Procyon AI Computer Vision BenchmarkのWindows MLはCPUを使ってAI処理を実行している。コア数の差が大きく、Predator Helios Neo 16のほうが約1.9倍もスコアが高くなった。
そのほかの処理はGPUがメインとなる。概ね同じ傾向で、Nitro 5よりも1.3倍ほどスコアが高い。AI処理でもGPUの世代差が出ているのが分かる。
大画面高機能なPredator Helios Neo 16
旧世代との性能差が見えたところで、Predator Helios Neo 16本体の特徴について紹介していこう。ディスプレイは16型で解像度はWQXGA(2,560×1,600ドット)。ゲーミングノートに多い15.6型とそれほど変わらないように思えるが、縦方向に少し大きいだけでかなり画面が見やすくなる。没入感がかなり高く、正直筆者が今回の試用で一番関心した部分だったりする。16型は思ったよりずっといいなと。
リフレッシュレートは240Hと非常に高く、遠くにいる敵のわずかな動きやすばやい画面の動きも把握しやすい。さらに、ノートPCでは珍しく画面のブレやちらつきを防ぐ可変リフレッシュレートのG-SYNCにも対応しており、競技性の高いゲームプレイにも十分対応が可能だ。
高い色の表現力が求められるデジタルシネマ向け「DCPI-P3」規格のカバー率100%と広色域なのもポイント。ゲームはもちろん、動画も鮮やかな画面で楽しめる。
このほかにも、配信やビジネスシーンで役立つWebカメラとノイズキャンセリング対応のマイク機能などを搭載している。
16型ノートサイズということもあり、インターフェイスは充実。背面にまでポート類が用意されているので拡張性はばっちり。ケーブルの取り回しもやりやすい。
キーボードはテンキー付きの日本語配列。独自ユーティリティの「PredatorSense」でLEDの配色を任意に設定可能だ。
優秀なクーリングシステムで静音性も確保
最後の冷却力について試してみよう。
Predator Helios Neo 16は、89枚(0.08mm)の極薄ブレードと、フクロウの羽から着想を得たという第5世代AeroBlade 3Dファン、熱を伝える接触面の広いベクターヒートパイプ、熱伝導率の非常に高い液体金属熱グリスなど複合的に熱対策を行なっている。それによって、動作モードを「バランス」や「静か」にしたときかなりの静音性を確保できているのは前述した通りだ。
ここでは、動作モードを「ターボ」、ファン制御を「自動」にし、サイバーパンク2077を10分間プレイしたときのCPUとGPUの動作クロックと温度の推移をHWiNFO Proで測定している。
CPUクロックは、1分半まではPコアが4.5GHz、Eコアが3.5GHz前後、その後はPコアが3.5GHz前後、Eコアが3GHz前後で推移となった。温度の推移を見れば分かるが、CPU温度が高くなったのでクロックを少し落としたということだろう。
その一方で、ゲームプレイで重要なGPUクロックは2,500MHz前後、温度は75℃前後でずっと安定。CPUクロックの調整で温度を下げ、GPUクロックを維持しようという動作はゲーミングノートとしてはうまい挙動と言える。冷却システムもそのコントロールも優秀と言ってよい。
どうだっただろうか、Predator Helios Neo 16は、大きめの16型画面で240Hzの高リフレッシュレート、それを生かせる高い基本スペックを持ち、重量級ゲームもeスポーツ系のゲームも存分に楽しめることが分かったはずだ。
これに加えて、色の表現力が高いので動画コンテンツの視聴にも向いており、AIを活用したWebカメラやマイクによってWeb会議も快適にこなせると仕事や学業にも活用できる。
CPU性能も高く、まさに全方位で使えるノートPCに仕上がっており、これだけのスペックで22万円台とコストパフォーマンスも良好。幅広いユーザーにおすすめできる1台だ。












![[Amazon限定ブランド]CCL い・ろ・は・すラベルレス 2LPET ×8本 ミネラルウォーター 無味 製品画像:2位](https://m.media-amazon.com/images/I/41h0MHfvhkL._SL160_.jpg)







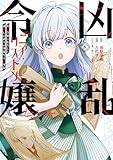






























![角川まんが学習シリーズ 日本の歴史 全16巻+別巻5冊定番セット [ 山本 博文 ] 製品画像:30位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/3697/9784041153697_1_28.jpg?_ex=128x128)
![スキル外来手術アトラス すべての外科系医師に必要な美しく治すための基本手技 [ 市田正成 ] 製品画像:29位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/8306/83062616.jpg?_ex=128x128)

![不夜脳 脳がほしがる本当の休息 [ 東島威史 ] 製品画像:27位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/2481/9784763142481_1_3.jpg?_ex=128x128)

![SPY×FAMILY 17 (ジャンプコミックス) [ 遠藤 達哉 ] 製品画像:25位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/0092/9784088850092_1_7.jpg?_ex=128x128)
![タッチペンでまなべる!はじめてのひらがなずかん 英語つき [ 小学館はじめてずかんチーム ] 製品画像:24位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/5548/9784099425548_1_12.jpg?_ex=128x128)
![きのう何食べた?(25)【電子書籍】[ よしながふみ ] 製品画像:23位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rakutenkobo-ebooks/cabinet/0973/2000019710973.jpg?_ex=128x128)
![咲良は上手に説明したい! [ 滝沢 志郎 ] 製品画像:22位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/0626/9784569860626_1_4.jpg?_ex=128x128)
![JTB時刻表 2026年 3月号 [雑誌] 製品画像:21位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/0364/4912051250364_1_2.jpg?_ex=128x128)