大河原克行の「パソコン業界、東奔西走」
レバノンでのトランシーバー爆発事件から半年。アイコムが風評被害を受けなかった理由とは?
2025年4月7日 06:17
2024年9月18日(現地時間)、レバノンで日本メーカー製の無線機(トランシーバー)が一斉に爆発するという事件が起きた。製造元とされたのは日本の無線機器メーカーであるアイコム。爆発した無線機には同社のロゴが残っており、その無線機に爆薬が仕掛けられていたのである。
だが、爆発した機種はすでに約10年前に生産を終了。その模造品が今でも世界中に出回っており、爆発した無線機は同社で製造した正規品ではないことが判明した。
アイコムでは、爆発した現物を直接確認できないなど、情報が少ない中でも迅速に公式情報を発信したことで、情報が短時間に正確に伝わり、結果として風評被害を受けることなく事業を継続することができた。そして、このときアイコムを支えたのが、アイコム製品を長年利用してきたアマチュア無線愛好家たちだったという。
事件から約半年を経過し、アイコムの中岡洋詞社長に改めて当時の様子を振り返ってもらった。これは、事件発生時の迅速な情報発信の重要性を示した成功事例の1つとも言える。
無線機が武器に使われた!
この事件は、イスラム教シーア派組織ヒズボラの戦闘員が使用していたトランシーバーが、レバノン国内で一斉に爆発し、死者を含む多くの負傷者が出たというものだ。
トランシーバーが爆発した2024年9月18日の前日にも、ポケットベルが一斉に爆発。ここでも多くの死者や負傷者が出ており、2つの爆発での死者は合計で40人以上、負傷者は3,400人以上と言われている。イスラエルは、当初は事件への関与を否定していたものの、のちに同国のベンヤミン・ネタヤナフ首相が軍事作戦として遂行したものであるとの関与を認めている。
爆発したトランシーバーとして特定されたのが、日本の通信機器メーカーであるアイコムの「IC-V82」という機種であった。
アイコムは大阪に本社を持つ企業で、1954年にアマチュア無線機メーカーとして創業。現在でもこの分野ではトップシェアを誇る。日本では1970年代にハム(アマチュア無線)ブームが到来し、その波に乗って業績を拡大。さらに、1980年に発売した小型アマチュア無線機がヒットし、同社の知名度が世界中に広がった。
現在でも、無線機本体だけで約200種類の製品をラインナップしており、陸上用、海上用、航空用と、多岐に渡る製品を展開。無線通信に欠かせない周波数帯であるRF(高周波)の電波を操る技術力の卓越ぶりには高い評価が集まっている。生産は、すべて日本の生産子会社である和歌山アイコム(和歌山県有田川町)で行なっている。
主力製品であるトランシーバーは、世界100カ国以上に展開。ここ数年は、無線LANアクセスポイントやワイヤレスIPカメラなどのネットワーク機器の品揃えも強化している。
ユーザーの声をもとにしたモノづくりに定評があり、船舶用無線機では、ユーザーニーズを捉えて、世界で初めて完全防水を実現。だが、ユーザーからは「水の中に沈んでしまったら見つけられない」という声に対応し、水に浮く無線機を開発。さらに、「水面でもっと見つけやすくしてほしい」との声に応えて、操作部が上方向で浮く無線機を開発し、着水したときには光が点灯し、見つけやすくするといった工夫などを行なっている。この事例からも分かるように、ユーザーとの距離が近いのもアイコムの特徴だ。
また、電話とトランシーバー通話が可能な製品を投入。日本政府のGIGAスクール構想によって整備された小中学校の無線LAN環境を活用することで、教員間の内線電話での利用だけでなく、学校内に不審者が侵入した場合にも教員間に一斉同報が可能であることが評価され、教育分野を対象に想定を大きく上回る売れ行きを見せたというエピソードもある。
情報を迅速に社内共有し、実行に移したアイコム
レバノンでのトランシーバー爆発の情報が、日本のアイコム本社に寄せられたのは、日本時間の9月19日午前2時ぐらいのことだったという。中岡社長を始めとして、幹部社員がやり取りしているSNSに通知があったそうだ。このとき、中岡社長は「普段は寝ている時間だが、たまたま目が覚めて」すぐに事件を把握。だが、想定外の出来事に文面を何度も読み返したそうだ。
中岡社長は、SNSを通じて早朝から会議を行なう指示を役員に出すとともに、緊急連絡網を活用して、総務部や広報部など関係部署の担当者にも召集をかけた。アイコムでは、災害時などにおける緊急対応体制を構築している。無線機は災害時の現場支援には不可欠なツールであり、これはメーカーとして、顧客からの問い合わせに迅速に対応するための仕組みでもあった。今回の社内連絡にもこの仕組みを活用した。
トランシーバーの爆発が起きたのが現地時間の9月18日午後5時頃と見られており、日本時間では9月18日午後11時となる。初期情報が迅速に本社側にもたらされていることが分かる。
同社が最初に情報を入手したのは、欧州の現地法人であるアイコムヨーロッパ(ドイツ)に、現地メディアから入った問い合わせであった。
「アイコムの社名が記載された無線機が爆発した。その機種はIC-V82ではないか」という問い合わせが入ったのだ。担当者は問い合わせに対して、10年前に製造を中止したものであり、バッテリの生産も終売していることから、「おそらく模造品であり、当社の製品ではない」と、まずは回答したという。
日本では、午前6時過ぎから幹部社員が本社に集まりだし、午前7時過ぎから対策会議がスタートした。
アイコムの中岡社長は、「アイコムの無線機が爆発することはない。そんなことが起こるはずがない。爆発した無線機が模造品であることは最初から強く信じていた」と確信していたものの、「憶測で情報を発信することは危険である。まずは分かっていることだけを発信することに決めた」という。危機管理チームを社内に立ち上げ、情報収集に努めるととともに、ここでの判断をもとに、社内外に向けた発信を行なうことにした。
この時間になると、日本のメディアからも連絡が入り始めた。前日まで海外出張で、この日は有給休暇を取る予定だった広報担当者も急遽出社し、メディア対応にあたることになった。
事件当日午前10時に第1報を公開
同社では、19日午前10時の段階で、「一部報道の件について」と題した情報を同社サイトに掲載。「本日未明、レバノンで当社ロゴの入ったシールが貼付された無線機が爆発したとの報道がありました。この事案については、ただ今事実関係について調査を進めております。判明した事実は、ホームページで順次お伝えいたします」と説明した。
この段階で、アイコム自らが事件を把握しており、それに向けて調査を開始している姿勢を明確にしたほか、この文言がアイコム社員にとっても、取引先や顧客からの問い合わせがあった場合の共通メッセージとして活用できるものになった。また、日本語とともに英語でも同時刻に発信を行なっており、全世界に向けた同時メッセージとしている。
「問い合わせを受けた社員が、それぞれに異なることを話すと、憶測が広がり、混乱を招くことになる。世界中のどこに問い合わせても、統一見解となることを徹底した。また、外部からの問い合わせがあった際には、最新の情報を随時、ホームページに掲載する予定であり、それを見てもらうように促すことを、イントラネットとメールを使って社員に通達した」という。社員への通達は、第1報を公開した午前10時よりも前に行なった。
また、取引がある国内外の販売店に対しては、19日午前の段階で、「サーキュラーレター」を配信。ここでも新たに分かったことがあった場合には、ホームページに掲載することを告知した。あらゆる方面に向けて、確実に言えることを、迅速に発信することを徹底したことが分かる。
爆発した無線機は生産中止から10年を経過
アイコムが第2報を配信したのは、19日正午であった。ここでは3つの点について発信した。
1つ目は、報道の対象となったトランシーバーの概要についてである。爆発したと報道された機種は「IC-V82」であり、アイコムが2004年から2014年10月にかけて、中東を含む海外向けに生産・出荷していたハンディ型無線機であることを示しながらも、約10年前に終売しており、それ以降はアイコム本社からの出荷が行なわれていない事実も示した。
また、本体を動作させるためのバッテリの生産も終了し、これも終売となっていることも示した。さらに、報道された写真などをもとに分析したところ、アイコムが偽造品防止のための貼付しているホログラムシールがなく、「当社から出荷した製品かどうかは確認できない」とも報告した。
事案が戦争の中で起きたものであり、爆発したトランシーバーを直接確認することができないため、この時点ではまだ模造品であることを特定することができなかったという。
2つ目は、製品の流通に関する同社の仕組みについてだ。アイコムは海外向け製品については、同社正規販売代理店でのみ販売を行なっているとともに、経済産業省が定める安全保障貿易管理の規定に基づく輸出プログラムである「アイコム安全保障貿易管理プログラム」を策定し、それに則って出荷。厳格な輸出管理を行なっていることを強調した。
3つ目は製造についてである。アイコムの無線機は、すべて和歌山県の生産子会社である和歌山アイコムで生産。ISO9001/14001/27001に基づく厳格な管理体制を敷いており、規定の部品以外を使用することがないことを明言。同社が販売している年間100万台の製品はすべて日本で生産しており、海外での生産は一切行なっていないことも示した。
同社によると、出荷前検査ではすべての製品で重量を確認。わずか数グラムでも異常を検知できることから、異物が混入しているものや、部品が足りないなど、仕様に準拠していない不正な製品は出荷できない仕組みとなっているそうだ。「ボールペン1本の重さでも検知する」というレベルだ。つまり、和歌山アイコムで生産している正規品には爆発物のようなものは混入できない。
実は、レバノンの爆発事件で使われたトランシーバーを解析するために、アイコムではレバノン当局に対して、回収したいとの旨を伝えている。だが、それは聞き入れてもらえず、結果として現時点でも公開されている写真などから模造品の状況を推察するしかないという。
第3報で模造品であることを特定
さらに、アイコムでは、9月20日午後6時過ぎに、第3報を配信した。
ここでは、レバノンの現地メディアが、18日午後7時頃(現地時間)、レバノン通信大臣のJohnny Corm氏のインタビュー内容を報道。その中で同大臣は、レバノン当局では爆発した無線機がアイコムが生産した正規品ではないことを認める発言をしており、この内容をもとに無線機の概要について説明した。
第3報では、同大臣の発言を用いて、通常は総合安全保障局と情報局の承認を得てから輸入を許可するが、爆発した無線機は同国通信省を経由したものではないこと、正規代理店を通じて輸入されたものでもないことに加えて、アイコムが生産を終了している機種であること、他国から同型番の無線機の模造品が持ち込まれている事実を当局が把握していたことを示した。さらに、「電話やその他の機器が爆発する不安が広がっているが、公式に輸入されている製品にその危険性はない」と、同大臣が発言したことも盛り込んだ。
それをもとに、アイコムでは、「レバノン当局は、爆発した無線機が当社製品ではないという認識を示していることになる」と結論づけた。
また、第3報では海外向け製品の流通体制についても触れ、海外向け製品には、アイコム安全保障貿易管理プログラムを策定し、正規代理店に届くまで厳格な管理体制で輸出していることに改めて言及。無線機のすべてにシリアルナンバーを付与しており、海外正規代理店から発注を受けると、和歌山アイコムから製品を出荷。出荷した製品はフォワーダー(運送物取扱業者)によって正規代理店に納入される仕組みとなっており、この間の輸送に携わる運送会社や、輸送手段、輸送経路などの情報は、シリアルナンバーに紐づく形ですべて把握していることを示した。実際、アイコムの正規ルートでは、5年以上に渡り、レバノンに同社製品は直接輸出されていないという。
その上で、「販売時まで、どのシリアルナンバーの製品が、どのエンドユーザーに販売されるかは確定しない。当社正規代理店に向けての流通経路において、特定のエンドユーザーが使用する無線機を標的として加工を施すことは、事実上不可能と考えている」と断定した。
また、爆発した無線機がアイコムの正規品でないことを特定するには、実際に爆発したものを確認するしか方法はないとしながらも、第3報の中で示したように、ホログラムシールが貼付されていないことや、通信大臣の発言、同社の流通経路における徹底した管理体制などをもとに、この時点で「爆発した無線機が当社製のものである可能性は限りなく低いと考えている」とも述べた。
加えて、「中東地域において、模造品が集まるマーケットの存在を確認している。明確な数字で伝えるのは困難だが、アジア地域を中心に模造品が多く出回っている」と報告し、「模造品は当社の売上を毀損するだけではなく、エンドユーザーが各国の電波法令に違反するおそれや、品質問題を引き起こす可能性、ひいては安全に対する問題にもつながりかねない。模造品の排除に企業の責務として取り組んでいく」との姿勢を示した。
アイコムでは、模倣されやすい製品については、QRコードの貼付による真贋認証システムの導入、ホログラムシールの貼付を行ない、利用者自らが確認できる仕組みを用意。さらに、地域に関わらず、模造品の製造、販売を行なう組織については、訴訟や当局の摘発への協力などを通して、断固とした取り組みを行なう姿勢も強調した。
アマチュア無線愛好家がアイコムを後押し
アイコムからの情報が的確に発信されたことで、メディアの報道内容も憶測をベースにした記事は1つもなく、模造品による一斉爆発であることが正確に伝わるようになった。
19日時点でのアイコムへの取材メディア数は15社(国内メディア10社、海外メディア5社)であり、約20人の記者が同社本社を訪れたという。アイコムの本社は大阪にあるため、当日に東京から取材に駆け付けた記者もいた。また、海外メディアにも、ドイツの現地法人が対応した。このとき、アイコムでは会見形式を取るのではなく、取材する記者に個別対応する形をとり、丁寧な説明を心掛けたという。
その一方で、情報発信においてアイコムには強い援軍が現れた点も見逃せない。
それがハムと呼ばれるアマチュア無線愛好家たちだった。日本でも、無線機の爆発に関する報道が始まり、そこにアイコムのブランドが記されていたことが知られるようになると、長年アイコムの製品を利用していたユーザーたちから、アイコム製品による爆発を否定する声が、SNS上にあふれた。
「アイコムが仕組むわけがない」、「アイコムが爆発物を仕掛けたなんてことはあり得ない」、「まず間違いなく模倣品」、「今日もアイコムの無線機を使って無線移動運用。当然ながら爆発なんてしない。今後もしない。するわけがない」などの書き込みが相次いだ。
中には、報道が始まった19日時点で、海外で流通している模造品の部品キットの写真を掲載し、正規品との違いを詳細に説明しながら、海外では模造品が出回っていることを指摘する投稿も見られた。
中岡社長は、「SNSには『アイコムが、そんなことするわけがない』という書き込みが相次いだのを見て、私自身とても心強かった。アイコムのことを信じてくれるユーザーが多いことに感動した」と振り返る。SNSの投稿を見ると、アイコムに対するネガティブな投稿はまったくなかったという。
不確かな情報をもとに憶測が広がり、それによって炎上するといった負のサイクルを、アイコム製品に信頼を寄せるアマチュア無線愛好家たちが、それを未然に防ぐ役割を担ったとも言えそうだ。
このように、アイコムによる的確な情報発信とともに、アマチュア無線愛好家の後押しもあり、レバノンでのトランシーバー爆発をもとにした実質的な被害はほとんどなかったという。
メキシコでは事件発生直後の2024年秋に、一時的に入札が取りやめになった例があったが、その後再入札が行なわれた。アイコムによると、今回の事件によるマイナス影響と言えるものはこの1件だけだったという。また、株価に対するマイナス影響はなく、むしろ投資家への認知度が向上したこと、製品の生産、流通を徹底管理している点が評価されるといったプラス要素もあったようだ。
アイコムでは、透明性を高める取り組みを進めており、これが社内に浸透している。「隠しごとが一番よくない。社員に対しても、なにか問題が発生したり、悪いことがあったりしたら、その場で言うように徹底をしている」と中岡社長。こうした社内に浸透した姿勢が、迅速な情報共有と、迅速な情報発信につながり、経営や業績への影響をゼロにしたと言える。
アイコムでは、今回の事件に伴う業績見通しへの影響や、中期経営計画への影響はないとしている。
アイコムの模造品対策はどうなっているのか?
今後、アイコムにとっての大きな課題は、模造品への対策と言える。同じような事件を起こさないためにも、これは重要な取り組みとなる。
アイコムの無線機は海外で高い人気を誇っており、東南アジアの一部地域では、無線機のことを「アイコム」と称していた時期もあったほどだ。つまり、「○○○○(メーカー名)のアイコムが欲しい」と表現されるほど、「アイコム=無線機」のイメージが浸透しているのである。今回の事案が発生したレバノンでも、警察官や要人警護の現場、警備員の間で広く使用され、市場シェアが高い。人気があるブランドだけに、模造品が出回りやすいという状況にあるのだ。
模造品による被害の解決は、アイコムにとって長年のテーマだ。
中岡社長もかつての経験から、こんなエピソードを明かす。「新入社員として、入社して間もないころ、ロングセラー製品のIC-2Nの修理のために、キーパーツを購入したいという海外企業から問い合わせがあった。だが、聞いてみると発注量が数万個とあまりにも多く、修理のための購入とは思えない水準だった。その頃から、筐体などを模造していた業者の存在は知っていたため、キーパーツの発注は、模造品を作るためのものと推測された」という。
無線機の模造品の問題は、すでに40年前からあったというわけだ。
もちろん、アイコムは、これを見過ごしてきたわけではない。正規品には、ホログラムシールを貼付しており、このシールにも改良を加えて、見分けやすいようにしているという。また、独自の認証QRコードを貼付することで、誰でも正規品であることを確認できるようにしたり、各国当局と連携などにより、模造品流通の監視と法的措置を講じたりといった活動を進めてきた。
たとえば、2021年1月にはタイ特別捜査局(DSI)が、模造品業者の摘発を実施。アイコムの無線機を始めとして、他社製品を含む3万7,694点、総額にして約5,000万バーツ(約2億円)の模造品を押収した。摘発された模造品業者には有罪判決が下されている。この事案では、警察官が使用していた無線機が故障し、それを調べたところ模造品であることが発覚。入札した企業の流通ルートを調べたところ、正規品でないことが分かった。アイコムでは、DSIに対して、感謝状を贈呈。今後も関係各所との協力を進めていく姿勢を明らかにしている。
さらに、模造品を販売しているサイトを発見した場合には、そのサイトを閉鎖させたり、販売や出品を停止させたりといった措置にも取り組んでいる。2024年だけで、4,000のサイト出品者による出品を停止させた。出品者ごとに、出品している台数が異なるため、模造品の販売を阻止できた全体台数は不明だが、アイコムでは、こうした地道な活動も進めているところだ。
ネットを通じた模造品販売も増加
レバノンの事件で模造されていた「IC-V82」は、アイコムが一般業務向け通信機として開発したものであり、警備や駐車場の誘導など、屋外で利用することを想定したものだ。
発売された2004年当時から、基本性能の高さと信頼性の高さが評価されていただけでなく、用途にあわせてプログラミングが可能であり、フレキシブルな設定ができる点も受けていた。また、購入しやすい価格設定となっていたことで高い人気を誇り、2014年10月の販売終了までの累計出荷台数は16万台に達している。ただ、トランシーバーとしてはやや大きめのサイズであったたため、日本では販売されておらず、日本市場向けにはより小型化したトランシーバーが販売されていた。
現在、後継機として、「IC-V86」が海外で販売されている。先にも触れたように、「IC-V82」は約10年前の2014年10月に販売を終了。正規の対応バッテリの販売も終了しているため、バッテリ寿命を考えると、本体バッテリを含めた正規品としては、すでに現役で稼働していることはあり得ない機種とも言える。
アイコムによると「IC-V82」の模造品は、2000年代後半から確認していたと言い、現在では同機種のほか「IC-V80」、「IC-M25」、「IC-2300H」など、複数の機種の模造品を確認。中にはアイコムには存在しない型番の製品にアイコムのロゴが付与され、販売されているケースもあるという。
昨今では、模造品をネットで販売する動きが加速しており、正規品の半額から75%引きといった価格で販売されているようだ。
市場に出回っている模造品を分析すると、製造工程や設計が異なるものとして、最低で3種類の模造品があることが確認できているという。つまり、アイコムの無線機の模造品を作る業者が最低でも3社あるということだ。そして、これらはアジア地域で作られている可能性が高そうだ。
模造品業者は模造品を作るために、金型などに投資をするのはメーカーと同じであり、言い換えれば、この費用の回収ができるだけの出荷台数が必要になる。金型を安く作ったとしても、数1,000万円の費用がかかり、これを回収するには、数万台規模の出荷が必要になる。それでも、精巧な模造品を作るメリットが、模造品業者にはあるということだ。
だが、正規品と模造品の差は明確だ。正規品はMILスペックに対応。筐体にオリジナルの曲線を持たせることで強度を高めたり、材料を厳選し、それを採用したりといったように、アイコム独自の設計となっている。
だが、模造品の形状はかなり精巧に作られているのも事実だ。「時間と投資をして、設計し、検証し、テストを行なって完成させたものが、勝手に模倣され、それが販売されていることには怒りを感じる」と、中岡社長は口調を荒げる。
また、無線機の最大の特徴は、常につながり続けるということであり、当然のことながら、正規品では電気特性や通信性能では高い品質を実現している。「特に受信性能の差は正規品と模造品には大きな差がある。また、送信性能においては輻射を制御する技術で差がある」と指摘する。
模造品は通信規制に関する認証を取得する必要がないため、電波の輻射の影響を気にせずに作っているのが一般的である。模造品を通常通話では問題なく使用できたとしても、それが周りの機器に影響を及ぼしたり、一度地面に落下させてしまった途端に通信品質がおかしくなったりするといったことも発生しているようである。
「安全、安心に利用してもらうためにも、正規代理店から購入してもらいたい。それが模造品対策の最も有効な手立てになる」と、中岡社長は語る。
正規品と模造品を比べてみる
今回の取材では、アイコムに残されていた正規品の「IC-V82」と、海外で流通している「IC-V82」の模造品を比べることができた。写真を通じて比べてみる。
模造品を撲滅するにはどうすべきか?
アイコムの中岡社長は、レバノンでの一斉爆発の事件を振り返り、「無線機をこんなことに使われるとは想定もしていなかった」とし、「当社が製造した製品であるかどうかに関わらず、安心安全を守るためのツールであるべき無線機が、このような形で使われたことが残念でならない。無線機への信頼がこのような形で毀損されたことには、強い憤りを禁じ得ない。アイコムは、先進のコミュニケーションで安全で、豊かな社会を創造する企業として、今後も安心して使ってもらえる製品を市場に供給できるように、引き続き取り組んでいく」と決意を新たにする。
その一方で、「工場ではしっかりとしたモノづくりを行ない、しっかりとした品質管理をしてくれている。海外営業部を始めとした輸出に関連する部門でも、正しい販売と正しい物流をしてくれている。だからこそ、早い段階から爆発した無線機が正規品ではなく、模造品であると確信を持つことができた。社員に感謝をしたい」とも語る。
中岡社長が指摘するように、安心安全を守るためのツールである無線機が、人を殺傷する武器として使われたことは怒りに堪えない。
アイコムの模造品との戦いはこれからも続くことになる。模造品をなくすための地道な取り組みが、痛ましい事件を引き起こさないことにつながる。一企業の問題だけでなく、業界や政府までを巻き込んだ本格的な対応が必要な段階に入っているのかもしれない。
































![[Amazon限定ブランド]CCL い・ろ・は・すラベルレス 2LPET ×8本 ミネラルウォーター 無味 製品画像:2位](https://m.media-amazon.com/images/I/41h0MHfvhkL._SL160_.jpg)


















![【中古】 ASUS EeeTop PC ET2002 Atom 330 1.6GHz Windows7モデル 液晶一体型 均一 BIOS表示可 HDMI ジャンク 送料無料 [91056] 製品画像:8位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/risemark/cabinet/pic/910b/91056.jpg?_ex=128x128)



![【3年保証】HP PRODESK 600 G5 [新品SSD] SSD256GB メモリ8GB Core i5 Windows 11 Pro 中古 返品 送料無料 中古デスクトップパソコン 中古パソコン デスクトップパソコン デスクトップ PC OFFICE付き 製品画像:4位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_gold/pcwrap/goods/4bo250011_1.jpg?_ex=128x128)











![【エントリーで最大2万ポイント当たる|2/25まで】 DELL|デル PCモニター Dell 27 Plus ホワイト S2725DSM-R [27型 /WQHD(2560×1440) /ワイド /144Hz] 製品画像:4位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/biccamera/cabinet/product/15031/00000014663194_a01.jpg?_ex=128x128)

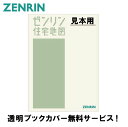

![REAL TRUCKS 9(トラック魂 特別編集) [ トラック魂 編集部 ] 製品画像:28位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/8254/9784865428254.gif?_ex=128x128)
![ドラゴンクエストの生みの親 堀井雄二 新学習まんが人物館 (小学館版 学習まんが人物館) [ 堀井 雄二 ] 製品画像:27位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/2073/9784092702073_1_50.jpg?_ex=128x128)
![[新品]進撃の巨人 (1-34巻 全巻) 全巻セット 製品画像:26位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/mangazenkan/cabinet/syncip_0020/si-506_02.jpg?_ex=128x128)
![【楽天ブックス限定特典】コアラ沼への招待状(豪華オリジナルシール1枚) [ 早川 卓志 ] 製品画像:25位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/8236/2100014838236.gif?_ex=128x128)
![超かぐや姫!(1) (ファミ通文庫) [ スタジオクロマト・スタジオコロリド ] 製品画像:24位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/7348/9784047387348_1_23.jpg?_ex=128x128)

![看護師・看護学生のためのレビューブック 2027 [ 岡庭 豊 ] 製品画像:22位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/9698/9784896329698_1_3.jpg?_ex=128x128)
![ルイ・ボナパルトのブリュメール18日 (講談社学術文庫) [ カール・マルクス ] 製品画像:21位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/3464/9784065193464_1_22.jpg?_ex=128x128)