eスポーツチーム代表者に聞く
数年先を見据えたeスポーツチーム運営を行なうSCARZ友利洋一氏。次の一手は?
2025年2月17日 06:17
今回取材したのは、老舗eスポーツチームのSCARZ。国内外を問わず、さまざまなタイトルや大会に挑戦してきており、日本のeスポーツを牽引してきた立役者のチームの1つと言えるだろう。eスポーツ界隈やチーム力の拡大を見越し、いち早く松坂屋やパルコなどを運営するJ.フロントリテイリングと提携したのは、eスポーツチームの在り方を示している。SCARZを運営する株式会社XENOZ代表取締役社長の友利洋一氏(以下、敬称略)に話を伺ってきた。
--SCARZはeスポーツと言う言葉すら聞いたことがないような時代からチームとして活動をしています。まずチーム発足の経緯を教えてください。
友利:現在のようなプロチームになる以前、SCARZはアマチュアのゲーム集団として2012年からありました。その当時は、競技シーンで戦うと言うのではなく、ゲーム内にクランを作って遊んでいました。当時から国際色豊かで、日本人が40%くらい、海外の人たちが60%くらいで100人くらいいたんじゃないでしょうか。
遊んでいたタイトルはFPS系で、当時はまだ公式の大会とかはありませんでした。クラン戦とかやっているうちに、段々とガチ勢になっていって、それじゃあ本格的にやってみるかとなりました。
--ゲームは子どもの頃からプレイされていたんでしょうか。
友利:親がゲーム機を持っていて、たぶんPlayStation 2あたりで自分から欲しいと思って買ってもらった気がします。たぶん、最初にゲームにハマったのは15~6歳くらいですかね。基本無料のFPSがたくさんあって、そこら辺を遊びまくっていました。
ゲーム機以外にも、家にはPCがあったんですよ。確かWindows95とかの時代です。なので、PCのオンラインゲームは友だちとかよりも早く触れることができていましたね。MMORPGもがっつりやりました。
--ゲームの腕前はどうだったんでしょうか。
友利:シューティングとかだとエイムが抜群にうまいとかではなかったですね。どちらかと言うと後ろから指示を出しています。ずっとドローンを飛ばしています(笑)。今で言うIGLみたいな感じですね。MOBAとかも指示役をすることが多いです。
今一番楽しんでいるのは「マーベルライバルズ」ですね。TPS(三人称視点)でプレイしやすいし、1ゲームがさくさく終わるし、初心者でも入りやすいのがいいですね。日本ではまだそこまで人気になっていませんが、海外だとプレイヤーが他タイトルからも流れてきており、盛り上がっているようです。
--話が逸れましたが、SCARZが発足されてすぐにプロ化したんでしょうか。
友利:しばらくはアマチュアチームで運営していました。いざ本気でやってみたけど、海外チームに圧倒されて手も足も出なかったんですよ。やはり、競技シーンでは海外が先行しており、チームも整備されていたんですよね。
ただ、ゲームプレイヤーとしては日本の選手もポテンシャルを持っているはずなのに勝てないのは、やはり環境が問題かと感じました。そうであればと、SCARZを結成したわけです。それから数年して2015~2016年頃にプロチーム化をして、本格的に始動しました。とにかく世界に飛び出して行きたいと思っていました。
--当時はまだ日本ではプロeスポーツチームはほとんどなかったんですよね。
友利:そうですね。DetonatioNとかDETONATOR、あとSUNSISTERはありましたね。ほかはもう少し後かも知れません。プロチームと言っても今のようにスポンサーがついて、選手活動だけで食っていけるようなことはなく、大会で勝利してヘッドセットが貰えたことがうれしいと思える程度でした。
一方海外では、その時代からゲーミングハウスが用意されていて、給料も支払われていました。海外の老舗チームであるFnaticの環境がすごく印象的でした。
そういうわけでプロチーム化してもいきなりお金が稼げたわけではなく、選手に分け与えられる部分は少なかったですね。チームとしてもそこら辺はある程度納得してやってくれていました。チームとして潮目が変わったのはやはり2018年ですね。
--いわゆるeスポーツ元年(笑)。
友利:そうですね。でも、急に変わったというより、2017年から兆候は見えていました。SCARZとして、スポンサーとの提携の発表など、毎月何かしらの発表をしていましたね。テレビ番組にも2カ月に1度くらいのペースで出ていたと思います。
逆に言うと、それまでは選手に満足のいく支援をできていなかったです。ただ、あの時代を支えてくれた選手や人たちがいたから、今があると思っています。古くからのお付き合いのあるスポンサーさんだと、2017年頃からついていただいていますね。
--SCARZはシューティング系のイメージが強いですけれども、これまでのタイトルの実績や軌跡としてはどんな感じなのでしょうか。
友利:自分自身が「League of Legends」にハマっていて、LJLの存在を知った時、すぐにプロリーグの参加を決めました。成績的には1部と2部の降格昇格を繰り返すような立ち位置でした。
--まだ2部制の時ですね。Riot Games公式のリーグとして1リーグ制になった時はトップリーグには入っていませんでしたね。
友利:最終的には、バーニングコアと一緒にやっていて、Scarz Burning Coreとしての参加でした。その後、撤退することになりました。その頃は「Counter-Strike」にも参戦していました。
SCARZとして名が通るようになったのは、「Call of Duty」の時です。東京ゲームショウとかニコニコ超会議とかの大会で実績を出し、eスポーツ界隈で名が知れ渡るようになりました。
--SCARZは、SCARZ EUなど、海外展開もされていますが、そこはどういった経緯でしょうか。
友利:SCARZの人気をどうやって伸ばして行こうかと考えた時、当時は海外の力を借りるのが最適だと思っていました。やはり日本とは比べものにならない市場の大きさがあったので、そこを狙っていました。
元々、日本から世界へ飛び出して行きたいと考えていましたし、ゆくゆくは北米、欧州、南米などに支社を作りたいとも思っていました。現地で選手を獲って、その地のゲーム文化を学びたいとも思っていましたね。結果として「APEX LEGENDS」で優勝でき、良い結果は残せました。
--日本のチームが海外の選手と契約する場合、その選手を日本に連れてくる場合が多かった中、SCARは海外チームとして、現地の選手が現地の大会に出ると言う形を取っていました。これはFnaticとか海外のチームが別の国で展開する場合のやり方ですよね。
友利:そうなんですよね。日本のチームはいろんなタイトルの部門を作って展開するんですけど、基本的に活動拠点は日本なんですよね。FnaticやC9、TeamLiquidとかは海外展開しているのに日本は日本で完結することが多いですね。
--海外展開は今後も続いていくんでしょうか
友利:海外はいったん落ち着かせる予定です。当時と現在では日本のeスポーツの環境が大きく変わっており、日本に注力しても十分な成果、価値を見い出せるようになってきました。「VALORANT」は海外と比べても盛り上がっていますよね。
2023~2024年は海外選手中心のロースターでやっていて、試合中の音声チャットも英語ベースでした。これは、海外選手の実力と自分達がVCTで目指すべきミッションがベストマッチした結果です。今は日本語中心でも実力派のメンバーが揃っているので、日本語にしています。この辺りもこの数年で日本のeスポーツ環境が変わったってことだと言えます。
--SCARZ EUが発足してすぐ後の大会の後にインタビューさせていただいた際に印象的だったのは、向こうの選手は生配信をしており、「チームのスポンサーを画面に載せるからスポンサーロゴのオーバーレイがほしいと言われた」っおっしゃってたことです。今では日本でも当たり前のように選手が配信をし、スポンサーロゴを載せて配信をしていますが、当時の日本ではほとんどやっていなかったと思います。
友利:そこは本当に驚きましたね。そういった面でも、海外が一歩も二歩も先に行っていて、選手自ら、自分が自分を売り込むために、自分がどんな選手かプロフィールとか略歴とかを作っていました。その当時の日本人選手と比べると、本気度が違うと言うか。こういうところは勉強になりました。その当時のことを考えると日本人選手も随分と成長しましたね。同時に、海外展開をやってみた結果、海外の難しさがあると言うことも実感しています。
SCARZとしてはチームで既存の大会に参加するだけでなく、大会の運営も行なっています。SCARZ CUPはプロとストリーマーのミックスチームを作って、融合させてみたり、昨年はオフシーズンの公式イベントとしてVALORANTで「HYPE UP!」も開催できました。
--HYPE UP!と言えば、大阪と名古屋の予選をCLUB QUATTROで、決勝戦をDragon Gateで開催しました。クラブを使ったeスポーツイベントは珍しいですが、これもSCARZがJ.フロントリテイリングと提携し、子会社化したことが大きいと思います。
友利:eスポーツチームが提携先を探していたのは、SCARZだけではなかったと思います。eスポーツの注目度があがり、市場が活性化することで、今後さらに規模が拡大していくと感じていました。その点で言えば、色々な方のご協力により今の形が叶ったと感じられてます。
--ちょうど取材日の前にいくつかの独立系eスポーツチームが解散、活動休止を発表されており、第一線で活動していくにはこれまでのチームでは資本力が足りないと言うことを再認識しました。友利さんは、現在の状況を2年以上前に予測していたわけですね。
友利:知っているチームさんが解散する話を聞くのは悲しく感じます。理由は詳しく存じてないのですが、eスポーツは可能性を広げることも重要で、何かのアクションに対してあらゆる支えも大事になってくる要素となる部分もあるので、新しい変化の時が来るのかもしれないと感じてます。
--企業系以外のチームの場合は、営業を経験した人がいなかったり、選手のマネジメントもできていなかったりと、コミュニティの延長戦上でしかないところが多いと思います。企業としての基礎が確立されていないところもある中、ゲーム以外のところのビジネスのノウハウも大事ですね。
友利:企業としての営業経験がないとスポンサー営業に行こうにも、どうやってスポンサーになってもらうか分からないです。最近はスポンサー企業もeスポーツに詳しい人が増えてきているので、逆に営業力があってもeスポーツのことが付け焼き刃だと、信用されなくなってしまいますよね。
そういった意味で、SCARZとJ.フロントリテイリングはうまく協業できていると思います。お互いができることをしっかりとやっていて、HYPE UP!などにつながりましたし、VCT Ascension Pacificの時はパルコ劇場でパブリックビューイングが行なえました。先日も大丸デパートで「グランツーリスモ」部門のイベントをやっています。池袋パルコでもファンミーティングを開催しました。
パルコとはすごくいい関係性が築けていて、一緒にやろうという感じがひしひしと伝わるんですよね。こちらもビジネスや流通のことなどで教わることが多くて、お互いに刺激しあっています。
--大丸のイベントは取材に行きましたが、SCARZは「グランツーリスモ7」にかなり注力している印象です。取材直前には、ストリートファイターのプロゲーマーであるストーム久保さんがクリエイターとしてSCARZ入りをしましたし、今後はさらに拡大していく印象ですが、いかがでしょうか。
友利:「グランツーリスモ7」については、力を入れていきます。宮園拓真選手とTakuAn選手、Goto選手、鍋谷奏輝選手と言うトッププレイヤーが揃っています。ただ、それだけの布陣でもeモータースポーツ自体の知名度はまだまだで、eスポーツ市場における認知は得られていないというのが現状です。
どうやってファン作りをして、「グランツーリスモ7」の競技シーンや選手に価値を持たせられるか考えています。もっとできることはあると思っていますので。
格闘ゲーム界での影響力も増していきたいと思っています。その第一歩としてストーム久保に白羽の矢を立てました。SCARZは対戦格闘ゲームのイメージが薄いと思いますが、「大乱闘スマッシュブラザーズスペシャル」のアシモ選手とM0tsunabE選手が在籍していますし、かつては「ストリートファイター」シリーズで活躍しているsako選手もSCARZに所属していました。
チームを率いている立場としては、SFLも目指してないわけではないです。あ、前回の西原さんの時みたいに、部門立ち上げの発表ではないです(笑)。あくまでも、やれるタイミングが来たらやりたいってことです。
--水派選手やShuto選手(当時あんまん名義)もSCARZに所属していましたね。SCARZのストリートファイター部門が復活するのを期待しています。
友利:「時が来たら」を楽しみにしといてください(笑)。あとはイベント関係ももっとやっていきたいですね。SCARZ CUPはもちろん、それ以外のことで新しいこともやりたい。それと、ファンとの交流。先ほども言った通り、パルコでファンミーティングを開催していますので、今後もやっていきたいです。
あとはDiscordにSCARZのサーバーがあり、そこでファンとコミュニケーションをとっています。Discord内での大会とかもやっていますが、今後は、私と対話するチャンネルとかも考えています。
--今の課題について教えてください。チームの課題も、業界の課題でも構いません。
友利:いっぱいあるなぁ(笑)。まずチームとしては、影響力を増していきたいですね。競技シーンで日本一だったり、世界一だったりと、SCARZをeスポーツを知らない人にも知ってもらえるようなことをしたいですね。ストリーマーにもっと力を入れるというのもあると思います。
業界としては、チームごとに仲がいいところはありますけど、業界全体が1つになっているとは言い難いです。団体で行動をすることも必要だと考えています。たとえば、海外には選手会やチーム会があり、そういうものも必要かもしれないですね。日本は地理的にまとまりやすい環境なので、それを生かしたいですね。
この前、Jリーグの関係者と話をする機会があったのですが、Jリーグは箱推しがあるけど、選手推しがされにくいと聞きました。eスポーツでは選手推しが中心で箱推しがほとんどないという真逆の状況です。おそらくeスポーツはスポーツと比べて拠点が分かりにくいので、ファン接点のエントリーが違うんだろうなと考えてます。
SCARZは現在、川崎と渋谷の2つを拠点しており、地域との関わり合いを強くし、箱推しできる環境を作ろうと頑張ってきました。ただ、数あるeスポーツチームの1つや2つがそれをやってもなかなか根付きません。いろんなチームがいろんな場所を拠点にして、チームカラーを出していければいいなと思います。
eスポーツはeスポーツ界隈で競っていく時代から、他のスポーツやエンタメと勝負していく時代になっていくと思います。今後、eスポーツがさらに上を目指していくなら、文化にしていく必要があるんでしょうね。そのためにはプロサッカーやプロ野球、プロバスケなどから学びつつ、いろんなチームと一緒に考えないといけないと思っています。
スポンサー視点では数字も重要な部分の1つだと考えています。Jリーグであれば、毎試合2万人入りますとかになりますけど、eスポーツでの指標は何にすべきなのか?おそらくオンライン性は強みなんですけど、登録者数や同時接続者数とかだけで見るのであればストリーマーの方がいいのでは、と言う意見も出てきますよね。
確かにストリーマーの影響力はeスポーツ界隈に大きな進化をもたらした1つだと捉えています。ただ、元々選手だった子たちも多いので、それを競技シーンとどのようにミックスさせて次の進化につなげていくのかが界隈への課題でもあると捉えてます。競技の熱狂とストリーマーの面白さの融合から生まれるものに期待しつつ、スポーツとしての楽しさが加わり、新しいeスポーツ文化を目指していければと考えてます。





















![[Amazon限定ブランド]CCL い・ろ・は・すラベルレス 2LPET ×8本 ミネラルウォーター 無味 製品画像:1位](https://m.media-amazon.com/images/I/41h0MHfvhkL._SL160_.jpg)



![【Amazon.co.jp限定】 伊藤園 磨かれて、澄みきった日本の水 2L 8本 ラベルレス [ ケース ] [ 水 ] [ 軟水 ] [ ペットボトル ] [ 箱買い ] [ ストック ] [ 水分補給 ] 製品画像:5位](https://m.media-amazon.com/images/I/41n0o65dSkL._SL160_.jpg)
























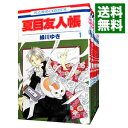
![予約の取れないセラピストの骨格小顔バンド [ 三木まゆ美 ] 製品画像:29位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/8296/9784865938296_1_16.jpg?_ex=128x128)
![ROCKIN'ON JAPAN (ロッキング・オン・ジャパン) 2026年 5月号 [雑誌] 製品画像:28位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/0561/4912097970561.gif?_ex=128x128)
![青天 [ 若林 正恭 ] 製品画像:27位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/0665/9784163920665_1_10.jpg?_ex=128x128)


![STORY (ストーリィ) 2026年 4月号 [雑誌] 製品画像:24位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/0464/4912054830464_1_2.jpg?_ex=128x128)
![ANIMATION WORKS「LUPIN THE IIIRD」シリーズ公式コンプリートブック [ MdN編集部 ] 製品画像:23位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/8389/9784295208389_1_2.jpg?_ex=128x128)
![だぶるぷれい 7【電子書籍】[ ムラタコウジ ] 製品画像:22位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rakutenkobo-ebooks/cabinet/1782/2000019711782.jpg?_ex=128x128)
![Numero TOKYO (ヌメロ・トウキョウ)4月号増刊 2026年 4月号 [雑誌] 製品画像:21位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/0466/4912172000466_1_2.jpg?_ex=128x128)