
 |
|
MICROPROCESSOR FORUM 2001レポートさらなる低消費電力を目指すTransmetaのTM6000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
会場:Fairmont Hotel(カリフォルニア州サンノゼ)
会期:10月15日~19日(現地時間)
x86市場のキープレイヤーと言えば、言うまでもなくIntel、AMDの2大メーカーだが、Transmeta、VIA Technologies/Centaur Technologyも両者ほどのシェアは獲得していないものの、低消費電力やローコストを売り物に一部市場に確実に食い込みつつある。本レポートでは、そうした両社のMICROPROCESSOR FORUMにおける発表についてお伝えしていきたい。
●Transmeta初のSoCであるTM6000
 |
| Transmetaの社長兼CEOのデビット・ディッツエル氏 |
これまで、製造プロセスルールが0.18μmでCMSのバージョンが4.1のTM5600(512KB L2キャッシュ)とTM5400(256KB L2キャッシュ)、0.13μmでCMS4.2のTM5800(512KB L2キャッシュ)とTM5500(256KB L2キャッシュ)の4製品がリリースされており、TM5600/TM5400を搭載した製品は既にソニーのC1、東芝のLibretto L1/L2、富士通のLOOXシリーズなどに採用されているほか、先日ソニーからは最新のTM5800を搭載したC1も発表されている。以前より、ディッツエル氏は次期Crusoeは256bit VLIWのRISCプロセッサを採用したバージョンと、SoCの両方があると説明してきたが、今回そのSoCの方がTM6000として発表されたという訳だ。
TM6000の仕様は次のようになっている。
・クロック:1GHz
・エンジン:128bit VLIW
・駆動電圧:0.9V~1.3V(LongRun対応)
・L1キャッシュ:128KB
・L2キャッシュ:512KB
・メモリコントローラ:DDR SDRAM(333MHz、ECC対応)
・2Dグラフィックスコントローラ
(24bitカラー、LVDSインターフェイス、DVD再生支援)
・PCIバスインターフェイス
・IDEコントローラ(2チャネル/4デバイス)
・USBポート(4ポート)
・AC-Link
・SM-bus
・LPC
・CMS 5.x
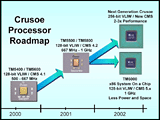 |
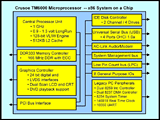 |
| Crusoeのロードマップ | TM6000の構成要素 |
●SoC化により実装面積や消費電力を削減
これまで、TM5600やTM5800を利用したシステムを構築する場合、CPUに統合されていたノースブリッジ以外に、サウスブリッジ、ビデオチップを必要としていた。ところが、TM6000ではこうしたビデオチップ、サウスブリッジまでもがCPUに内蔵されているのだ。
こうしたSoCのアドバンテージは、実装面積の減少と消費電力減少だ。ディッツエル氏の説明によればTM5800に比べ、TM6000を採用した場合、実装面積は1/3以下になるという。実装面積が小さくなるのは、チップ数が減ることと併せてコストの削減につながる。さらに、消費電力はDVD再生時において、TM5800で構成されたシステムに比べて44%消費電力が低減しているという。
ディッツエル氏はTM6000の使用用途として、タブレットPCやソニーのC1のようなミニノート、サブノートと呼ばれるノートパソコン、さらにはインターネット専用端末、高密度サーバーなどをあげている。なお、ディッツエル氏はTM6000のファーストシリコンは第4四半期中に行なわれ、2002年の前半にサンプル出荷が開始、2002年の後半にTM6000を搭載したこれらのシステムが登場するだろうという見通しを明らかにしている。製造は台湾のTSMCで行なわれ、利用されるプロセスルールは0.13μmになるということだ。
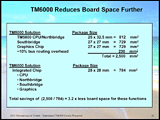 |
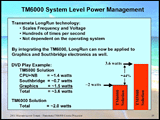 |
 |
| 実装面積を説明するスライド。TM5800を利用した場合に比べて1/3以下の実装面積ですむという | TM5800を利用したシステムに比べて消費電力は44%の削減が期待できるという | TM6000を利用したシステムのブロック図 |
●課題はSoC特有の性能に対する柔軟性の欠如をどうするか
ところで、今回発表されたTM6000は、x86系のSoCとしては、初めての製品ではない。既にNationalSemiconductorはGeodeと呼ばれるかつてのCyrix MediaGXの後継製品を投入しているし、台湾のチップセットベンダであるSiS(Silicon Integrated Systems)もSiS550というSoCを発表している。これらの製品が、どちらかと言えばセットトップボックスなどの組み込み系を狙った製品で、TM6000はモバイルにフォーカスした製品という違いはあるが、基本的にはこれらがライバルになる可能性が高い。
だが、GeodeにせよSiS550にせよ、採用例はさほど多くなく、これまでのx86系のSoCはお世辞にも大成功を納めたとは言えない状況だ。その最も大きな理由は、SoCには構成上の自由がないことだ。例えば、TM6000は2Dグラフィックスのみのグラフィックスサブシステムを内蔵している。しかし、現在ではノートパソコンにも3D描画機能をサポートしたビデオチップが主流になっており、3Dグラフィックスに対応させるにはPCIの3Dビデオチップを別途追加する必要がある。これでは、実装面積が小さくすみ、消費電力が低いSoCとしての魅力が低下してしまう。このように、一度シリコンになってしまったSoCでは、各コンポーネントを気軽に切り替えることは難しく、構成上の柔軟性がないというデメリットがある。
そうした意味では、数カ月のサイクルで新しい製品がリリースされ、コンポーネントの置き換えが早いPCに利用するのは難しいのではという意見もあり、実際PCでSoCが成功を収めなかったのはそれが理由だ。この点をどうクリアにするのか、それがTM6000の課題の1つである。しかし、逆に製品のライフサイクルが長い、家電やセットトップボックスなどに利用するのであればメリットは大きいと言え、そうした市場を開拓していくことができるか、それがTM6000成功の鍵を握るといっていいだろう。
●ローコスト市場にかけるVIA/CentaurのC3プロセッサ
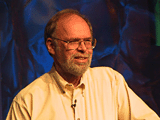 |
| Centaur Technologyの社長 グレン・ヘンリー氏 |
その中で、「世の中の90%近くの人はギガヘルツのCPUなんて必要ないはずだ。それよりも、必要な処理能力をより安価に供給できたほうがいいだろう」(ヘンリー氏)と同社の方針がこれまでと変わらず、一般的なアプリケーションを使うのに十分な処理能力を持つCPUを安価に供給するのだという方針を改めて確認した。
ヘンリー氏がこうしたプレゼンを行なう理由は、ヘンリー氏がこうした方針でCPUを作っているということはあるが、親会社であるVIA Technologiesの意向が働いている。VIAの社長兼CEOであるウェン・シー・チャン氏は、バリューPCよりも下のセグメントのPCでインターネットオリエンテッドな“Information PC”構想や、そのInformation PCを作るためのビルディングブロックである“Value Internet Architecture”構想などを常々語っており、安価にPCを作るためのパーツを供給するというのを会社の方針としている。当然子会社であるCentaurのヘンリー氏もその意向には従わなければいけないわけで、いかに安価なCPUを供給するか、これが1つのテーマとなっているのだ。
実際、VIA/CentaurのC3プロセッサは、業界最低水準の製造コストで作られていると言われている。CPUのような半導体の製造コストは、ダイサイズの小ささに比例して下がると言われている。初日の午前中に開かれたIn-Sat/MDR主催のセミナーである「Inside Today's PC Processor」では、「MICROPROCESSOR REPORT誌のアナリストであるケビン・クレウェル氏が「VIA/CentaurのC3は業界最低水準の製造コスト」であると説明している。
 |
| VIA TechnologiesのC3/1.0A GHz、右上にあるのが52平方mmのCPUダイ |
実際、日本や米国などの市場ではほとんど搭載PCを見かけることはないが、中東や発展途上国といったコストオリエンテッドな市場では確実に市場を獲得しつつあり、VIAとしてもそちらの拡大に全力を注いでいる現状だ。
●C5Xのローコスト版C5XL、C5YLによりさらなる低価格化を実現
 |
| 2001年から2002年にかけてのロードマップ。Ezra-TはEzraにAGTL(1.25V)対応を付加したもので、C5Nでは銅配線が利用されるようになる |
現在、VIAはC3プロセッサに、0.15μm/0.13μmのハイブリッドの製造プロセスルールを利用している。これはVIAのCPUを製造するTSMC(Taiwan Semiconductor Manufacturing Company)の CL013LP( http://www.tsmc.com/technology/cl013.html )というプロセスルールで製造され、ゲート長は0.13μmなのだが、ジオメトリの観点では0.15μmとなっている。
この0.15/0.13μmのハイブリッドを利用したCPUコアはEzra(エズラ、CentaurのコードネームではC5C)と呼ばれており、システムバスの電気信号をAGTL(1.25V)というTualatinと同じ仕様に変更したEzra-T(エズラティー、CentaurのコードネームではC5MとC5N)が登場する予定となっている。
そのEzraの後継となるのがC5Xファミリーで、製造プロセスルールは完全な0.13μmのプロセス(つまりジオメトリの観点でも0.13μmのプロセス)に変更され、製造は引き続きTSMCで行なわれる。C5XはCentaurの新世代CPUであるCZA(昨年はCXとして紹介されていたが、今年は変更されている)と、現行のSamuel(C5A)、Samuel2(C5B)、Ezra(C5C)のアーキテクチャを融合させたCPUで、パイプラインのステージ数を12から16へ、命令実行ユニットの数をシングルからデュアルへ、L2キャッシュの容量を256KBへ増やすなどして性能面での強化が図られているのが特徴だ。
昨年はC5Xは単一の製品だったのだが、今年はC5Xファミリーとなっており、C5X自体以外に、廉価版のC5XL、その進化版であるC5YLが追加されていた。C5XLはC5Xでデュアル化されているデコーダ、命令実行ユニットなどをシングルに戻し、L2キャッシュの容量を64KBと現行のSamuel2(C5B)/Ezra(C5C)と同じ64KBに減量したローコスト版だ。そのねらいは明らかで、C5Xでは78平方mmであったダイサイズが、C5XLでは54平方mmとSamuel2、Ezraとほぼ変わらないレベルにまで減っているのだ。さらに、C5XLではチップの実装方法もこれまでと同じ手堅いワイヤーボンディング方式が利用できる。これに対して、C5XではフリップチップというIntelやAMDがPentium III、Pentium 4、Athlonなどで利用している実装方式を利用する。フリップチップ方式の方が、配線遅延も少なく高クロック化には有利なのだが、ワイヤーボンディングに比べるとコストは高くついてしまうのだ。
このように、C5XLではとにかく安価に作れるように、高コストになる要素をできるだけ排除している。ヘンリー氏によれば「C5XLはC5Xに比べて30%程度ダイサイズが小さくなっている。しかし、実際のパフォーマンス低下は10~20%程度で、コストパフォーマンスには優れている」と述べ、C5XLがとにかくコストオリエンテッドなCPUであると説明している。さらにC5XL(そしてC5)ではパイプラインのステージ数がSamuel2/Ezraの12ステージから16ステージに細分化されており、よりクロックをあげやすい仕様となっており、少なくともSamuel2、Ezraよりは高い性能を発揮できるようにはなるだろう。
なお、昨年のMICROPROCESSOR FORUMではC5Xは今年中に出荷することになっていたのだが、今回明らかにされたロードマップでは2002年の後半に出荷されることになっている。CXあらため、CZAとなった次世代アーキテクチャのCPUは2004年のリリースとなっている
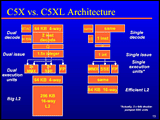 |
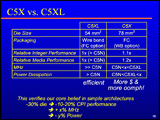 |
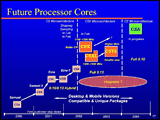 |
| C5XとC5XLの比較。C5XLではローコストを実現するために機能を削り、54平方mmという小さいダイサイズを実現していることがわかる | 将来のCPUロードマップ。CZAに関しては今回は特に言及はなかった | |
●デュアル動作の高密度サーバーでPentium III-Sの置き換えをねらう
なお、C5XファミリーではAPICの機能を搭載しており、デュアルの動作が可能となっている。C5XではSamuel2/Ezraと同じようにCPUのシステムバスはP6バスを利用し、やはりTualatinと互換のAGTL(1.25V)にも対応している。
この機能を追加したのは、明らかに高密度サーバーにおいて、Intelからの置き換えをねらったものだろう。Intelは高密度サーバー向けにTualatinコアのPentium III-Sや低電圧版モバイルPentium IIIーMなどを投入している。今後これらを利用した高密度サーバーが市場に登場してくるが、そうした市場においてC5Xファミリーをそれらの代替えとして利用してもらう戦略だと考えるのが妥当だろう。実際、Centaur Technologyのテクニカルマーケティングを担当するC.J.ホルトス氏は「μPGAパッケージのC5Xを用意する予定もある」と説明しており、高密度サーバーにおいても、Intelのオルタナティブになっていきたい意向であるようだ。
●ニッチだが確実にニーズがある市場で生き残りをかける両メーカー
このように、新しいCPUをリリースした両メーカーだが、現在までのところ、どちらのメーカーも大きな市場を手に入れた訳ではない。例えば、米国では株価が企業を評価する最も重要な指標となっているが、Transmetaの株価は一時期は40ドルを超えていたのにもかかわらず、現在はわずか2.5ドル前後と大幅に下がっている。正直なところ、かなり厳しい状態であることは間違いない。しかし、実は今回のTM6000の発表前にはTransmetaの株価は1ドル台の前半をさまよっていたのだが、今回の発表後に2ドル台まで回復している。つまり、市場はこの発表をポジティブに評価したということだ。
正直なところ、TM6000自体はPC向けとしては、3Dの問題などもあるので、難しいのではと思うが、タブレットPCやx86を利用したエンベデットといった新しい市場では非常に有効なソリューションだ。また、VIAのC5Xシリーズも、低価格というメリットは特に発展途上国などにPCを普及させるために重要な製品であり、どちらもさほど大きくはないものの確実にニーズがある市場であるといえるが、これまでにない市場を作っていくという努力が必要になる。それらにTransmetaやVIAが、どれだけコミットしていけるか、それがポイントであるといえるだろう。
□MICROPROCESSOR FORUMのホームページ(英文)
http://www.mdronline.com/mpf/
□関連記事
【10月16日】MICROPROCESSOR FORUM 2001開幕速報
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/article/20011016/mpf01.htm
(2001年10月18日)
[Reported by 笠原一輝@ユービック・コンピューティング]
|