 |


■後藤弘茂のWeekly海外ニュース■Intel、IDFでAtomプロセッサを正式発表 |
●低消費電力と低コストがAtomの武器
Intelは「Atomプロセッサ(Silverthorne:シルバーソーン)」と、Atomをベースとしたプラットフォーム「Centrino Atom(Menlow:メンロー)」プロセッサテクノロジを正式発表した。現在、上海で開催されているIntelの技術カンファレンス「Intel Developer Forum(IDF)」でアナウンスを行なった。IDFでの発表内容の詳細は後ほどレポートするが、ここでは、現時点で明らかになったAtomの概要をまとめたい。
 |
 |
| Atomのウェハを披露するIntelのアナンド・チャンドラシーカ氏 | Centrino Atomの概要 |
 |
 |
| Atomプロセッサのダイサイズは歴代最小 | AtomとPoulsbo |
Atomブランドは、携帯情報機器向けのSilverthorneだけでなく、Intelが「Nettop」「Netbook」と呼ぶローコストPC向けの「Diamondville(ダイヤモンドヴィル)」にも冠せられる。DiamondvilleはPC向けチップセットとセットになるが、Silverthorneは専用チップセット「Poulsbo(プールスボー)」との組み合わせでCentrino Atomプラットフォームとなる。
 |
| Silverthorneのフィーチャ PDF版はこちら |
 |
| Silverthorne-Poulsboのシステム図 PDF版はこちら |
SilverthorneとDiamondvilleは、どちらもベース機能は共通した製品で、同じダイ(半導体本体)から派生させていると推定される。また、CPUコア自体の元々のコードネームは「Bonnell(ボンネル)」だ。Bonnellコアは、LPIA(Low Power Intel Architecture)としてゼロから開発された最初のCPUコアだ。
Bonnellコアの最大の特徴は、x86 CPUとしては、極めて低い消費電力と低い製造コストを、PCとして使うことができる性能レンジで実現したこと。TDP(Thermal Design Power:熱設計消費電力)は、携帯情報機器向けのSilverthorneで最大2.4W。低消費電力と低コストが2大特長だ。そのため、今までのIntelのPC向けCPUでは届かなかった低消費電力のレンジと、低価格のレンジの製品をカバーできる。
Silverthorneは5製品のSKUで登場する。
| Silverthorneの製品種別 | ||
|---|---|---|
| SKU | Frequency | TDP |
| Z540 | 1.83GHz | 2.4W |
| Z530 | 1.6GHz | 2W |
| Z520 | 1.33GHz | 2W |
| Z510 | 1.1GHz | 2W |
| Z500 | 800MHz | 0.6~0.7W |
Intelは、もともとは1.83GHz版を2WのTDP枠で投入する予定だった。そのため、Silverthorneのうたい文句も、“サブ2W(2W以下)のCPU”だった。だが、製品化が近づいた段階で、TDPは仕切り直しとなり、1.83GHzは2.4Wへとはみ出した。2Wの枠で1.83GHz動作できるSilverthorneが、充分な歩留まりで取れなかった可能性がある。そのため、現在のSilverthorneは“サブ3WのCPU”と、謳い文句も変えられている。
 |
| Silverthorneレイアウト PDF版はこちら |
●マイクロアーキテクチャ面でも新たな情報を公開
Intelは今年(2008年)2月に米サンフランシスコで開催された半導体カンファレンス「ISSCC(IEEE International Solid-State Circuits Conference) 2007」で、Silverthorneのマイクロアーキテクチャの概要や実装を発表した。Intel Developer Forum(IDF)では、より詳細が明らかになりつつある。下のブロックダイアグラム図は、ISSCCで発表されたブロック図をベースに、新たに明らかになった情報を加えたものだ。
 |
| Silverthorne BlockDiagram最新版 PDF版はこちら |
 |
| Silverthorneパイプライン PDF版はこちら |
Intelは、Bonnellコアでは、分岐予測機能を強化したことを明かした。また、命令発行ステージの前に据えた命令キューは、2つのスレッドそれぞれに16エントリとやや深めに確保されていることも明らかにされた。命令スケジューラは、各16エントリのキュー2つから内部命令を各サイクル2つずつ実行パイプに発行することができる。
ちなみに、ISSCCでは、Bonnellコアは、x86命令のLoad-Op-Store命令フォーマットの実行に合わせたパイプラインになっていると説明された。このことから、Bonnellコアでは、x86命令をほとんどそのままの形で内部命令に変換して実行していることがわかる。そのためか、Silverthorneの説明では、内部命令を通例の「uOPs(マイクロオペレーションズ)」ではなく、「OPs(オペレーションズ)」と呼んでいる場合もある。x86命令を細かく砕くのではなく、そのまま1対1変換しているというイメージだと思われる。ただし、ISSCCではuOPsとしており、統一はされていない。そのため、図ではuOPsとした。
浮動小数点/SIMD演算パイプラインでは、演算ユニット群の構成がより明らかにされた。整数SIMD演算では128bitsのSIMD演算を実行できる、2つのSIMD ALUと1つのシャッフルユニットを備える。浮動小数点SIMD演算では、乗算ユニットは64bitsだが、加算ユニットは128bitsになっているという。
この構成では、Bonnellコアは各サイクルにSIMD型の単精度浮動小数点演算を6オペレーション実行できることになる。これは、Pentium M(Banias:バニアス)やPentium 4マイクロアーキテクチャより強力だ。しかし、ISSCCでは、IntelはBonnellコアが実行できる浮動小数点オペレーションは各サイクルに128bits分、つまり単精度4個分だと説明している。この点は矛盾がある。
また、IntelはSilverthorneのパフォーマンスについては、整数演算パフォーマンスを強調する。このことは、Bonnellコアがどちらかと言えば整数演算性能にフォーカスして設計されたことを意味している。ただし、Bonnellコアは、アウトオブオーダ実行によってシングルスレッドの命令並列性を高めるのではなく、インオーダ実行でマルチスレッディング「SMT(Simultaneous Multithreading)」技術を導入することで、マルチスレッド時の性能を高める方向へ向かった。
シンプルなCPUコアで、マルチスレッド性能を高める。Bonnellコアは、こうした現在のCPUの技術トレンドに沿ったCPUマイクロアーキテクチャとなっている。
 |
 |
| Cステートの変移に伴うコア電圧の変化 | HyperThreadingにより消費電力の上昇分以上に性能を向上できる |
 |
 |
| ARMプロセッサとの性能比較 | |
 |
| Silverthorneのthreading PDF版はこちら |
●Silverthorneの2つの顔
BonnellマイクロアーキテクチャCPUには2つの顔がある。1つの顔は、Intel PC向けCPUとしては超低消費電力であるという特色。製品としてはSilverthorneが、主にこの特色を体現する。もう1つの顔は、IntelのPC向けCPUとしては超低コストであるという特色。製品としてはDiamondvilleが、こちらの特色を強く打ち出す。もちろん、低消費電力と低コストは密接に絡み合うため、きれいに2つに特質と製品を分けられるわけではない。しかし、IntelがSilverthorneでは低消費電力にフォーカスし、Diamondvilleでは低コスト低価格にフォーカスしようとしているのは確かだ。
CPUの製造コストの多くを占めるのは、ダイ(半導体本体)とパッケージとテスト。とりわけCPUダイはコストに大きな割合を占めるため、ダイが小さいほど製造コスト的に有利となる。Silverthorne/Diamondvilleのダイは、横7.8mm×縦3.1mmで、ダイサイズ(半導体本体の面積)は約24.2平方mm。デュアルコアの45nm版Core 2 Duo(Penryn 6M/Wolfdale)の107平方mmの約1/4、2個のPenrynを1パッケージに納めたクアッドコアのYorkfield(ヨークフィールド)の214平方mmと較べると約1/8だ。実際には、この上に、さらにMP(Multi-Processor)サーバー向けの大型CPUがある。こうしてダイサイズのチャートを見ると、Intelのx86系CPUのダイサイズのバリエーションは、かつてないほど広がっていることがわかる。それだけ製造コストの幅も広がっている。
ちなみに、Silverthorneのトランジスタ数は、初代Pentium 4(Willamette:ウイラメット)とほぼ同じ。つまり、原理的にはSilverthorneは初代Pentium 4と同レベルの機能と性能をパックできることになる。ムーアの法則の指数関数的伸びが顕著に活かされた例だ。
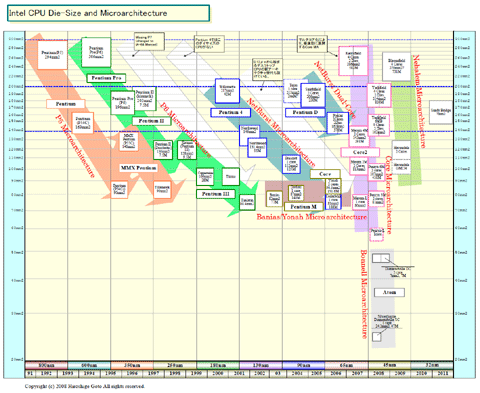 |
| Intel CPUダイサイズ移行図 最新版 PDF版はこちら |
●Silverthorneのコストは10ドルを大幅に下回る
では、実際にSilverthorne/Diamondvilleのコストはどの程度低いのか。これについて、IntelのStacy Smith氏(VP, Chief Financial Officer)が次のように説明している。
「クアッドコアはデュアルコアの約2倍のコスト、Silverthorneコストはデュアルコアコストの約1/4。なので、相対的なコストをクアッドコアと較べるとSilverthorneは約1/8となる。これはCPUだけのコストの話だが」
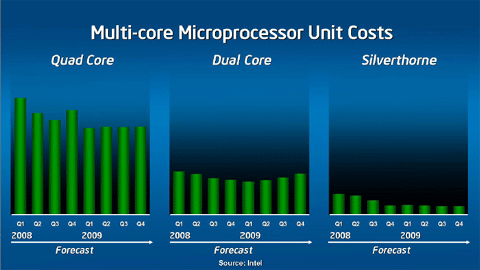 |
| ダイサイズとコストの関係 PDF版はこちら |
上のスライドはSmith氏が3月のInvestor Meetingで示したコストの比較だ。ダイサイズが1/4になると、1枚のウェハから採れるチップ数が増える。IntelのShreekant (Ticky) Thakkar氏(Intel Fellow, Mobility Group, Director, UMG Platform Architecture, Intel Corp)によると、「12インチウェハ1枚から2,000個のSilverthorneが取れる」という。通常のCPUの取れる個数は、1枚のウェハから数百個のレベルなので、Silverthorne/Diamondvilleは桁違いに多い。また、ダイが小さくなると、1個のダイ上に欠陥が含まれる確率が減るため、歩留まりも向上する。
そのため、ダイが1/4になると、1枚のウェハから採れる良品チップの数は4倍以上になる。ダイだけのコストなら1/4を下回るようになる。しかし、ダイが小さくなっても、CPUのパッケージとテストのコストは同じ比率では減らない。そのため、ダイコストの減少ほどは、全体のCPUコストは減らない。平均のコストでは、デュアルコアの1/4という説明は納得できる範囲だ。
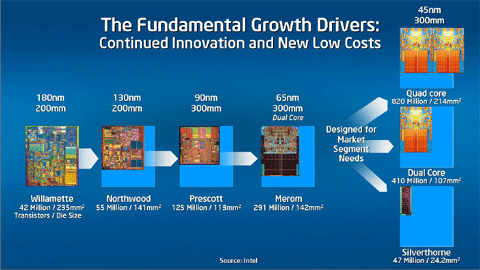 |
| Intel歴代CPUのダイサイズ PDF版はこちら |
45nmのデュアルコアはPenryn 6Mで107平方mm、キャッシュ量を減らしたPenryn 3Mで81平方mm。100平方mm程度のPC向けCPUの製造コストは30ドル前後から30ドル台と言われており、それより小さい3MB版は20ドル台と推定される。そこから逆算すると、Silverthorne/Diamondvilleの製造コストは6~8ドル程度と推定される。つまり、IntelはDiamondvilleをかなり安く売っても、充分にマージンを取ることができるはずだ。
●SilverthorneとDiamondvilleを差別化するIntel
しかも、Intelは、Diamondvilleでは、従来のCPUよりマージンを削る。下がIntelが示した、各CPUの2009年末時点での相対的な製品マージンのチャートだ。CFOのSmith氏によると、クアッドコアは、デュアルコアと較べるとコストも高いが、マージンも9ポイント高くなるだろうという。それに対して、Silverthorneのマージン率は、メインストリームのデュアルコアと較べると11ポイントほど低くなるという。つまり、高コストCPUはより高マージンで、低コストCPUは低マージンということになる。
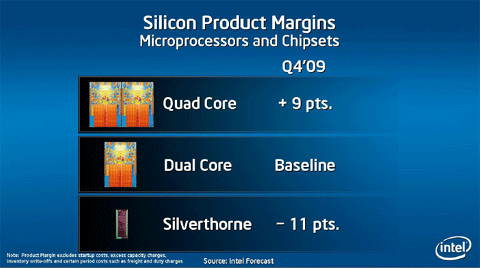 |
| CPU構成によるマージン率の変化 PDF版はこちら |
ここでSilverthorneと説明している中には、Silverthorneより安く売るDiamondvilleも含まれると考えられる。そのため、これは、IntelがDiamondvilleを安売りして行くことが示唆されている。Diamondvilleは多くのケースでは、マザーボード込みで販売されると見られるため、CPU自体のコストは隠されるだろう。しかし、Intelは、Diamondvilleでは競争と市場のニーズのために、低コスト化した分以上に価格を抑えるようだ。
そのため、Intelは携帯情報機器向けに付加価値をつけるSilverthorneと、ローコストPC向けのDiamondvilleでは差別化を行なう必要がある。DiamondvilleもTDPはシングルコアで4W、デュアルコアで8Wと比較的低い。しかし、IntelはDiamondvilleには、C1/C2までの単純な省電力機能しか提供しない。Silverthorneの平均消費電力を下げる要の技術であるC6は、Diamondvilleでは提供されない。Intelは、こうした形で、両者を差別化してゆくと見られる。ブランド的には、単なる「Atom」と、「Centrino Atom」は差別化されることになる。
 |
| DiamondvilleとPineviewの比較 PDF版はこちら |
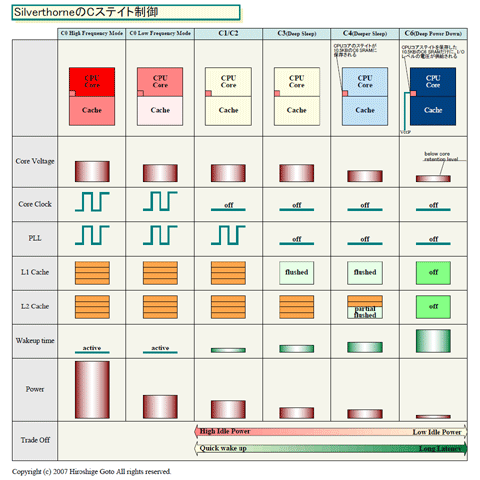 |
| SilverthorneのCステイト制御 PDF版はこちら |
□関連記事
【3月26日】【海外】32nmプロセスの「Westmere」は6コアに
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/2008/0326/kaigai428.htm
【3月10日】【海外】IntelのAtomプロセッサとSoC戦略
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/2008/0310/kaigai425.htm
【3月3日】インテル、Silverthorneの正式名称を「Atom」に決定
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/2008/0303/intel.htm
(2008年4月2日)
[Reported by 後藤 弘茂(Hiroshige Goto)]
【PC Watchホームページ】
PC Watch編集部 pc-watch-info@impress.co.jp ご質問に対して、個別にご回答はいたしません
Copyright (c) 2008 Impress Watch Corporation, an Impress Group company. All rights reserved.