
 |
|


●今後は効率のいいCPUへと向かう
これまで、CPUのパフォーマンスの指標は、一般ユーザーレベルでは、クロック(周波数)だった。だが、近い将来、指標が変わる。「効率×クロック」が、CPUのパフォーマンスを示すようになる。つまり、クロックが高いだけではなく、性能/クロック比も高い、つまり『効率のいいCPU』が、パフォーマンスの高いCPUと認められるようになる。いや、正確に言うなら、CPUメーカーは、そうなるようにユーザーを誘導して行かなければならなくなる。それは、今後のCPUが性能/クロックの向上へと向かうだろうからだ。
もちろん、これまでだって本当はCPUの性能は、クロックだけで測れたわけではない。しかし、エンドユーザーにわかりやすくするため、CPUメーカーは意図的にクロックを前面に押し出してきていた。特に、その時点でクロックで勝るメーカーは、クロックがすべてみたいなマーケティングをこれまで行なってきた。また、CPUのアーキテクチャも、P6系(Pentium Pro/II/III/Celeron)とPentium 4系のように、クロックの向上にフォーカスしたものへと向かう傾向があった。その結果が、昨年のGHz戦争だったりしたわけだ。
だが、Intelは先週のカンファレンス「IDF」で、明確に違う方向性を示し始めた。IDFでIntelが説明したのは、将来もCPUクロックは上がってゆくが、それ以上に、性能/クロックや性能/消費電力を上げるというストーリーだ。
その1つはマルチスレッディングで、この技術のアドバンテージは、基本的にCPUの実行ユニットなどリソースを効率よく働かせることにある。つまり、性能/クロックが高い=同じクロックでもパフォーマンスが優れたCPUを作ることができるようになる。よりアグレッシブなスペキュレイティブスレッディングなんかをやって行けば、ますますその傾向は強まる。
もう1つは次期モバイルCPU「Banias(バニアス)」で、こちらは性能/消費電力を引き上げることに注力する。性能/消費電力を高めるために、Baniasもやはり性能/クロックのいいアーキテクチャになっていると見られる。また、次期IA-64プロセッサ「McKinley(マッキンリ)」でも、Intelは同様に性能/クロックの向上を追求する姿勢を見せた。そう、どこを向いても、これまでのような「GHzがすべて」的なアプローチが見えないのだ。一体、Intelは、どうしてしまったのだろう。
いや、これはIntelだけの話ではない。AMDも同じように性能/クロックを前面に押し出そうとしている。AMDは、次期Athlon(Palomino:パロミノ)の投入と合わせて、CPUを実クロックで示さないスタイルに変えようとしているという。IntelといいAMDといい、なぜここへ来て、CPUの効率をテーマにし始めたのだろう。
●CPUの最大の敵『熱』に対抗するためアーキテクチャを変革
まず、Intelの方は、CPUの設計上の制約から変わろうとしている。それは、熱のせいだ。熱が、CPU設計の最大の壁になり始めたからだ。
2月に米サンフランシスコで開催された半導体学会「2001 ISSCC (IEEE国際固体回路会議)」で、Intelのパット・ゲルシンガー副社長兼CTO(Intel Architecture Group)は、今後のIntel CPUの大きな方向性を示した。そのなかで、ゲルシンガー氏は、今後は消費電力が最大のチャレンジになると指摘し、性能/消費電力を高めるアーキテクチャをIntelが推進して行くことを明確にした。同氏によると、これまで、30年間、CPUの進化の制約は、単純に製造コストと製造技術上のものだけだったという。しかし、これからは熱を征するものが、CPUのパフォーマンスを上げ続けることができるようになるそうだ。
CPUの“熱”と一口に言っても、いろいろなスペックがあるわけだが、ゲルシンガー氏が最大の問題と指摘したのは電力密度(Power Density)だ。これは、特に、0.13μm以降のプロセスでは、大変な問題になる。というのは、微細になるにしたがって、CPUの電力密度が上がってしまうからだ。ISSCCのプレゼンテーションでは、0.10μm世代のプロセッサの電力密度は約90W/平方cm、消費電力は約210W程度になるという。今の世代のCPUの電力密度は、Athlonでも最大60W/平方cm程度。それでも“燃える”のだから、90W/平方cmといったら悪夢のような状態になる。さらにその先の0.07μmあたりになると、もうハンドルできる限界を超えてしまう。つまり、CPUの熱は、あと2~4年で現行技術で対処できなくなってしまうのだ。
この熱の問題に対する答えが、性能/クロックと性能/消費電力を引き上げることだ。IntelのCPUアーキテクチャを担当するアーキテクトたちは、少なくとも数年前にはそういう結論に達していたと思う。それが、現実的な構想となって示されたのが、今回のIDFだったというわけだ。
●IntelのマーケティングとR&Dのギャップ
例えば、マルチスレッディング技術の応用を押し進めれば、CPUのリソースを有効に使い、クロック当たりに実行できる命令数を増やせるようになる。そうすれば、熱の発生源であるロジックトランジスタをあまり増やさなくても性能を上げることができるようになる。
McKinleyも、先週のこのコラムでレポートしたとおり、クロックの向上よりも効率を上げることに力点を置いた設計になっているように見える。パイプラインの切り方は、非常に控え目で、そのために、McKinleyは0.18μmでターゲット1GHzという大人しいクロックとなっている。CPU関連に詳しいライターの渡辺玲氏はその理由を「プロセッサの性能のためといったレベルではなく、クロックを上げると熱が上がり過ぎるといった問題が判明したため、こうしたアーキテクチャを取った可能性がある」と指摘していた。おそらく、これは当たっていると思う。
McKinleyのマイクロアーキテクチャは、0.13μmはもちろん、0.10μm世代にも使われるだろう。0.10μmプロセスでは、電力密度は巨大な問題になる。それを未然に防ぐために、クロックよりも効率を重視したアーキテクチャになったのかも知れない。いずれにせよ、この方向へIntel CPUが向かっているのは確かだ。
このように、IntelのCPU開発やCPUアーキテクチャのR&Dは、すでにクロックより性能/クロックを高める方向へ向かっている。ところが、Intelのマーケティングサイドは、まだGHzを前面に押し出している。ここには、ギャップが見える。
もっとも、これは当然で、マーケティングや営業のスタッフが、今盛り立てなければならないのはPentium 4で、その利点は高クロックだからだ。つまり、時間的なズレがあるわけだ。しかし、Intel CPUがどんどん世代交代してゆくと、Intelのマーケティングも、クロックではなくクロック×効率を強調する方向に変わって行かざるをえない。
例えば、Intelの最初のマルチスレッディング技術「Hyper-Threading」をインプリメントしたデスクトップ版Pentium 4が登場したとする。このCPUは、同じクロックで、これまでのPentium 4より最大30%性能が高くなる。これを説明するために、Intelはうまいマーケティングプログラムを立ち上げる必要が出てくる。
●AMDはマーケティング上の必要性から
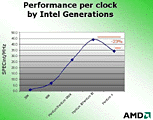 |
| Pentium 4のクロック当たりのパフォーマンスの低さを訴えるAMDのプレゼンテーション(投資家向け情報より) |
IntelのPentium 4は、4月以降、2回も地滑り的な値下げを重ね、かつてない低価格になっている。そのため、AMDが同クロックのPentium 4にAthlonの価格を合わせると、Athlonをとんでもない安売りをしなければならなくなってしまう。例えば、AMDがPalominoで1.533GHzを出しても、Pentium 4 1.5GHz価格に合わせるなら130ドル程度で売らなくてはならない。そうすると、AMDのCPUのASP(平均販売価格)がさらに下がってしまう。
チップベンダーにとって、ASPの変動は死活問題だ。今以上にASPが下がると、AMDはまた干上がってしまう。いちばん高価格なCPUが130ドルでは、ASPは地に落ちてしまう。だから、AMDはPalominoを同クロックのPentium 4より高い価格で売らなくてはならない。そのためには、AthlonのPentium 4に対する優位点である、性能/クロックを前面に打ち出し、例えば、Palomino 1.53GHzがPentium 4 1.7GHzに匹敵するといたことを、エンドユーザーに認識させなければならない。つまり、AMDはマーケティング上の理由から、性能/クロックにフォーカスし始めたのだ。
このように、IntelとAMDは、それぞれまったく逆の理由から、CPUの効率にフォーカスし始めた。理由はどうあれ、トレンドは確実に変わりつつある。
(2001年9月5日)
[Reported by 後藤 弘茂]