 |


■後藤弘茂のWeekly海外ニュース■45nmプロセスで展開するIntelのモバイルクアッドコアCPU |
●45nmプロセスの強みが活きるIntelのモバイルCPU
Intelは、いよいよ45nmプロセスのCore Microarchitecture(Core MA)群を投入し始めた。今回、Intelがリリースしたのは、サーバー&ワークステーションとハイエンドデスクトップのセグメントだが、45nmの利点がより明瞭なのはモバイルだ。45nmプロセスでは、High-kとメタルゲートの新材料の組み合わせによって、リーク電流(Leakage)が抑えられるからだ。
実際、Intelの製品計画を見ても、45nmプロセスへのシフトはモバイルCPUの方がずっと急ピッチだ。来年(2008年)の第3四半期までには60%以上が45nmへとシフトする計画となっている。明らかにデスクトップよりモバイルに、重点的に45nmを投入する。また、45nmシフトの効果も明瞭だ。Intelは、45nmプロセスでメインストリームモバイルCPUのTDPを35Wから25Wへと下げる。また、ノートPC向けでは初のクアッドコアCPUをハイエンドに投入する。
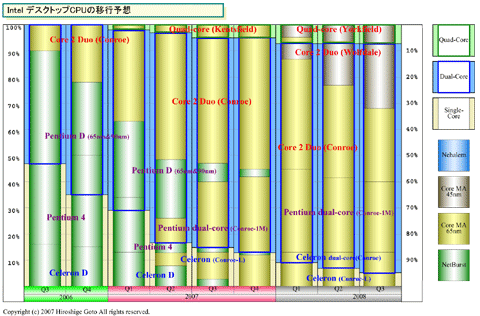 |
| Intel デスクトップCPUの移行予想 ※別ウィンドウで開きます PDF版はこちら |
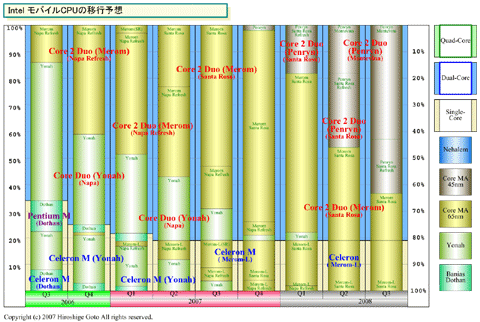 |
| Intel モバイルCPUの移行予想 ※別ウィンドウで開きます PDF版はこちら |
Intelは来年第3四半期に、ノートPC向けクアッドコアCPU「Penryn QC(ペンリンクアッドコア)」を投入する。IntelはPenrynベースのデュアルコアのCore 2 Extremeも提供するが、次のステップでクアッドコアのPenrynを導入する。
Penryn QCは、デスクトップのクアッドコア「Yorkfield(ヨークフィールド)」と同様に、2個のPenrynダイをパッケージ上で統合したMCM(Multi-Chip Module)だ。電力消費は当然大きくなるが、TDP(Thermal Design Power:熱設計消費電力)は45W(Intelの保証するレンジ)と、ほぼ現在のモバイル系「Core 2 Extreme」と同レベルに止める。
PenrynベースのCore2 Extremeは、「Montevina(モンテヴィーナ)」プラットフォームで3.06GHz(FSB 1,066MHz)の予定。クアッドコアのPenryn QCは、それよりは動作周波数を下げる必要があると推測される。電力のうちスタティックなリーク電流だけでなく、アクティブ成分も下げる必要があるからだ。いずれにせよ、Core 2 ExtremeとPenryn QCは、IntelのモバイルCPUとしては、もっともホットなCPU系列だ。
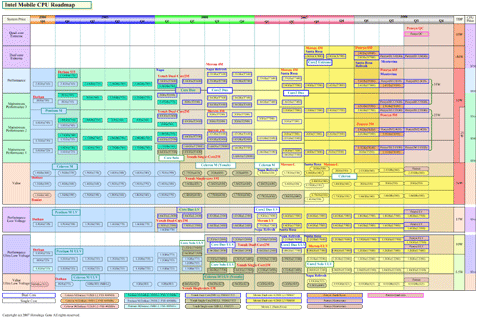 |
| Intel モバイルCPUロードマップ ※別ウィンドウで開きます PDF版はこちら |
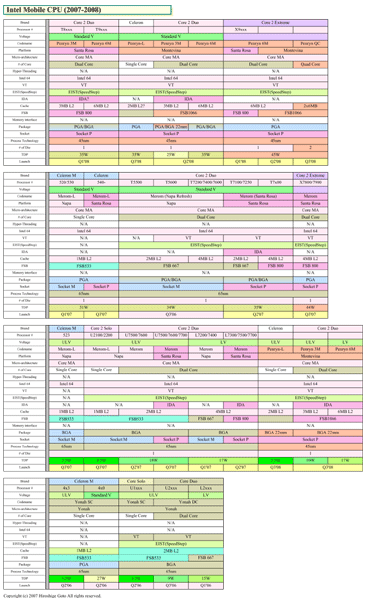 |
| Intel モバイルCPU(2007-2008) ※別ウィンドウで開きます PDF版はこちら |
●位置付けが異なるモバイルのクアッドコア
Penryn QCの平均消費電力は3~4Wと、これもIntelのノートPC向けCPUとしては大きい。ダイ(半導体本体)温度の指標「Tj(junction)」の最大値は100度とされており、通常電圧版の105度より低い。それだけサーマルバジェットが少なく、冷やしにくいことを示している。
Penryn QCでは、2個のPenrynのダイが4mmと狭い間隔で配置されている。これは、ヒートスプレッダを介さずに提供されるモバイルでは、ダイ間隔が狭い方が、冷却機構をアタッチしやすいという事情からだという。その分、サブストレート上の配線は難しくなる。パッケージはPGA478のみ、ピン配列はSocket Pで、通常電圧版Core 2 DuoのSocket PのPGAと互換性がある。
Penryn QCは、Core 2 Extremeラインのパフォーマンスオリエンテッドなエンスージアスト市場に特化した製品で、価格もそれに応じたエクストリーム価格となる見込みだ。出荷量も極めて限られる。デスクトップのようにクアッドコアCPUがパフォーマンスセグメントの価格帯で、ある程度のボリューム出荷されるわけではない。
Penryn QCは、明らかにクアッドコアNehalem導入への地ならしだ。Intelは2009年にはネイティブクアッドコアのNehalemをモバイルにも投入する。Intelは今後も各セグメントのTDPレンジは維持されると示唆しているため、Nehalemも同じ45W枠に収められると推定される。
ただし、Nehalem世代ではCPUの消費電力自体の意味も変わってくる。ノースブリッジ機能がCPU側に統合されるため、システム全体の消費電力の中でCPUのダイが占める割合が増えるからだ。AMD側が常に主張していることだが、ノースブリッジ統合型CPUの消費電力は、「単体CPU+ノースブリッジチップ」の組み合わせの電力と比較する必要がある。おそらく、Nehalem世代では、AMDに続いてIntelもそう主張するようになるだろう。Penryn QCとMontevinaのチップセットCantiga(カンティーガ)を合わせた電力と、Nehalemの電力を比べることになるだろう。
CPUに取り込まれたノースブリッジブロックは、外部FSBを必要としない分、単体のノースブリッジチップより電力消費が少なくなる。Intelは、その分、Nehalemコアの電力を引き上げる余地ができる。
●歴史は繰り返されるIntelのTDPロードマップ
Intelは現在、モバイルCPUを大きく分けて5レンジのTDPで提供している。エクストリームデュアル(&クアッド)コアの45W、通常電圧版デュアルコアの35W、LV(低電圧)版デュアルコアの17W、ULV(超低電圧)版デュアルコアの10W、ULV版シングルコアの5.5Wの5階層だ。
IntelモバイルCPUのTDPには、ごく簡単な法則がある。通常電圧版に対して、LV版は約半分のTDP、ULV版デュアルコアはLV版のおよそ58%のTDP、ULV版シングルコアはULV版デュアルコアの55%のTDPとなっている。誤差を大目に見れば、大まかに言って通常電圧版から下は1階層毎にTDPがおよそ半分強に減少して行く。通常電圧版を1とすると、LV版が1/2、ULV版が1/4のイメージだ。
一方、同じCPUコア数の場合の動作周波数は、TDPの減少比率の平方根に近い数字となる。つまり、1階層で50%台にTDPが下がると、動作周波数はおよそ70%台に下がる。消費電力の低減の方が比率が大きいのは、電圧の低下分が2乗で消費電力に効いているからだ。そのため、TDPに対するパフォーマンスの比率は、下のTDP CPUになるにつれて30%前後ずつ上昇する。下のCPUであればあるほど、電力的に魅力の大きなCPUとなる。
IntelモバイルCPUのTDPレンジは、Pentium M(Banias:バニアス)導入以降拡大の一途をたどっており、トップTDPのCPUとボトムTDPのCPUの差はどんどん広がっている。45WのCore 2 Extreme系と、5.5WのULV版の差は8倍だ。そして、差が広がると、その間隙を埋めるTDPレイヤが設定される。
今回の場合は25W枠で、IntelはMontevinaプラットフォームで25Wの通常電圧版を導入する。Montevinaでは、6MB L2キャッシュのデュアルコアのPenryn 6Mが2.53~3.06GHzで現在通りの35W枠で投入される。しかし、小容量L2キャッシュ版のPenryn 3Mは2.13~2.53GHzで25Wとなる。ちょうどボリュームゾーンにあたる、大量に出荷される価格レンジのメインストリームCPUが25Wになるわけだ。
これまで、モバイルCPUは、小容量L2キャッシュ版や低周波数版も、トップビン(最上級)のTDPレンジである35Wに設定されていた。しかし、実力的には、低パフォーマンス版のTDPは25Wに設定しても動作するチップが本当は多数あったはずで、今回はそうした実態に合わせたのかもしれない。ちなみに、MontevinaではIntelは3MB SRAM版を25Wとするが、SRAMはリーク電流(Leakage)は大きいもののTDPに対する影響は相対的に小さい。6MB SRAM版でも25Wを提供できない理由はそれほど大きくないため、将来的には6MBの25Wも出てくるかもしれない。
Penryn 25Wは一見新機軸に見えるが、振り返って見ると2003年の最初のBaniasのTDPはまさに24.5Wで、Penryn 3M Montevinaと同じレンジだった。2003年のラインナップに重ねると、25W帯のBaniasのTDPレンジをPenryn 3M Montevina、35W帯のMobile Pentium 4-MのレンジをPenryn 6Mが引き継いでいることがわかる。45W帯のCore 2 Extremeに相当する枠は2003年には存在しないが、この時はデスクトップCPUの転用が実質このレンジをカバーしていた。長いスパンで見ると、Intelは同じTDPの帯でノートPC向けCPUを提供し続けている。
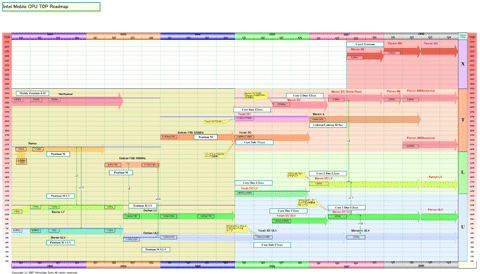 |
| Intel モバイルCPU TDPロードマップ ※別ウィンドウで開きます PDF版はこちら |
●チャレンジの大きなNehalemのモバイルへの投入
では、このTDP帯がNehalem世代も継続され、NehalemがメインストリームCPUに入ってくるとどうなるのか。現在のCore MAは、メインストリームをターゲットに、前世代のNetBurstと同程度のCPU規模で、しかもより低い消費電力で登場した。そのため、モバイルにはすんなりフィットした。
それに対して、Nehalemは見るからにサーバー&ワークステーション&ハイエンドデスクトップにフォーカスしている。CPUコアのサイズも、Core MAより1.5x倍程度大きい。当然、Nehalemはロジック部分のトランジスタが多いため、原理的にはよりTDPが高くる。つまり、NehalemアーキテクチャのモバイルCPUは、ハードルが非常に高い。
もっとも、Intelのモビリティ部門が、メインストリームへのNehalemアーキテクチャの導入を先送りし、Penryn系を使い続けるのなら、また話は微妙に違ってくる。IntelにはPenrynにGPUを統合する選択肢もある。ただし、IntelはモバイルにもNehalemアーキテクチャが入って来ると言っている。
Nehalemはノースブリッジの統合という、消費電力上の利点を持っている。また、Nehalem世代になると、メインストリームの製品ではGPUコアもCPU側に含まれるようになる。今年(2007年)の夏前の段階では、モバイルではデスクトップに先行してGPU統合版Nehalemが投入される計画になっていた。GPUコアの分、CPUのTDPレンジは上がり、より局所的に冷やす必要が出る。
GMCHがラフにいって10W以上。それが25から35WのCPU本体にプラスされると計算すると、大まかに言って35~47W程度のTDPになる。これが、GPU統合のNehalemのTDPレンジだと推定される。もっとも、CPUコア部とGPUコア部が同時にビジーになるとは限らない。GPU統合CPUの場合、例えばGPU部が比較的ライトな処理の場合には、よりCPUの電力消費を上げることができるかもしれない。ただし、そのためには、CPUとGPUそれぞれのコアのホットスポットの熱を効率よく分散させる必要がある。
●やや大きめとなるGPU統合のNehalemのダイ
ちなみに、Nehalemのデュアルコア版とGPU統合版のダイサイズは、クアッドコア版からある程度予想ができる。クアッドコアNehalemのダイから、CPUコアを2個取り去り、QuickPath Interconnect(QPI)を片側だけ、DRAMコントローラを2/3のサイズに、ノースブリッジを半分、キャッシュを3~4MBに押さえたとすると、ラフに言って140~160平方mm程度のダイサイズになると推定される。もし、クアッドコアのNehalemが2コアで共有するL2と4コアで共有するL3の階層を持っているのなら、デュアルコア版ではキャッシュ階層も減らせるだろう。
GPU統合版Nehalemの場合は、GPUコア分のダイエリアがさらに加わる。GPUコアは、100平方mm前後のGMCHのダイの60~70%を占めている。おおまかに言って60~70平方mmのダイエリアとなる。しかし、GPUコアは通常、CPUより1世代古いプロセスで製造されている。これをCPUと同じプロセスに移すと、3x~50平方mm程度のダイエリアに収まることになる。
もっとも、時代とともにGPUパフォーマンスを上げなくてはならないため、GPUコアを強化する必要がある。それでも、2倍になることはないだろう。GPUコアが40~60平方mmだと仮定して、デュアルコアのNehalemに加えると、約200平方mm前後のダイとなる。もし、IntelがCPUとGPUをMCMで搭載するとしたら、チップ間インターフェイスを加える必要があるので、合計ダイサイズは、やや大きくなる。また、MCMならGPUコア側は65nmプロセスで製造する可能性もあり、その場合も合計ダイサイズが大きくなる。とはいえ、メインストリームへ投入するためには、IntelはGPU統合のダイを200平方mm前後か、それ以下に抑える必要がある。
こうした試算から見えるのは、45nmプロセスではGPU統合CPUを本格的にバリューCPUのレンジに入れることは難しいということだ。32nmプロセスになれば、ボトムエンドまでのCPUを、GPU統合に持って行くことはできるだろう。
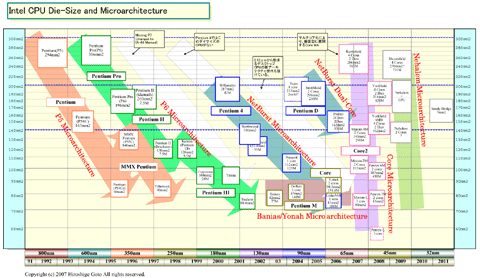 |
| Intel CPUダイサイズとアーキテクチャ ※別ウィンドウで開きます PDF版はこちら |
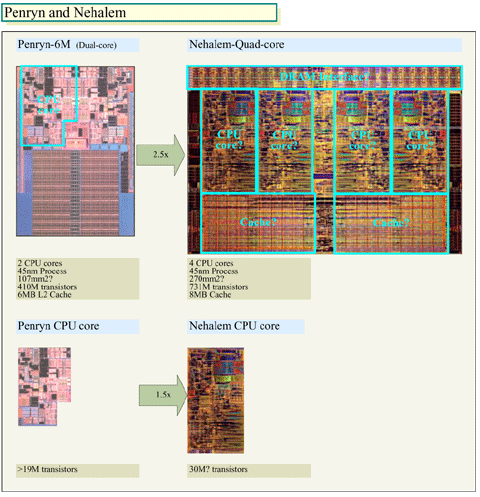 |
| PenrynとNehalemのダイ比較 ※別ウィンドウで開きます PDF版はこちら |
□関連記事
【11月12日】Intel、45nmプロセスのプロセッサを正式発表
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/2007/1112/intel.htm
【11月9日】【海外】2008年中に95%をデュアルコアにするIntel CPUロードマップの秘密
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/2007/1109/kaigai399.htm
【10月26日】【海外】Intel版「8x4」で広がる2008年のCPUロードマップ
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/2007/1026/kaigai397.htm
(2007年11月14日)
[Reported by 後藤 弘茂(Hiroshige Goto)]
【PC Watchホームページ】
PC Watch編集部 pc-watch-info@impress.co.jp ご質問に対して、個別にご回答はいたしません
Copyright (c) 2007 Impress Watch Corporation, an Impress Group company. All rights reserved.