 |


■笠原一輝のユビキタス情報局■新ブランド戦略に隠されたIntelの狙い |
Intel Developer Forum(IDF)は、すでに2日間の日程を終了し、残るは最終日のみとなっている。ところで、今回のIDFのテーマを読者の皆さんはご存じだろうか? 今回のIDFで、Intelの幹部が盛んに繰り返しているのが、そのテーマの一部にも採用されている“プラットフォーム”という言葉だ。
Intelの幹部が“プラットフォーム”という言葉を繰り返す背景には、1月の組織変更により、各事業本部がデスクトップPC、PCサーバー、モバイルPCといった製品ベースの体制から、デジタルホーム(コンシューマ向け)、エンタープライズ(企業向け)、モビリティ(モバイル向け)といったプラットフォーム別の体制に変更されたことがある。
そして、今回のIDFで明らかになったことは、事業本部だけでなく、今後の製品展開も“プラットフォーム”をベースにしていくというIntelの強い意志だ。
●“Pentium Extreme Edition”や“Pentium D”というブランドネームの謎
筆者が今回のIDFで“あれ?”と思ったことの1つ目が、“Smithfield”の開発コードネームで呼ばれてきたデュアルコアCPUのブランドネームの発表だ。Intelは、昨年からデュアルコアCPUの重要性を強調してきた。“デュアルコアにあらずばPC用のCPUにあらず”のような勢いで、2006年にはサーバーからノートPCまで、すべてのセグメントでデュアルコアCPUを導入する。そのSmithfieldは、Intelにとって大変重要な製品であることに疑いの余地はない。
ところが、そのSmithfieldのブランドネームである“Pentium Extreme Edition”(以下Pentium XE)、“Pentium D”はいずれも、実に静かに発表された。通常であれば、新しいブランドネームが発表されるときには、かなり大々的な発表が行なわれるものだし、間違いなくキーノートスピーチの中で、クレイグ・バレット氏やポール・オッテリーニ氏のような上級幹部が高らかに発表する……というのが常識だろう。
だが、実際にはPentium Extreme Edition、Pentium Dの発表は、一部の報道関係者だけが集まる記者説明会の中で発表された。Intelは初日に「Intel Multi-Core Briefing」という記者説明会を開催し、その中でSmithfieldのブランドネームを発表したのだった(その模様は後藤氏の記事を参照してほしい)。
そして、もう1つ“あれ?”と思ったことは、その名前だ。考えてみれば、Pentium XE、Pentium Dともにおかしな名前だ。両製品とも、Pentium 4 Extreme Edition(以下Pentium 4 XE)、Pentium 4の後継製品であり、その流れから言えばPentium 5 Extreme Editionとか、Pentium 5とか、あるいはPentium 64(いやいやこれは無いか……)とか、そんな名前になってもおかしくない。なのに、なぜ数字が消えて先祖に戻ったようなPentium XEであり、地味なPentium Dなのだろうか?
こうしたことを疑問として考えているうちに、筆者は1つの結論に至った。ああ、そうか、IntelはデスクトップPC向けのCPUブランドネームの重要性を1ランク下げたのだ、と。
●Pentium DとPentium Mの違いは“D”と“M”の違いだけ
前出の疑問を解く鍵は、Pentium XEとPentium Dのロゴマークに隠されている。以下がPentium XEとPentium Dのロゴマークだ。
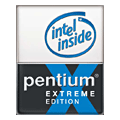 |
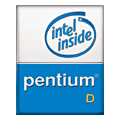 |
 |
| Pentium XEのロゴマーク | Pentium Dのロゴマーク | Pentium Mのロゴマーク |
これらのロゴをまじまじと見ているうちに、これはPentium Mのロゴと同じレベルに位置づけられているのだな、と気づかされたからだ。
見てわかるように、Pentium Dとの違いは、MとDというアルファベットの違いでしかない。Pentium XEの方は、若干豪華仕様で、Xの文字と黒が使われているが、いずれにしても地味なロゴであることは間違いない。
そもそも、これまでIntelはデスクトップPCの世界では、パフォーマンス向けのPentium 4にはオレンジ系の色をベースにした色を、バリュー向けのCeleronにはIntelのコーポレートカラーでもあるブルー系の色を利用してきた。ところが、今度のPentium Dではブルーをベースにした色に変更されている。
ちょっと話を脱線するが、Intelの製品ロゴには、実は厳しいガイドラインがある。各国のオフィスなどがこうしたロゴを利用したノベルティなどを使うときには、RGBの色要素の細かい規定があるという。Intelとしてはそれほど製品ロゴの色にこだわりを持っているのだ。
ついでにもう1つ脱線しておくと、この製品ロゴ色の選定には、Intelはかなり神経質になっている。というのは、実は昨年ひっそりとCentrinoのロゴの色が変えられるという“事件”があったからだ。最近のCMTのロゴは以下の色になっているが、2003年3月のリリース当時の色と比べると微妙にピンク色が濃くなっている。
 |
 |
| Centrinoモバイル・テクノロジのロゴ | 以前のCentrinoモバイル・テクノロジのロゴ |
こちらの記事にある発表時のCMTのロゴと比べて見てほしいのだが、明らかに今のものと比較してロゴの色が異なることがわかる。
Intelの関係者はその理由に関して口をつぐむのだが、ある業界関係者によれば、どこかの国で、その色が何らかの理由で問題になり変更されたのだという。
話を戻すと、Intelのマーケティングでは、このロゴの利用に関しては非常に注意深く行なっているし、Intelのブランド戦略は、世界中の企業から賞賛されるくらいきっちりとしたものだ。そうしたIntelが発表した、今回のPentium XEやPentium Dのロゴには、何らかのメッセージが含まれていると考えてしかるべきだろう。
●プラットフォームブランドに前向きな答えをするIntel幹部
ここまで読んできた方は、すでに答えがわかったはずだ。理由は、Pentium Dというブランドのポジションが、Pentium 4のようなトップレベルから、Pentium Mと同じくらいのセカンドレベルに引き落とされた、ということだ。
これまで、Intelのコンシューマ向けのトップレベルブランドは、Centrinoモバイル・テクノロジとPentium 4だった。よく知られていることだが、OEMメーカーが広告を出稿する際に、Intel製品のロゴを出すことで、広告費の一部をキャッシュバックするIPP(Intel Inside Program)におけるキャッシュバック率は、CentrinoやPentium 4というトップレベルのブランドと、Pentium MやCeleronのようなセカンドレベル、サードレベルのブランドでは異なるという。
要するに、広告にCentrinoやPentium 4を出せば、よりたくさんキャッシュバックしてもらえるし、Pentium MやCeleronではあまりキャッシュバックしてもらえないということだ。このことからもわかるように、Intelは製品のブランドにランクをつけ、そのプロモーションにかける費用に差をつけている。
では、Pentium XEやPentium Dがセカンドレベルのブランドだとして、トップレベルのブランドはどうなるのか? これも、ここまで読んできた人は、すでに答えがでているだろう。デスクトップでも、Centrinoモバイル・テクノロジに相当するような、プラットフォームレベルのブランドネームが用意される、そういうことだろう。
実際、Intelの幹部たちは、プラットフォームのブランド名をつけるのかという質問に対して、明らかに前向きな答えをしている。たとえば、エンタープライズ事業本部のアビ・タルウォーカー副社長は「それはよい質問だ。もちろん、そういう可能性はあるが、現時点では何も決まっていない」と発言したし、同じくエンタープライズ事業本部のパット・ゲルジンガー上級副社長などは「これまでは、CPU、チップセットなどのコンポーネントレベルで認識してもらってきたが、人々はプラットフォームレベルで製品を認識するようになるだろう」とまで発言している。
これを聞けば、もうプラットフォームにブランド名がつかないと考える方が無理だ。
●日本のユーザーにとって歓迎してよいプラットフォームレベルという考え方
そして、もう1つの証拠は、今回ゲルジンガー上級副社長が発表したエンタープライズ事業本部のロードマップも、ショーン・マローニ上級副社長が発表したモビリティ事業本部のロードマップも、ドナルド・マクドナルド副社長が発表したデジタルホーム事業本部のロードマップも、プラットフォームのコードネームが含まれていた。
たとえば、クライアントのプラットフォームのコードネームをまとめてみると、以下のようになる。
 |
| Intelのクライアント向けプラットフォームロードマップ(07年に関しては筆者予想) |
重要なことは、各ジェネラルマネージャが発表したコードネームの表では、プラットフォームのコードネームが、CPUやチップセットよりもフォントのサイズが大きかったことだ。もちろん、これはプラットフォームこそが製品を認識するものになるというIntelの意思の表れだと考えられる。
 |
 |
| デジタルホーム事業本部のロードマップ、デスクトップPCのプラットフォームのコードネームが、CMTを意味する“Sonoma”や“Napa”と同列であることに注目 | エンタープライズ事業本部のデスクトップPCロードマップ |
こうした傾向は、日本のユーザーとしては、歓迎してよいものだ。たとえば、マクドナルド副社長の基調講演では、Yonahを利用した超小型デスクトップPCがデモに利用された。重要なことは、これがIntel自ら提案していると言うことだ。これまで、筆者はIntelの幹部にことあるごとに「BaniasのラインをデスクトップPCに持ってきたらどうか」という質問をしてきた。多くのIntel幹部は判を押したように「いやいや、もちろんOEMメーカーが望めば、そういう製品を作ることは問題ありません」と述べてきた。
だが、Intel自ら積極的にBaniasのラインをデスクトップPCに持ってくるという提案をしたことはなかった。言うまでもなく、そうはいっていても本音の部分では世界市場を見れば、NetBurstマイクロアーキテクチャベースのCPUの方がデスクトップPCには適していると考えていたからだろう。
だが、今回、その殻を破り、Intel自らが、そういう提案をしてきた。つまり、Intel自身としても今後のデジタルホームにはそうした製品が必要だと考えてきたからだろう。確かに、日本の動向と比べれば明らかに遅いことには違いないが、それでもよい傾向であることは間違いない。
●デジタルホームとエンタープライズで違うコンポーネントを採用する可能性も
プラットフォームごとの製品化という意味では、将来のNetBurst系からBanias系への移行という意味でも、大きな意味があるかもしれない。
デジタルホーム事業本部 ジェネラルマネージャのマクドナルド副社長は、「我々デジタルホーム事業本部は、直接CPUやチップセットを開発しているわけではない。従って、エンタープライズ事業本部やモビリティ事業本部の顧客となり、製品を“買う”という立場になる。だから、デジタルホームの実現にとって、その時々によい製品を選択していく」と発言している。
つまり、デジタルホーム事業本部としては、顧客がどんな製品を要求しているかによって、エンタープライズ事業本部が開発しているSmithfieldやPreslerのようなNetBurst系のコアを選択する場合もありうるし、逆にDothanやYonahのようなBanias系のコアを選択する可能性もあるということだ。
OEMメーカーの関係者は、IntelがYonahの後継として計画しているMeromの世代で、Banias系のコアがデスクトップPCにも採用されると説明していると証言するが、こうしたプラットフォームごとの製品体系を採用したことで、たとえばデジタルホーム事業本部の方はMeromに移行した後でも、エンタープライズ事業本部の方はもう少しNetBurst系で引っ張るということがあってもいいのではないだろうか。
今回のIDFでは、2005年と、2006年のプラットフォームに関しては発表されたが、2007年のプラットフォームに関しては何も発表されなかった。デジタルホームも、エンタープライズもプラットフォームのコードネームこそ異なるが、いずれも構成されているコンポーネントは同じものとなっている
だが、モバイルで言うところのSanta Rosaに相当する、デジタルホーム事業本部とエンタープライズ事業本部の2007年のプラットフォームが、どんな内容になるのか、興味が尽きないというところではないだろうか。
□関連記事【3月3日】【海外】間に合わせ的なIntelのデュアルコアCPU
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/2005/0303/kaigai161.htm
【2月28日】IDF Spring 2005 前日レポート
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/2005/0228/idf01.htm
【1月19日】Intel、「Sonoma」こと新Centrinoプラットフォームを正式発表
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/2005/0119/intel1.htm
【2003年3月12日】Intel、「Centrinoモバイル・テクノロジ」を正式発表
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/2003/0312/intel1.htm □バックナンバー
(2005年3月4日)
[Reported by 笠原一輝]
【PC Watchホームページ】
PC Watch編集部 pc-watch-info@impress.co.jp 個別にご回答することはいたしかねます。
Copyright (c) 2005 Impress Corporation, an Impress Group company.All rights reserved.