 |
|


■元麻布春男の週刊PCホットライン■新年早々の業界の動きから |
●Rambusとソニー陣営の提携
1月も成人式を過ぎると、お正月気分も終わり仕事に本腰を入れるころだ。しかし、長期のお正月休みのない(その代わりにクリスマス休暇があるわけだが)海外からは、一足先にニュースが飛び込み始めている。今回は、こうしたニュースの中からいくつかをピックアップしてみようと思う。
まず、1月7日に飛び込んできたのが、Rambusがソニー、ソニー・コンピュータエンタテインメント(SCE)、東芝の3社と技術ライセンス契約を締結したというものだ。上記3社がライセンスするのは、将来の高速メモリインターフェイスとして「Yellowstone」のコード名で開発中の技術と、ロジックチップ間の相互接続技術として「Redwood」のコード名で開発中の技術。「Cell」という開発コード名で呼ばれている、3社が共同開発中のチップ(将来のPlayStation 2後継機に使われるとか、ゲームサーバに使われるといわれているプロセッサ)に使われるものと思われている。
ちなみにCellに用いるYellowstone技術を用いたDRAMだが、これについては昨年10月に東芝はすでにライセンス契約を締結している。汎用DRAMからは撤退した東芝だが、PS2向けのDirect RDRAMの生産と供給は続けており、ダイサイズの縮小にも継続的に取り組んでいる。
Emotion EngineとRDRAMがどれくらいシュリンクされたかというと、最初のPS2に使われていたものを示しており、それぞれダイサイズは225平方mmと107平方mmであった。それが、111平方mmと67平方mmにそれぞれシュリンクされている、今ではEmotion Engineが75平方mm、RDRAMが40平方mmまで縮小されており、PS2本体の低価格化に貢献していることが示されている。
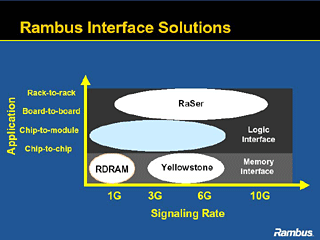 |
| 図 |
図は、Rambusが提供するインターフェイスのロードマップで、Yellowstoneは現行のRambus DRAMの後継となる技術であることが分かる。また、一番上にあるRaSerはGigabit EthernetやPCI Expressといった高速シリアルインターフェイスのバックプレーン用のインターフェイス技術で、1~3Gbpsのデータレートに対応したものが実用化段階にあり、10Gbpsに対応するRaSer Xが開発段階にある。Redwoodというのは、RaSerの下の空白となっている楕円の部分(このスライドはRedwoodの発表前のものなので、こういう具合になっている)に該当する技術だ。
この2つのスライドでもう一つ注目して欲しいのは、スライドの右下に刻まれたRambusのロゴ。これが新しい同社のロゴである。Rambusというと、RDRAMというイメージ(メモリの技術を売る会社というイメージ)が強いが、最近はRaSerやRedwoodのように、直接メモリとは関係しないインターフェイス技術に力を入れている。ロゴを変更した理由の1つは、高速インターフェイスのIPを売る会社という新しいイメージをアピールすることが目的のようだ。
これらの技術がPC分野に与える影響だが、現在PCのメモリの主流となりつつあるのはDDR SDRAMで、RDRAMはニッチのメモリになりつつある。RDRAMは、クロックを引き上げたり(PC1200、PC1333)、チャネル数をさらに引き上げたり(4チャンネル化)という工夫をしてくることが予想されるものの、メインストリームになるとは考えられていない。Yellowstoneの世代になっても、PCのメインメモリで主流になれるかというと、かなり微妙なところ。DDR IIあるいはDDR IIIがつまずかない限り、メインストリームになることは難しいだろう。ただし、Intel 820チップセットのリリース前に、RDRAMが技術的につまづく、と予想した人は決して多くはなかった。何が起こっても不思議ではない。少なくともYellowstone技術を用いたDRAMが民生機器では使われることは、ほぼ確定したわけで、DDR II/DDR IIIにアクシデントが生じた際に、いつでも代替となれる体制は築けることになる。
RaSerについては、Gigabit Ethernet対応製品に、徐々に使われていくことになるだろうが、それをユーザーが意識することはまずないだろう。Redwoodにしても基本的には同様だと思われる。ただ、ある意味RedwoodはHyperTransportやPCI Expressと競合する技術であり、PCにそのまま採用されるとは考えにくい。PCよりコンシューマー機器が主力となるかもしれない。これまでに比べてRambusの技術は、表からは見えにくくなるわけだが、同社はそれでも構わない、ということのようだ(見えすぎてかえって反発を招いた、というRDRAMからの教訓かもしれない)。
●AMDとIBMの次世代プロセス共同開発
続く1月8日には2つのニュースが飛び込んできた。1つはAMDとIBMが65nmおよび45nmプロセスを用いたチップ製造技術の共同開発で合意した、というもの。もう1つはIntelがBaniasプラットフォームの正式名称をCentrinoに決めた、というものだ。
まずAMDとIBMの提携だが、間違いなく言えることは、AMDとUMCの共同開発はうまくいかなかった、ということだ。共同開発が順調なら、ここにきて開発パートナーを変更する必要などない。共同開発がうまくいかなかった理由が技術的な問題なのか、経済的な問題なのかは明らかではないが、おそらく両方だろう。ただ、ある程度の技術的な問題なら、お金で解決できることなので、経済的な理由がより濃いかもしれない。
AMDのヘクター・ルイスCEOは就任以来、資本投下の効率化をとなえてきた。言い換えれば、設備投資額を減らしたい、ということである。それが、単独での新技術開発ならびに新Fab建設から、UMCとの共同開発ならびに生産会社の合弁へとシフトさせたわけだが、このところのIT不況でその余裕もなくなった、ということが考えられる。
AMDは、IBMとの共同開発による65nmプロセス技術の導入を2005年としているが、2年後に迫った製造技術について、今頃共同開発を発表していて間に合うのか、という疑問はつきまとう。ライバルであるIntelが65nmプロセスの導入を2005年と言っている以上、AMDも何がなんでも2005年から導入すると言わざるをえないという事情もあるだろうが、65nmプロセスによる量産をどこで行なうかも決まっていないようでは、雲行きは怪しい。65nm~45nmの世代では、製造設備は300mmウェハを前提にしたものになるといわれている。が、AMDには300mmウェハの工場は存在しない。
UMCとの合弁会社(シンガポール)だけが300mmウェハに対応した工場となる予定だったが、UMCとの共同開発がご破算になった以上、合弁もご破算と見るのが妥当だろう。(UMCへの生産委託だけは継続できる可能性がある)。ドレスデンのFab 30の周囲には、まだ空き地があり、工場を拡張することは可能だが、現時点での可能性はゼロだろう(資本投下額が増えてしまう)。かといって、既存のFab 30を300mmウェハに転換しようにも、唯一マイクロプロセッサの量産工場として稼動しているこの工場を止めるわけにはいかない(転換にも莫大な費用が必要となるだろうが)。
この難題に答えられる唯一の回答が、IBMに製造を委託する、ということだ。あるいは、限りなく生産委託に近い、共同生産である。かつてAMDはマイクロプロセッサの生産をIBMに委託していた時代があった。IBMへの委託をやめ、自社生産(すでにフラッシュメモリの工場に転換されたFab 25およびFab 30)に切り替えて、現在のAMDがあるのだから皮肉な話だが、それ以外に選択肢はないように思われる。ただ今回は、単なる生産委託ではなく、プロセスの開発段階から参画することで、以前と同じ轍は踏まないということなのではないか(AMDが若干の出資をする可能性もある)。
IBM側にもAMDをパートナーとして迎えるメリットはある。いくらIBMが巨大な企業だといっても、半導体という1つの事業だけを取り出せば、Intelの規模には遠く及ばない。次世代、さらにはその先と、単独で投資を続けていくのは決して容易なことではない。かつてなら、それだけで半導体の工場を支えられたかもしれないメインフレーム事業は縮小の傾向にあり、それと反対に半導体製造への投資額は肥大化を続けているからだ。AMDのプロセッサという製品が加われば、最先端プロセスを用いた工場の稼働率を高めることができる。
また、全社的にサービス化を唱えているIBMにあって、半導体事業部(Microelectronics)だけが、その例外とはなりえない。IBM Microelectronicsも、他社からの生産委託(ファウンダリサービス)や設計サービスなどに力を入れている(最近、IBMのファウンダリサービスが顧客として獲得したのが、それまでUMCの顧客だったXilinxであるというのは何とも皮肉だが)。そこで問題となるのが(というか、これまでのIBMへの生産委託で常に問題だったのが)、同社のプロセス技術のコストの高さだ。IBMの半導体技術は、銅配線、SOI、歪みシリコンなど、どれをとっても高いレベルにあるものの、高くつくのが欠点として指摘されている。AMDやCyrix、Transmetaなど、IBMにマイクロプロセッサの生産を委託した企業は数多いが、みな止めてしまったのは、コスト競争力に問題があったからだ。
今回のAMDとIBMの提携は、共同開発といっても、ベースとなる技術はほとんどすべてIBMのものではないかと思われる。そんな中にあって、IBMがAMDから学ばなければならない技術の一つは、どうすれば製造コストを低く抑えられるか、ということのハズだ。少なくともAMDは、AthlonやDuronで、Intelと競争できるだけのコスト構造を築いてきた。そのノウハウは、IBMが他の顧客を獲得する際にも役立つだろう。
IBMと組むことで、65nmや45nm世代についてある程度のメドがたったAMDだが、もっと身近な90nm世代について、見通しがハッキリしない。ほぼ確実なのは、Hammerシリーズのプロセッサを対象に、Fab 30で200mmウェハによる90nmプロセスの量産を行なうことだが、これだけではAMDの目標とするキャパシティを満たすことはできないだろう。そこで、すでに述べたUMCへの生産委託ということになるのだが、これもうまくいっているようには見えない。
ファウンダリ業界で1位の企業であるTSMCは、TransmetaのCrusoeやVIAのC3の生産を行なっている。これらのマイクロプロセッサはAMDやIntelのものに比べトランジスタ数が少ないにもかかわらず、ようやく1GHzで動いているのが実情だ。業界2位のUMCが、実クロックで2GHzを超えたAthlonをバンバン量産できるというのは、あまりに楽観的過ぎる見方に違いない。
もちろん、ファウンダリ企業にも言い分はあるだろう。2GHzや3GHzといった高クロック動作を必要とするようなハイエンドのプロセスを利用する顧客は、極めて限られている。そうした顧客を前提に工場を作っては、全体のコストが上がり、顧客が限られてしまう。現時点でマイクロプロセッサは、半導体プロセスにおけるテクノロジドライバとなっており、そうである以上、単純な生産委託は難しいということかもしれない。
残るCentrinoだが、これはBaniasという開発コード名で呼ばれていたプロセッサの名前ではない。マイクロプロセッサとしてのBaniasの正式名称は、Intel Pentium Mプロセッサで、チップセットはIntel 855チップセットファミリ、Calexicoというコード名で呼ばれていたワイヤレスLAN技術は、単にIntel PRO/Wireless network connectionと呼ばれることなった。
Centrino(正確にはCentrino Mobile Technology)は、以上の3つを包含したBaniasプラットフォーム全体を指すブランド名、と考えれば良いだろう。つまり、Banias/Pentium Mプロセッサを搭載しても、チップセットやワイヤレスLANチップが非Intel製だとCentrinoにはならないわけで、Centrinoがブランドとして確立すればするほど、サードパーティは厳しい立場に追い込まれてしまうかもしれない。
□関連記事
【1月7日】米Rambusがソニー、東芝ら3社と次世代DRAM技術でライセンス締結
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/2003/0107/rambus.htm
【1月9日】AMDとIBM、チップ製造技術開発で提携
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/2003/0109/amdibm.htm
【2002年7月31日】UMCとAMD、Infineonが65/45nm製造技術の共同開発で合意
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/2002/0731/umc.htm
【1月9日】Intel、Baniasの正式名称を「Centrino」に
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/2003/0109/intel.htm
(2003年1月17日)
[Text by 元麻布春男]
【PC Watchホームページ】
PC Watch編集部 pc-watch-info@impress.co.jp 個別にご回答することはいたしかねます。
Copyright (c) 2003 Impress Corporation All rights reserved.