 |


■後藤弘茂のWeekly海外ニュース■デュアルコアCPU“Smithfield”は来年第3四半期に登場 |
●サーバー、デスクトップ、モバイルのデュアルコアプランが明確に
Intelは、デスクトップ向け初のデュアルコアCPU「Smithfield(スミスフィールド)」を最高3.2GHzで投入する。登場時期は、2005年第3四半期。SmithfieldはNetBurst系CPUコアを2個搭載し、L2キャッシュは各CPUコアに1MBずつ、合計2MBを搭載する。FSB(フロントサイドバス)は800MHzのままで、パッケージも従来通りのLGA775だ。ただし、サポートチップセットは、2005年の「Glenwood(グレンウッド)」と「Lakeport(レイクポート)」ファミリからとなる。
また、IntelのデスクトップCPUでの64bit化プランも明確になってきた。Intelは来年第1四半期に、Prescott 2MコアのPentium 4 Extreme EditionとPentium 4 6xxファミリを投入する。これらのCPUから、64bit拡張「EM64T(Extended Memory 64 Technology)」をイネーブル(有効)にする。ダイナミックな電圧&クロック切り替えによりTDP(Thermal Design Power:熱設計消費電力)を抑える「Enhanced Intel SpeedStep Technology(EIST)」もイネーブルされる。これらのフィーチャはSmithfieldでもイネーブルにされる。
Smithfieldのプラットフォームとして、Intelは2005年春に新チップセット「Glenwood/Lakeport」を投入する。以前にもレポートした通り「Glenwood(グレンウッド)」は、EM64Tをサポート、最大8GBのメモリに対応できる仕様になっている。Glenwood/Lakeportとも、メモリはデュアルチャンネルのDDR2-667で、ICH7との組み合わせとなる。ICH7側はSATA-2をサポート、フィーチャの異なる5種類のバリエーションがある。
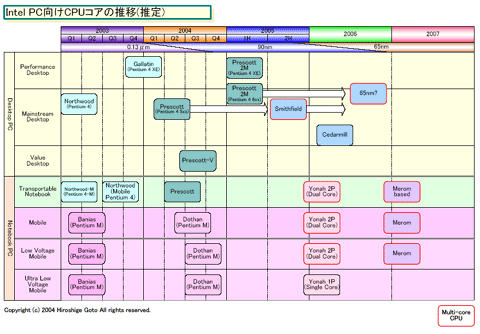 |
| CPU移行図 PDF版はこちら |
●サーバーでは新コードネームが登場
モバイルのデュアルコアCPU「Yonah(ヨナ)」はテープアウトを終え、いよいよサンプルに向かう。65nmプロセスで製造するYonahについては、Intelは検証期間を十分に取っており、量産は2005年第4四半期、ローンチ(立ち上げ)は2006年第1四半期が予定されている。つまり、デスクトップから1シーズン遅れでモバイルにもデュアルコアが登場するわけだ。
YonahもSmithfield同様に2MBのL2キャッシュを搭載するが、こちらは2つのコアでL2キャッシュを共有すると見られている。Yonahでは、FSBは667MHzに引き上げられる。Yonahは、第2世代PCI Expressチップセット「Calistoga(カリストガ)」、次世代無線LANモジュール「Golan(ゴラン)」との組み合わせで、Napa(ナパ)プラットフォームとなる。Calistogaでは、DDR2-667メモリもサポートされる。
サーバー&ワークステーションサイドでは、デュアルプロセッサ(DP)プラットフォームで、2006年頭にデュアルコアの「Dempsey(デンプシー)」が登場する。マルチプロセッサ(MP)でも、同時期に「Paxville(パークスビル)」が登場する。いずれも2006年中に、第2世代目のデュアルコアCPUに入れ替わる。MPの第2世代デュアルコアは、65nmプロセスの「Tulsa(タルサ)」となる。
DPプラットフォームでは、次世代チップセットとして「Blackford(ブラックフォード)」と「Greencreek(グリーンクリーク)」がデュアルコアと同時に投入される。新チップセットは、2つの独立したFSBを備え、2個のCPUと1個のMCHをそれぞれポイントツーポイントで接続すると見られる。また、シリアル系インターフェイスを使う「Fully Buffered DIMM(FB-DIMM)」をサポートする。チップセット側の改良で、デュアルコアの性能を発揮するのに必要なFSBとメモリ帯域&メモリ容量を確保する見込みだ。
Intelの全体戦略から見えるのは、それぞれの分野のデュアルコアCPUの前倒しのスケジュールが維持されていること。デュアルコアに舵を切って以来、Intelの計画自体は遅滞はない。その一方、次世代製造技術である65nmプロセスは、予想より若干ペースが遅い。最初の製品と見られるYonahが市場に登場するのは2006年頭。デスクトップの65nmプロセスCPU群も、2005年中は姿が見えない。90nmプロセス以降、スケジュールが後ろへずれている。
結果、Intelのデュアルコア前倒しは、本来デュアルコアにはまだ早すぎる90nmプロセスに無理矢理載せての展開となっている。デスクトップのSmithfieldは90nmプロセスであることが明らかになっているが、おそらく、サーバー側のDempseyとPaxvilleも90nmプロセスだと推定される。その代償は、大きなダイサイズ(半導体本体の面積)による高コストと、TDPの制約による比較的低い動作周波数だ。デスクトップ/サーバー系デュアルコアが65nmへと移行するのは2006年に入ってからとなる。
●Smithfieldの概要が明らかに
Smithfieldについては、今回までに次の概要が明らかになった。
・90nmプロセス
・1MB×2のL2キャッシュ(各CPUコアに1MBずつと見られる)
・EM64T(64bit拡張)
・Execute Disable Bit(XD bit)
・対応チップセットはGlenwood/Lakeport
・Hyper-Threadingディセーブル(実装はされているらしい)
・Enhanced Intel SpeedStep Technology(EIST)
・LGA775
・FSB 800MHz
・周波数は3.2/3.0/2.8GHz
・Processor Numberはx40/x30/x20
・3.2/3.0GHzはPerformance FMB 2005準拠(TDP 125W)
・2.8GHzはMainstream FMB 2005準拠
・出荷は2005年第3四半期
また各種情報から次のような仕様が推測されている。
・Vanderpool Technology(仮想化)
・LaGrande Technology(セキュリティ)
・CPUコアはPrescott相当
・Processor Numberは700番台?
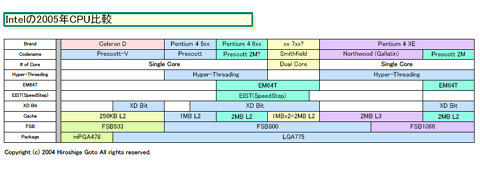 |
| CPU比較図 PDF版はこちら |
まず、Smithfieldの基本的な仕様は、Pentium 4 6xx相当となる。機能的には、2世代目のPrescottであるPentium 4 6xxをデュアルにしたと考えてよさそうだ。パッケージもFSBも同じで、TDP枠も同じ、共通するチップセットGlenwood/Lakeportでサポートされるため、両シリーズはほぼ同等に扱うことができるだろう。
違いは、Hyper-Threadingとデュアルコアだが、ソフトウェア側からはどちらも同じ2CPUに見える。ただし、CPUコア自体は1個しか持たないPrescottと、実際に2コアを備えるSmithfieldでは、パフォーマンス面ではSmithfieldの方がぐっと有利になる。Intelには、デュアルコア+Hyper-Threadingで、仮想的には4プロセッサ相当にする選択肢もあったはずだが、今回はその方法は取らなかった。その理由はまだわからないが、OSライセンスの問題も絡んでいるかもしれない。Hyper-Threadingはメモリレイテンシの隠蔽につながるので、デュアルコアとの併用はより効果的だ。ただし、仮想CPUと物理CPUコアの組み合わせは、スレッド割り当てに若干インテリジェンスが要求されるようになるだろう。
Smithfieldでは、2つのコアそれぞれに専用のL2キャッシュを1MBずつ備える。バスロジックとのアービタを備えて、調停すると見られる。Intelのモバイル関係者によると、一般論としてデュアルコアCPUではL2キャッシュは共有した方が効率がいいという。それを、あえて独立したL2キャッシュにしたのは、設計の容易性のためだと推測される。独立したL2の設計にすれば、シングルコアの設計を流用しやすいからだ。
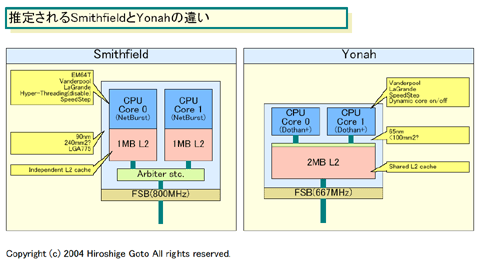 |
| CPUコア推測図 PDF版はこちら |
●Smithfieldを3.2GHzで稼働できる理由
IntelはSmithfieldのTDPを、シングルコアのPrescottと同程度に押さえ込む。そのため、トランジスタの速度から予想できる最高周波数よりも、動作周波数を抑える。周波数を下げることで、電力消費を抑え、シングルコア並のTDPにする。しかし、Smithfieldの動作周波数は最高3.2GHzと、Prescottの2005年の最高周波数3.8GHzの84%に達する。どうしてこれだけ高い周波数が可能になるのだろう。
それにはいくつかの理由がある。(1)デュアルコアではTDPの増大は1.x倍に留まる。(2)SpeedStepの応用によって、比較的少ない性能低下でTDPの上限を下げることができる。(3)90nmプロセスの改良が進みリーク(漏れ)電流がある程度抑えられるようになって来た。(4)Prescottの方の動作周波数の向上を抑えている。
(1)コアが2個になってもTDPは単純に2倍にはならない。これは、2つのCPUコアが同時に負荷のピークになるケースが少ないからだ。ほとんどのケースで、片方のCPUコアの消費電力がピークになっても、もう片方のCPUコアの消費電力はピークに至らないため、TDPは1.x倍にしかならない。特に、PCの場合は1スレッドに処理が偏る傾向が強いため、TDPは抑えられる。
(2)SpeedStepの応用もTDPに効果を発揮する。モバイルでは平均消費電力を引き下げるためにSpeedStepを使うが、「デスクトップでは熱設計などを容易にするために使う方向を検討している」とIntelのウイリアム(ビル)・M・スー(William M. Siu)副社長兼ジェネラルマネージャ(Vice President and General Manager, Desktop Platforms Group)は言う。
実際、Intelは「Foxton(フォックストン)」テクノロジと呼ぶSpeedStepライクな技術を、90nmプロセス版IA-64サーバーCPU「Montecito(モンテシト)」に採用する。Montecitoでは、FoxtonによってTDPを、シングルコアの0.13μm版Itanium2の130Wから100Wへと下げるという。そのため、SmithfieldでもEISTによってある程度のTDP低減が期待できる。ただし、このアプローチはきつく適用しすぎると、パフォーマンスを削ぐことになる。つまり、周波数通りのピーク性能が出にくくなってしまう。
(3)Intelは90nmプロセスの改良を進めており、量産開始時の90nmプロセスよりも、2004年の90nmプロセスでは大幅にリーク電流を抑えることができるようになったと説明している。つまり、Intelの90nmプロセスCPUは、後ろのリビジョンになるに従ってリーク電流が減るわけだ。そのため、初代のPrescottと比べると、Smithfieldはリークによるスタティック成分が少なく、全体の電力消費とTDPも減るものと見られる。
(4)IntelはSmithfieldのために、Prescottの動作周波数を抑えようとしている傾向が見られる。これは、次のレポートで詳説するが、Prescottの周波数をぎりぎりまで上げずに、3.8GHzまでに抑えることで、2つのアーキテクチャの周波数ギャップを狭めようとしていると推測される。
このほか、Smithfieldでは周波数が低い分、CPUの供給電圧を落とすことで消費電力を抑えている可能性もある。消費電力は周波数×電圧の二乗に比例するので、電圧の引き下げは効果がある。
こうした要素を重ね合わせると、Smithfieldが3.2GHzを達成できる理由も見えてくる。だが、それでもIntelにとってはぎりぎりの勝負だ。というのは、AMD系CPUとの周波数ギャップが狭まる可能性があるからだ。
Pentium 4対Athlon 64の構図になってから、IntelはAMDに対して最大1.5倍程度の周波数優位を保ってきた。もし、AMDのデスクトップ版デュアルコアCPU「Toledo(トレド)」が2.2GHz以上で出てきたら、ギャップが狭まり始めることになる。パフォーマンス/周波数の高いAthlon 64にIntelが対抗するには、周波数でのギャップを広げる必要がある。AMDは、Intelと同じTDPを設定すれば、デュアルコアCPUの周波数をもっと高めることができる。Intelとしては、最初の世代のデュアルコアで、コア当たりの消費電力がやや低いAMDに対抗するには、かなり苦労することになりそうだ。
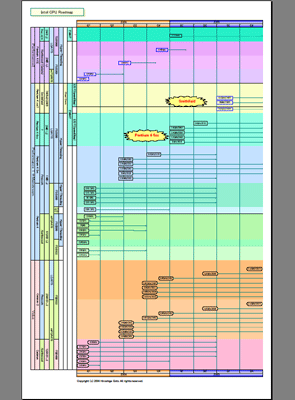 |
| デスクトップCPUロードマップ PDF版はこちら |
□関連記事
【8月5日】【海外】Intelの2005年のデュアルコアCPU「Smithfield」
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/2004/0805/kaigai108.htm
【8月9日】【海外】デュアルコアプロセッサ「Smithfield」のアーキテクチャ
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/2004/0809/kaigai109.htm
(2004年10月22日)
[Reported by 後藤 弘茂(Hiroshige Goto)]
【PC Watchホームページ】
PC Watch編集部 pc-watch-info@impress.co.jp 個別にご回答することはいたしかねます。
Copyright c2004 Impress Corporation, an Impress Group company. All rights reserved.