 |


■後藤弘茂のWeekly海外ニュース■IntelのAtomプロセッサとSoC戦略 |
●2009年にはGPUを統合したLincroftに移行
Intelは、新しい低消費電力CPUファミリに「Atom」ブランドを冠した。Atomは、LPIA(Low Power Intel Architecture)としてゼロから開発された「Silverthorne(シルバーソーン)」と「Diamondville(ダイヤモンドヴィル)」系CPUのブランドとなる。また、Silverthorneのプラットフォーム「Menlow(メンロー)」には「Centrino Atom」ブランドがつけられた。
Menlowプラットフォームは、Silverthorneと、対応するチップセット「Poulsbo(プースボー)」で構成される。Poulsboは、ノースブリッジ(GMCH)とサウスブリッジ(ICM)の機能を統合したワンチップで、低消費電力のDirectX 9グラフィックスコアとビデオデコーダ、DDR2(400/533MHz)インターフェイス、PCI Express x1×2を始め、基本的なI/Oを全て備える。下がSilverthorneとPoulsboのシステム構成図だ。
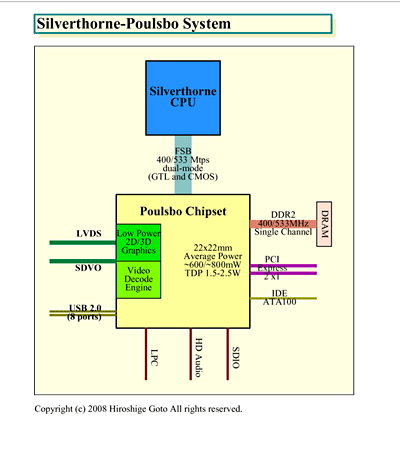 |
| SilverthorneとPoulsboのシステム図 PDF版はこちら |
チップセットのワンチップ化には2つの利点がある。実装面積と消費電力の縮小だ。StealeyベースのMcCaslinプラットフォームに対して、Menlowではチップ面積では2/3に、平均消費電力では1/2に減るという。
さらに2009年には、IntelはBonnellコアにGPUとメモリコントローラを統合する。CPUプラスGPUは『CPUハブ』呼ばれ、コードネームは「Lincroft(リンクロフト)」。Lincroftに対応するI/Oハブチップは「Langwell(ラングウェル)」で、この組み合わせで「Moorestown(ムーアズタウン)」プラットフォームとなる。この世代から、ノースブリッジ(GMCH)とCPUはノースコンプレックス(North Complex)に、サウスブリッジ(ICH)はサウスコンプレックス(South Complex)へと新たなパーティショニングとなる。
この移行は、実は、IntelのPC向けCPUの進化と同期している。IntelのPC向けCPUは、Nehalem(ネハーレン)世代でノースブリッジがCPU側に取り込まれる。Silverthorneマイクロアーキテクチャは、ローコストPCセグメントもカバーする。そのため、ローコストPCとバリューPCの間でのチップセットの互換を保つため、システムパーティショニングも互換にすると推測される。
もっとも、PC向けCPUでは、ノースブリッジ(GMCH)機能はシリコンレベルでは統合されない。Nehalem世代のGPU統合CPU「Havendale/Auburndale」は、真の統合CPUではない。CPUとGMCH(ノースブリッジチップ)の2つのチップを1パッケージに封止したMCM(Multi-Chip Module)だ。それに対して、Lincroftはワンチップにシリコンレベルで統合された製品となる。IntelのShmuel(Mooly) Eden(ムーリー・エデン)氏(Vice President, General Manager, Mobile Platforms Group, Intel)は、昨年(2007年)9月に次のように語っていた。
「全体的には、モバイルテクノロジでは統合化は、I/Oを減らすことで消費電力とフットプリントを減らす利点がある。また、CPUとグラフィックスをタイトに統合できれば、(GPUとCPUの)実行ユニットをそれぞれが使うこともできるようになる。多くの面で、統合は理にかなっている。だから、私はCPUとGPUの統合が、(CPUの)正しい方向だと信じている。
市場によっても統合のペースは異なる。ウルトラモバイル機器では、CPUとGPUの統合は、より迅速に起こる。なぜなら、他に選択肢がないからだ。GPUを統合しなければ、ウルトラモバイル機器にフィットさせることはできないだろう」。
●Silverthorne系の単体CPUとDothan系のSoCの2本立て
Intelは、SilverthorneとMenlowを、ウルトラモバイル機器だけでなく、さまざまな市場に展開して行く。また、SilverthorneのCPUコアである「Bonnell(ボンネル)」は、単体CPUだけでなく、将来的にはSystem on a Chip(SoC)製品のCPUコアにも使われて行くと見られる。つまり、AtomブランドのLPIA系CPUは、まず、単体CPU製品でスタートし、中期的にはIntelの組み込みCPUコアとしても転用されると推測される。ただし、そうした変化はステップバイステップで漸進的に行なわれるようだ。
IntelがLPIA系CPUでカバーしようとしている市場は大きく分けて4つある。携帯機器、ローコストPC、家電(CE)、組み込み(エンベデッド)だ。Intelは、システム要件の異なるこれらの市場に、まず、単体CPUであるSilverthorne系CPUを投入して行く。2チップ構成である強味を活かして、チップセット側を変えることで異なる市場向けのカスタマイズを行なう。フレキシビリティのために、LPIA系では、2チップソリューションを当面は維持する。IntelのAnand Chandrasekher(アナンド・チャンドラシーカ)氏(Senior Vice President, General Manager, Ultra Mobility Group)は次のように説明していた。
「2チップ構成にしたのはフレキシビリティのためだ。我々の目前に開けている市場セグメント群は、まだ完全に開発されたわけではなく、要件も異なる。例えば、PC、携帯電話、家電、車載では、市場によって必要な要素が異なる。もし、我々がシングルチップ製品を作ったとしたら、それらの市場を全てカバーすることは難しい。
しかし、CPUハブとI/Oチップの2チップ構成なら、潜在的にI/Oカスタマイズができる。それによって、市場に合わせたフレキシビリティが得られる。例えば、Intel内部の他のグループが、(LPIAを)使う場合も、2チップ構成なら家電や組み込みに使うことができる。Intel内部での再利用を考えて、2チップ構成を採った」。
Silverthorneに組み合わせるチップセットを変えることで、多様な市場に迅速に対応できるという。実際、ローコストPC向けのDiamondvilleには、Poulsboではなく、デスクトップでは945GCとICH7/R/DH、モバイルでは945GSEとICH7Mが対応する。既存のPC向けチップセットと基本的に同じプラットフォームを使う。ローコストPCは市場で要求される機能は基本的にバリューPCと同じだからだ。
しかし、Intelは単体CPUだけでなく、古い世代の90nm版Pentium M(Dothan:ドタン)コアを使った、SoC製品も家電や組み込み市場に投入して行く。家電向けが「Canmore(キャンモア)」、組み込み向けが「Tolapai(トラパイ)」だ。SoC製品では、その市場に必要な全ての機能をワンチップに統合する。SoC製品のCPUコアも、DothanコアからBonnell(Silverthorne)コアへと移って行くという。
SoC製品でBonnellコアへの移行がずれるのは、SoC製品は開発期間が長く、先端プロセス技術への移行にも時間がかかるからだと推測される。また、SoCではフレキシビリティも狭まる。しかし、その反面、実装面積と消費電力では、2チップ構成よりさらに有利となる。
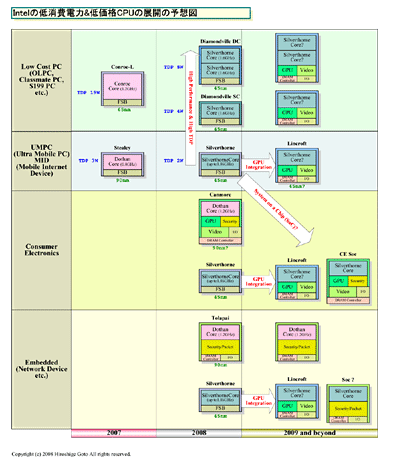 |
| Intelの低消費電力&低価格CPUの展開の予想図 PDF版はこちら |
●TolapaiからSilverthorne系SoCへと移行する組み込み系
Silverthorne系のCPU単体製品と、Dothanコアの組み込み製品の2本立て戦略が明確に見て取れるのは組み込みプロセッサ市場だ。Intelは、この市場に、今年(2008年)後半にSilverthorneとTolapaiの2つを平行して提供する。Silverthorneは、組み込み向けのPoulsboとの組み合わせによる「Embedded Menlow」プラットフォームとなる。また、Intelは2009年には組み込み製品で要求される広い動作保証温度範囲に対応するSilverthorne XLとPoulsbo XLも投入する。
基本的にはウルトラモバイル用と同じ機能のEmbedded Menlowに対して、SoCであるTolapaiは特定市場にカスタマイズされている。Embedded Menlowはグラフィックス機能込みで2チップの汎用プラットフォーム、Tolapaiはグラフィックス機能は持たない1チップでネットワーク回りの機能が大幅に強化されている。そのため、かなり用途は異なる。
Tolapaiは、ネットワーク機器やストレージ、各種インタラクティブクライアント、セキュリティ機器、プリンタといった機器への搭載を目的としたCPUだ。ネットワークに接続する機器で高度なグラフィックス&ビデオ機能が必要ないものをカバーする。そのため、TolapaiにはCPUコアと、1チャネルのDDR2インターフェイス、セキュリティとパケット処理の専用プロセッサなどが搭載されている。
IntelがTolapaiにDothanコアを使った理由は、開発を急いだことや、周辺回路が90nmプロセスでなければ揃わなかったことなどが考えられる。しかし、ダイサイズや消費電力を考えると、この市場向けCPUコアも、Silverthorneコアが望ましいはずだ。
事実、昨年(2007年)9月のIDFの際に、IntelのPatrick(Pat) P. Gelsinger(パット・P・ゲルシンガー)氏(Senior Vice President and General Manager, Digital Enterprise Group)は次のように説明していた。
「Tolapaiについては、現在のコアに新フィーチャを加えたリビジョンもある。最初のリビジョンと2つ目のリビジョンは、既存のPentium M(Dothan)コアをベースとしている。それから、低消費電力のSilverthorneコアへと移る。ただし、Silverthorneに移行するにはしばらく時間がかかるだろう」。
Gelsinger氏のニュアンスは、明らかにTolapai型のSoC製品へのSilverthorneコアの搭載を指している。
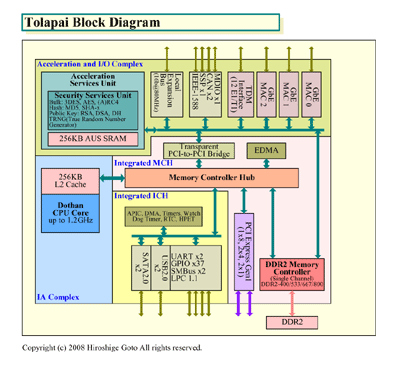 |
| Tolapaiのブロックダイアグラム PDF版はこちら |
●兄弟のように似ているCanmoreとTolapai
単体CPUとSoCの2重戦略は、家電市場にも共通すると見られる。Intelがデジタル家電でターゲットとしているのは、デジタルTV、デジタルSTB(セットトップボックス)、BDプレーヤー、家電型のホームサーバーなど。Intelはこの市場に、今年後半に「Canmore(キャンモア)」と呼ばれる製品を投入しようとしている。それと平行して、Silverthorneも提供されると見られる。
Canmoreは、CPUコアにグラフィックスコアやビデオデコーダ、セキュリティプロセッシング機能、3チャネルDDR2インターフェイスなどを統合した製品だ。ハイエンドビデオ機器に必要な機能を全て統合したSoC製品となっている。フルHD品質のビデオを、HD品質のサブビデオとともにデコードし表示できる性能を持つ。また、3Dグラフィックス機能も統合し、リッチなユーザーインターフェイスやアプリケーションを提供できる。下がCanmoreのブロック図だ。
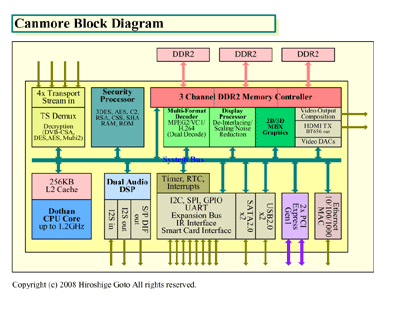 |
| Canmoreのブロック図 PDF版はこちら |
CanmoreとTolapaiのブロック図を較べると、両者は大きく異なっているにもかかわらず、共通する要素があることがよくわかる。Canmoreは、Tolapaiのネットワークアクセラレーションユニットや、3連のGbE(Gbit Ethernet) MACといったフィーチャは持たない。その代わり、Tolapaiにはない2D/3Dグラフィックスやビデオプロセッサ、オーディオDSP、ストリームインなどを備える。
両者で共通するのは、Dothanプロセッサコアと256KBキャッシュ、ICH部分に当たる各種I/OやPCI Express Gen1など。機能は同じだが構成が異なる部分もある。TolapaiはDDR2メモリインターフェイスが1チャネルだが、Canmoreは3チャネル。これは、Canmoreがメモリ帯域を食う、高度なグラフィックスとビデオ機能を統合しているためだ。また、CanmoreはTolapaiのセキュリティユニットと機能が似たセキュリティプロセッサを備える。
IntelのEric B. Kim(エリック・B・キム)氏(Senior Vice President, General Manager, Digital Home Group)は次のように説明していた。
「TolapaiとCanmoreは似たようなルーツを持っている。実際には、同じ開発チームによって開発されたTolapaiとは異なる派生品がCanmoreだ。つまり、多くの共通する要素があるが、異なるブロックも使っている。
これは、PC市場と家電や組み込みスペースでのキーとなる要求の大きな違いの1つ。PCスペースでは、全てのPCセグメントに渡る高レベルの共通性が求められる。しかし、家電ではそうではない。機器によって全く異なる機能が供給される。これは、組み込みでも同じだ。そのため、SoCのブロックを入れ替えることで、シリコンに異なるフレバーを与え、異なる派生品を作っている。
これが、Intelの新しい戦略だ。Intelは、こうしたこと(市場毎に異なるSoCの開発)は行なってこなかった。しかし、今後は、異なる特定の市場セグメントに対して、多くの異なる派生品を提供して行く」。
つまり、TolapaiとCanmoreが示すのは、Intelが特定用途向けのSoC製品に本格的に乗り出したことだ。そして、Silverthorne(Bonnell)系CPUコアは、その中で中核の要素となって行くだろう。
□関連記事
【3月7日】【CeBIT】Centrino2/Centrino Atom/4シリーズチップセット説明会
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/2008/0307/cebit11.htm
【3月3日】インテル、Silverthorneの正式名称を「Atom」に決定
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/2008/0303/intel.htm
【2月7日】【海外】これが超低消費電力「Silverthorne」の正体だ
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/2008/0207/kaigai417.htm
(2008年3月10日)
[Reported by 後藤 弘茂(Hiroshige Goto)]
【PC Watchホームページ】
PC Watch編集部 pc-watch-info@impress.co.jp ご質問に対して、個別にご回答はいたしません
Copyright (c) 2008 Impress Watch Corporation, an Impress Group company. All rights reserved.