 |


■森山和道の「ヒトと機械の境界面」■音楽で広がる身体、コミュニケーション
|
 |
楽器は接続機器である。遠くない将来、ピアノにはIPアドレスが振られ、楽器同士がインターネット経由で接続されるかもしれない--。
いきなりこんなことを言うと違和感があるだろうか。だが、これがヤマハのビジョンなのである。
2003年12月に行なわれた「TRONSHOW2004」でヤマハが、T-Engineを使ったネット経由のピアノセッション・遠隔教育システム「iSession」をデモしていたことを耳にした、あるいは実際に眼にした読者の方も多いと思う。会場入り口そばのブースと、反対側のブースとの間をつなぎ、ピアノ初心者が先生にレッスンを学ぶというデモンストレーションだった。あのときはピアノだったが、実際にはMIDI対応機器ならば何でも接続することが可能だという。
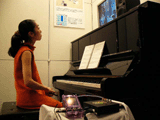 |
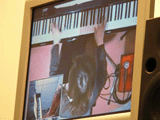 |
 |
| TRONSHOW2004での「iセッション」の模様。画像とMIDIデータをネットワーク経由でやりとりする。講師は実際の演奏の様子を見て、マイクで生徒に指示を与える。またユーザーを4人まで登録しての連弾もできるという | ||
「電子楽器は組み込み機器の典型例です。ですから他の組み込み系家電と同じくネットやユビキタスといったキーワードは意識してます。取り組みとしてはまだまだですが、研究部門を中心に未来の楽器像に取り組んでいます」と語るのは、ヤマハ楽器事業本部 マーケティング企画室の櫻田信弥氏。電子楽器はITRONが入った組み込み機器であり、20年前からMIDIという接続規格を持っている。ユビキタスで俄に注目を浴びている「リアルタイム処理」や「繋ぐ」ことに関しては古参だというわけだ。インターネットへの対応はまだまだだが、親和性はあるのではないかという。言われてみれば、冷蔵庫にIPを振るよりも遙かに現実的だし、楽しい世界が待っているかもしれない……。
ヤマハは最近、初心者でも弾き語りのまねごとができるEZシリーズなど、エンターテイメント性の高い楽器も世に送り出し、新しい取り組みに挑んでいる。その一方、実は売り上げの半分近くは楽器以外の半導体などの事業という企業でもある。シンセサイザーのようなレベルではなく、もっと違った意味合いでも音楽とPCは思っている以上に近い世界にあるかもしれない。そこでヤマハに、音楽の未来についての考え方を取材した。読者の方々には少し違った角度でのインターフェイスの話として、お読み頂ければ幸いである。
●「ユビキタス・ミュージック」を実現するための技術
 |
| ヤマハ アドバンストシステム開発センターNDプロジェクト 多田幸生氏 |
まず、iSessionとその周辺について、アドバンストシステム開発センターNDプロジェクトの多田幸生氏に説明してもらった。
ヤマハは2002年6月にアムステルダムで開催されたBluetoothCongressで<ユビキタス・ミュージック>というビジョンを提案している。たとえば電車のなかでHMDをつけてヴァーチャル・キーボードを弾く人、公園でタンバリンを振っている人、喫茶店で音楽を聴いている人たちがいたとする。彼らは実はネットワークで繋がっていて、電車の中の人と公園の人はネットを介したセッションをしていて、それを喫茶店の人が聴いている、といったイメージだ。
「つまり、どこでも演奏ができて、どこでも聴くことができるのがユビキタスミュージックです」(多田氏)
そのために必要なものはなにか。ケーブルはわずらわしいので、とりあえずMIDIをケーブルレスにするためにBluetooth MIDI通信チップを製作した。
 |
| Bluetooth MIDI通信チップ。PHY/LINK両方の機能をワンチップ化、レイテンシ10msを実現 |
インターネット経由でMIDIリアルタイムセッションを可能にするiSessionは、この流れの研究の一つである。無線MIDI通信が近距離、遠距離がインターネット利用のiSessionというわけだ。
最大の問題はネットワークによる遅延とパケットロスだった。原理上、遅れが生じることは避けられない。問題は、どれだけの遅れであれば問題ないかだ。多田氏らは認知心理学的な実験を行なった。
たとえば電子ドラムのような電子楽器を叩くとする。ポンと叩くと、センサが叩かれたことを感知し、処理が始まって、スピーカーから音が出る。ピアノであれば、鍵盤を押していく途中で処理が始まり、処理が進んで、音がスピーカーから出る。ここに遅延、つまりズレを作ってやる。ポンと叩いたあとに、ある時間の遅れを間に挟んで音を出すように細工するのである。実験の結果、遅延が30ミリ秒(0.03秒)以下であれば、人間は遅延が起きたことにすら気づかないという結果が出たという。つまり30ミリ秒以下であれば、セッションができることが分かった。
「50ミリ秒くらいだと、何となく遅れているな、とは分かるけど、一応演奏はできる。それより遅くなると演奏ができない。だから実際のインターネットセッションでもそのくらいに遅延を抑えれば、ほとんど気が付かないでセッションができるだろうと」(多田氏)
FTTHで結ばれたネットワークの中ならば遅延は20m秒以下なので、ネット越しのセッションは非現実的なものではないという。ちなみにパケットが50ミリ遅れる環境とは、18m離れた人と実際にセッションするのと同じくらいの遅延に相当する。音速は意外と遅いのである。
 |
| 「Sound Bit」モックアップ |
パケットロスに対しては、パケットを送るたびに一緒に「ジャーナル」と呼ぶ履歴を送ることで対応している。MIDIでは「鍵盤を押した」という情報と「離した」という情報の2つが送られている。もし離したことを示す情報が通信路上で消えてしまうと、向こうでは音が鳴りっぱなしになってしまう。それを避けるために定期的に、送信側の鍵盤では音が止まっているはずだという情報も送っている。受け取ったほうは音が止まったよという信号が来たら音が止まるようになっている。そのような信号の欠落や順番入れ違いをジャーナルで補正してやるのである。
また、今後はHMDやウェアラブル、位置認識などのテクノロジーを使った新しい音楽の可能性も模索して行きたいという。たとえば「Sound Bit」は、所有者それぞれが固有の音を持っていて、それをお互いが交換しあうことで、その場その場の音楽コミュニケーションができないかというものだ。2002年度のヤマハ社内イベントで提案されたものだという。いわば着メロの進化版みたいなものだろうか。
多田氏らの話によれば、同じ好みの人々が集まることで街特有のファッションが自然に出来ていくように、同じ好みの音楽を持っている人々が自然に集って音楽を奏であうようなシーンを演出したい、ということのようだ。
●ネットワークならではの音楽
 |
| PA・DMI事業部商品開発部 技術開発グループ 原貴洋氏 |
また、ネットワークを介してのセッションにしても、はじめは音だけを送ることに終始していたが、実際の合奏時には音以外にも目線や身ぶりなど多くの情報が必要であり、ネットを介して相手が向こうにいるという実感が必要だと分かったという。かといって、重たい専用ネットワークでないと動きません、というのでは、何のためにネットワークを使っているのか分からなくなる。こちらはPA・DMI事業部商品開発部 技術開発グループの原貴洋氏らを中心に研究を進めている。
ネットワーク越しであろうがなかろうが、合奏はもともとそれなりの経験が必要だ。どうしても遅延が生じるネットワーク経由で、プアな情報でやれるような形態を模索する必要がある。そこで現在では、ネットワークならではの音楽を模索中だという。
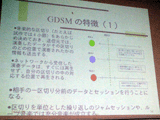 |
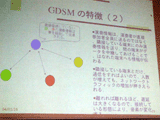 |
| GDSMの特徴 | |
具体的には、静岡文化芸術大学の長嶋洋一氏が提案している「GDSM(Global Delay Session Music)」という通信遅延による音楽の破綻を防ぐセッション方法を独自に拡張したものを実験中だ。これは、どうせ遅延するのだから、遅延を最初から取り入れてセッションしようというものだ。
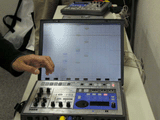 |
| 実際のセッションの様子。画面上では相互に送りあった音が視覚化されている |
GDSMでは小節ごとに音楽を区切り、そのデータとセッションしていくことになる。相手とは一区切り前のデータとセッションすることになるため、通常の意味でのセッションは無理だが、区切りが最初から存在しているような、たとえばリズムをやりとりするような音楽では、コミュニケーションが成立するのだという。ジャムセッション、クラブの箱同士のセッションのようなものをイメージすると良いようだ。
データはネットワーク上で隣あった端末間でしかやりとりされない。だから距離が離れれば離れるほど、遅延の幅は大きくなる。だがその分、多くのユーザーとのセッションが可能であり、端末間で同期を取るためのシステムなどを必要としない。自分の区切りの良いところから再生・セッション参加ができる点も大きな特徴だ。「ループ音楽を用いた一種のコミュニケーション」と位置づけているという。なお相手の演奏は、一部の音楽系ゲームのような感じで視覚化されており、音が出る前にディスプレイ上で見ることができる。そのため、こちら側がどんな演奏を返すか、考えることが可能だ。
 |
| ヤマハが1月15日に発表したエレクトーン「STAGEA」 |
ヤマハは、USB無線LANを持ち、ボタン1つでネットを介してMIDIデータをダウンロードできるエレクトーン「STAGEA」など、ネットの分かりやすい利便性を組み込んだ電子楽器も開発している。いずれは、有名プレーヤーのライブ演奏のデータが、そのまま自宅のエレクトーンそのほかの電子楽器で演奏される日も近いだろう。その一方で、新しい可能性も模索中、ということのようだ。
現在の電子楽器は過去のアコースティック楽器のしがらみを引きずっている。インターフェイスデザインとは拘束条件のデザインでもある。既存の楽器の形をしていれば、操作法がすく分かるというわけだ。つまり「そのほうが分かりやすい」という圧倒的な理由の結果、現状の形になっているのだが、アコースティック楽器そのものも実際には様々な模索を経て現状に至っている。失敗したデジタルものにありがちな分かりにくく必然性のないインターフェイスだと困ったことになるだろうが、まだ全く新しい可能性はあるかもしれない。VRやARのようなテクノロジーも使っていきたいという。
「楽器と音楽って切り離して考えられないんですよね。ある楽器が出来ると、それを使った音楽ができる。音楽が出来るとまた必要とされる楽器が固まってさらに発展する。そうやって両方が階段を上るように発展するんですが、そこを無理矢理既存の音楽にはめ込もうとすると失敗するんだと思います」(櫻田氏)
ヤマハはこの分野で「MIBURI」という手痛い失敗作を出している。手足の動き、「身ぶり」で音楽を奏でるというものだ。'95年に発表され、'96年に改良版も出た。だが一部のマニアを除き、皆に使われるものになることはなかった。直感的に分かるインターフェイスではなかったし、演奏法と奏でようとした音楽の間に相関性がなかったからだ。
●気持ちいい楽器ってなんだろう
~インターフェイス思想としてのボディイメージ
 |
| ヤマハが「ヤマハピアノ製造100周年」記念に製造したPC内蔵グランドピアノ「SILENT ENSEMBLE Pro2000」。2000年夏の「ゆめテク」などでも展示されていた、「21世紀のピアノを予言する未来型ピアノ」として製造されたコンセプトモデル。Windows 98ベースで動くインターフェイス、タッチパネルになっている14.1型のディスプレイやDVD ROMそのほかを備える。自分のペースに伴奏と楽譜がついてくるほか、有名な演奏家の演奏を再現することもできる。アルミがふんだんに使われたボディにはヤマハの技術が詰まっている。価格は3,000万円を超える |
では、どんな楽器が望まれているのだろうか? 人の琴線に触れる楽器とは何だろうか。
先ほど、ネットワーク経由での遅延の話をした。だが実際には、遅延は楽器のなかでも発生する。また、自分はただ聞いているときに遅れて聞こえる場合と、自分が押した瞬間に遅れて聞こえた場合では意味あいが違ってくる。楽器はプロになってくると、打鍵するときの木のしなりに伴う数ミリ秒の音発生のタイミングのずれも込みで演奏しているのではないかと言われる世界だという。そのため、ちょっと処理を変えると「気持ち悪くなった」という表現をする人もいるそうだ。
この「気持ちの悪さ」の正体は何だろうか。あるいは逆に、気持ちいい楽器とは何か。そこを探ることが必要になってくる。
たとえばPDAやPC上のアプリケーションでも、ボタンを押して起動するまでのタイミングによって、気持ちいいものと悪いものがある。それと似たような感覚だろうか。ちなみに普通のPDAのタッチパッドは、一部メーカーを除き指を離した瞬間に起動するようになっている。
楽器のインターフェイスはどうあるべきなのだろうか。この点について多田氏は、以下のように語る。
「認知科学に『ボディイメージ』という言葉がありますね。自分の体のイメージのことです。たとえば車だと、もっさりした車よりもインターフェイスに『透明性がある』--つまりアクセルを踏んだら自分の後ろにある後輪が回るのがすぐに実感できるとか、ハンドルを切ったらタイヤがこう動くのかと実感できる車のほうが気持ちいいでしょう。あたかも自分の体の延長のように操作できる機械のほうが、気持ちがいいですよね。つまりボディイメージに取り込みやすく、なおかつ自分自身を拡張してくれるような機械が、操作していて気持ちがいい機械なんだと思います。
楽器でも同じようなところがあるんです。インターフェイスが単純で分かりやすい、透明性が高い楽器のほうが、楽しい楽器なんだと思うんです。『楽器を弾くときの楽しさ』は、自分のボディイメージを広げられる楽しさなのかもしれないと思います」
インターフェイスができるだけ透明で、それを弾きこなせるようになっていく。その結果、ボディイメージが広がっていく。そこが楽器演奏の楽しさなのかもしれない、という。
最近ではボディイメージ(身体像)は単なる概念ではなく、脳に実在していることが身体座標の研究などの結果、明らかになっている。手に棒のような道具を持ったときには、ボディイメージは棒の長さにまで伸びるという現象も、神経細胞レベルで検証されている。
音楽演奏しているときのボディイメージがどのような状態になっているのかについては定かではない。だが、たとえばパイプオルガンの演奏者(オルガニスト)の場合は、体全体がホールに広がっているような感覚なのかもしれない。また、オーケストラや合唱などのように複数の人々が一緒になって音楽を奏でるときの喜び・快感は、ひょっとするとボディイメージや脳に存在する座標系と何か深い関連があるのかもしれない。真相は、今後の研究を待つしかないが--。
 |
| ヤマハ発動機「dolsa wind」 |
現状の楽器だけが、ボディイメージを拡張してくれるものとは限らない。2003年のモーターショウにヤマハ発動機が「dolsa wind」という二輪車のモックアップを発表していた。「風に乗ったような不思議な走行感覚と楽器を奏でるような優雅な演奏感覚を融合した感性で楽しむ新しい乗り物」をコンセプトに掲げ、ハンドル部に8個、シート下に2個あるスピーカーから、2軸超音波風速センサーで感知した風の動きに合わせて走行に応じた音を奏でるというものだった。ヤマハではこの音楽部分を担当している。これもまた新しい「楽器」を模索する一環だという。走ることによって風を感じ、音楽を感じる。それがどんな感覚なのかは試してみないと分からない。
「楽器の場合、インターフェイスの試行錯誤が100年単位で行なわれているんです。デジタルが楽器に入り始めてまだたかだか20年ですから、これから変わる余地はいっぱいあると思います」(原氏)
●誰でも弾ける楽器を目指した「EZシリーズ」
 |
| EZシリーズ。真ん中のウクレレとトランペットは試作品 |
ただ、単純にインターフェイスを透明にすればいいかというとそうでもない。ある程度練習していくことで自分のほうを慣らしていく過程も、インターフェイスでは重要な側面だ。
特に楽器演奏はその側面が強かった。高度成長期の間は「音楽のある暮らし=良い暮らし」というイメージがあり、そもそも音楽というよりもむしろ「音楽教育」そのものが、ある種の社会的ステイタスだったこともある。だが少子化や社会の価値観の変化の結果、楽器演奏人口はこのままでは先細る可能性があるとヤマハでは見ている。少なくともかつてのような「ピアノ神話」はもうなく、普及する家庭には普及しきってしまっており、逆に誰にも弾かれることなく放置されている家庭もある。今までのように、弾きたければ練習してください、ということでは、音楽演奏人口は増えない可能性がある。
「それを技術の力でもうちょっと簡単にしてやればいいかな、というのがEZシリーズのコンセプト」と櫻田氏は言う。
 |
| マーケティング企画室 櫻田信弥氏 |
ヤマハとしては、これまでの音楽の世界を大事にしながら、新しいところに布石を打っていかなくてはならない。そのため、取りあえずはかつて楽器をやっていたけど、今はもうやってないという世代、具体的にはかつてのフォーク世代をターゲットに、新しい楽器を開発した。それがEZギターだ。昔フォークに憧れ、ちょっと触ったことがあるけど、今は指がもう動かないよ、という人をターゲットにしたものだ。
EZギターならばピックでボロロンとやるだけで、それっぽい演奏ができる。練習する動機を持ってなくても楽しめる楽器だ。表面上は既存の楽器を模すことでわかりやすくし、だが裏では電子技術をフルに生かした電子機器である。「最終的には、気持ちいい、楽しい世界を認識・演出できることを目標としています」(櫻田氏)
もちろん初心者が実際のコード進行を覚えるために使うこともできる。実際に櫻田氏や原氏らもEZシリーズでギターを覚えたと笑う。もちろん、真似ている以上、「本物」には勝てない。だがメンテナンス等一部では本物以上に優れている面もある。
開発にあたっては、「そもそも楽器とはなんだろうか」ということから考えたのだという。「人間と音楽のインターフェイスであろう」というのが開発グループの答えだった。「インターフェイス」だと見れば楽器を使いこなすこと自体は手段であって、目的でしかない。たとえばピアノは、言ってみれば88個の押しボタンが並んでいるだけだ。しかしながら無限の世界を表現することができる。
目的は鍵盤を押すことではない。その先にある世界を表現することであるはずだ。だが多くの人は、楽器自体を使いこなすことに四苦八苦してしまう。その結果、音楽を楽しんで価値を感じるところまで達することのできる人が少ない。そこを何とかするための橋渡しがEZシリーズだ。
●楽器は「エモーショナル・インターフェイス」
感覚を伝えあえるインターフェイス。それをヤマハでは「エモーショナル・インターフェイス」と呼んでいる。現在は、楽器単体での商売よりも、楽器で何ができるかが本当に問われているという。今後はたとえば、家電や風呂などを楽器として取り込んだり、センサーで取り込んだ情報を音楽という形で知らせるといったものを構想しているという。冒頭で触れたTRONSHOWに出展されていたユビキタスリモコンなどもその一環だ。
 |
 |
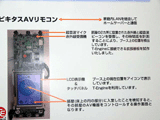 |
| ユビキタスAVリモコン。もちろん試作品 | ||
最後に今後、どんな楽器シーン、音楽シーンを作っていきたいか聞いてみた。
「楽器全体としては伝統的な世界を残すべきだと思います。そこを崩すというのはない。でもどうやったら楽器屋の敷居をまたいでくれるかを考えないといけないと思います。値段が安いだけじゃ来てくれない。かっこいいとか楽しいとか、そこの想像をどうやってかきたてるかでしょうね。『こうなりたいでしょ』っていう想像をどうかき立てるか、こういうやり方もありますよ、と出していくのをどうやるかが問題だと思います」(櫻田氏)
「僕個人の見解では、楽器は音楽を創るためのものであり、音楽の目的はコミュニケーションの手段だと思うんです。できるだけたくさんの人が音楽を使ったコミュニケーションができるようにする。それが自分の使命だと思っています。そのためには楽器を演奏できる人とできない人の差をなくすことだと思ってます。そうしないと音楽コミュニケーションはできない。そこで技術による演奏支援や、新しいインターフェイスの開発をしていきたい。誰でも音楽ができるような楽器をつくること、そしてお互いの楽器をきちんと繋いであげて、色んな人とコミュニケーションとれるような形にしてあげようということですね。それが『ユビキタス・ミュージック』です。
もう1つは楽器を演奏する楽しみの中には“ボディイメージ”を広げる楽しみもあると思うんです。演奏そのものが楽しいと。ではボディイメージを広げるような楽器にするためにはどうすればいいか。ここは既存の楽器にも繋がる部分です。より演奏性を高めたピアノ、バイオリン。オルガン。そういったものを探求していきたいと思います」(多田氏)
「僕は発信できる楽器です。今は受け身が多いでしょう。でも楽器っていうのは本来自分から出すものですよね。自分が表現するということです。ボディイメージでも、ホールで演奏しているときはホール全体に広がっているかもしれない。でも部屋で演奏しているときは部屋くらいにしか広がらないのかもしれない。それがネットワークに繋がると、部屋のなかで演奏していても、もうちょっと先まで手が届くかもしれない。音が広がっている空間のイメージにまで。そうなってくると、音だけじゃなくて、楽器が主体になることで色々なものが繋がるかもしれない。ともかく、楽器があるということは武器になる。自分を発信するためのツールとして、楽器にはもっと広がりや可能性があるはずです。そこを考えてみたいと思ってます」(原氏)
 |
オーケストラで演奏しているときに、だんだん馴れてくると、遠くの音が聞こえてくるのだという。そうなると「自分の体がすごく広がったような感じがする」と原氏は言う。「皆で演奏する感動は代え難いものがある」と。
音楽家は「楽器を手足のように操る」。それをテクノロジーの力を借りつつ、いかに普通の人、多くの人に体験してもらえるか。感動をやりとりすることを目指すヤマハの取り組みは続く。
□ヤマハのホームページ
http://www.yamaha.co.jp/
□関連記事
【2003年12月12日】TRONSHOW2004レポート ~極小キューブPCやCEとの複合機を展示
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/2003/1212/tron.htm
【2003年8月4日】おもちゃみらい博で「ROBO-ONEバンダイカップ」開催(EZシリーズの記事あり)
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/2003/0804/roboone.htm
【2003年2月27日】ヤマハ、歌詞と音符から歌声を合成するソフト
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/2003/0227/yamaha.htm
【2002年9月12日】ヤマハ、「ラジカセ風操作」が可能なMP3ミキシングレコーダ
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/2002/0912/yamaha.htm
(2004年1月28日)
[Reported by 森山和道]
【PC Watchホームページ】
PC Watch編集部 pc-watch-info@impress.co.jp 個別にご回答することはいたしかねます。
Copyright (c) 2004 Impress Corporation All rights reserved.