ニュース
NVIDIA、メモリ24GBのQuadro P6000でレイトレVRをデモ
~VR向け機能を積んだPascal世代のQuadroを活用
2016年10月18日 18:03
NVIDIAは18日、Pascal世代のワークステーションGPU「Quadro P6000」および「Quadro P5000」を使ったプロフェッショナル向けVR体験会をメディア向けに開催した。
Quadro P6000とP5000は今年(2016年)の7月に発表されたGPUで、現在コンシューマ市場で手に入るPascal版の最上位GPU「TITAN X」よりもメモリ容量などが多く作られている。主な違いは下表の通り。
| Quadro P6000/P5000のスペック | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Quadro P6000 | Quadro P5000 | TITAN X(Pascal版) | GeForce GTX 1080 | Quadro M6000 | |
| CUDAコア数 | 3,840基 | 2,560基 | 3,584基 | 2,560基 | 3,072基 |
| メモリ | GDDR5X 24GB | GDDR5X 16GB | GDDR5X 12GB | GDDR5X 8GB | GDDR5 12GB |
| 単精度浮動小数点演算 | 12TFLOPS | 8.9TFLOPS | 11TFLOPS | 8.2TFLOPS | 7TFLOPS |
| 最大消費電力 | 250W | 180W | 250W | 180W | 250W |
| インターフェイス | PCI Express 3.0 x16 | ||||
今回のプロフェッショナル向けVR体験会では、NVIDIAが取り組んでるQuadroを活用したビジュアライゼーションプラットフォームに焦点を当て、Quadroがプロフェッショナルの世界でどのように使われているかといった紹介が行なわれた。
Kepler世代から2倍性能が向上したQuadro P6000/P5000
エヌビディア ジャパン マーケティング本部 エンタープライズ マーケティング マネージャーの田中秀明氏は、Quadro P6000/P5000の説明の中で、1つ前のMaxwell世代のQuadroと比較して、CUDAコアが増えただけでなく、Quadro P6000に至ってはGDDR5Xを採用したことでメモリ帯域が100GB/s以上も増えていることを言及。最大4基の5K表示が可能になったことなどを挙げた。
さらに、VR環境に向けた機能として、ジオメトリを演算し直さずに最大16の視点を設定できる「同時マルチプロジェクション(Simultaneous Multi-Projection)」をサポートしたこと、ダイナミックロードバランシングやピクセルレベルのプリエンプションによってGPUのワークロード管理が改善されたことも大きいという。
Quadro P6000/P5000での活躍の場は主に「3Dモデリング/4K編集」、「物理ベースレンダリング」、「プロフェッショナルVR」であり、国内での使いどころとしてもは自動車デザイン、BIM(Building Information Modeling)/CIM(Construction Information Modeling)を活用した建築土木設計に使われており、今回の主題であるプロフェッショナルVRでは手術シミュレーション、自動車デザインの開発でも、フォトリアルな建築空間、建築施工性の確認といった用途で力を発揮するという。
田中氏は、Quadro P6000/P5000がKepler世代の製品と比較した場合に、2倍ほど性能が向上していることをグラフで示し、ビデオメモリの増大とGDDR5による帯域の向上が、プロフェッショナル向けのVR環境に最良の性能を提供できるとする。下位モデルのQuadro P5000については、昨今12GBを超えるグラフィックデータが扱われることもあり、ビデオメモリが16GBになったことで活用の幅が広がっていることを強調した。
Iray VRでフォトリアルなVR空間を表現
次いで、エヌビディア ジャパン エンタープライズソリューションプロダクト事業本部 Quadroプロダクトマネージャ シニア ソリューションアーキテクトの柿澤修氏がPascal世代のGPUによるIrayのVR活用について説明を行なった。
Irayは昨年(2015年)にNVIDIAが提供を開始したレイトレーシングソフトで、Mayaや3dsMax、Cinema 4DなどのCG制作アプリ向けにプラグインという形で提供されている。柿澤氏はOpenGLといった程度のレンダラーでは、フォトリアルな絵を描き出せないとし、NVIDIAはこのほかにも、mental ray、OptiXなどといったレンダラーを擁していることをアピールした。
NVIDIAは、IrayによるVR向けのレンダリングソリューションとして「Iray VR」を発表しており、こうしたフォトリアルなレンダリング技術をVR環境にも提供している。Iray VRでは、IrayでレンダリングしたCGを映像として見るといった活用が行なわれ、自動車の外見から内部、建築物の内部構造把握といったプロトタイプ設計を仮想体験を通して作り込んでいくことができる。柿澤氏は例として、オリンピック会場を建造する際に注意が必要とされる選手らを映すための最適なカメラ位置、光の加減といったシミュレーションを建物を建てる前にあらかじめ割り出し、設計者がVR HMDを通して確認が行なえるといった活用の場を挙げ、仮想とは言え実際に建物内に入った体験を行なえる点は大きな影響があるとした。
ただ、現状提供されているIray VRによる仮想体験はリアルタイムレンダリングではなく、プリレンダリングとなっている。昨年にNVIDIAが行なったIrayの説明会ではハンドドリルをIrayでリアルタイムレンダリングする様子をデモして見せたが、建築物や自動車といったマテリアルが豊富なシチュエーションにおいては、リアルタイムレンダリングでVR提供することは難しいという。
そのため、NVIDIAが今回のIray VRのデモで披露した一昔前のイギリスの銀行を使ったVR体験では、指定されたいくつかの定点で風景を確認するといった内容になっていた。それでも、VR HMDを通して360度あたりを見回しつつ、時間帯を変えて光りの加減を見るといった操作を行なうことができ、内部構造の確認といった使い方ではそれなりの感触が得られるものだった。おそらく自動車の車内を再現したデモがあれば、そもそも動き回る必要がないので、プリレンダリングであっても十分な体験ができると思われる。ただ、現状のVR HMDの解像度が不足気味であり、デバイスがフォトリアルを表現し切れていないという残念な点が目についてしまった。
Iray VRのレンダリングにはTesla P100を8基搭載する同社スパコンの「DGX-1」またはQuadro VCAが用いられ、現状ではこの2つの選択肢しかない。また、プリレンダリングと言えども、ビデオメモリは24GB縛りになっており、その映像を見るにはQuadro P6000かM6000を搭載したマシンである必要がある。
柿澤氏は、今日の時点ではこれだけの建造物をVRで作るにはハードルは高いが、今後数年でこういった使い方が増え、マンション内の配管どのようになっているかなど、事細かな部分をも映し出すようになっているだろうとした。










![[Amazon限定ブランド]CCL い・ろ・は・すラベルレス 2LPET ×8本 ミネラルウォーター 無味 製品画像:2位](https://m.media-amazon.com/images/I/41h0MHfvhkL._SL160_.jpg)
![【Amazon.co.jp限定】 伊藤園 磨かれて、澄みきった日本の水 2L 8本 ラベルレス [ ケース ] [ 水 ] [ 軟水 ] [ ペットボトル ] [ 箱買い ] [ ストック ] [ 水分補給 ] 製品画像:3位](https://m.media-amazon.com/images/I/41n0o65dSkL._SL160_.jpg)



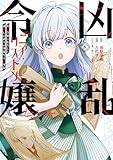


















![変な絵(コミック) : 4【電子書籍】[ 雨穴 ] 製品画像:30位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rakutenkobo-ebooks/cabinet/2047/2000019702047.jpg?_ex=128x128)
![週刊少年マガジン 2026年11号[2026年2月10日発売]【電子書籍】[ 宮島礼吏 ] 製品画像:29位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rakutenkobo-ebooks/cabinet/1827/2000019701827.jpg?_ex=128x128)

![sweet (スウィート) 2026年 3月号 [雑誌] 製品画像:27位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/0368/4912154410368_1_2.jpg?_ex=128x128)
![The Art of Dragon Age: The Veilguard ART OF DRAGON AGE THE VEILGUAR [ Bioware ] 製品画像:26位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/2961/9781506732961_1_2.jpg?_ex=128x128)
![【楽天ブックス限定特典】乃木坂46川崎桜 1st写真集『タイトル未定』(限定カバー) [ 須江隆治 ] 製品画像:25位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/1009/2100014821009_1_2.jpg?_ex=128x128)
![50歳ラジオパーソナリティ佐久間の深夜3時のエンタメ過剰摂取~佐久間宣行のオールナイトニッポン0(ZERO)2023-2025~ [ 佐久間宣行 ] 製品画像:24位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/2197/9784594102197.jpg?_ex=128x128)
![蜘蛛ですが、なにか?(16)【電子書籍】[ かかし朝浩 ] 製品画像:23位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rakutenkobo-ebooks/cabinet/5231/2000019615231.jpg?_ex=128x128)
![賢者の孫(28)【電子書籍】[ 吉岡 剛 ] 製品画像:22位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rakutenkobo-ebooks/cabinet/5226/2000019615226.jpg?_ex=128x128)
![公式テキスト第4版対応版 生成AIパスポート テキスト&問題集 [ 生成AI活用普及協会(GUGA) ] 製品画像:21位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/3917/9784800593917_1_6.jpg?_ex=128x128)