 |


■後藤弘茂のWeekly海外ニュース■IntelがIntelを食う共食いを起こしたAtomプロセッサ |
●IntelのCPU戦略を根幹から揺るがす
Intelに襲いかかった「キャニバリゼーション (Cannibalization:共食い現象)」は、同社のCPU事業の根幹を揺るがしつつある。低コストかつ低消費電力のAtom系CPUが、PC向けCPUの市場を侵食することで、Intelの利益を減らす可能性があるからだ。最悪の場合、非PCの新市場を切り開くというAtomの目的は達成できずに、単にIntelの市場でPC向けCPUをAtomに置き換えるだけで終わってしまうかもしれない。
現在の状況は、9カ月ほど前の記事「ムーアの法則がIntelに逆襲する~Nettop/Netbookの脅威」の中で予測した“バッドシナリオ”を予感させる進み方をしている。この時の記事では、AtomがIntelにとっての新市場を拡大することができず、既存のPC向けCPUを脅かしてしまうというシナリオを予測した。今、日本など一部市場で発生しているAtom旋風は、そのストーリの序章に見える。
実際に、日本でのAtomは、Intelの思惑を超えて、通常のノートPC市場を食い始めている。まず、携帯ノートPCを購入していた(あるいは潜在購入層)ユーザーが流れ、続いて、低価格に引かれた初心者ユーザーもひきつけた。Intelの既存のPC向けCPUが占めていた市場を、ある程度はAtomが食ってしまっている。
この方向へと歯止めがかからず進めば、最終的にAtom系CPUが、バリューPCからメインストリームPCの市場まで広がる可能性もある。もしそうなると、IntelのCPUのASP(Average Selling Price:平均販売価格)が下降し、これまでのような高売り上げを確保できなくなる。現在のFabの製造キャパシティも埋めることができなくなり、CPU戦略を根本から見直しせざるを得なくなる。
以前の記事で推測した、Intelにとって理想的なAtom成功のシナリオは、次のようなものだ。PC&サーバー市場は、そのまま従来のPC向けCPUが保持。Intelは、CPUを高いASPで売って、売上と利益を守る。一方で、AtomでPC向けCPUでは浸透できなかった携帯機器、家電、各種組み込み機器の市場を開拓する。新市場の売り上げがプラスされることで、Intelはますます大きくなる。このシナリオを成功させるカギは、従来のPCとAtomベースのデバイスの境界を明確にすることだ。Intelが今年(2009年)1月のCESなどで懸命に訴えていたのは、まさにこのポイントだ。
もちろん、Atomが市場に広まる方向へ向いてしまったとしても、IntelやMicrosoftは、PCの低価格化を招くAtomの浸食を避けるために、さまざまな歯止めをかけるだろう。しかし、Atomで一度開いた“パンドラの箱”は、メーカーの思惑を超えて進展する可能性を秘めている。Intelにとって難しいのは、Atomがムーアの法則に牽引される半導体のスケーリングに沿った自然な製品であることだ。ユーザーの要求する性能が一定なら、ムーアの法則でデバイスのコストが下がるという、当たり前の現象が起きているに過ぎない。
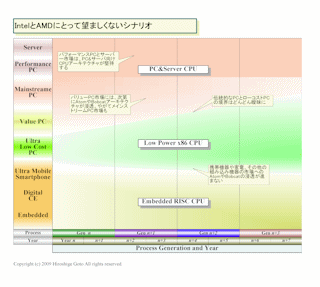 |
| IntelとAMDにとって望ましくないシナリオ |
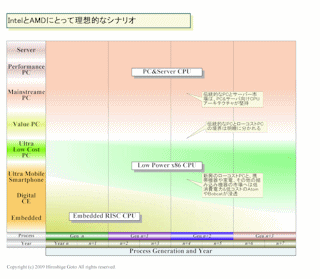 |
| IntelとAMDにとって理想的なシナリオ |
●脱大型コアのCPUアーキテクチャ変革を反映
AtomがPC向けCPUの市場を一部なりとも食っていることは、もっと大きな変化も示唆している。それは、市場で求められる、CPUアーキテクチャの根本的な変化だ。多数のユーザーが、もはや従来型の汎用CPUのパフォーマンスを求めていない可能性がある。今後も、シングルスレッドの整数演算性能は一定以上は求められず、ニーズはマルチスレッドの浮動小数点演算性能へとシフトするかもしれない。
プロセッサ業界では、過去5年、「命令レベルの並列性(ILP:Instruction-Level Parallelism)」から、「スレッドレベルの並列性(TLP:Thread-Level Parallelism)」と「データレベルの並列性(DLP:Data-Level Parallelism)」への比重の変化が話題となって来た。こうした根幹のアーキテクチャの変化が、Atomのキャニバリゼーションとして現れている、と見ることもできる。だとすれば、Atom現象は、CPUメーカーがアーキテクチャの方向性をシフトすることを加速するかもしれない。
つまり、Atomのキャニバリゼーションが示唆しているのは、単に、安いCPUが同じメーカーの高いCPUの市場を食うという、単純な販売戦略上の自己矛盾ではない。1つは、ムーアの法則でデバイスが安くなるという、半導体業界では当たり前の原則がPCにもやって来たこと。もう1つは、これがCPU業界の現在の最大課題であるCPUアーキテクチャの構造的な変革の反映である可能性だ。
示唆の通りだとすれば、将来のPC向けのCPUのあり方が、根本から変わる可能性もある。具体的には、将来のPC向けCPUの主流は、現在のAtom (Silverthorne:シルバーソーン)のような、ILPを抑えた小さなCPUコアに、高いDLPで浮動小数点演算性能を強化したコアを融合。コアを多数並べることでTLPを高めたスタイルになるかも知れない。Atomを強化して、Larrabee(ララビ)のようにDLPとTLPを追求したようなCPUだ。現在のPC向けCPUより、シングルスレッドの整数演算性能は落ちるが、CPU全体の浮動小数点演算性能は、同数のトランジスタで10倍になるだろう。
その一方で、サーバー&ハイエンドPC向けCPUは、現在のコアからの進化を続け、高いILPを維持しながらDLPとTLPも強化する方向へ向かうかもしれない。ただし、Atom系の小型コアCPUが躍進した場合、ハイエンドPC&サーバー向けCPUが市場に占める比率は、今のPC向けCPUのシェアより、ずっと小さくなるだろう。そのシナリオなら、PC向けx86系CPUの市場は、ハイエンドPC&サーバー向けと、メインストリームから下のPC向けに2分されるようになる。
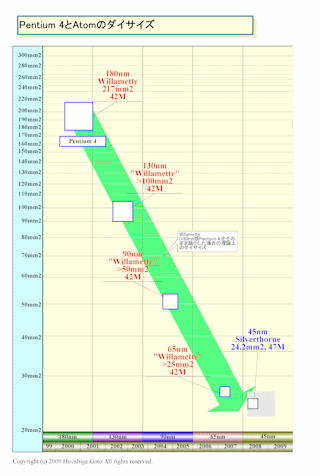 |
| ダイサイズ移行図 PDF版はこちら |
●AMDとIntelがスタートさせたx86 Anywhere戦略
原点に戻ると、本来、IntelがAtomブランドを冠した「LPIA (Low Power Intel Architecture)」CPUを開発し始めた理由は、新市場の開拓だった。AMDもIntelのLPIAとよく似た低消費電力&低コストのCPU「Bobcat (ボブキャット)」を開発しているが、その理由も同じだ。x86命令セットアーキテクチャを、組み込み系CPUの市場にももたらすことで、非PCの市場を開拓するというものだ。具体的には、興隆しつつあるスマートフォンなどの携帯情報機器、インテリジェント化するデジタル家電、ネットワーク機器といった市場をターゲットにした計画だった。x86アーキテクチャをPC&サーバーだけでなく、どこにでも広げる「x86 Anywhere」戦略と言い換えてもいい。
これらの市場を集めれば、年間数億個、あるいは10億個を超える需要を見込むことができる。そして、機器の高度化にともなって、これらの市場でも高度なCPUが必要になると考えられた。そこで、IntelやAMDも、早くからこの市場群に向けた製品計画を立てていた。手を付けずにいれば、組み込みRISC系CPU系のベンダーが、この市場の支配を継続させてしまうからだ。IntelとAMDは、成長の鈍ったPC&サーバー市場に留まり、急成長する組み込み市場を逃すことになってしまう。
現在、この市場は組み込みRISC系CPUアーキテクチャで占められている。伝統的に、x86は携帯電話のレベルの低消費電力設計には向かないと考えられていたからだ。また、PC向けCPUはダイ(半導体本体)が大きく製造コストも高いため、数ドルレベルの低コストが要求される市場には適合できないと見られていた。
そのため、IntelやAMDも、当初はこうした市場向けにはRISC系CPUを製品化していた。AMDは「Geode」のようなx86も投入したが、焦点が定まっているとは言い難かった。しかし、両社とも2002~2003年頃に戦略を完全に転換。組み込み市場向けに最適化した、低消費電力&低コストのx86系CPUを新規に開発することにした。
●PC向けCPUの方向転換と同時期にAtomの開発をスタート
ここで重要なのは、両社が低消費電力&低コストx86 CPUの開発に乗り出した時期が、両社のPC向けCPUのアーキテクチャの方向転換をした時期とほぼ一致していることだ。Intelは巨大CPUコアのPC&サーバー向けCPU「Tejas (テハス)」の開発をキャンセル、マルチコアへと転換した。AMDも「K9」の開発をストップしてマルチコア化を促進し始めた。Intelの場合は、Tejas開発チームを、そのままAtomファミリ開発チームにスライドさせたと見られる。
時期の一致は、両社がPC&サーバー向けCPUのCPUコアを巨大化させ、ILPを高める戦略を捨てた時点で、派生的に低消費電力&低コストx86 CPUのプランが産まれたことを示唆している。これは不思議ではない。CPUコアを一定にとどめてCPUコア数を増やすマルチコア路線に転換するなら、CPUコアをより小さくするという方向へもアイデアが広がることは容易に想像ができる。また、マルチコア化に向かう最大の原因となった消費電力の低減からも、小型CPUコアというアプローチが出てきたと推定される。
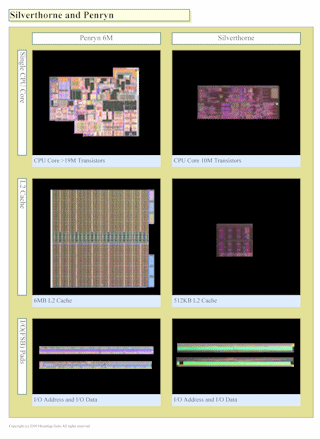 |
| SilverthorneとPenrynの比較 PDF版はこちら |
●AMDとIntelがともに同じ結論に達する
両社は水面下で低消費電力&低コストCPUの開発をスタートさせたが、公の場でこの構想を最初に明らかにしたのはAMDの方だった。AMDは、2003年の秋のCPUカンファレンス「Microprocessor Forum」で、「Towards Instruction Set Consolidation」と題した講演を行なった。その中で、AMDの当時のCTOだったFred Weber (フレッド・ウェバー)氏が、x86命令セットアーキテクチャが、低消費電力や家電といった市場に浸透して行くと説明した。下がその時のスライドだ。
 |
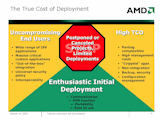 |
 |
| マクロレベルのアーキテクチャの進化 | 本当の導入コスト | マクロレベルのアーキテクチャの進化2 |
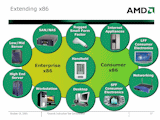 |
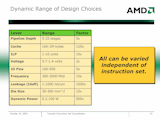 |
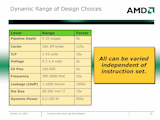 |
| x86領域の拡大 | 設計選択のダイナミックレンジ | 設計選択のダイナミックレンジ2 |
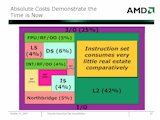 |
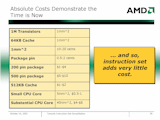 |
|
| ダイ内部のコスト分布 | ダイ内部のコスト分布2 |
AMDは、命令セットアーキテクチャは、消費電力やコストに大きなインパクトを与えないと主張した。CPUの各コンポーネントで、x86命令セットでの不利があるのはごく一部で、RISCでなければ低消費電力かつ低コストに作れない理由はないとした。ほぼ同様の説明は、IntelのJustin R. Rattner (ジャスティン・R・ラトナー)氏(Intel Senior Fellow, Vice President, Director(Corporate Technology Group) and Intel CTO)も2004年のインタビューで語っていた。
「私は、命令セットアーキテクチャが低消費電力の障壁にならないという意見に基本的には異論はない。しかし、個々の要素で見ると、多少、説明が必要だろう。まず、(CISCであるIA命令セットの)可変長命令のデコーダは、(固定長命令のRISCのデコーダ)より電力を消費する。その意味では、ISAはゼロコストではない。もう1つの要素はキャッシュアクセスだ。Intelアーキテクチャでは、レジスタファイルが少ないため、データキャッシュに負担をかける。ここにもトレードオフがある。
これらのペナルティは、電力&面積効率の面からは、おそらく10~20%のレンジだと思う。正確な数字を出すのは難しいが、ゼロコストでないことは確かだ。ただし、パフォーマンス面を見ると、面白い逆転がある。なぜなら、CISCは、RISCよりもより多くの命令を実行できるからだ。これは、CISCの方がコード密度(プログラムサイズ当たりの命令数)が高くなるからだ。電力効率で見ると、実行する命令はできるだけ少ない方が有利だ。そのため、ここでは逆に可変長が有利になる。こうしたトレードオフの結果、ローパワーの固定長命令セットプロセッサに対して、ローパワーのIntelアーキテクチャプロセッサも競争できるだろう。ダイサイズは多少(RISCより)増えるが、十分、競合できる範囲だと考えている」
アーキテクチャトレードオフを考えると、x86で充分にRISCに対抗できる低消費電力&低コストCPUを開発できると判断したわけだ。そして、IntelとAMDがともに同じ結論に達した。
●わき上がった低コストコンピュータの波
この時点での両社の狙いは明瞭だった。開発環境やソフトウェア資産が豊かであるというx86アーキテクチャの利点を活かし、組み込みCPU市場も征するというものだった。そのため、両社とも、PC&サーバー向けCPUとの命令セット上の互換性を重視した。これまでの組み込み向けx86は、PC&サーバー向けx86とは命令セットの互換の面で完全ではなかった。しかし、今回は互換性を高めることで、x86の利点を組み込み市場で享受できるようにしようと計画した。
IntelとAMDが、低消費電力&低コストx86 CPUでメインターゲットに据えたのは、非PCのデバイスで、多様な組み込み機器だった。しかし、IntelとAMDが、具体的にAtomとBobcatの計画を進めている間に、コンピューティング機器を巡る情勢が変わった。超低価格のPCライクなコンピュータを立ち上げようという機運が高まってきた。
これは、当初はOLPC (One Laptop per Child)やクラスメイトPC (Classmate PC)、199ドルPCと呼ばれたジャンルだ。構想では、主に政府機関などが学校に供給したり、新興市場で低価格に販売される製品を主眼にしていた。後には、成熟市場向けのサブマシンも視野に入れるようになる。現在のMicrosoftのOSライセンスの定義では「ULCPC (Ultra Low-cost PC)」となるジャンルだ。この市場は、発展途上国の教育機関への提供といった要素を含むため、世界企業としては社会的責任上でも取り組まざるを得ない。
こうした状況で、Intelは昨春にAtomをリリース。まずAtom、Atom Zシリーズ(Silverthorne)を携帯情報機器向けにリリースする一方、同ダイ(半導体本体)のAtom Nシリーズ(Diamondville:ダイヤモンドヴィル)をULCPC向けに投入した。スマートフォンなどもターゲットに含めるのは、今年(2009年)後半の「Lincroft (リンクロフト)」から。組み込み市場向けには、現在90nm版Pentium M (Dothan:ドタン)コアを統合しているSoC (System on a Chip)型のネットワーク機器向け製品「EP80579 (Tolapai:トラパイ)」とデジタルTV向け製品「CE 3100 (Canmore:キャンモア)」の後継にAtom系コアの製品を持ってくる。
しかし、現状では、IntelはAtomとDothan系組み込みCPUで、非PCの市場を大きく花開かせることに、まだ成功していない。時間がかかるのは当たり前だが、今のところは目標に達していない。組み込み市場では、特に問題が大きいという指摘もある。
その一方で、Nettop/NetbookのULCPC系は、日本を含めた一部市場で花開いてしまった。安いだけで、結局はPCであるULCPCでは、Atomの利点はそのまま活かされる。待ちかまえていた市場に、最適なCPUが投下されたわけだ。
実際には、世界的に見たNetbookの勢いは、日本国内の状況のような大きな波ではない。影響の大きな市場はまだ限られている上に、デスクトップにはほとんど波及していない。しかし、日本の状況は、Intelにとってのバッドシナリオそのものであるため、Intelの戦略に暗雲が立ちこめているのは確かだ。そして、小型ダイで低コストかつ低消費電力のCPUが、PCに受け容れられることは、今のCPUアーキテクチャと半導体スケーリングから見れば自然な流れでもある。CPUメーカーは、この流れに逆らうためには、大型ダイのCPUの必要性を明確にして行かなければならない。
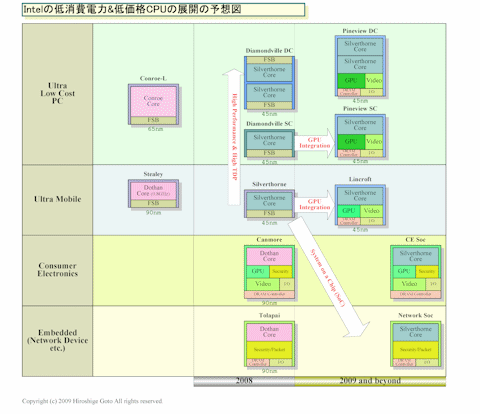 |
| Intelの低消費電力CPU&低価格CPUの展開の予想図 PDF版はこちら |
□関連記事
【2008年4月18日】【海外】ムーアの法則がIntelに逆襲する
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/2008/0418/kaigai436.htm
【2007年6月21日】【海外】AMDの省電力CPUコア「Bobcat」とFUSION構想
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/2007/0621/kaigai367.htm
(2009年1月30日)
[Reported by 後藤 弘茂(Hiroshige Goto)]
【PC Watchホームページ】
PC Watch編集部 pc-watch-info@impress.co.jp ご質問に対して、個別にご回答はいたしません
Copyright (c) 2009 Impress Watch Corporation, an Impress Group company. All rights reserved.