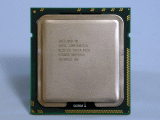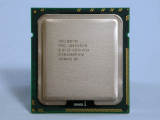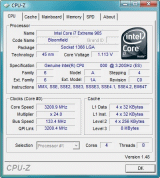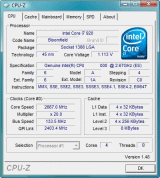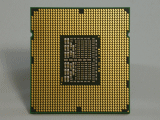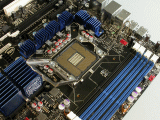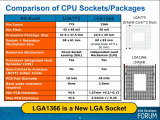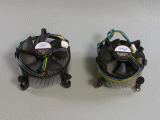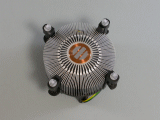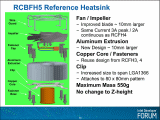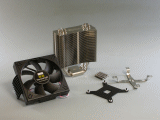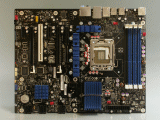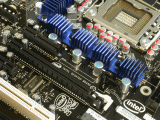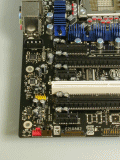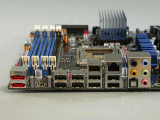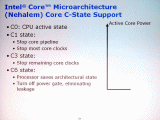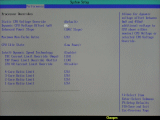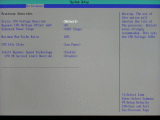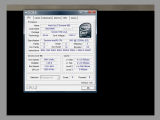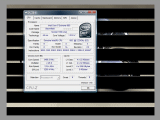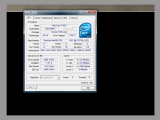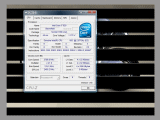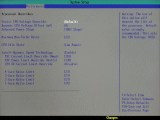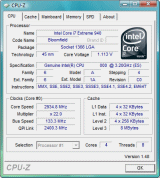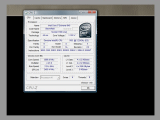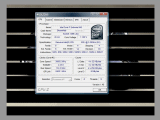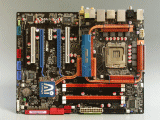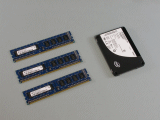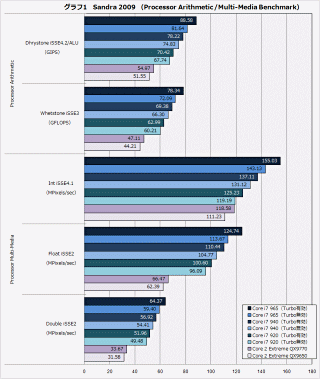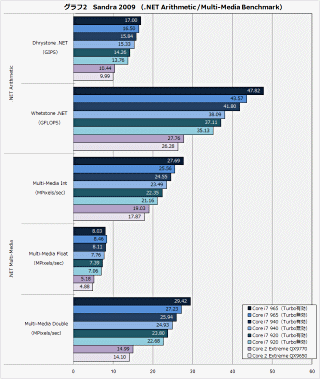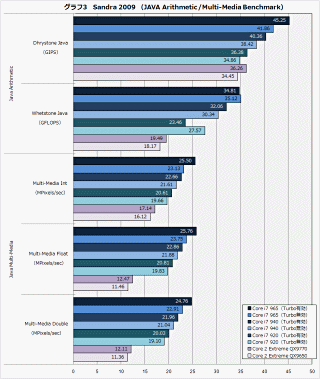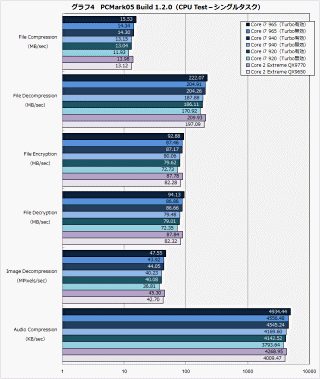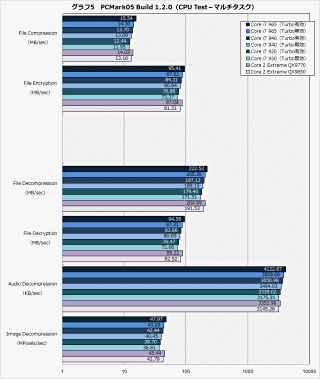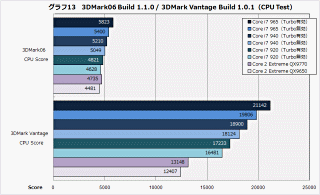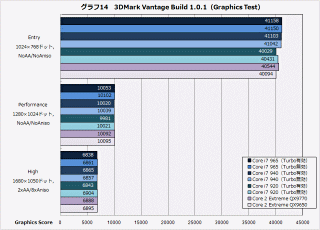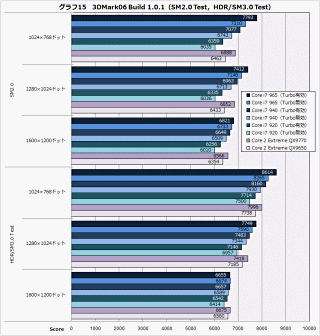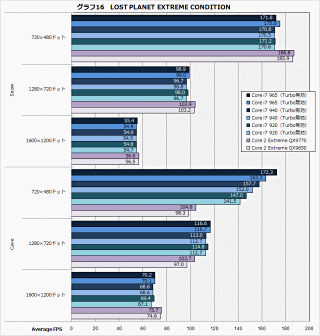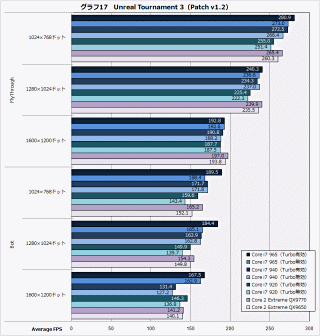|


■多和田新也のニューアイテム診断室■いよいよ登場するNehalemこと「Core i7」シリーズ |
すでにアナウンスされている通り、Coreマイクロアーキテクチャの登場から2年が経過した今年、IntelのTICK-TOCKモデルに従い、新マイクロアーキテクチャを採用したCPUが登場する。開発コード名である「Nehalem」、新ブランド名である「Core i7」といったキーワードのほか、マイクロアーキテクチャなどの詳細も多くの情報が公開されており、期待している読者も多いのではないだろうか。今回、デスクトップ向け製品のテストキットを入手できたので、これを利用してCore i7のパフォーマンスをチェックしてみたい。
●デスクトップ向けには3製品を最初に投入
今回のテストするCore i7プロセッサはデスクトップ向けの製品で、「Bloomfield」の開発コード名を持つものだ。Bloomfieldは今年中にも発売が見込まれている製品で、ラインナップは表1に示した通りとなる。今回のキットには、「Core i7-965 Extreme Edition」と「Core i7-920」が含まれている(写真1~2、画面1~2)。いずれもクアッドコア製品。Core 2 Extreme/Quadで採用されている2つのデュアルコアを1つのパッケージに封入する方式ではなく、シングルダイのクアッドコアとして製造される。
【表1】Core i7シリーズのスペック
| Core i7-965 Extreme Edition | Core i7-940 | Core i7-920 | |
|---|---|---|---|
| 動作クロック | 3.20GHz | 2.93GHz | 2.66GHz |
| QPI転送速度 | 6.4GT/sec | 4.8GT/sec | |
| L1キャッシュ(命令) | 32KB×4 | ||
| L1キャッシュ(データ) | 32KB×4 | ||
| L2キャッシュ | 256KB×4 | ||
| L3キャッシュ | 8MB | ||
| 対応メモリ | DDR3-1066 | ||
| TDP | 130W | ||
| 価格 | 999ドル | 562ドル | 284ドル |
既報の通り、NehalemではPentium 4の一部に採用されていたHyper-Threading技術が復活する。これは、1つのコアで2スレッドを実行可能にする技術で、クアッドコアとHyper-Threadingの組み合わせでは計8スレッドが実行可能となる。
外観上の特徴としては、Core i7は、Pentium 4からCore 2シリーズまで利用されてきたLGA775からCPUパッケージが変更され、LGA1366と呼ばれるものになる(写真3~4、図1)。ピン数が大幅に増えているのは、チップセット間インターフェイスの変更や、メモリコントローラの内蔵など、アーキテクチャの変更に依る。
そして、LGA1366になったことでソケット形状やクーラーも変更され、クーラーは一回り大きなものとなった(写真5~6、図2)。形状は従来と似た円柱状のものとなるが、サイズが大きくなったこともあってか、130W TDPを冷却する必要があるにも関わらず、それほど回転数が上がらず静かである。
なお、テストキットにはThermalrightの「Ultra-120 eXtreme RT」も付属していた(写真7)。こちらは専用のリテンションキットによりLGA1366に取り付けするものである。テストではこちらのクーラーを使用している。
話はチップセット間インターフェイスに遡るが、Core 2シリーズとはチップセット間インターフェイスが異なるので、従来のチップセットとの互換性は一切ない。Core i7で採用されるインターフェイスはQPIと呼ばれるもので、ハイエンド向け製品となるCore i7-965 Extreme Editionは6.4GT/sec、Core i7-940/920は4.8GT/secになる。
この帯域幅は、6.4GT/secの場合に片方向12.8GB/sec、双方向25.6GB/sec、4.8GT/secの場合に片方向9.6GB/sec、双方向19.2GB/secとなる。従来のハイエンドセグメントでは1,600MHz FSBで12.8GB/secなので、6.4GT/secのモデルでは帯域幅が2倍になったことになる。メインストリーム向けの1,333MHz FSBは10.6GB/secなので、4.8GT/secのモデルで2倍弱の向上となる。
Core 2シリーズまではチップセット側にメモリコントローラを搭載していたが、NehalemコアではCPU側に内蔵され、CPUとメモリがダイレクトに通信するようになる。チップセット間インターフェイスのトラフィックも大きく軽減されるわけで、この帯域は相当な余裕ができたことになる。
そのチップセットは、「Tylersburg」の開発コード名を持つ「Intel X58 Express」が使用される。従来のチップセットではノースブリッジがMCH(Memory Controller Hub)と呼ばれてきたが、ノースブリッジ側にメモリコントローラを有していないので、IOH(Input/Output Hub)という名称に変更された(図3)。
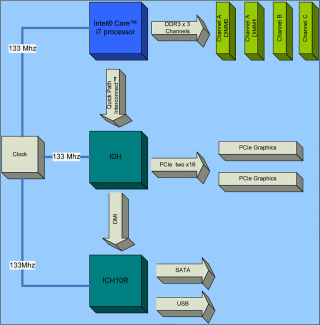 |
| 【図3】Intel X58 Express+ICH10Rの簡単なブロックダイヤグラム。CPUには133MHzがベースクロックとして供給されており、このクロックを元に、CPU内のPLLがCPUコアのクロックやメモリクロックを生成することになる |
IOHにはPCI Expressインターフェイス機能が内蔵され、2つのx16スロットを持たせることができる。マザーボード側の個別の対応が必要になるものの、このチップセットでNVIDIA SLIがサポートされるのも既報の通りで、AMDのCrossFireとNVIDIA SLIの両方を使用可能な数少ない環境となる。
サウスブリッジ側は、Intel 4シリーズチップセットでも使用されているICH10シリーズを使用。従来のチップセットと同じく1GB/secの帯域幅を持つDMI(Direct Media Interface)を用いてIOHと接続されている。
今回のテストキットに含まれるIntel X58搭載マザーボードは、同社製の「Intel DX58SO」である(写真8~13、画面3~4)。「Smackover」のコード名で開発された、IntelのExtremeシリーズに分類されるハイエンドユーザー向けマザーボードとなる。
マザーボードのディテールについては写真をご覧いただきたいが、メモリに関して少し補足しておく。メモリコントローラをCPU側に内蔵していることは先述の通りであるが、Core i7シリーズでは3chのメモリインターフェイスを持つ。マザーボード上には4本のスロットを備えており、このうちの青いスロットに3枚のDIMMを装着すれば、3chでの動作となる。
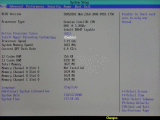 |
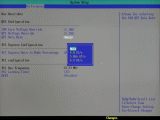 |
| 【画面3】Core i7-965 Extreme Edition搭載時のBIOS画面。BIOSバージョンは2260。テストには間に合わなかったが、バージョン2624もリリースされている。市場に投入される製品には2624、またはそれ以降のバージョンが採用されている可能性が高い | 【画面4】QPIのデータレートも変更が可能 |
加えて、マザーボード上には黒いメモリスロットもある。このスロットは容量重視のユーザー向けに用意されたもので、もちろんちゃんと動作する。この動きもかなり柔軟で、例えば、2GBを2枚と1GBを2枚装着した場合は、3chそれぞれに2GBのDIMMを挿したのと同じ動作となる。また、容量が異なる場合は利用可能な範囲内で3chアクセスが可能だ。例えば、4つのスロットすべてに1GBのDIMMを搭載した場合、3GBの範囲内では3ch動作、残りの1GBの範囲は1chで動作することになる。
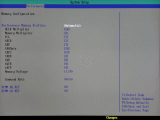 |
| 【画面5】BIOSのメモリ設定。動作クロックの設定は「Multilier」から行う。図3でも示されている通り、CPUには133MHzがベースクロックとして供給されており、デフォルト設定では133×8で1,066MHzとなる |
メモリの種類はDDR3-1066までの対応となるが、非公式にはオーバークロックでの動作も可能で、BIOSで高いクロックを指定できなくはない(画面5)。手元に対応メモリがないため試せていないが、XMP対応メモリを装着すれば、そのプロファイルを指定することもできるようである。
ただし、メモリ電圧に関して制限が設けられており、資料によれば1.6Vを超える電圧は指定しないよう注意書きがなされている。これを超える電圧を指定するとCPUが壊れるという話もあるほど。こうした高電圧の設定が記録されたXMPプロファイルを指定してはいけないなど、メモリのオーバークロックに関しては従来よりも注意を要する。
もっとも、3chインターフェイスなので帯域幅は十分というのがIntel側の主張であり、Core i7向けには、クロックよりもレイテンシを短縮したようなプロファイルを持つようなXMP対応メモリが登場するだろうとしている。
このほか、Core i7では、「Turbo Boost Technology」と呼ばれるパフォーマンスユーザー向け機能が搭載される。余談ながら、この技術名についてはIntelの資料などにバラつきがあり、当初はTurbo Modeという表現が多用されていたほか、DX58SOのBIOSではDynamic Speed Technologyという名称も登場している。ただ、最新の資料では先述のTurbo Boost Technologyとなっており、これが正式に採用されたものと考えている。
Core i7では、省電力時の動作ステートとして新たにC6ステートというものが設定され、C6ステート時にはコアの消費電力が限りなくゼロに近い状態になる(図4)。コアが休止状態になることでCPUの熱設計電力に余裕が生まれることから、この余裕を利用して動作中のコアのクロックを引き上げるのがTurbo Boostである。モバイル向けCPUのCore 2 Duoには「Intel Dynamic Acceleration Technology」という機能が用意されていたが、Turbo Boostはクアッドコア製品ということもあって、より複雑なクロックアップが可能になっているのが特徴だ(図5)。
BIOS上には、この機能を有効にするための設定項目が用意されており、デフォルトでは有効になっている。そして、オーバークロックプロテクトが解除されているCore i7-965 Extreme Editionの場合は、Turbo Boostで動作する条件クロック(倍率)やTDP/ICCの上限を超えるような指定も可能になっている(画面6)。一方、Core i7-920はそうした項目は用意されておらず、Intelが指定する安全な範囲でTurbo Boostを利用することになる(画面7)。
ちなみに、Core i7-965 Extreme Editionのデフォルト値では、コア1~3が25倍、コア4が26倍となっており、これが確実に動作する安全な圏内と見て良いだろう。Intelの資料によると、現在29倍動作(3.86GHz)の確認が取れているという。ただ、筆者が試した環境では、29倍はおろか、27倍でも動きが怪しいところがあった。結局、後述のテストは、すべてのコアを26倍に設定して行なっている。
Turbo Boostの実際の動作であるが、かなり敏感にクロックが上下する。画面8~11はCore i7-965/920それぞれで、CineBench R10のシングルCPUレンダリングとマルチCPUレンダリングを実行しているときのクロックをチェックしたものだが、いずれの場合もTurbo Boostで指定した最高クロックへ上昇していることが分かる。CineBench R10のスタート直後はクロックが下がることもあったりするので、常にトップスピードで動いているというわけでもない。余裕があれば、とにかく動作クロックを引き上げるような印象である。
なお、上記テストはWindows Vistaの電力オプションを高パフォーマンスモードに設定して試したものである。Turbo Boostは、CPU動作中の最高ステートであるP0ステート時にのみ作動する。Windows Vistaでいえば、電力オプションの省電力モード指定時はP0ステートに達することがないのでTurbo Boostが作動しないことになる。バランスなら状況次第で、高パフォーマンスなら上述のように頻繁に作動する格好となる。その意味では、(機能本来の対象ではあるが)消費電力に妥協できるパフォーマンス重視のユーザーにとって嬉しい機能になるだろう。
●Core 2 Extreme上位モデルとの性能比較
それでは、ベンチマーク結果の紹介に移りたい。テスト環境は表2に示した通り。今回入手したテストキットには、Core i7-965 Extreme Editionの設定を変更することでCore i7-940相当として利用するための設定ガイドが同梱されていたので、その設定を施したものもテストに加えている(画面12~15)。
比較対象は、クアッドコアのCore 2シリーズの上位モデルの2つを用意した。マザーボードは、Intel X48を搭載するASUSTeKの「P5E3 Premium/WiFi-AP@n」を使用している(写真14)。
なお、メモリであるが、Core i7が3ch、Core 2が2chとメモリインターフェイスが異なり、容量の統一が難しいため、それぞれ3GBと4GBとなっている。Core i7環境はテストキットに付属したQimondaのDDR3-1066を使用(写真15)。Core 2環境ではKingstone製モジュールを使用しているが、コマンドレートを1Tにすると動作しないという問題が発生したため、ここも相違が生じている。
このほか、Core i7のテストキットには、Intel製SSDが付属しており、今回テストにも使用している。MLCを採用した80GBモデルの製品である。
【表2】テスト環境
| CPU | Core i7-965 Extreme Edition Core i7-940相当 Core i7-920 |
Core 2 Extreme QX9770 Core 2 Extreme QX9650 |
|---|---|---|
| チップセット | Intel X58 Express | Intel X48 Express |
| マザーボード | Intel DX58SO | ASUSTeK P5E3 Premium |
| メモリ | DDR3-1066(1GB×3/7-7-7-20/1T) | DDR3-1066(1GB×4/7-7-7-20/2T) |
| ビデオカード | NVIDIA GeForce GTX 280(GeForce Release 178.24) | |
| HDD | Intel X25-M(80GB MLC) | |
| OS | Windows Vista Ultimate Service Pack 1 | |
では、順に結果を紹介していく。まずは、CPU性能をチェックするために実施した、Sandra XIIのProcessor Arithmetic/Processor Multi-Media Benchmark(グラフ1)、.NET Arithmetic/Processor Multi-Media Benchmark(グラフ2)、JAVA Arithmetic/Processor Multi-Media Benchmark(グラフ3)、PCMark05のCPU Test(グラフ4~5)である。
まず、Sandra関連の結果から見ると、一部で例外はあるものの、おおむね、Core i7の全製品が、Core 2 Extreme QX9770/9650を上回る演算性能を見せている。ちなみに、Processor Arithmetic BenchmarkのDrystoneは早々にSSE4.2をサポートしている。
マルチスレッド動作が行なわれるベンチマークではあるが、Turbo Boostの効果も多くのシーンで出ている。なお、Whetstone JAVAのCore i7-920のTurbo Boostの結果が奮わないが、ほかのテスト傾向から見ても明らかに特殊な結果であり、異常値だと思われる。ご了承いただきたい。
一方、アプリケーション利用のイメージに近いCPUベンチマークであるPCMark05のCPU Testの場合は、演算性能を見るSandraとはかなり違った傾向が出ており、全体にCore i7の性能が伸び悩む印象を受けるものとなった。ただ、マルチタスクテストでも最大4タスクまでで負荷はわりと軽めであることから、Turbo Boostはしっかり効いている結果になっている。
続いてはメモリ周りのチェックだ。テストは、Sandra 2009のMemory Bandwidth Benchmark(グラフ6)、Cache & Memory Benchmark(グラフ7)と、PCMark05のMemory Latency Test(グラフ8)である。
Memory Bandwidth Benchmarkはメモリ帯域幅の測定を行なうものである。3ch DDR3-1066の理論帯域幅は25.6GB/sec、2chの場合は17GB/secとなり、その差は1.5倍である。しかしながら、結果はCore i7が2倍以上の帯域幅を発揮しており、効率の良さを感じさせる結果となっている。
Cache & Memory Benchmarkによる実際のメモリアクセス速度も倍以上の差が付いており、メモリコントローラをCPUに内蔵したことの効果が非常に明確に出ている。また、Memory Lantency Testにおいても16MBテストのメモリレイテンシがよい結果になっている。
キャッシュ周りを見てみると、Core i7の4KBのメモリレイテンシが奮わない結果となっていることが分かる。アクセス速度の方も8KB以下ではCore 2両製品以下の速度になっている。Core i7では最終的にメモリのレイテンシを削減するため、キャッシュTLBに大きく手が加えられ、エントリ数が増やされるなどしている。このTLBの仕組みの変更により、こうした小容量アクセスの効率が落ちているのではないかと想像される。
一方、L2キャッシュのTLBエントリ数も増やされているのだが、こちらはコア単位に256KBとなっており、2コア共有で6MBというCore 2両製品に比べて低容量であることから、こちらは効率が良いと見えて、アクセス速度も良好だ。新採用されたL3キャッシュは4コア共有で8MBという構造であるが、Core 2両製品のL2キャッシュに比べると、アクセス速度は遅めの結果となっている。L3という構造上、これは致し方ないだろう。
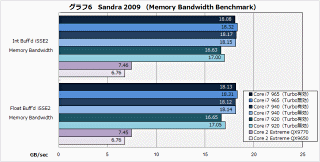 |
| 【グラフ6】Sandra 2009 (Memory Bandwidth Benchmark) |
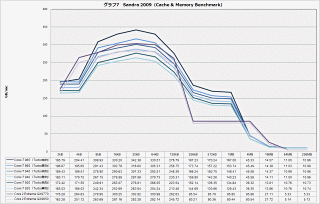 |
| 【グラフ7】Sandra 2009(Cache & Memory Benchmark) |
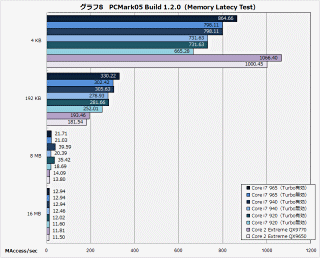 |
| 【グラフ8】PCMark05 Build 1.2.0(Memory Latecy Test) |
次は実際のアプリケーションを用いたベンチマーク結果だ。テストはSYSmark 2007 Preview(グラフ9)、PCMark Vantage(グラフ10)、CineBench R10(グラフ11)、動画エンコードテスト(グラフ12)である。なお、PCMark VantageはGame関連とProductivity関連で確実にフリーズするというトラブルが発生したため、テストが完走したもののみ掲載している。
Core i7の良さが出たアプリケーションと、Core 2の良さが出たアプリケーションが、かなりはっきり分かれる結果となった。例えばSYSmark 2007やMPEG-2(TMPGEncエンジン)を除く動画エンコードではCore i7が良好な傾向を見せる。
Core i7-965 Extreme EditionのTurbo Boostに限っていえば、ほとんどのテストでCore 2両製品を上回っているが、Turbo Boostを無効にした場合やHyper-Threadingが活きないCineBench R10の4スレッドレンダリングあたりはCore 2 Extreme QX9770に劣るシーンも見られる。Core i7がいかに、これらのテクノロジに支えられているかよく分かる結果である。一方で、Core 2両製品がかなり健闘しているテストも多い。
もっとも、Core i7-940や920は、Core 2 Extreme QX9770よりも下のセグメントで勝負する製品であり、似た価格帯となるCore i7-940と(現在ではCore 2 Quad Q9650に置き換わっている)Core 2 Extreme QX9650との比較では、Core i7-940が多くのテストで上回る結果を見せている。
さらに前向きな見方をすえれば、TMPGEncエンジンを除く動画エンコードあたりはCore i7-920が価格が2倍以上となるCore 2両製品を上回る結果を見せるなど、得意なところで凄まじい性能を見せる。Core i7は得手不得手が出ている点に少々意外な印象を受けてはいるものの、ハマったときの性能は高さは特筆できるものである。
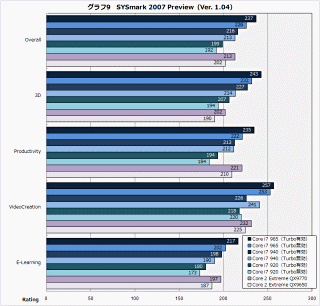 |
| 【グラフ9】SYSmark 2007 Preview(Ver. 1.04) |
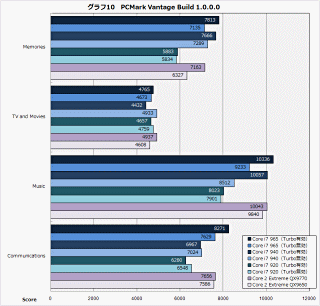 |
| 【グラフ10】PCMark Vantage Build 1.0.0.0 |
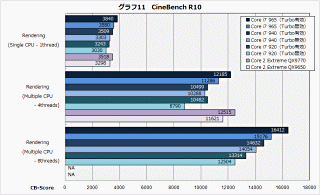 |
| 【グラフ11】CineBench R10 |
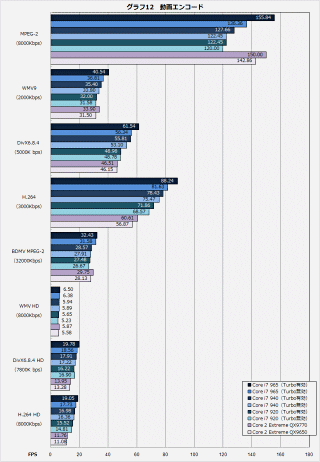 |
| 【グラフ12】動画エンコード |
続いて3D系のベンチマークである。テストは3DMark 06/VantageのCPU Test(グラフ13)、3DMark VantageのGraphics Test(グラフ14)、3DMark06のSM2.0 TestとHDR/SM3.0 Test(グラフ15)、LOST PLANET EXTREME CONDITION(グラフ16)、Unreal Tournament 3(グラフ17)だ。
両3DMarkのCPU Testにおいては、Core i7の結果が非常に良好である。3DMark Vantageでは、物理演算テストのゲート数による負荷調整が行なわれるが、それでいて圧倒的な性能を見せている。また、LOST PLANETのCaveテストや、Unreal 3のBotテストのように、CPU性能が活きるような内容ではCore i7が好結果を残す傾向を見せており、ゲームエンジンにおいてCPUが行なうべき処理の素行は良好といえる。
一方で、そのほかのグラフィック中心のテストにおいては、Core 2環境が健闘を見せる。典型的なところでは、LOST PLANETのSnowや、Unreal 3のFlyThroughで描画負荷が高くなるUXGA解像度が分かりやすい。また、LOST PLANETのCaveでも3D描画負荷が高くなるUXGA解像度では似たような傾向を示している。
また、3D描画負荷が高くなるとビデオカード側がボトルネックとなり、CPU処理の側に余裕(待ち)が生まれることになるので、当然ながらTurbo Boostによるクロック向上効果はほとんど出なくなる。
グラフィック描画に関してはチップセットの影響も考えられるわけだが、Core i7とIntel X58の組み合わせがゲームに向いているか、と問われると、そうとも言い切れない結果といえるだろう。3Dゲームはハイエンド環境が求められるアプリケーションの一つであるが、マルチGPU環境を柔軟に構築できるというメリットをのぞけば、パフォーマンス面ではあと一歩、魅力に欠ける印象が残る。
最後に消費電力の測定結果である(グラフ18)。ここでは、使用スレッド数別に結果を把握するため、アイドル時のほかはCineBench R10の結果のみを利用した。マルチCPUレンダリングは、Core i7各製品が8スレッド、Core 2両製品が4スレッドで動作させている。なお、Core i7-940は先述の通り倍率を変えて相当品を作っているものであるため、消費電力は参考程度にしたい。
全体的に見ると、Core i7の消費電力がCore 2から極端に増えている印象は受けないかも知れない。ただ、8スレッドがすべて動作したときは、わりと大きな消費電力になっている。また、Core 2 Extreme QX9770は、Core 2シリーズの中でももっとも消費電力が大きい製品であり、メインストリーム製品であるCore i7-920が、この製品と似た消費電力なのは好ましくない。
面白いのは、Core 2両製品に比べ、Core i7各製品は動作によって消費電力の幅が非常に大きい。アイドル時はCore 2両製品よりも消費電力が抑えられ、シングルCPUレンダリング時はCore 2両製品の中間レベル、マルチスレッドCPUレンダリング時は跳ね上がるといった格好である。コアごとの省電力機能が非常に有効に働いていると見られる結果であり、必要なだけ電力を消費し、無駄な電力をうまく抑制できている。
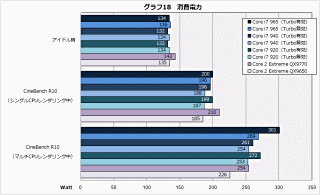 |
| 【グラフ18】消費電力 |
●高パフォーマンスを求めるユーザーには価値ある存在
以上の通り、Core i7のパフォーマンスをチェックしてきたが、ハイエンドを中心としたデスクトップ向け製品の性能の底上げには成功しているように思う。意外にもCore i7の得手不得手が色濃く出るなか、(Turbo Boost前提とはなるが)Core i7-965 Extreme EditionはCore 2 Extreme QX9770を、Core i7-940相当品はCore 2 Extreme QX9650を、ほとんどのテストで上回ることができているのは好印象である。
前半でも触れた通り、今回のテストではCore i7-965 Extreme EditionのTurbo Boostを26倍にしている。さらに上のクロックで動作させることができるようであれば、この性能はさらに高まる。
Core i7-920については、284ドルという意欲的な価格付けがされているが、動画エンコードなどはCore 2 Extreme Edition両製品を上回る結果も見せている。今回、似た価格帯のCore 2製品を比較できていないので、その点に言及はできないが、少なくとも用途を限定すれば、Core 2のハイエンドに勝ることがあるのは確かで、この爆発力は魅力的である。
ただ、LGA1366というプラットフォームはハイエンドデスクトップ向けという限られたセグメントでのみ利用される見込みで、より一般的なデスクトップユーザー向けにはLGA1156という別のソケットを用いたプラットフォームが用意される点は気に留めておきたい。
200ドル台のCore i7-920のような製品が存在している以上、ハイエンドユーザー限定プラットフォームとも言い切れない(その意味ではSkulltrailほど究極的なものではない)が、ある程度パフォーマンスを重視するハイエンド寄りユーザー向けのプラットフォームではある。そうしたプラットフォームのためにマザーボードを買う必要があることを考えれば、ユーザーがかなり限定されるのは間違いないだろう。
とはいえ、LGA1156のNehalem製品は早くても来年終盤になる予定で、1年以上も先の話だし、LGA1366は3chメモリインターフェイスとなるが、LGA1156は2chメモリインターフェイスと、パフォーマンスに影響する明確な機能差を付けている。現状のCore 2 ExtremeやQuadの高クロックモデルを上回るパフォーマンスを求めるユーザーにとっては、このLGA1366を採用したCore i7-965/940/920も十分に検討価値のある製品といえる。
□関連記事
【8月28日】【NVISION08】NVIDIAが、Intel X58チップセットでのネイティブSLI対応を緊急発表
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/2008/0828/nvision07.htm
【8月26日】【海外】Nehalemの性能を引き上げる切り札「ターボモード」
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/2008/0826/kaigai463.htm
【8月11日】インテル、Nehalemのブランドを「Core i7」に決定
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/2008/0811/intel.htm
【4月24日】【海外】Intelの次期CPU「Nehalem」の設計思想は“1 for 1”
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/2008/0424/kaigai437.htm
(2008年11月3日)
[Text by 多和田新也]
【PC Watchホームページ】
PC Watch編集部 pc-watch-info@impress.co.jp ご質問に対して、個別にご回答はいたしません
Copyright (c) 2008 Impress Corporation, an Impress Group company. All rights reserved.