 |


■後藤弘茂のWeekly海外ニュース■Core 2 Extreme+NVIDIA SLIで攻めるIntelのモバイルCPU |
●動作周波数がゆるやかな向上へ向かうモバイルCPU
Intelの今年(2007年)から来年(2008年)頭にかけてのモバイルCPUのロードマップは、非常に穏当だ。デュアルコア化とCore Microarchitecture(Core MA)化を着実に進め、新プラットフォーム「Santa Rosa(サンタローザ)」への移行も進める。ただし、1点だけラディカルな変化がある。それは、ハイエンド向けの「Core 2 Extreme」プロセッサの投入で、このCPUでは、Intelは異例なことにNVIDIA SLIとの組み合わせも推進する。つまり、Intelで固めたプラットフォームに固執せず、ゲーム市場向けにハイパフォーマンスプラットフォームを投入しようとしている。
モバイルCPUでも、デスクトップCPUと同様、今年は緩やかに動作周波数が向上する。同価格同TDP(Thermal Design Power:熱設計消費電力)のラインで、周波数が年間で10数%から20%程度上昇する。デスクトップと同じで、過去2年の周波数の停滞がようやく解除される。Intelは次の「Penryn(ペンリン)」では、45nmプロセスのおかげで周波数向上の余地があると説明している。
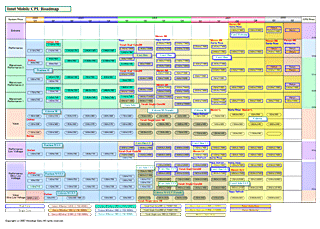 |
| IntelモバイルCPUのロードマップ PDF版はこちら |
Penrynは2008年第1四半期に登場する。これは、デスクトップと同じタイミングだ。Intelは顧客に対してPenrynのエンジニアリングサンプル(ES1)を5~6月に提供する予定で、8~9月には次のエンジニアリングサンプル(ES2)を、第4四半期には量産サンプルを提供する。IntelはSanta Rosa(サンタローザ)プラットフォームのガイドラインで、すでにPenrynに対応できる熱設計について伝えている。計画通りなら、PCメーカーは同じSanta RosaベースのノートPCで、MeromからPenrynへとスムーズに移行できるはずだ。
MeromがNapa Platformで登場し、Santa Rosaへと移行したように、PenrynもSanta Rosaで登場し、Montevina(モンテヴィーナ)へと2008年第2四半期に移行する。Montevinaでは、チップセットが「Cantiga(カンティーガ)」と「ICH9M」の組み合わせとなる。Montevinaでは、WiMAXがサポートされる無線モジュール「Ebron」が加わるほか、Robsonも2.0になる。チップセットの機能としては、「Intel Trusted Execution Technology(TXT)」と「Intel Virtualization Technology」の「VT-d」もサポートされる。MontevinaプラットフォームでのCPU側の違いはFSBが800MHzから1,067MHzへと高速化すること。
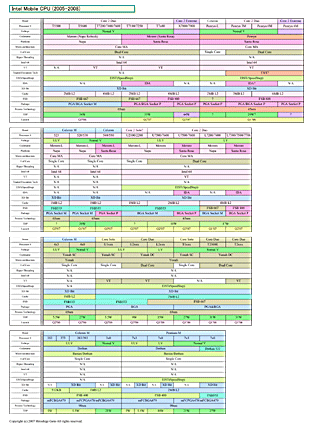 |
| IntelモバイルCPUのスペック比較 PDF版はこちら |
●デュアルコアが80%強になるIntelのモバイルCPU
モバイルCPU全体のデュアルコア化とCore MA化のペースは下のチャートの通り。Intelは、昨年(2006年)後半までに7割以上のモバイルCPUをデュアルコアに置き換えた。デュアルコア化のペースはデスクトップCPUより急速だった。
しかし、今年(2007年)に入るとペースは緩み、第2四半期以降は8割強のところでデュアルコア化が止まる。デスクトップCPUの方がデュアル/マルチコア化率が高くなる。また、Core MAへの移行でも、デスクトップCPUに追い抜かれる。つまり、モバイルCPUとデスクトップCPUを比べると、今年に関しては、デスクトップの方がずっとアグレッシブだ。
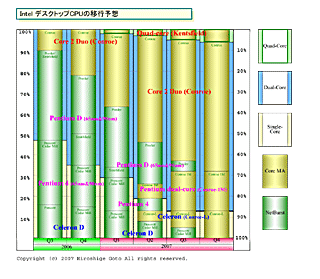 |
| モバイルCPUの移行予想 PDF版はこちら |
モバイルCPUでの移行は非常に穏当で、まず、ほとんど消えかけているPentium M(Dothan:ドタン)系コアがフェードアウト、Core(Yonah:ヨナ)が今年末にかけて消えてゆく。つまり、1年交代の波で新CPUアーキテクチャへの移行が完了する。
Intelはデスクトップではパフォーマンス系とバリュー系の両CPUの比率をラディカルに変えた。旧バリュー系ブランドのCeleron系は今年は10数%に押さえ込まれるが、その上のPentium系ブランドも実質バリュー価格。そのため、バリュー価格の100ドル以下のCPUは全体の30%以上を占める。
それに対して、モバイルCPUでは、全体の価格体系の変化はずっと小さい。Core系ブランドがパフォーマンスCPU、Celeron系ブランドがバリューCPU。バリューCPUは200ドル以下のラインで、20%台後半の比率を予定する。つまり、Intelは今のところモバイルCPUでは、価格や構成でアグレッシブな戦術を採らなくても、市場を維持できると見ていることになる。ちなみに、ブランディングでは、バリューCPUは従来の「Celeron M」から、Santa RosaベースのMeromではMがとれた「Celeron」ブランドになる。デスクトップCPUと同じブランド変更だ。
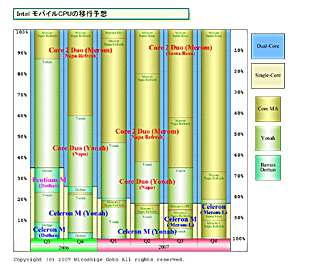 |
| モバイルCPUの移行予想 PDF版はこちら |
●NVIDIA SLIが最大のフィーチャとなるCore 2 Extreme
Santa Rosa世代の大きなポイントは、IntelがノートPC向けにエンスージアスト向けの「Core 2 Extreme」プロセッサを投入することだ。Core 2 ExtremeはMerom(メロン)ベースで、今年(2007年)第3四半期に2.6GHz(X7800)、第4四半期に2.8GHz(X7900)がリリースされ、来年(2008年)第1四半期に「Penryn(ペンリン)」へと移行する。
ブランド名から分かるとおり、Core 2 ExtremeはデスクトップのCore 2 Extremeと同様にエンスージアスト向けで、特にゲームPC市場を狙っている。Core 2 ExtremeがこれまでのIntelモバイルCPUと異なる特徴は、オーバークロックを前提としている点と、NVIDIA SLIとの組み合わせを主眼に据えている点。「モバイルにSLIによるデュアルグラフィックスとオーバークロックCPUの組み合わせを」と提案している。
Core 2 Extremeでは、バスとコアのクロック比を固定するオーバークロックプロテクションは解除されている。TDP(Thermal Design Power:熱設計消費電力)は44Wだが、これはあくまでも定格の周波数で動作させた場合。オーバークロック時にはサーマル対策の強化が必要となり、それはPCベンダー側の責任範囲となる。
Core 2 Extremeではオーバークロックが容易な反面、「IDA(Intel Dynamic Acceleration)」はサポートされない。IDAはSanta RosaのCore 2 Duoでサポートされるデュアルコア制御で、シングルスレッド性能だけが要求される時に、片方のコアをC3ステイトに留めて、シングルコアの周波数を上げるモードだ。Core 2 Extreme系では、このモードはサポートされず、デュアルコア性能を追求する。
チップセットは「Intel GM/PM965 Express」がバリデーション済み。つまり、正式サポートチップセットはGM/PM965だが、NVIDIAとのNVIDIAの「nForce SLI 100」チップセットも推奨される。Intelは2006年中盤からNVIDIAのチップセット部隊と頻繁にミーティングを行なっていたが、その成果の1つがこれだ。両社は、SLIをIntelのノートPCプラットフォームにもたらすことで合意したという。
このコラボレーションの結果、Core 2 Extremeでは、nForce SLI 100による2x16のPCI Expressデュアルグラフィックスの組み合わせが主流になると見られる。MXMフォームファクタでのグラフィックスカードを2基搭載した、または2基搭載可能なノートPCが、Core 2 Extremeベースで登場すると推定される。
こうしたCore 2 Extremeの動きは、ゲームPCで重要なカギとなる、オーバークロックとSLIの2要件をIntelも理解しており、ノートPC向け製品でもそのための積極策を打ったことを意味している。ただし、日本ではマルチメディアノートPCは強く求められていても、ゲームノートPCは市場規模が小さい。そのため、メーカーにはインパクトが小さい。
もっとも、海外でもゲーミング市場の規模自体は、それほど巨大なわけではない。しかし、海外市場ではゲーミング市場が、ハイエンドPCを牽引している。そのため、ここを押さえることは、Intel製品に対する高パフォーマンスイメージを強化するのに有効だ。そうした効果を考えたマーケット主導の戦略と見て取れる。
モバイル版Core 2 ExtremeのProcessor Numberのプリフィックスは「X」。これはデスクトップのシングルコア版Core 2 Extremeと同じ。ややこしいことに、これでXがデスクトップとモバイルの両方に存在することとなった。プリフィックスがTDPレンジを示すという原則は崩れたことになる。
「X」は英語的にはインパクトがあるので、エンスージアスト向けに共通化させた結果だと見られる。些細なことだが、このあたりの一貫性のなさは、IntelのProcessor Numberが技術的に設定されているというより、むしろマーケティング上の産物であることが再確認される。
●さらにローパワーへ向かうIntel CPU
Core 2 ExtremeはPC的には話題でも、CPU的に見るとそれほどトピックスではない。CPUの潮流としては、むしろ、より低いTDPレンジへの拡大の方が顕著な流れだ。IntelとAMDのどちらも現在、モバイル系CPUアーキテクチャをさらに下のレンジへ伸ばす方向にある。低コストかつ低消費電力のx86系CPU製品の開発に拍車をかけつつある。
ターゲットとしているのは、伝統的PC市場以外の、エマージングマーケットと組み込み系、携帯機器の3分野。成熟市場となった先進国のPC&サーバー市場の成長は鈍化している。それに対して、先進国以外のエマージングマーケット地域向けコンピュータやデジタル家電、携帯機器の市場はより成長率が高い。そのため、IntelとAMDともに、比重をこれらの市場に移していこうという動きが出ている。そして、両社とも、これらの市場でのx86アーキテクチャのソフトウェア上の利点が出始めたと考えている。
Intelは、主に携帯機器市場向けに「LPIA(Low Power Intel Architecture)」または「LPP(Low Power Processor)」と呼ばれる、IA-32系命令セットアーキテクチャの超低消費電力CPUを開発している。最初のLPIAはPentium M(Banias:バニアス)系CPUコアを使った、それほど画期的なCPUではない。しかし、2008年にはフロムスクラッチで開発された新しいCPUコアを使った製品が出てくる。
IntelのLPIAについては、多少状況が見えてきた。LPIAプロセッサの計画では、Intelは初期には「MMX Pentium(P55C)」コアを再利用・拡張するプランも出たという。しかし、現在必要とされているフィーチャを実装するには、新コアを開発する方がよいと判断されたようだ。機能的には現在のPC向けCPUに近いが、パフォーマンスとTDPレンジが低いCPUコアとなるらしい。機能面で古い、前世代のCPUアーキテクチャを再利用する、旧来のアプローチではない。
この2008年のLPIAプロセッサでは、CPUのダイ(半導体本体)は現行のシングルコアPentium Mの約1/4程度のサイズになると言われている。ただし、out-of-order型スーパースカラといった、IntelのPC向けCPUの基本的な方向性は変わらないらしい。つまり、動的スケジューリング機能を完全に省くような、ラディカルなアーキテクチャは採らないと見られる。このことは、LPIAでも、シングルスレッドの汎用コンピューティング性能も、一定水準が維持されることを意味している。
消費電力はチップセットと合わせて3W以下。さらに、その後に登場するCPUとチップセットの統合型SoC(System on Chip)製品では、合計で1Wの消費電力に抑えられると言われている。
Intelは、以前は一定の消費電力レンジから下はARMアーキテクチャの「XScale(旧StrongARM2系)」を据えていた。しかし、現在のIntelは方向を転換、IA-32アーキテクチャを低消費電力のレンジにももたらそうとしている。また、Intelには、LPIAとは別系統で、Pentium M(Banias:バニアス)系CPUコアを使った組み込み型SoC(System on Chip)製品のプランがある。
こうして見ると、IntelはPC&サーバーではCPUコアアーキテクチャを一本化しつつ、その一方で他の新市場向けに新しいCPUコアアーキテクチャや派生品を導入しようとしていることがわかる。別な見方をすれば、x86系アーキテクチャのバリエーションを広げようとしている。RISC系XScaleなどに分散していたリソースをx86集結させるイメージだ。また、IntelがSoC型のアプローチに積極的になってきたことも1つの傾向だ。LPIAや組み込み型x86のいずれでもSoCへと向かっている。
最後に訂正を1点。前回の記事中のPenrynベースのサーバー向けクアッドコアCPUのコードネームに間違いがあった。「Harpertown(ハーパータウン)」が正確なコードネームだ。
□関連記事
【2月6日】【海外】45nmプロセスの利点を活かすIntelの次世代CPU「Penryn」
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/2007/0206/kaigai334.htm
【1月30日】【笠原】見えてきたSanta Rosaの全貌
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/2006/1130/ubiq169.htm
(2007年2月8日)
[Reported by 後藤 弘茂(Hiroshige Goto)]
【PC Watchホームページ】
PC Watch編集部 pc-watch-info@impress.co.jp ご質問に対して、個別にご回答はいたしません
Copyright (c) 2007 Impress Watch Corporation, an Impress Group company. All rights reserved.