 |


■三浦優子のIT業界通信■ソースネクストが進める1,980円ソフト戦略の影響 |
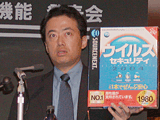 |
| ソースネクスト 松田憲幸社長 |
こうした動きを見て、競合ソフトメーカーも、「一部製品の価格は見直さざるを得なくなった」と話す。ユーザーからすると、ソフトが低価格になることは歓迎すべき動きに思えるのだが、「収益を越えた低価格化によって、日本のソフトメーカーは商品作りをじっくり進めていくことができなくなる。結局はユーザーにマイナス影響を及ぼす」との指摘もある。果たして、ソフト低価格化はユーザーに何をもたらそうとしているのか。
●「価格の壁を取り払う」と市場拡大に挑戦するソースネクスト
 |
| ソースネクスト版1・2・3のパッケージ |
'88年時点、NEC PC98シリーズ用MS-DOS版の「ロータス1-2-3」の価格は98,000円だった。ちょうど10年前の'93年に58,000円となり、最新の「1-2-3 2001」で20,000円まで下がっていたとはいうものの1,980円とはまさに桁が違う価格だ。(価格は標準版)。
1-2-3自身の位置の変化や、Super Officeという形では低価格化が進められていたという事情はあるものの、10年で価格が10分の1どころか、20分の1以下になったというのは、感慨を抱かせる。
1,980円戦略の張本人であるソースネクストの松田憲幸社長は、「ゲームソフトに比べ、パソコンソフトはハードに比べてソフトの販売本数が少なすぎる」と指摘。ソフトの売れ行きはもっと伸びてしかるべきなのに、伸び悩んでいる原因のひとつを、「ソフトの単価の高さ」として、1,980円戦略はユーザーにとってもプラスメリットが大きいものであることを強調する。
最初にソースネクストがソフトの単価を1,980円とすることを発表したのは今年2月。各ソフトメーカーは、この戦略は注目を集めたものの、すぐに追随する企業は現れず、様子見状態が続いていた。しかし、6月にソースネクストが、「1,980円のソフトの数を年末までに100タイトル以上揃える」と戦略を加速することを発表。8月にはTDKが「手軽に役立つ1,980円シリーズ」を揃えることがアナウンスされると、そろそろ競合メーカーも様子を見ているだけではいられなくなったようだ。
「実は、当初予定の価格を発売直前になって見直したんです」--9月12日に初めてユーティリティソフト「パソコンのビタミンシリーズ」として、インターネット高速化ソフト「ネットハイスピーダー」、バックアップソフト「オートバックアッパー」などを発売したNECインターチャネルでは、「オートバックアッパー」の価格が3,980円なのに対し、「ネットハイスピーダー」の価格を1,980円とした。
インターネットを高速化するソフトとしては、ソースネクストの「驚速シリーズ」が先行している。さらに、TDKも1,980円のシリーズを発売するという発表があったことを受けて、「戦略的に1,980円という価格にした」と説明する。
今後もNECインターチャネルのように、「直接競合となる商品については、価格を見直す」という企業が出てくる可能性は高い。
●デメリットを指摘する声も
こうしたソフト低価格化の動きは、ユーザーにとっては有り難い動きだといえる。ロータス1・2・3が98,000円という時代であれば、「ちょっと試しに」でソフトを購入するのは無理だった。
近年、1万円以下のソフトが増えたとはいうものの、普通のサラリーマンや学生であれば、月に何本もソフトを購入するのは難しい。ソースネクストの松田社長の指摘通り、「ソフトの単価が、パソコンソフト市場拡大の障壁となっている」ことは間違いないだろう。
だが、「ソフトの低価格化は、ユーザーにプラスをもたらすばかりではない」との指摘もある。
FAX通信ソフト「まいとーくシリーズ」をはじめ、最近では積極的にユーティリティソフトを販売するインターコムの高橋啓介社長は、「ソフトの低価格化はユーザーにプラス面ばかりではないとはいえないのではないか」と訴える。
高橋社長は、「メーカーが収益を得ることができなければ、積極的な開発投資ができなくなる。価格面で対抗していこうとすれば、自社で開発するのではなく、海外から製品を持ってきたり、他社が開発した製品を販売していかざるを得ない。つまり、日本のソフトメーカーにモノ作りの力がなくなってしまう」と指摘する。
高橋社長が、「日本のソフトメーカーのモノ作り」という点に固執するのには理由がある。すでに、企業向けシステム開発において、低コストに抑えることを目的に、中国やインドのソフト開発力をどう活用するのかが大きな焦点となっている。こうした動きを横目に見ると、「せめてパソコン用パッケージソフトは日本で」という気持ちになるのも無理はない。
しかも、ソフト開発拠点が海外にシフトし、海外製のものを日本向けに一部手直しするだけでは、「日本独自のニーズというものに応えられなくなる」と高橋社長は続ける。具体例として、DVD関連ソフトをあげる。「DVDのハード側の規格には、日本発というものが少なくない。海外ではデファクトとなっていないものの、日本では多くの企業が採用する規格もあるため、海外からソフトを持ってくるだけでは、日本のユーザーには支持してもらえない。日本の状況にあわせて開発するということは、ユーザーにとっては必要なことではないか」。
高橋社長が指摘する、「日本で支持されている規格に対応する」といったニーズは、DVD以外にも起こり得ることだろう。確かに、こうした細かい部分が必要になる場面もある。
 |
| イメージキャラクターにボブ・サップを起用(6月の戦略説明会) |
さらに、販売本数を増やすために、ソースネクストでは格闘家のボブ・サップを起用した広告展開を行なったり、パソコン販売店以外の書店、大型スーパー、コンビニエンスストアなど販売拠点を増やし、これまでパソコン売り場以外のところでのセールスを増やすなど、市場拡大に積極的だ。
その一方で、ソースネクストの1,980円戦略を実施後も、「ソフト市場が活性化しているとはいえない」という声がパソコン販売店からはあがっている。低価格ソフトが増えたことで、「ソフト売り場では収益を確保しにくい。ソフト売り場を縮めて、デジタルカメラや書籍など他の商材を増やした方が収益が取りやすい」というのだ。
おそらく、松田社長の言うように「販売本数が増やす」ことが実現できれば、パソコンショップ側も1本あたりの単価が低くても、ソフト売り場を縮めるという発想は出ないはずだ。現状では、1,980円ソフトが増加したことで、「ソフト市場が大きく盛り上がっている」という声は聞こえてこない。市場が活性化されれば、ユーザーにとってもメリットある低価格化が実現するのではないだろうか。
□関連記事
【9月29日】ソースネクスト、インドのウイルス対策ソフトなど1,980円シリーズ拡充(INTERNET)
http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2003/09/29/579.html
【6月2日】ソースネクスト、事業戦略説明会を開催
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/2003/0602/source.htm
(2003年9月30日)
[Text by 三浦優子]
【PC Watchホームページ】
PC Watch編集部 pc-watch-info@impress.co.jp 個別にご回答することはいたしかねます。
Copyright (c) 2003 Impress Corporation All rights reserved.