|
|
 1月のCESで初公開された日本ビクター初のデジタルスチルカメラ「GC-S1」が日本国内でも正式発表された。本機は光学式10倍ズームレンズを採用したコンパクトサイズのVGAモデル。最近はズーム付きモデルが増えつつあるが、光学10倍ズーム搭載のパーソナル機となると、ソニーのフロッピー採用機「MVC-FD7」くらいしかなく、なかなか貴重な存在だ。
1月のCESで初公開された日本ビクター初のデジタルスチルカメラ「GC-S1」が日本国内でも正式発表された。本機は光学式10倍ズームレンズを採用したコンパクトサイズのVGAモデル。最近はズーム付きモデルが増えつつあるが、光学10倍ズーム搭載のパーソナル機となると、ソニーのフロッピー採用機「MVC-FD7」くらいしかなく、なかなか貴重な存在だ。注:この記事に掲載している写真は、本体の写真を除いて全てGC-S1で撮影したサンプル画像です。また、この製品の詳細については関連記事をご覧ください。(編集部)
●小型軽量な光学10倍ズーム搭載機
 いまや数多くのメーカーがデジタルカメラ市場に参入しているが、そのなかで本機で初めて市場参入する日本ビクターは、大手ビデオカメラメーカーとしては最後発といえる存在だ。それだけに、この時期に登場するモデルとしては、かなりインパクトのある製品である必要がある。
いまや数多くのメーカーがデジタルカメラ市場に参入しているが、そのなかで本機で初めて市場参入する日本ビクターは、大手ビデオカメラメーカーとしては最後発といえる存在だ。それだけに、この時期に登場するモデルとしては、かなりインパクトのある製品である必要がある。
私自身、今回の「GC-S1」を米国のCESで初めて見たときは、結構インパクトがあり、「10倍ズームでもコンパクトだなあ~」というのが本機の第一印象だった。
今回、ベータ版モデルを手にしてみると、あらためてその小ささに感心する。VGAの3倍ズーム機と同等のコンパクトさだ。常時持ち歩けるレベルであり、回転式のレンズ部を立てることで凹凸が少なくなるので、携帯性はなかなか良好だ。
また、電源が入手しやすい単三形電池4本で、記録媒体も大容量化に有利で安定性の高いコンパクトフラッシュ(CF)カードという点も好ましい。
●不満を感じる、不明瞭でレスポンスの遅い液晶表示
しかし、同社初のデジタルカメラということもあってか、実際に使い始めてみると、不満な点が目立つ。
まず、一番気になるのが、液晶ファインダーの見にくさだ。本機は光学ファインダーのない液晶専用機であり、液晶表示の品質はカメラの使い勝手や印象を大きく左右するポイントである。
ところが、本機の液晶のレスポンスはかなり(おそらく現行の液晶専用機のなかで最も)遅い。CESやPMAの会場で見た参考出品モデルでも気になっていたが、今回使用したベータ版モデルに至っても改良されておらず、実用上支障があるレベルだ。人物の表情を捉えるどころか、正確なフレーミングをするのも難しいほどで、とてもビデオカメラメーカーの作ったものとは思えない。
もっとも、このレスポンスの遅さを軽減するために、液晶表示をモノクロ化するモードが用意されており、通常のモデルに近い表示レスポンスにはなるが、これは本末転倒の策であり、急場しのぎにすぎない。
また、液晶はTFT式にも関わらずバックライトが暗いせいか、表示自体も不明瞭だ。周囲が暗い屋内ではいいが、晴天の日中屋外での視認性がきわめて悪い。液晶に手をかざして影を作らないと、構図の確認すらできないほどで、液晶ファインダー専用機としては致命的といえる。
撮影時に10倍ズームをズーミングする際にも、液晶表示がスローでコマ送り状態でしか見えないため、どこまでズームすればちょうどいい画角になるのかという判断がつきにくい。また、10倍ズームの望遠側では35mmカメラ換算で400mm相当の超望遠になるのだが、これもコマ送り状態のため、どこを撮っているのかわかりにくい。これではせっかくの10倍ズームも本領を発揮できないだろう。
●猛烈な電池消耗
電池の消耗の早さにも驚かされる。本機がベータ版であるとはいえ、通常の使用条件で、新品のアルカリ電池で20枚程度しか撮影できない。銘柄の違う新品電池で、何度も確かめたが、結果は同じようなものだ。ノーマルモードで約60枚撮影できる4MBのCFカードをフルに撮影するのに、3セット(12本)もの新品電池を消費してしまった。
最近は昔ほど電池の消耗が激しいモデルは少なく、電池の消耗が気になるケースはめっきり減ったが、本機はおそらく、現行モデルのなかでもトップクラスの大食漢といえそうだ。
●記録時間は約5秒と長め
 記録時間は約5秒。待てる範囲ではあるが、最近のVGAクラスでは3秒クラスが主流であり、1秒を切るモデルもあることを考えると、さすがに遅さを感じる。
記録時間は約5秒。待てる範囲ではあるが、最近のVGAクラスでは3秒クラスが主流であり、1秒を切るモデルもあることを考えると、さすがに遅さを感じる。
また、シャッターを半押しすると、AFや露出がロックされるのはいいが、液晶表示画面も止まってしまう。さらにシャッターを押し込むと撮影されるわけだが、半押しで表示が静止してしまうので、最良のシャッターチャンスがつかめない。撮影後は写った画面が表示されるが、望遠側ではシャッター半押し時からかなり画面がずれていることもあった。正直なところ、なぜこのような仕様になっているのか、理解に苦しむ部分だ。
●レンズ回転に対応しないストロボ
ストロボは内蔵式だが、ボディ本体の上面に固定されているため、レンズを正規の位置にしないと、きちんとしたストロボ撮影はできない。つまり、レンズ部を回転させると、ストロボ光とレンズの向きが別々になってしまうため、ストロボは発光するが被写体にきちんと当たらなくなる。この点はレンズ回転式モデルで、ストロボを内蔵させるときに、各社が苦労する点だが、本機はこの照射方向のズレに対して何の策も施していない。せめて、レンズとストロボが同一方向を向いていない時には、液晶で警告したり、ストロボの発光を停止させるといった工夫をしてほしい。
●ビデオからの流用で、やや無理のある10倍ズームレンズ
 【超望遠効果1】 |
 【超望遠効果2】 |
35mmカメラ換算で40~400mm相当という、かなり望遠系に強いズームレンズなので、最望遠側ではほとんど望遠鏡のような感覚だ。実際に写る面積でいえば、ワイド側の1/100の範囲が画面いっぱいに写るため、その迫力は相当のものがある。
実際に、本機の発表会では、「なぜかデジタルスチルカメラは光学系にお金がかかっていないものが多いので、DVカメラのノウハウを生かして作りました」という趣旨の説明がメーカー側からおこなわれたほど、レンズには自信があるようだ。
とはいっても、本機のレンズは同社のDVカメラからの流用であり、デジタルスチルカメラ用に新設計されたものではない。そのため、レンズ性能は、あまり期待することはできない。
というのは、本来、動画を中心としたビデオ用レンズと、静止画用のデジタルカメラ用レンズでは、要求されるクォリティが大きく異なる。つまり、ビデオの場合には被写体が動いていることもあって、多少レンズの性能が低くても実用になる。しかし、静止画の場合には一枚の画像をじっくり眺めるため、より高い解像力が要求されるうえ、画面周辺までにじみのないシャープな画像が必要になる。
 【広角側で撮影】 |
 【望遠側で撮影】 |
そのため、カメラやフィルム系メーカーの製品では、35mmカメラよりも高い解像度のデジタルカメラ用レンズを新規に設計して、その要求に対応しているのが現状だ。このレベルのレンズ性能を実現するためには、単焦点レンズが理想的で、ズームレンズにしても性能面から3倍程度にとどめている。また、レンズを明るくすると、その分、画質に無理がかかるので、明るさもそこそこに抑えられている。
さて、実際に本機の画像を見ると、10倍ズームならでは迫力は感じられるものの、画質面ではDVカメラ用レンズの流用品らしい欠点が見られる。まず、ワイド側でのレンズの解像度は明らかに不足しており、明確なピントのない写りになっている。また、最望遠側では意外にシャープな写りとなっているが、それでも画面の周辺部で色の滲み(色収差)が明確に見られ、画像の輪郭部ではそれが顕著に見られる。
「なぜかデジタルスチルカメラは光学系にお金がかかっていないものが多い」と他社に対していえるレベルではないようだ。
●インパクトはあるが、彩度を強調し過ぎた不自然な色調
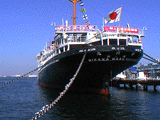 【広角側で撮影】 |
 【望遠側で撮影】 |
一方、色調や階調性も、ややクセがある。本機はCCDに補色タイプを採用しているが、これは解像感の高さもさることながら、ビデオで培った技術が活かせるというメリットを買って採用という。
本機の画像は、パッと見たときの印象は強く、なかなかきれいな写りに見える。しかし、彩度を無理に高めたような感じもあり、やや人工的な雰囲気を備えたものになっている。
とくに、青空や遠景の色調に関しては、ちょっと強調しすぎという感じもあり、シーンによってはやや現実離れした感じさえあるのが残念だ。
また、明暗の再現域も狭めで、ハイライトが真っ白く飛んでしまう傾向がある。このあたりは、好みが分かれるところだろう。
 このほか、レンズが明るく、しかも感度的に有利な補色系CCD採用機にもかかわらず、夜景のような暗いシーンがやや苦手なのは意外だった。
このほか、レンズが明るく、しかも感度的に有利な補色系CCD採用機にもかかわらず、夜景のような暗いシーンがやや苦手なのは意外だった。
本機の場合、絵作りのベースがテレビやビデオの世界という感じがする。別にそれを否定する気はないが、一枚の画像を鑑賞したり、プリントしたりするデジタルスチルカメラの場合には、もう少しおとなしい絵作りの方が好ましいのではないだろうか。
●空回りした意欲作
本機は、同社が長年ビデオカメラの世界で培った技術と経験を生かして完成させた、いかにもビデオ系メーカーらしいデジタルカメラといえる。確かに、このサイズでF1.6の光学10倍ズームレンズを搭載した点は注目に値するし、スペック的に見ると、過不足のないものに見える。
しかし、デジタルカメラの基本といえる、液晶モニターの見え具合や画質、電池の持ち、記録時間など多くの点で、未完成といわざるを得ないレベルに留まっている。これは細かな操作性もついても同様のことがいえる。
確かに個性的なモデルではあるが、大手メーカーとしては最後発であり、飛ぶべきハードルはかなり高くなっている。また、目立つための際だった特徴も必要だろう。しかし、機能の充実よりも先に、まずは現時点で最低限クリアすべき要素を、きちんと充実させるのが先決だ。その点で本機は、メーカーとしての熱意が空回りした意欲作という感じになってしまったのが残念でならない。発表会ではメガピクセルクラスへの参入という話題もあったが、次期モデルではぜひとも、デジタルカメラとしてのベースをきちんと充実させたうえで、日本ビクターらしい個性的な意欲作を見せてほしい!
■注意■
('97/3/10)
[Reported by 山田 久美夫 ]