 |


■大河原克行の「パソコン業界、東奔西走」■ヨドバシ、ビックと真っ向勝負を挑むヤマダ電機 |
 |
| ヤマダ電機 山田昇社長兼CEO |
「駅前でも日本一を狙うのかと言われても、すでにヤマダは日本一ですからね。駅前でどうだとか、そんな次元の低い話はしませんよ」――記者会見の最後の質問に、ヤマダ電機の山田昇社長兼CEOは、普段はあまり見せない笑みを浮かべながらこう答えて見せた。
ヤマダ電機は3月10日、大阪・難波に同社初となるターミナル駅隣型の大型店舗「LABI1 NAMBA(ラビワンナンバ)」をオープンした。ヤマダ電機の発表によると、オープン初日には、雨にもかかわらず、1万人が列が作ったという。
3月8日に行なわれた新店舗オープンの記者会見において、山田社長は、最後の発言を除けば、極力、他社を刺激しないような発言に終始するように心がけていたように感じた。
 |
 |
| 3月10日にオープンしたヤマダ電機 LABI1 NAMBA店 | 地下鉄難波駅に貼り出されたオープン告知 |
年商目標として掲げた300億円は、2001年にオープンしたヨドバシカメラマルチメディア梅田がすでに年商1,000億円を突破していることを考えれば、慎重すぎる数字ともいえるし、それに関するコメントも「無理な計画を立てるのではなく、着実に年間の目標を達成していくことが重要だと社員に言っている。郊外店では、3年目からうまくいけばいいといってきたが、今回の店舗もそれと同じ。経営は一気に伸ばせばいいというものではない」と、やはり慎重な姿勢を崩さなかった。
また、「当社の特徴といえば、家電製品の取り扱いであり、その点では負けない。だが、小物関係については弱いという点がある」とし、ヨドバシカメラやビックカメラ、あるいは専門色をより鮮明に打ち出した日本橋電気街に比べて、まだ改善する余地があることを自己分析してみせた。
さらに今回の出店に関しては、「郊外型店舗だけでは、お客に不便を与えていたところがあった。他の同業者に流れ、歯がゆいと感じることもあった。ナショナルチェーンとして、そのネットワークをさらに生かす一方で、都市型のLABI1 NAMBAによって、お客の不便を解消することができるようになる」とコメントしたが、これも競合他社との戦いという観点よりも、顧客中心の姿勢を全面に打ち出すコメントをしている。
続けて、日本橋電気街との問題に関しても、「話し合いの調整がうまくいかなかった経緯があるが、今後はお互いに理解を深めていきたい。会見の前には、地元町内会の方がきて喜んでくれた」とするなど、友好的な関係を築きたいとの姿勢を打ち出して見せた。
これらのコメントは、競合をむやみに刺激しないことを前提としたものだったことが感じられて仕方がない。
●ヨドバシ、ビックを強く意識した店づくり
だが、冒頭に触れた会見の最後の言葉からもわかるように、日本一の売上高を誇る実績を背景に、LABI1 NAMBAの出店によって、関西No.1、駅前No.1を目指す姿勢を強く感じざるを得ない。
それは、ヨドバシカメラ、ビックカメラ、そして、日本橋電気街を強く意識した店づくりが、店舗の端々に見て取れることからもわかる。
 |
 |
 |
| 左からヨドバシカメラマルチメディア梅田、ビックカメラ、日本橋電気街 | ||
例えば、家電製品を強みとするヤマダ電機ではあるが、実は家電製品の売り場面積は、3階フロアの2分の1程度に抑えている。
それに対して、ヨドバシ、ビックが得意とするカメラ関連の売り場の品揃えは、これまでのヤマダ電機には見られないほどの充実ぶりだ。
デジカメ売り場の担当者は、「カタログに掲載されている商品は、ほとんどが品揃えしている。アクサセリーを含めた展示数は23,000アイテム。カメラ本体については、そのほとんどを実際に操作することができる」と胸を張る。実際、「カメラ量販店に負けない展示を実現している」とまで言い切る。
デジカメ売り場には、デジタルプリントサービスのコーナーや簡易スタジオまで用意したほか、本来はウインドウの中に置かれてしまうような高価な一眼レフカメラや最新機種にも直接触れる「わくわく体験コーナー」も用意している。
また、ヤマダ電機があまり得意とはいえない、時計やアクセサリー、バックなどのブランド品売り場の面積を大きく割いているのも、ヨドバシ、ビックが得意とする分野への対抗と受け取れる。
自らが得意とする白物家電の展示よりも、カメラ量販店が強いとされる分野において、あえて展示を強化しているのだ。
 |
 |
 |
| LABI1 NAMBAのフロア構成 | 店内に設置されたカジュアルスタジオ。デジタル機器を利用して簡易に撮影ができるようにしている | |
それは、日本橋電気街が得意とする小物部分にも発揮されている。
会見では、山田社長が「小物は当社の弱い部分」としたが、それは既存の平均1,000坪の売り場面積の店舗において、小物の展示が少ないということを指していたように感じる。
「年に1個しか売れないような小物はとても在庫できなかった」と山田社長は語っていたが、裏を返せば、都市型の大規模店舗では、年に1個しか売れないような小物でも在庫できるということにつながるだろう。
実際、PCサプライの展示の品数はもとより、オーディオ製品においても、高級オーディオ向けのケーブルをはじめとするアクセサリー類の展示には目を見張るものがある。
そして、専門知識を持った店員をそれらの売り場に配置している点でも、日本橋電気街との対抗を鮮明にしているといえよう。LABI1 NAMBAの開店にあたり実施したキャリア社員の採用では、他のヤマダ電機店舗に比べて、専門知識を持った社員を、比較的多く採用しているとされていることからも、それがわかるだろう。
 |
 |
| オーディオ売り場は細かなアクセサリーの展示を充実 | PC周辺機器の充実ぶりも特筆される |
●なんばパークスとの相乗効果も
一方、ヨドバシカメラが先鞭をつけた家族向けの集客という点でも、LABI1 NAMBAの店づくりから、それを強く意識していることがわかる。
4階の書籍売り場では、男性誌に混じって、女性向けのファッション誌、幼児向けの童話、子供向けの漫画などが数多く並んでおり、女性客や子供を連れた家族の集客にも力を注いでいる。
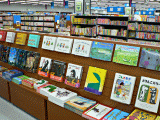 |
 |
| 書籍売り場には、児童書や童話、女性向けファッション誌などもあり普通の書店と変わらない | 書籍売り場に置かれた試読コーナー |
 |
| 2007年春に完成予定のなんばパークス第2期工事の完成パース図 |
隣接するなんばパークスの第2期工事が完了する2007年春になると、ヤマダ電機の2階部分となんばパークスが直結し、いまよりも来店しやすい環境になる。今は、難波駅から距離が離れていることが来店においてはマイナス要素だという指摘もあるが、なんばパークスの第2期工事の完成とともに、ショッピングのついでにヤマダ電機まで足を延ばすといった来店や、ヤマダ電機を訪れた帰りになんばパークスで食事をするといった相乗効果も期待できるようになる。
また、家のリフォームコーナーも、ヤマダ電機ならではの取り組みとして見逃せない。これも家族での来店を増やすには効果を発揮しそうだ。
「リフォーム、デューティーフリー、ソフト、本、サプライ、消耗品は、家電ほど競合が激しいわけではない。また、これらの分野に関しては郊外店でも経験があり、実績もある。顧客ニーズに対して、どう提案していけばいいのかといったノウハウも、自分なりに蓄積している」と山田社長は語る。
これまでに300店舗を出店し、それぞれの地域特性にあわせた販売手法やサービスを創出してきたヤマダ電機。LABI1 NAMBAでは、その数多くの手法のなかから、ヨドバシカメラ、ビックカメラ、日本橋電気街にはないものを取り揃えたともいえる。
また、山田社長はこうも語る。
「ヤマダ電機はー味違うと言われたい。そのためには、商品単品の商売をしていては店の特徴が打ち出せない。80万点に及ぶ品揃えを活用しながら、単品プラスαの提案をしていく必要がある。それが差別化につながるだろう。また、これからはサービスが重要である。そのサービスをできる限りわかりやすくお客に提案していくつもりだ」
リフォームコーナーを設置したり、カメラ売り場で自由に商品を触れるコーナーを作ったり、自動車のタイヤ販売では、取り付けのための専用車まで配置して出張サービスを行なっているが、これもヤマダ電機ならではの差別化につながる。
実は、会見の中で、「300億円は、これだけいけばペイできるというライン」であることを山田社長は漏らした。300億円の売り上げ計画は、あくまでも最低ラインであることがこの言葉からもわかるだろう。
●高い知名度を持つヤマダ電機
ヨドバシカメラやビックカメラが東京からの新規参入であったのに対して、ヤマダ電機はすでに関西地区に数多くの店舗を出店しており、その知名度は高い。
「北海道から沖縄まで、ヤマダ電機はあらゆるところに出店している。いまや全国にヤマダ電機を知らない人はいない。今回の出店でも、田舎ではヤマダを使っているから、都会でもヤマダを使ってやろうという人が少なくないはず」というのも頷ける。これがヨドバシカメラ、ビックカメラの出店時との差でもある。
さらに、「今、当店で購入している顧客のほぼ100%が当店のポイントカードを所有している」ともいう。つまり、不特定多数ではなくて、特定多数の顧客を対象にした商売がヤマダ電機の販売手法であり、ターゲティングした売り場づくりや顧客の誘導も可能なのだ。
ヤマダ電機は、LABI1 NAMBA開店のリリースの中で、「加熱する家電大阪南北戦争」という言葉を使っている。ヨドバシカメラが出店しているキタ(=梅田)に女性やファミリーが流れたことを指摘しながら、「今一度、ミナミ(=難波)への人の流れを造成し、なんば南再開発の一翼を担うべき役割を果たして参ります」としているのだ。
ヤマダ電機は、LABI1 NAMBAで大きな勝負に出た。それは、山田社長の言葉の端々や、店づくりの端々で見せているように、ヨドバシカメラ、ビックカメラ、そして日本橋電気街との対抗を強力に打ち出したものであることは明らかだ。
2007年春には、東京・池袋に「LABI」を冠にした2号店がオープンすることになる。ここはビックカメラの本拠地でもあり、しかも、ビックカメラに隣接する場所に、2,500坪以上の売り場面積で出店する可能性が高いといわれている。
そして、LABI1 NAMBAがどれだけ成功するかによって、池袋への出店時のインパクトは大きく変わるだろう。そのインパクトがどの程度のものになるのかは、現段階ではわからない。
ただ1つ確かなことは、日本一の家電量販店が、ヨドバシカメラ、ビックカメラと真っ向から戦い始めたのは明らかだということだ。
□関連記事
【3月10日】ヤマダ電機の大型店舗「LABI1なんば」開店
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/2006/0310/yamada.htm
【3月9日】ヤマダ電機、大阪なんばの大型店舗「LABI1 NAMBA」を10日オープン
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/2006/0309/yamada.htm
【2005年1月24日】ヤマダ電機、大阪難波店の工事開始
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/2005/0124/yamada.htm
(2006年3月14日)
[Text by 大河原克行]
【PC Watchホームページ】
PC Watch編集部 pc-watch-info@impress.co.jp ご質問に対して、個別にご回答はいたしません
Copyright (c) 2006 Impress Watch Corporation, an Impress Group company. All rights reserved.