 |


■大河原克行の「パソコン業界、東奔西走」■ウィルコム、過去最高契約者数突破の軌跡 |
 |
ウィルコムが12月23日付けで、過去最高となる契約者数を更新した。
これまで、最も契約者数が多かったのは、旧DDIポケット時代の'98年7月に記録した3,617,000契約。実に、7年5カ月ぶりに記録を更新したのだ。
一時期は、PHS限界説まで流れ、PHS専業のウィルコム(旧DDIポケット)の先行きを不安視する見方もあったが、ウィルコムのこの躍進を見る限り、そうした限界説は大きな誤りだったといっていいだろう。
この躍進の背景で見逃せないのが、音声定額制度の導入だ。ウィルコム加入者同士に限定しながらも、音声定額制度にいち早く乗り出したインパクトは大きかった。
実は、この音声定額制度の導入にいち早く乗り出すことができたのも、携帯電話にはない、PHSならではの特徴が生きている。
●マイクロセル方式で音声定額を実現
PHSは、1つのアンテナがカバーする領域が少ないため、多くの基地局を設置する必要がある。かつては、この基地局の数が十分ではなく、つながる場所が少ない、あるいは移動しながら話すと切れてしまうという問題が起こっていた。今でも、PHSに対して、そうした印象を持っているケータイ利用者も多いはずだ。
だが、基地局の数が増えてくると、この仕組みが逆に強みになってくる。現在、ウィルコムの基地局数は約16万。人口カバー率で最大規模といわれるNTTドコモが屋外で23,900カ所、屋内6,000カ所を年度内の設置目標にしていることに比べると、圧倒的に多いのがわかるだろう。
ウィルコムのPHSが採用しているのは、マイクロセルと呼ばれる方式で、複数の基地局が、電話から発信される電波を受信する。そのため、トラフィックが増加しても、複数のアンテナがその領域をカバー。データ通信では速度が落ちにくく、音声通話では音声品質が落ちにくいという特徴がある。これに対して、携帯電話各社が採用しているのがマクロセルという方式。携帯電話は、1つの基地局でカバーできる範囲が広いという特徴があるが、カバーしているエリアでのトラフィックが増加すると、つながりにくい、音声品質が落ちるといった問題が起こる。
災害時などに、携帯電話よりもPHSがつながりやすいというのは、実は、このマイクロセル方式によるところが大きいのだ。
トラフィックの増加に強いマイクロセル方式だからこそ、ウィルコムはデータ通信の定額サービスを導入でき、さらに、音声定額のサービスを開始できたのだ。
●音声定額はPHSだからこそできたもの
実は、音声定額のトラフィックは、データ通信定額のトラフィックに比べると圧倒的に少ない。
同社の発表によると、音声通話の時間は、定額制に導入によって、平均642分と、通常利用者の7.5倍にも増加したが、それでも、音声定額のトラフィックは、データ通信定額制の10数分の1程度だ。
データ通信の定額サービスを安定的に提供しているウィルコムにとって、音声定額の導入はそれほど大きな問題ではなかったといえる。
唯一、大きな問題は、音声定額利用が増えれば、NTTに支払うアクセスチャージが膨れ上がるという点だった。
アクセスチャージは、NTTに対して、回線使用料としてウィルコムが支払うもので、従量制を採用している。そのため、定額制の回線利用が増えれば、その分、アクセスチャージが増加することになる。
だが、これも、ITXと呼ばれる装置を開発し、導入することで解決。NTTの地域網をバイパスして、アクセスチャージを最小限に抑えることができたのだ。
音声定額の契約者は、すでに50万件を突破。ウィルコムの純増数拡大において、大きな原動力となっている。
●一時的に加入者が減少!
だが、こんな逸話もある。
一時期、音声定額制度の加入者数が減少した時期があった。今年8月の話だ。なんと、音声定額の契約者が相次いで解約をはじめたのだ。
ウィルコム社内でも焦りが走った。サービス品質には問題がなく、大きなトラブルは発生していなかった。解約の決定的な原因がわからなかったのも、社内の焦りを助長した。
だが、解約者に1つの傾向が出ていることを掴み、その理由解明が一気に進んだ。
それは、2台一緒に解約するという傾向だった。ウィルコム社内ではピンときた。
もともと音声定額サービスは、恋人同士が通話料を気にすることなく、長電話をするために、2台一緒に購入するという使い方が目立っていた。そのため、不要になった恋人たちが、これを解約するという動きが出始めていたのだ。
さすがに、恋人同士が別れる時期の予測までは不可能。解約増加という形で、思わぬ影響が出たといえる。
だが、この傾向は普及初期段階の問題だといえよう。ある程度の台数が普及しはじめると、別れたあとも、そのまま端末を持っていても、多くの人と定額通話ができるという状況であれば、解約しなくともそのまま所有する人が増えるはずだ。
実際、サービス開始当初は、定額サービスへの申し込みも、2台同時という比率が高かったものが、現在では、1台ごとに契約するというケースがほとんどだという。これも今後の解約率の減少につながることになるだろう。
●ラストスパートに威力を発揮したW-ZERO3
そして、記録更新のラストスパートとなったのが、「W-ZERO3」の発売である。
12月9日に予約が開始された同製品は、早朝から一部の量販店店頭には列ができ、ウェブサイトを通じた予約販売においても、サーバーの動きが不安定になるほどアクセスが殺到した。マスコミ関係者の間でも、W-ZERO3の人気は絶大で、この年末は、これを持っていることが自慢の1つになったほどだ。
同社では、W-ZERO3の販売台数を公表していないが、契約者数増加に大きな影響を与えているのは明らかだといえる。
 |
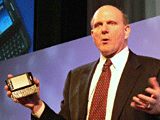 |
| W-ZERO3は、記録更新のラストスパートに大きく寄与した | Microsoftのスティーブ・バルマーCEOも来日した際に、W-ZERO3を持って講演。「わずか数カ月前には、こんなにすばらしい製品が登場するとは夢にも思っていなかった」と大絶賛 |
●大きく変わった社内の体質
こうした魅力的なサービスの存在も見逃せないが、実は、社内体質の変化も見逃せない。
2004年に、KDDIからPHS事業を独立。同時に、カーライルグループという外資系企業が筆頭株主になるとともに、2005年1月には、日本IBM、日本AT&T、日本テレコムで経験を持つ八剱洋一郎氏が社長に就任するというように、体制は大きく変更した。もちろん、社名変更も大きな変化を象徴するものだといっていい。
こうした体制変更が、社内の体質を大きく変えたのである。
KDDIグループにおけるDDIポケット時代には、音声通話サービスに関しては、どうしてもau優先の風潮があった。また、ツーカーブランドもあっただけに、PHSのDDIポケットはそのポジショニングが難しかった。結果として、データ通信に特化したブランドという位置に追いやられてしまっていたのが実状だった。
これがKDDIグループから分離独立したことで、こうした制約から解き放たれた。音声定額サービスを実施できることも、KDDIグループからの独立無しには実現しなかったものだといっていい。
また、カーライルグループの出資も、経営を変化させた。AIR H"というのは、日本人だからこそエアーエッジと読めるが、外国人で構成されるカーライルグループの経営陣にはとても読めない。そして、エッジという英語は、「最先端」などの意味があり、日本人が思う以上にいい印象がある。これもカーライルの進言で、ブランドを変更し、AIR EDGEとなったのだ。このほかにも、音声サービスに重点を置くことに強く賛同したこと、さらにカーライル流の経営手法が随所に導入されたことなど、経営面から見たカーライルの存在は欠かせない。企業体質の強化に威力を発揮したのだ。
そして、八剱洋一郎氏の社長就任も、ウィルコムの体質転換に大きな影響を与えている。それは、一言でいえば、「スピード経営」の浸透だ。
例えば、音声定額制は当初、9月からの導入を計画していた。それは、先にも触れたITXの完成が夏頃と見込まれていたからだ。だが、八剱社長は、ITXが完成していない春からの実施を決断した。いち早くサービスを開始すること、そして、春という携帯電話の買い換えや新規加入者が増加する時期を捉える必要があるとしたからだ。
つまり、音声定額の当初サービスは、従量制のアクセスチャージをそのまま活用しながらサービスを実施していたのだ。
しかし、その戦略はまんまと当たった。音声定額制の加入者が一気に増加したのだ。
「1年でできる仕事は半年で、半年でできる仕事は3カ月でやってほしい」-八剱社長は、社内にこう呼びかけているという。
また、失敗を恐れない風土も定着しつつある。若い経営陣とフラットな組織をベースに、現場が新たなことに挑戦できる風土を作り上げることで、判断を早めることが、八剱流ともいえる経営スタイルだといえそうだ。
「三振してもいい。全社員が争うようにしてバッターボックスに立ってほしい。そのための風土を作るのが私の仕事だ」と八剱社長は語る。
さらにもう1つ、欠かせないのが稲盛和夫氏の存在だ。京セラの創業者である同氏は、現在、ウィルコム取締役最高顧問に就任している。同時に、京セラで名誉会長、KDDIで最高顧問を務めているが、ウィルコムでは取締役となっている分、経営への関与が深いともいえる。それだけに、節目には必ず同氏の助言があるという。
ウィルコムのある幹部社員からは、「稲盛氏が、いま一番、気にしてくれている会社がウィルコムではないか」と評する。
音声定額制度の導入についても、稲盛氏はウィルコム社内に、こう助言したという。
「1,000万人の加入体制を見越したインフラができているのか」
社内の担当者は、この言葉に最初はポカーンと口を開けた。ウィルコムの加入者数は300万を越えたところ。しかも、全契約者が音声定額に移行するとは限らない。また順次、加入者が増加するに従って設備を増強するということも可能だ。
だが、稲盛氏は、ここでビジネスのやり方を徹底させた。それだけのインフラを用意することの大切さ、そして、ビジネスの拡大を見越した準備をする大切さを社内に教えたのだ。
すぐに社内はインフラの点検を行ない、必要なところは増強した。その結果、サービス開始時には、1,000万人の加入者を見込んだインフラ体制が用意できたのだ。これだけのインフラがあるからこそ、積極的な営業活動、マーケティング活動ができるというわけだ。
●2006年も成長を続けるのか?
では、2006年もこの勢いを維持できるのだろうか。
 |
| 11月8日に社内に設置されたボード。初日の段階では、このように6桁の数字だったが、12月下旬の段階では4桁台に突入していた。 |
ドコモが5,011万契約、auが2,451万契約、ボーダフォンが1,505万契約ということを捉えれば、360万契約を突破したばかりのウィルコムの事業は、まだ桁が1つ小さい。言い換えれば、拡大の余地は大きいといえる。
だが、2006年には、ナンバーポータビリティと新規携帯電話事業者の参入という新たな動きもある。
PHSはナンバーポータビリティの制度からは、蚊帳の外だが、そうした外圧的な動きに押され、これまでの手法がそのまま通じるかどうか、という不安もある。
だが、八剱社長は、あまりこうした「外圧」を気にしていないようだ。
例えば、現在、音声定額の加入者の50%以上が2台目の携帯電話としてウィルコムを購入しており、携帯電話の動向とは、まったく別の動きをしていると見ているからだ。
また、新規事業者についても、データ通信での競合はあるものの、音声分野ではPHSならではのインフラを生かした定額制度によって、明らかにリードできると判断しているようである。
こうしてみると、外圧は、ウィルコムの事業にはほとんど影響がなさそうである。
八剱社長は、「ウィルコムをワクワク感のある会社にしたい」と抱負を語る。それは、「ウィルコムは、なにかおもしろいものを常に出す、というイメージを植え付けたい」ということでもある。
2006年も、加入者数の記録更新が続くのは明らかだろう。いまの事業体質がある限り、しばらくの間は、ワクワクする製品、サービスの登場を期待してもよさそうだ。
□関連記事
【12月26日】ウィルコムの契約数、過去最高に(ケータイ)
http://k-tai.impress.co.jp/cda/article/news_toppage/27142.html
【10月20日】ウィルコム、VGA液晶搭載のモバイル端末「W-ZERO3」
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/2005/1020/willcom.htm
【3月15日】WILLCOM、月額2,900円の音声定額サービスを5月1日から(ケータイ)
http://k-tai.impress.co.jp/cda/article/news_toppage/23050.html
(2005年12月26日)
[Text by 大河原克行]
【PC Watchホームページ】
PC Watch編集部 pc-watch-info@impress.co.jp ご質問に対して、個別にご回答はいたしません
Copyright (c) 2005 Impress Watch Corporation, an Impress Group company. All rights reserved.