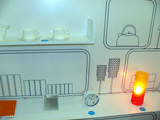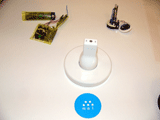|


■森山和道の「ヒトと機械の境界面」■「SFC Open Research Forum 2005」レポート
|
慶応義塾大学湘南藤沢キャンパス(SFC)による「SFC Open Research Forum 2005」が、11月22日から23日にかけて六本木アカデミーヒルズで開催された。
「SFC Open Research Forum」はSFCで行われている産官学連携研究の発表と、研究シーズを披露することでさらなる連携を推進することを目的としたイベントである。さまざまな研究者たちと実際に会って話を聞くことができる。
10回目となるオープンリサーチフォーラム(ORF)の今年のテーマは「レッドクイーンの法則 - 知の遺伝子進化を加速せよ -」。レッドクイーン、赤の女王とは『鏡の国のアリス』に出てくる言葉で、同じ場所に留まるためにも走り続けなければならない現代社会その他の様を例えるのに使われることが多い。
ORFでは講演のほかパネル展示、デモ展示などが行なわれた。内容もバイオテクノロジーや政策関連など多種多様だが、ここでは主にIT関連のデモンストレーションを中心にレポートする。
まず受付をすませてすぐの場所にあったのが、スマート環境を実現するオープンモバイルプラットフォーム「ユビキタスコア」技術の実証実験の展示。徳田英幸研究室、シャープ、産業技術総合研究所による研究だ。
uCoreプロジェクトでは、スマート環境を構築するためのオープンな基盤技術を提供することを目指し、スマート環境構成技術、uCoreLink技術、ユビキタスコア要素技術に関して研究開発を行なっている。展示では、赤外線、無線LAN、RFID等を組み合わせ、街角のポスターから動画などを使った詳しい商品情報を電子的に取得する「モノなび」、ユーザーが首からぶらさげたタグを使って街角のものを閲覧した記録をとっていく「モノがたりアルバム」が展示されていた。
「俺デスク」はユーザーが閲覧したデスクトップの履歴を残すソフトウェアだ。ウインドウに対する着目度や検索やコピー&ペーストなどのアクションから、時系列で閲覧することができる。
「u-Texture2」は自由に組み替えできるパネルである。1個1個のパネルはタブレットPCのように使うことができるだけではなく、パネル自体が自分の位置や傾き、そして近くにあるパネル、組み立てられた全体形状を認識して適切に情報を提示する。
たとえば、パネルを左右に並べるだけで、パネルは相互に無線で通信して、お互いの位置関係を把握する。右のパネルから左のパネルへのドラッグ&ドロップなどもできる。近い将来、駅や街角などの案内板として見ることができるかもしれない。
「あしナビ」はセンサをつけたスリッパを使う利用者の位置を検知し、プロジェクターで足跡を出すことでナビゲーションするアプリケーション。迷路や幽霊屋敷のような場所でのナビゲートや、居酒屋でトイレの場所をナビゲートしてもらえると嬉しいかもしれない。
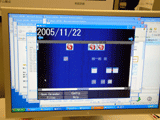 |
 |
 |
| 俺デスク。自分の履歴を時系列で閲覧することができる。上にあるものが着目度が高かったウインドウ | u-Texture2。ユビキタスサービスを創造するユニバーサルパネル | あしナビ。たとえば宅配業者をマンションの入り口から部屋の前までナビゲートするような用途を想定しているそうだ |
「ポケットコンシュルジュ」はPDAとRFIDを使った視覚障害者用ナビゲーションシステム。今回のORFでは、こういったデモが目立った。
「ふらっと」は、以前、本コラム「ポストGUIの可能性を探る~慶應義塾大学安村研究室探訪記」でも紹介したことのある安村研究室の児玉哲彦氏による「未来の地図」の研究。会場では参加者はRFIDのタグをぶらさげて歩いているので、それによって位置情報をとることができ、その全体地図を見ることができる。
面白いのは、平面で見ている状態から向きを傾けて変えると3Dビューに変わること。2Dと3D、それぞれの地図を目的に応じて切り替えることができる。また当日はうまく動いてなかったが、人の訪問量を地図上の丸の大きさなどで表現することができるという。
同じく渡邊恵太氏は「ReflectiveClock」という時計をデモ展示。前日の情景を背景に映し出す時計だ。見ていると自分が前日に行なった行動や周囲の風景から、今から、今ここで起こることがだいたい予想できたりするから不思議である。
「Flog(ふろぐ)」は安村研の久保美那子氏によるデモ。デジカメや携帯電話で撮影した記録をお風呂のなかで振り返ることを支援するためのツール。MemoryBottleと呼ぶボトルのポンプを押すことで洗面器に画像を出し、その洗面器を回すことで画像を切り替える。
風呂の中で1日のことを思い出すことはみなやっていることだし、携帯電話でメールをやりとりする人も増えつつある。将来、風呂場で情報端末を使う機会はさらに増加するだろう。面白い研究が生まれてくるかもしれない。
共同研究しているJR東日本フロンティアサービス研究所もデモ展示を行なっていた。Suicaを使ったサービスで、JR東日本社内に対しても提案しているものだという。なお2月中旬には「電車展」という形で研究発表を行なうという。
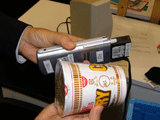 |
 |
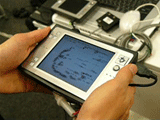 |
| ポケットコンシュルジュ | ふらっと | 【動画】デバイスの向きを変えるだけで2Dによる全体地図から3Dへなめらかに切り替えることができる |
 |
 |
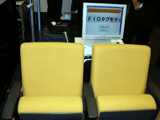 |
| ReflectiveClock。前日の様子を映し出す時計 | 「Flog(ふろぐ)」 | JR東日本フロンティアサービス研究所によるSuicaを使ったサービスの提案。Suicaをタッチすることで使えるようになるシート |
ユビキタス・サービス技術を広く展示していた徳田研究室と並んで目立っていたのがKMDのブースである。KMDとはKeio Media Designの略で、複数の研究室からなるプロジェクト。ユビキタス・コンテンツ、ユビキタス・デザインの研究を行なっている。「21世紀ユビキタス社会のためのデジタルコンテンツやメディアデザインを世界に発信」することを目標としたものという。ユビキタス技術が普及した将来の衣食住のトータルデザインの研究を行ないつつ、人材の育成を行なっているという。
これまた数多くの展示があったのだが、いくつか雰囲気が伝わるものを抜粋して紹介する。
田中浩也研究室では「ナチュラル=自然さ」を持った環境装置/道具のデザインの研究を行なっている。同研究室で「環具」と呼ぶいくつかの展示が行なわれていた。
奥出研究室では、映像万華鏡「moo-pong」、円筒型読書支援ツール「BiblioRoll」、さいころ型映像デバイス「Z-agon」などを展示していた。
「moo-pong」は、カメラで撮影した映像をボール内のRFIDを経由して集め、それを万華鏡のように見て楽しむ道具である。
「BiblioRoll」は円筒型の読書支援ツール。3段の円筒をくるくる回すことで、ディスプレイを操作する。本をこの画面で読むというよりも、本と本との関連づけを支援することを考えているようだ。
「Z-agon」はサイコロ型映像デバイス。現時点で動くのはLEDで文字表示ができるプロトタイプだけだが、6面全てがディスプレイになっているムービープレイヤーを目指している。手のなかでデバイスそのものを回転させることで操作する6面スクロールゲームなどを想定しているという。
 |
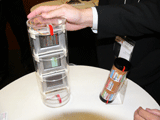 |
 |
| 「moo-pong」。デジタル映像万華鏡 | 「BiblioRoll」円筒型の読書支援ツール。左が現時点での実機で右はコンセプト・モックアップ | 「Z-agon」。サイコロ型映像デバイス。現時点ではコンセプトモックだが、ゲーム機などに応用されると面白いかもしれない |
 |
| 「発電床」。環境情報学部の速水浩平氏による「音力・振動力発電」の研究。音のエネルギー、振動エネルギーを使った発電。発電した電力を蓄電することでLEDを点灯させたりすることができるという。スポンサー募集中とのこと |
まだまだポスター展示はあり、デモ展示だけでも、ここでは紹介仕切れないほど多くの展示が行われていた。1つ1つの研究の奥にあるだろう思想そのほかまではなかなか聞くことができなかった。またデモ展示の類は、実際に体験しないと分かりにくいものも多い。記事ではなかなかお伝えできなかったかもしれない。その点はお詫びしておきたい。
最後に全体の感想を述べておきたい。
もはや「ユビキタス」という言葉は当たり前になりつつあり、ユビキタスをイメージしたシチュエーションや、ケータイ(または将来、高機能化したケータイを視野に入れたPDAやタブレットPC)に、RFIDやGPSを組み合わせたという展示/研究が目立った。目立ったというよりは、そういうものばかりで、多くの研究が似て見えなくもなかった。
また会場内全体には、学生による研究から、研究室で長年研究が行なわれているもの、コンセプトデザインレベルのものから、既に実装されているもの、実装のなかでも綺麗に見せているもの、そうでないもの、メディアアート的なものと、情報技術の研究と、実にさまざまなレベルの展示が混在して行なわれており、全貌が掴みにくいものになっていた点も少々残念である。全体が融合しているのであれば、それはそれで良いのだが、融合というよりはサラダボールのようにモザイク状になっているように感じた。
ユビキタス・サービスを謳っている、それを前提とした研究展示が行なわれているという点ではいずれも共通しているのだが、各々の研究がバラバラなだけではなく、展示に対する考え方もバラバラなので、繋がっていないのだ。せめてコンセプトと将来イメージを繋ぐためのロードマップやプロジェクトの目標は掲示して欲しいように思う。
ユビキタスサービスを実現するためには、各々のサービスやデバイスを繋ぐためのミドルウェアがハード・ソフト両面において必要だが、このような研究発表の場においても、各展示を繋ぐミドルウェア的なものが必要なのではないだろうかと逆に考えさせられた。
これはORFだけではなく、今後も続々と予定されているユビキタス関連の研究発表全体の課題かもしれない。スポンサードや共同研究相手を探索しているのであればなおさらだろう。
というより、もしかすると、ユビキタス研究をめぐる現状そのものが、上記のような、ごちゃごちゃの状況にあるのかもしれない。ユビキタスという言葉が人口に膾炙し、既に古び始めている今、1度大規模な交通整理が必要なのかもしれない。会場の熱気を感じながら、そんなことを思った。
□SFC Open Reserch Forumのホームページ
http://orf.sfc.keio.ac.jp/
□関連記事
【2003年12月25日】【森山】ポストGUIの可能性を探る
~慶應義塾大学安村研究室探訪記
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/2003/1225/kyokai19.htm
【2003年5月15日】【森山】ユビキタスってこんな感じ?
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/2003/0515/kyokai08.htm
(2005年11月28日)
[Reported by 森山和道]
【PC Watchホームページ】
PC Watch編集部 pc-watch-info@impress.co.jp ご質問に対して、個別にご回答はいたしません
Copyright (c) 2005 Impress Corporation, an Impress Group company. All rights reserved.