 |


■元麻布春男の週刊PCホットライン■傍系へ追いやられるItanium |
●WSJでリークされた延期
10月24日(現地時間)、米Wall Street Journal紙は、Intelのサーバープロセッサロードマップに変更が生じたことを伝えた。要点は、次の2点だ。
1. 量産時の品質向上のため、Montecitoのリリースを約半年遅らせて2006年初頭から2006年半ばにスライドさせる。と同時にFSBの667MHzへの引き上げを見送り、動作クロックも2.0GHzから1.6GHzに後退
2. 開発中だったMP版サーバープロセッサ(x86系)のWhitefieldとそのプラットフォームであるReidlandをキャンセル、代わりにTigertonプロセッサとCanelandプラットフォームの開発を行なう
記事にはIntelの広報担当者が実名で登場しており、信憑性は高い。むしろ、実質的には意図したリークである。Intelはネガティブな発表については、この手をよく使う。
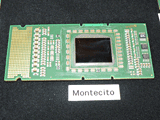 |
| 6月に展示された「Montecito」 |
ただその内容については、正直言ってそれほど驚くものではない。IA-64系プロセッサのリリースが遅れるのは半ば常態化しており、今に始まった話ではない。またか、という感じではあるのだが、Montecitoの開発がそれほど遅れていたのかというと、それもまた良く分からない。Montecitoに関してはすでに動作するシリコンがOEMに渡されており、NECのハイエンドサーバーで実際に動いているのを公開の場で見たこともある。それどころか、動作中のMontecitoに触らせてもらったくらいだ(十分触れる程度の温度であった)。
大量生産するPentium系プロセッサならいざしらず、メインフレーム用の少量生産の高価なプロセッサで、多少の歩留まりの良し悪しはあまり関係ないような気がするし、どうもピンとこない。あるいは長期使用時の信頼性不足、とかいった事情があるのかもしれない。いずれにしても思うのは、Itanium系プロセッサがIntelの中でどんどん後退していることだ。はっきり言うと筆者は、そう遠くない将来、Itaniumの開発グループは、Intelから切り離され、別会社になるのではないかと思っている(あくまでも筆者の勝手な思い込みである)。
●Itaniumの過去と現在、そして未来
Itaniumがハッキリと冷遇されるようになったのは、2004年の戦略転換からだ。この年の春、Intelはそれまでの路線(後述)から、デュアルコア/マルチコア/メニイコア路線へと転換する。と同時に旧路線に属するTejas/Jayhawkがキャンセルされ、Montecitoと同時にリリースされる予定だった新チップセット(Bayshore)もキャンセルされた。同時に事業部長だったMike Fisterも辞任している。
Itanium系プロセッサに対しIntelが提供しているチップセットは「E8870」だが、これは2002年7月に第2世代のIA-64プロセッサであるMcKinleyと同時にリリースされたもの。当初2005年後半と言われたMontecitoのリリースから数えると3年前のことになる。今回見送りとなったFSB 667MHzどころか、すでに発表済みのFSB 533MHzにさえ対応していないチップセットである。
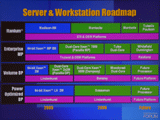 |
| Tukwilaのプラットフォームが870に逆戻りしたGelsinger副社長の基調講演。Reidlandプラットフォームがキャンセルになった以上、同じプラットフォームを共有するWhitefield後継のDunningtonも道連れになったと見るのが順当だが |
さらにIntelは、2005年夏に開かれたIDFで、Xeon MPとの共通プラットフォーム構想を実現するハズだったRichfordプラットフォームをも放棄した。Richfordプラットフォームは、当初2007年といわれたTukwilaプロセッサと、新しいチップセット(少なくともPCI ExpressとFB-DIMMをサポート)で構成されるものだったが、2日目のPat Gelsinger副社長の基調講演では、TukwilaのプラットフォームはRichfordではなく、5年落ちの870(E8870の旧称)およびOEM製とされていたのだ。最近のIntelは自らをプラットフォームカンパニーと称しているが、ことItaniumに関してはすっかりCPUカンパニーである。
もちろんItaniumについてIntelのプラットフォームが後退したのには理由がある。上述の戦略転換により、IA系のハイエンドサーバー向けプロセッサから、メインフレーム用のプロセッサに祭り上げられたことで、ItaniumのOEMはほとんどが自前でプラットフォームを開発することが可能なメーカーばかりになってしまった。HP、SGI、NEC、日立製作所、富士通など、現在Itaniumをサポートするメーカーは、すべて自前で開発したItanium対応チップセットを持つ。
唯一、Intel製チップセットを使っていた米Unisysは、10月25日にNECとの提携を発表、Itaniumを用いたハイエンドサーバーについて、共通プラットフォーム(Xeon MPとの共通ではなく、NECとUnisysの共通)の開発で協力、NECが製造・供給を行なうことを明らかにした。残るBullは以前からNEC製だし、富士通やシーメンスが富士通製を使うのは極めて明白だ。Intelのチップセットを利用するDellのようなベンダは、すでにItaniumという船から逃げ出してしまった。
つまりIntelはItaniumのプラットフォームについて、すでに2回キャンセルしている。これは、プラットフォームカンパニーにあるまじきことである。逆にいえば、ItaniumはIntelの戦略から浮いた存在になっている、ということだ。浮いたものをどうするか。そりゃ切り離すよね、というのが筆者の発想の原点である。
そう思うと、最近のItaniumがらみのニュースは、分離を示唆するようなものばかりに思えてならない。まず2004年12月、IntelはHP社内のItanium開発チームを吸収しているが、これはHP側のリストラというだけでなく、Itaniumから特定ベンダ色を抜く意味があるのではないかと考えられる。また、1カ所にまとめておいた方が、別会社にもしやすかろう。
2005年9月に出されたプレスリリース(マサチューセッツ州ハドソンのFab 17とコロラド州コロラドスプリングスのFab 23、両200mmウェハFabに追加投資して生産力を増強)では、うしろの方にひっそりとコロラド州フォート・コリンズでItanium開発チーム用にオフィス物件を購入する契約を結んだ、という記述が見られる。これも、Intelのほかの部署からItanium開発チームを分離するためではないか、という見方ができる。
さらに2005年9月26日、Intelは上述したOEMやソフトウェアメーカーと共同でItanium Solutions Allianceを旗揚げしているが、これも分社に向けた体制作りと受け取れなくもない。リリースが2006年半ばに延びてしまったMontecitoは、ひょっとすると「IntelのItanium」としては最後になるのでは、という気がしてしまうのである。しかし、だからといってItaniumを急に止めるわけにもいかない。
すでに述べたように、HPやNECをはじめとするOEMはItaniumに投資している。Intelの都合で止めることなどできない。
そこで思いつくのが分社化のシナリオである。とりあえず生産はIntelに委託するとして、Itaniumの開発チームを別会社に分離する。当面はIntelが筆頭株主でないと収まらないだろうが、できればサーバーベンダに少しづつ出資してもらう。アライアンスにも出資してもらうとなお良いだろう。
こうして分社した方が、みんな幸せになれる気がしてならない。Intelはプラットフォーム戦略に合致しない継子をとりあえず目につかないようにできるし、Itaniumの開発チームは親のイジメにおびえる心配が減る。OEMもItaniumのロードマップにこれまで以上に関わることが可能になり、製品戦略を立てやすくなるだろう。心配は「船頭多くして……」になることだが、ソフトウェア互換性という枠組みがあるから、それほど滅茶苦茶なことにはならないのではないかと楽観してみたりする。
●消えた「共通プラットフォーム構想」が目指したものは
ただ、こうやって分離されてしまえば、もはやXeon MPとItaniumの共通プラットフォームなんてものは意味をなさない。しかし、メインフレーム用のプロセッサに祭り上げられた時点で、もう共通プラットフォームは意義を失っていたのではないか。元々、共通プラットフォーム構想は、Itaniumのプラットフォームコストを引き下げ、販路を広げることにあった。だが、メインフレームといわゆるIAサーバーで、プラットフォームを統一することにどれだけ意味があるだろう。
もちろん、だからといって、バスの更新をしないで済むわけではない。ItaniumのFSBは第2世代のMcKinley以来、ほとんど改良が加えられていない(だからチップセットが継続になる)。Xeonについては、共有バス(FSB)アーキテクチャがAMDに差をつけられる、いわばアキレス腱になっている。いずれのプロセッサとも、そう遠くない将来、バスの見直しが行なわれるだろうが、その時にプラットフォームの共通化はもはや議論に上らないのではなかろうか(技術的にはPCI Expressの物理層からインスパイアされる、という点で類似性を備えるかもしれないが)。
共通プラットフォームが意義を喪失したことを思えば、その片割れであるWhitefieldがキャンセルになったのも自然な流れともいえる。が、筆者は、共通プラットフォームはWhitefieldのキャンセル以前、つまり夏のIDFの時点で消えていたのではないかと思っている。
以前からWhitefieldはTukwilaとの共通プラットフォームを実現するプロセッサ、とされてきた。が、そのアーキテクチャがどのようなものなのか、公開されることはなかった。公開されたのは2005年夏のIDFであり、そこで初めてMerom/Conroe/Woodcrestと同じ「新マイクロアーキテクチャ」によるクアッドコア構成であることが明らかにされた。
その同じIDFでTukwilaから共通プラットフォームが消えているということは、この時点でWhitefieldの側からも共通プラットフォーム構想は消えていた、と考えるのが自然だろう。また、もし2005年夏のIDFで余計なこと(新マイクロアーキテクチャによるクアッドコア構成)を言わなければ、ひょっとしたら謎のプロセッサのままWhitefieldは、今もロードマップ上で生きていたかもしれない。
実は筆者は、共通プラットフォーム構想が生きていた頃のWhitefieldは、キャンセルされたTejas/Jayhawkのアーキテクチャ(NetBurst発展型)だったのではないかと思っている。Whitefieldが新マイクロアーキテクチャであると決まった時点で、バスは共通プラットフォームをにらんだPoint-To-Pointインターコネクトから、Merom/Conroe/Woodcrestに類似したFSBタイプになっていたのではないだろうか。今回のキャンセルの要因は、4コアに1FSBでは性能(あるいは性能のスケーラビリティ)が不足する、という事情ではないかと思う。そうであるなら、TigertonとWhitefieldの大きな違いは、外部バスにある、と考えるのが自然だろう(Whitefieldをキャンセルすると発表せざるを得なかったことからすると、Xeon MPについてはもう1世代NetBurstを使うという可能性も考えられるが)。
キャンセルされた旧路線が何をやろうとしていたのかは、今となっては知る由もない。が、おそらくはNetBurstの特徴をさらに強化したものだっただろう。つまり、プロセッサハードウェアの仮想化をもうワンステップ進めたものだ。NetBurstで取り入れられた技術、あるいは取り入れようとしていた技術は、Hyper-Threading、LaGrande、VT、といずれもプロセッサの仮想化と密接なかかわりを持つ(見方によってはEM64Tも)。
その行き着く先は、おそらくソフトウェアインターフェイスが完全に仮想化されたプロセッサ、リコンフィギュアブルプロセッサであり、32bitや64bit、コアの数といったことは、単にソフトウェアに見せるインターフェイスに過ぎない、という姿である。これが実現した時、IA-64とIA-32のアーキテクチャの差は問題ではなくなる。プラットフォームを共通化する意味も、実はこの辺りにあったのではかと考えている。
正確なことは忘れたが、来日したMicrosoftの役員が、将来のWindowsとして、リコンフィギュアブルプロセッサ上で動作する、リコンフィギュアブルなOSといったことを述べた記憶もある(この構想もTejas/Jayhawkと共に消え去っただろうが)。とはいえTejas/Jayhawkがリコンフィギュアブルプロセッサだったとは思っていない。あくまでも現在のNetBurstから、また1歩そちらの方に踏み出したプロセッサだったろう、と想像しているだけだ。
この旧路線には2つの大きな問題があった。最終形に到達すればともかく、その過程として仮想化を進めるステップにおいて、このテクノロジは性能向上(ベンチマーク的な性能の向上)にほとんど寄与しないだろう、というのが最初の問題だ。
NetBurstは、仮想化の実現にトランジスタを割き、性能向上はクロックアップに依存していたと考えられる。リーク電流の増大とそれに伴う熱により、当初計画どおりクロックが上がらなくなると、性能面でのアドバンテージを失う。個人的にはもうベンチマーク的な性能なんて、とも思うが、営業やマーケティングの現場的には、AMDのプロセッサにベンチで負ける石が売れるか、と激しく叩かれることだろう。
もう1つの大きな問題は、ソフトウェアのサポートだ。デュアルコア/マルチコアが基本的に大幅なソフトウェアの書き直しを必要としないのに対し、リコンフィギュアブルプロセッサの真価を発揮させるには、OSの対応が不可欠だろう(既存のOSと互換性を持つ形にコンフィギュアできるだろうが、それでは真価を発揮できないのではないかと思う)。そんなOSをいつ、誰が提供してくれるのか。現在のVistaの開発状況1つをとってみても、長い長い道のりが必要に思える。これも、旧路線がうまくいかないと判断された大きな理由ではないかと思っている。
□関連記事
【10月27日】【海外】IntelのサーバーCPU計画に大幅な遅れ
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/2005/1027/kaigai219.htm
【8月26日】パット・ゲルシンガー副社長基調講演レポート
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/2005/0826/idf06.htm
【6月8日】インテル、テクノロジ・ショーケースを開催
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/2005/0608/intel.htm
【2004年5月17日】【元麻布】IA-64派のMike Fister氏が辞任
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/2004/0517/hot320.htm
(2005年10月28日)
[Reported by 元麻布春男]
【PC Watchホームページ】
PC Watch編集部 pc-watch-info@impress.co.jp ご質問に対して、個別にご回答はいたしません
Copyright (c) 2005 Impress Corporation, an Impress Group company. All rights reserved.