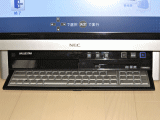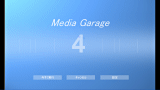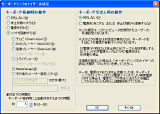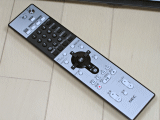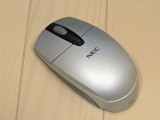|
|
26型液晶を採用した新世代一体型PC
|
 |
| VALUESTAR S |
昨年NECで最も売れたPCは、CPUにCeleron Mを採用した液晶一体型モデル「VALUESTAR S」シリーズであった。玉木宏と山本太郎のTV CMでもおなじみのVALUESTAR Sだが、そのCMで「TVなの、それともPCなの」ということが1つのテーマになっていたことを覚えている読者もおいでだろう。
こうした液晶一体型PCは、特に独身の20代ユーザーに受け入れられていると言われている。というのも、単身者の多くはワンルームに住むなど、住宅事情はあまり恵まれていないことが多いからだ。メーカー関係者によれば、TVとPCを兼ね、しかも省スペースというところが受け入れられている理由だという。実際、NECによれば、2005年の2月には一体型PCの市場シェアは35%に達しているという。
しかし、液晶一体型PCは20型未満で、ノートPCよりはやや大きめという液晶ディスプレイを搭載した製品がほとんどで、20型以上の液晶一体型PCというのは、数えるほどしか無かった。そんななかで、今回登場したのが、26型液晶を搭載した「VALUESTAR W」だ。
●大きな26型液晶を搭載
VALUESTAR W(以下、本製品)の最大の特徴は、26型液晶というPCとしては巨大な液晶ディスプレイを搭載していることだ。液晶TVの売れ筋は26型や32型と言われており、それに対抗できるだけの大きさだ。
 |
| 本体の右側面に用意されている入力端子。下から2段目にある入力端子が、液晶TV側の入力端子。Sビデオないしはコンポジット入力となっている。D端子などのコンポーネント入力は用意されていない。個人的には、D端子もさることながら、DVIなどのデジタル系の入力も欲しい |
しかし、本製品の狙いはリビングに置いて家庭のメインディスプレイとして利用するという用途ではないと思う。なぜなら、リビングセンターに置くには足りない要素が2つあるからだ。
1つは、D端子などのコンポーネント入力だ。本製品では、外部入力としてはSビデオ/コンポジットの1系統のみが用意されているだけで、D端子やコンポーネント入力端子は用意されていない。このため、HD映像を出力できるデジタル放送対応のHDDレコーダなどを接続して利用することはできない(もっともSビデオ入力はあるので、SD解像度で楽しむことは可能だ)。また、リビングでは、複数のビデオデッキなどを接続したいというニーズもあると思うが、それも難しい。
もう1つは、地上デジタル放送に未対応であること。NECは地上デジタル放送に対応したモデルもリリースしているが、この製品は対応していない。今後、地上デジタルに対応する地域が増えていくことを考えると、リビングに置くTVは地上デジタルに対応した製品がベターと言えるだろう。
むしろ、従来の一体型PCの小さい画面に物足りなさを覚えたユーザーに向けて、従来の一体型PCの大画面版として、個室で楽しむというコンセプトで作られたのが本製品だと考えた方がいいだろう。
●部屋の美観も配慮したデザイン
本製品の26型液晶は、解像度が1,366×768ドットとなっており、現在液晶TVなどで一般的に利用されている720p用のパネルと同じものだ。本製品に採用している液晶は「スーパーシャインビューEX2液晶」と呼ばれ、以前のモデルに採用されていた「スーパーシャインビュー液晶」に比べると色彩表現範囲(色の鮮やかさ)や輝度などが大きく改善されているという。
確かに、近づいて見ていると、PCの液晶としては、やや目に痛いほど明るく、色鮮やかになっていることがわかる。なお、液晶部分の左右には、NECが多くの製品で採用しているフラットスピーカーが採用されており、本体の底部にはサブウーファーも搭載されている。
特筆できるのは、画面角度の調整範囲が広いことだ。詳しくは以下の写真を見て欲しいが、液晶の角度が縦方向に大きく変えられるようになっており、座った場所に合わせて調整できる。
また、ケーブル類も、うまく納められるように工夫されている。TVアンテナやEthernetのケーブルは、うまく格納できるように蓋が用意されており、本体の後面にくる蓋の穴から出るように設計されている。背面に回らない限り、ケーブルは目に入らないので、部屋の美観を損ねることはない。こうしたデザインへのこだわりも本製品の美点の1つだ。
●すぐに見られるインスタントTV機能
本製品では、インスタントTV機能が実装されており、PCの電源が入っていない場合でも、TVの電源だけを入れることが可能になっている。リモコンのスイッチをTVに切り替えて電源スイッチを入れるか、本体に用意されているTVの電源スイッチを入れれば、3秒程度で起動する。ただし、HDDやDVDドライブ上のコンテンツを再生する機能は用意されていないので、インスタント機能を利用して閲覧できるのはTVだけということになる。
もっとも、インスタント機能にHDDやDVDドライブ上のコンテンツを見る機能を含めると、常にそれらにも電源が入っている状態にしなければならない。また、インスタント機能用OSの起動時間に長い時間がかかるようになる上、機能的(例えば再生できるファイルの種類など)にも結局はPCに比べて劣っている場合が多い。かえって、“電源ポン”でTVだけは見られるという方がわかりやすいともいえる。
インスタント機能用のチューナーは、PCのチューナーカードとは別に用意されている。例えば、PCでTVを録画しながら、インスタント機能のTVチューナを利用してライブでTVを見るという使い方も可能だ。画面の切替はリモコンないしは、本体に用意されている画面切替のボタンで可能になっており、単純切替だけでなくPCの画面の中にTVを表示するPinP表示も可能だ。例えば、PC側で番組を録画しながら、Wordで文章を作成し、さらにPinPでライブTVを表示するような使い方も可能だ。
気になるTVの表示品質だが、低解像度のアナログ放送を、高解像度の液晶ディスプレイに引き延ばして表示していることもあり、どうしても多少のざらつき感が残ってしまうのは事実だ。しかし、それは他の液晶TVにも共通する問題点であり、本製品だけが目立つというわけではない。3D Y/C分離、ゴーストリデューサ、デジタルノイズリダクションなどの高画質回路を搭載しており、液晶TVと比較して引けを取るものではない。実際、筆者宅にあるシャープのアクオス(LC-32GD1)と比較しても、筆者の主観では十分匹敵するか、どちらかと言えば本製品の方が上回るとさえ感じた。
 |
 |
 |
| 本体の下部に用意されているスイッチ類。TVとPCの電源は別々に用意されており、画面切替のボタンを押すことで、ワンタッチで切り替えられる。なお、左側には液晶の設定などをワンタッチで切り替えるボタンも用意されている | ライブ放送をPinPで表示することが可能。なお、PinPの位置は設定ツールを利用して位置を変更することもできる | |
●PCでの録画やコンテンツの再生はMediaGarageを利用
PC側での録画やコンテンツの再生は、10フィートUIである「MediaGarage」を利用して行なう。MediaGarageでは、ビデオの再生、写真の再生、音楽の再生のほか、EPGの閲覧やライブTVの視聴、録画したTV番組の再生などができる。これらの操作はすべてリモコンで可能になっており、まさにHDDレコーダ感覚で利用することができる。コンテンツの再生などは10フィートUIのMediaGarageで行ない、コンテンツを作る場合にはWindows UIにおりて操作するという使い分けが可能だ。
なお、MediaGarageにはDLNAガイドライン対応のクライアント機能も統合されており、ローカルにあるメディアファイルも、家庭内にある他のPCにあるメディアファイルも、シームレスに再生することができる。他のPCに、デジオンの「DiXiM」やMicrosoftの「Windows Media Connect」などのメディアサーバーソフトをインストールしておけば、本製品でネットワークを経由して再生することが可能になる。
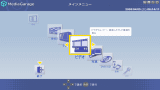 |
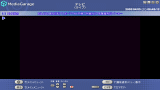 |
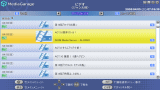 |
| 10フィートUIのMediaGrageを利用してコンテンツの再生を行なう | EPGの機能も実装されており、視聴中の番組情報を表示したり、EPGを利用した予約録画もMediaGarageでできる | DLNAガイドラインに対応したクライアント機能も統合しており、他のメディアサーバー上のファイルを再生できる |
●使い勝手のよいヒューマンインターフェイス
本製品で、もう1つ特筆しておきたいのは、ヒューマンインターフェイスの使い勝手の良さだ。
キーボードは、2.4GHzの無線を利用したワイヤレスキーボードになっている。従来のワイヤレスキーボードは、もっと低い帯域の無線を利用していたため、飛距離が1.5m程度と机の上で利用するには十分だが、こうした大型の液晶を搭載した製品と組み合わせてやや離れた距離で利用する場合には不十分だった。
しかし、本製品では、2.4GHzというIEEE 802.11b/gやBluetoothなどでも使われている帯域を利用することで、3mという飛距離を実現している。例えば、寝室において、やや離れた距離にあるベッドから操作するなど、従来方式のワイヤレスキーボードではできなかった使い方も可能だ。
ちなみに、筆者宅は、無線LAN、Bluetooth、2.4GHzのコードレス電話などの機器があり、2.4GHzの無線機器には非常に厳しい環境だが、それでも軽く4~5m程度離れても操作することができた。
もう1つキーボードは、きちんと本体に収納でき、かつ収納するというアクションで、ソフトウェアなどを起動できる。例えば、標準状態では、キーボードを本体に収納すると、10フィートUIであるMediaGarageが起動するようになっている。
この機能は、とても便利だ。というのも、10フィートUI環境ではキーボードでは操作せず、リモコンで操作することがほとんどだ。つまり、キーボードをしまうということは、Windows UI環境を終了し、10フィートUIでメディアを再生する場合か、電源を切ってPCを終わらす場合のどちらかということになる。
そこで、本製品では設定ツールを用意してあり、キーボードが本体に入ったことを検知した場合、どのような処理をさせるかを設定することができるのだ。設定できるのは、ソフトを起動させたり、電源を切ったり、サスペンド状態へ移行するなどで、ユーザーの好みに設定することができる。
ただ、キーボードを引き出す時は、電源をONにするという設定しか用意されておらず、ソフトウェアを起動するオプションは用意されていない。それがあれば、キーボードを出したときにはWindows UIで、キーボードをしまったときには10フィートUIでという使い方ができただけに残念だ。ぜひ次機種あるいは将来のソフトウェアアップデートなどで対応して欲しい。
マウスも同様に2.4GHzの無線で接続されており、通信距離は3mと十分確保されている。また、電源スイッチも用意されており、本製品をほとんど10フィートUI環境で利用して、マウスはたまにしか使わないというユーザーは、電源を切っておくことができるので、不用意なマウスの動きや無駄な電池の減りを防止することができる。なお、個人的には、キーボードが収納できるのだから、マウスも収納できればなおよかったのにと思う。
リモコンも、非常にシンプルで使いやすく、かつ高級感のあるデザインとなっている。TVを操作する場合にはTVに切り替えて、PCを操作する場合にはPCに切り替えて操作でき、明確に2つの機能を分けられるのでわかりやすくてよい。
●Pentium 4 520Jを採用するなどPCとして十分な基本製品を実現
PCとしての機能も充実しており、十分すぎるスペックが実現されている。CPUは、HTテクノロジに対応したPentium 4 520J(2.8GHz、Prescottコア)で、チップセットはIntel 915GVとなっている。
メインメモリは標準では512MB(PC3200 256MB×2)という構成になっており、本体の上部に用意されている2本のメモリスロットはすでに利用済みとなっている。このため、メモリを増設するには標準の256MBの2枚のモジュールを外して、より大容量のものと交換する必要がある。あらかじめ大容量にしたいというのであれば、NECダイレクトで販売されているBTO可能なモデルをチョイスするという手もある。
HDDの容量は標準で300GB、光学ドライブはDVDスーパーマルチドライブとなっており、こうした製品としては十分すぎる仕様だと言っていいだろう。
Pentium 4を採用しているということで、気になる騒音だが、かなり優秀な仕上がりだ。実際に騒音計を利用して計測してみたが、PCの起動前が33dBAだったのに対して、PC起動後は33.5dBAとほとんど変わらなかった。もちろん、この状態はCPUをフルロードさせた状態ではないが、通常の使い方の範囲内であれば、この程度で納まるだろう。どちらかと言えば、光学ドライブの騒音の方が気になる程で、一般的な家庭において利用するのであればほとんど気にならないレベルだと言っていいだろう。
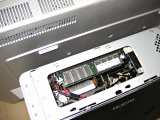 |
 |
| 本体上部の蓋をはずすとメモリにアクセスすることができる。取り外し、取り付けは大変だが、ユーザーでもなんとか作業できる位置にある | デバイスマネージャの表示 |
●26型の液晶TV+HDDレコーダー+PCで30万円というお得な価格設定
以上のように、本製品は、PCとしての基本性能も十分で、静音性も確保され、操作性も優れている。また、インスタントTVの機能により、PCを起動しなくても、すぐTVとして利用することができるという、TVとしての使い勝手の良さを備えつつ、MediaGarageにより、HDDレコーダとしての側面も備えている。
では、どういうユーザーが本製品を購入するのかということになるが、冒頭でも述べたように、D端子などのコンポーネント入力やデジタル放送のチューナーが用意されていないことで、家庭のリビングのセンターをねらうというのは難しいだろう。むしろ、スペースには余裕はないが、PCとHDDレコーダとTVすべてが欲しくて、かつできるだけ大画面が欲しいというユーザーにうってつけだ。
実売価格で30万円を切る価格も、26型の液晶TV+HDDレコーダ+PCの価格としてはお買い得と言えるだろう。
□関連記事
【4月13日】NEC、26型液晶一体型などデスクトップPC夏モデル発表
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/2005/0413/nec1.htm
(2005年4月20日)
[Reported by 笠原一輝]
【PC Watchホームページ】
PC Watch編集部 pc-watch-info@impress.co.jp ご質問に対して、個別にご回答はいたしません
Copyright (c) 2005 Impress Corporation, an Impress Group company. All rights reserved.