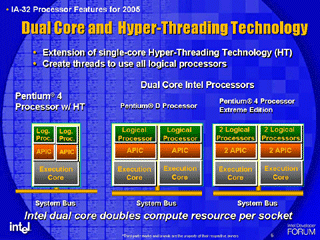|


■元麻布春男の週刊PCホットライン■デュアルコア+HTはゼニが取れる技術か |
●差別化のネタになる技術と、ならない技術
 |
| ラウンドテーブルで質問に答えるパット・ゲルシンガー副社長 |
実際、これまでIntelは、PCプラットフォームに新しいアプリケーションをもたらそうと努力してきたし、少なくともその時点、時点でのキラーアプリケーションを加速させることに努めてきた。今では単にSSEと呼ばれる拡張命令セットが当初はInternet Streaming SIMD Extensionsと呼ばれていたこと、Pentium 4のマイクロアーキテクチャがNetBurstマイクロアーキテクチャという名称であるのは、当時のキラーアプリケーションであった「インターネット」の加速に腐心した現われでもある。もちろん逆に、Intelがインターネットブームに便乗した側面も大いにあっただろうが、ある種の相乗効果がそこにはあったハズだ。
しかし、一般のユーザーにとって「最初のインターネットOS」であるWindows 95が登場してから10年、最初のInternet Streaming SIMD Exetensions搭載プロセッサであるPentium III(Katmai)が登場してすでに6年を迎え、キラーアプリケーションとしてのインターネットは息切れしつつあるのに、それに代わる「何か」は見つからない。
NetBurstマイクロアーキテクチャは、P6マイクロアーキテクチャからの乗り換えにはアピールしたかもしれないが、現在のデスクトップPCのように上から下まですべてNetBurstになってしまえば、差別化のポイントにはならない。
ひるがえって、今回のIDFにおける最大のトピックであるデュアルコア/マルチコアだが、単にこれだけでは一般のユーザーにはどうにもアピールが難しい。プロセッサのコアが2つあることで何が良くなるのか、ということをうまく訴求できなければ、相変わらず日本ではCeleronが売れ続けるだろう。
この点でうまく行っているのはMobility Group(旧Mobile Platform Group)だ。彼らは負荷に応じて動作クロックと動作電圧をダイナミックに切り替えるEnhanced Intel SpeedStep Technology(EIST、拡張版Intel SpeedStepテクノロジ)の有無によるバッテリ駆動時間の違いと、Centrinoモバイルテクノロジのブランディング(Celeronプロセッサにはこのブランドを与えない)で、高価な方のプロセッサ(Pentium M)を売り込むのに成功した。EISTが、処理性能(狭義の性能)を上げるための技術でないことも、次世代のキラーアプリケーションをまだ模索している現状にマッチしていると筆者は思っている。
それはともかくこの結果、ノートPCの市場では、デスクトップほどCeleron化が進まず、プロセッサの平均売価(ASP)の落ち込みは食い止められているようだ。要するにMobility GroupにとってEISTは「銭(ゼニ)になる技術」だったわけである。先日のIntelの機構改革で、Desktop Platform Groupが大幅な組織変更を受けることになったのは、結局これが理由なのではないかと筆者は思っている。どんな組織であれ、うまく行っているところには触らないものであるからだ。
●Pentium 4 Extreme Editionは差別化に成功しているか
もちろん旧Desktop Platform Groupが何もしなかったとは思っていない。その1つの試みがExtreme Editionの投入だ。AMDのAthlon 64 FXへの対抗的な意味合いが強く感じられるPentium 4 Extreme Editionは、ハイエンドのニッチ向けのプロセッサ。Pentium MとCeleron Mの関係に比べて、数量的にはかなり小さいのだが、粗利益率は高い。
最初に投入されたPentium 4 Extreme Editionは、通常版のPentium 4が搭載しないL3キャッシュを搭載することで性能を強化したものだった(実際にはサーバー向けプロセッサの転用なわけだが)。Pentium 4とPentium 4 Extreme Editionの両方が90nmプロセスになった現時点では、キャッシュ回りの仕様は同じになり、FSBクロックが差別化のポイント(Pentium 4の800MHzに対しPentium 4 Extreme Editionは1,066MHz)となっている。
次のデュアルコア世代では、Pentium 4改めPentium Dプロセッサ(Smithfield)と、Pentium Extreme Edition(Smithfield XE)の違いはHypter-Threading(HT)の有無になり、キャッシュサイズやFSBクロックは同じ(800MHz)となっている。
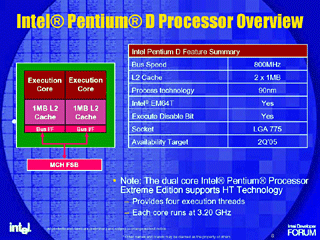 |
| 図1:それぞれのコアの最大動作クロックは3.20GHzとされており、現状(3.80GHz)からは後退してしまう |
つまり、通常のPentium 4/DプロセッサとExtreme Editionの違いは、世代によって異なっており、わかりにくい印象がある。Extreme Editionの顧客は主にマニア/エンスージャストだから、それは問題にならない、ということなのだろう。
ただ、Extreme Editionは高価なプロセッサである。現在の価格で比べて、ハイエンドのPentium 4プロセッサに対し300ドル~400ドルの違いがある。HTは、300ドル~400ドルの違いに値する技術なのだろうか。
原価を考えた場合、Pentium DもPentium Extreme Editionも大差はない。機能要素としてはHTを可能にするアーキテクチャステート(論理プロセッサを具現化するレジスタ等のリソース)の有無と、APICの数が異なるが、ほぼ確実にダイは同じもののハズだ(図2)。これまでNorthwoodコアのPentium 4プロセッサにおいて、HTのあるプロセッサとないプロセッサがあったが、動作クロックによる違いはともかく、HTの有無で価格が変わる(HTによる価格プレミア)とは思えなかった。
そういう意味において、これまでHTはIntelにとって「銭になる技術」でなかったのだが、デュアルコアになったとたん、金のなる木に変わってしまうのだろうか。筆者は、HTの有無は300ドル~400ドルと想定されるPentium DとPentium Extreme Editionの価格差に見合った差異か、という趣旨の質問をプレスブリーフィングでパット・ゲルシンガー副社長にぶつけてみたが、「僕が乗っているBMW5シリーズとM5では倍ぐらい販売価格が違うけれど、原価まで倍違うと思うかい」と切り返されてしまった。要するにExtreme Editionというのは、そういう「違いの分かる人」向けのラグジャリーでコージャスなプロセッサなのである(筆者のようにどうしても価格性能比を考えてしまう貧乏性のユーザー向きではない)。
●デュアルコア+HTの有効性
それはともかく、今回のIDFにおけるIntelの説明によると、デュアルコア化でHTの効果がそれなりに上がる場合があるようだ。現在のシングルコアプロセッサにおいて、HTの有無がそれほど性能向上に寄与しているとは思えない。特に、ベンチマークテストの数字で、HTの効用を納得させるのはかなり難しい(体感的には実感できる局面が確かにあるのだが)。
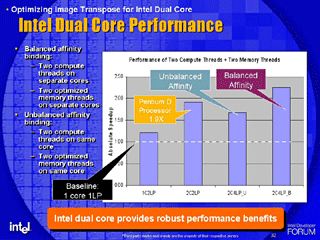 |
| 図3:デュアルコアプロセッサのピーク性能予測。ソフトウェアの最適化(スレッドの配分)によっても性能は大きく変わるようだ。しかし真の問題はこれが3.0GHzに均しての比較であることで、現状のPentium 4 570J(3.80GH)と、今後登場する3.20GHz動作のPentium Dプロセッサの性能比較ではない点にある |
図3はデュアルコアプロセッサの性能とHTの関係を、1C1LP(1コア、1論理プロセッサ、HTなしのPentium 4プロセッサ)を1として、1C2LP(1コア、2論理プロセッサ、HTありのPentium 4プロセッサ)、2C2LP(2コア、2論理プロセッサ、Pentium D)、2C4LP(2コア、4論理プロセッサ、Pentium Extreme Edition)のピーク性能を相対的に示したものだ。
2C4LPのグラフがUnbalanced AffinityとBalanced Affinityの2つあるのは、同時実行する4つのスレッドをうまくバランスさせた場合(2つの計算スレッドと2つのメモリスレッドを、それぞれ別のコアに振り分けた場合)と、アンバランスに振り分けた場合(2つの計算スレッドを1つのコアに、2つのメモリスレッドをもう1つのコアに、それぞれ振り分けた場合)を意味している。この図3そのものは、ソフトウェアの最適化をとりあげたセッションのもので、ソフトウェア最適化の重要性をISVに説くことを目的としたものだが、ソフトウェアの最適化ができれば、それなりの効果が期待できることが分かる。
Extreme Editionを購入するような「違いの分かる」(しかも経済力もある)ユーザーにとって、最も大きく購入動向を左右するのが性能であることは間違いない。それは特定のキラーアプリケーションに対する性能といった相対的な尺度ではなく、まさに性能そのものに対する絶対的な信奉が、彼らを支えているのだろう。普段走る道路の制限速度が50km/hであることが、M5を買うことの障害にはならない、ということに似ているかもしれない。このセグメントに対しては、今も性能こそが差別化のポントとなるのは確かだ。
しかしExtreme Editionの価格が法外だと感じる多くの一般的なユーザーにとって、もはや性能は購入動向を左右する差別化ポイントではない。性能による差別化は、キラーアプリケーションに対して、プロセッサの性能が下回っている時は、一般的なユーザーにもうまく働くのだが、次の「何か」を探している状況ではうまく働かない。現状のPentium 4とCeleronのような、キャッシュ容量の違いを用いた性能による差別化がうまく働かなくなってしまったのはこうしたことが原因だ。次の「何か」を見つけるか、モバイルのEISTに匹敵する「銭になる技術」を見つけるか、デスクトップの復権にはそのどちらかが必要だと思うが、どちらも容易なことではない。
●デュアルコアCPUとチップセットの非互換性
今回のコラムは以上なのだが、新しいCPUとチップセットの互換性について、触れておきたい。
2005年第2四半期にリリースされるデュアルコアのプロセッサ(Smithfield)と同時に、955X(Glennwood)、945P/G(Lakeport)の両チップセットがリリースされる。これらのチップセットには、サポートするメモリクロックの引き上げ(DDR2-667対応)、メモリ容量の増大(最大8GB)、RAID5および10のサポート、ブリッジを用いることによるSLIのサポートといった新機能が含まれる。
が、Pentium Dプロセッサ/PentiumプロセッサExtreme Editionにとって、何にもましてこのチップセットが重要なのは、同じLGA775ソケットを用いながら、既存の925X/915G/Pチップセットと互換性がないからだ。925Xチップセットや915G/Pチップセットベースのマザーボードにデュアルコアプロセッサをインストールしてもブートしない。ただし、電圧レギュレーターがシャットダウンされるため、プロセッサが損傷したり、マザーボードから煙が出る、といった障害は発生しないという。
逆に955Xおよび945P/Gチップセットを用いたマザーボードは、現在販売されているLGA775ソケットのPentium 4プロセッサと互換性を持つ。Smithfieldがリリースされても、Celeronプロセッサまでデュアルコアになるとは考えられないこと、OEMは同一プラットフォームでBTOによるプロセッサの変更を望むと考えられることなどがその理由だろう。
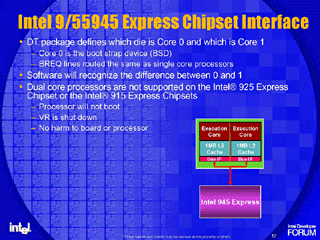 |
| 図4:新しいチップセットの非互換性について触れたスライド。表題の表記に誤植が残っているなど生々しい。Smithfieldでは常に同じコアからブートすることも書かれている |
□Intelのホームページ(英文)
http://www.intel.com/
□IDFのホームページ(英文)
http://www.intel.com/idf/us/spring2005/systems/
□関連記事
【3月3日】【元麻布】ムーアの法則はまだ必要とされているのか
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/2005/0303/hot357.htm
(2005年3月4日)
[Reported by 元麻布春男]
【PC Watchホームページ】
PC Watch編集部 pc-watch-info@impress.co.jp ご質問に対して、個別にご回答はいたしません
Copyright (c) 2005 Impress Corporation, an Impress Group company. All rights reserved.