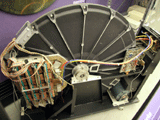|
カリフォルニア州マウンテンビューにあるSGI跡地。現在、ここはボストンから移転してきたComputer History Museumへと模様替えされている。アナログコンピュータからマイクロプロセッサまでの歴史はもちろん、そろばんや電卓、計算尺、あるいはコンピュータゲームや小型ロボットといったものまで、電子計算機によってもたらされた、さまざまなテクノロジーイノベーションの歴史を見ることが可能だ。
●計算機の今・昔
コンピュータの歴史に関しては、インターネット上、書籍を問わず、多くの資料がある。ここではまず、そうした過去のテクノロジーを写真で追いながら、現在のコンピュータとの違いに驚いてみるのもいいかもしれない。
 |
 |
 |
| ご存知、そろばん。最も原始的な計算機として展示されている |
こちらはさまざまなタイプの計算尺。異なるピッチのメモリを合わせていくことで、簡単に計算結果を得られる。僕らの年代までは計算尺に触れることもあったのだが、今はもうコンピュータの時代。初めて見るという人もいるかも? |
第2次世界大戦中に開発された真空管を用いたコンピュータ「ENIAC」。爆撃時の着弾計算にも使おうとしたそうだが、'46年になっても完成することが出来なかったとか。18,000本の真空管と1,500個のリレー、7万個の抵抗と1万個のコンデンサで作られている。ENIACは現在のようなプログラミング可能なノイマン型コンピュータではなく、問題解決のアルゴリズムを変更するためには、配線をやり直す必要があった。毎秒35,000回の加算を行なう性能がある。開発コストは48万7千ドル |
 |
 |
| 同じく第2次世界大戦でドイツが使った暗号装置「ENIGMA」。その原型はオランダで'19年に生まれたそうだが、それを改良する形で'35年にドイツが完成させた。手前のプラグの接続パターンと3つの異なるローターの組み合わせにより、膨大な暗号のバリエーションが生まれるという |
現在はごくごく特殊な用途でしか使われていないというアナログコンピュータ。写真はGeneral Precision Computer製。電気的な入力に対して、ダイヤルでパラメータを与えることで、アナログの電気出力として結果を出す。センサー、算術モジュール、I/Oユニット、それにオプショナルアンプなどを用い、測定範囲を拡張したり、異なるアルゴリズムに組み替えるといった事が可能だったそうだ。'50年製 |
 |
 |
| おびただしい数の真空管が並ぶのはElectrodataの「E-205」(左)とThe Rand Corporationの「JOHNNIAC」。このころになると商用システムとして確立され、軍用ではなくビジネスや科学の現場で使われるようになった。E-205の場合、システム規模の最も大きなバージョンを動かすには16人のオペレータが必要だった |
 |
 |
 |
| 米空軍とIBMが'54年に共同開発した防空システム「Sage」。非常に巨大なシステムのため、ごく一部の展示となっている。毎秒8万回の加算を行なう能力がある。1システムあたりのコストは80~120億ドル。27個の筐体に分かれたSageは2つの異なるコンピュータで構成され、片方が常に起動したままバックアップするフェイルセーフ機能を備え、システムの稼働率は99.6%を達成した。メモリ容量は69,632ワード(1ワード33bit)のコアメモリを採用。グラフィックディスプレイやライトガンによるユーザーインターフェイス、モデムによる導入サイト間の電話回線を用いた通信機能を備えていた。総重量は300tにも達する |
NEC製の最も初期のトランジスタを用いたコンピュータ「NEAC 2203」。'60年に開発された。このモデルはカナをサポートしており、日本国内のみながら'79年までに30台のシステムを販売したという。演算速度は毎秒3,300回の加算。価格は約2,800万円だった |
'60年前後に開発されたさまざまなコンピュータのロジックボード。現在のコンピュータからすると隔世の感があるが、一方、これまで写真で紹介した真空管ベースのシステムと比べるとトランジスタ化で劇的な小型化が図られているのがわかるだろう |
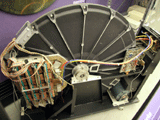 |
 |
 |
| 初期のHDD。ディスクの直径は表記されていなかったが、ざっと見たところ1.2m程度か。容量は100MB |
各種磁気メディア。筆者が通っていた学校でも、16インチ程度のリムーバブルディスクパックを使っていたことがあるが、この分野の小型化、高密度化も実にすさまじい。初期のリムーバブルディスクパックは、円盤をネジ止めしてから装置から空気を抜いて使用したものだ。ここまで来ると、使ったことのあるモノが出てくるはず |
'67年に開発された光学式の外部記憶装置「IBM 1360」。世界ではじめてTerabitクラスの記憶容量を実現した。写真はその露光ユニット部。電子ビームで460万bitを小さなプラスティックフィルムカードに書き込む。32枚のプラスティックカードをストレージボックスにセットでき、機械的な仕組みでカードを自動交換する機能があるそうだ。ただしライトワンスメディアのため書き換えは行なえない。7台が製造され、すべて米政府が購入したとのこと |
 |
 |
 |
| メインフレームの世界を知るものなら、誰でも知っている、'65年にIBMが開発した「S/360」。非常に複雑なOS/360を採用し、PL/Iという高級言語がサポートされていた。別途、FORTRAN、COBOL、RPGといった高級言語もサポートしている。現在で言うIBM互換汎用機の元祖とも言うべきコンピュータシステム |
'60年代に、後のPC時代の礎を築いたのがDigital Equipment Corporation(DEC)。その最初の製品が'61年の18bitミニコンピュータ(これでも当時は十分に“ミニ”)「PDP-1」。毎秒10万回の加算を実行できる。DECが生まれた'57年はマサチューセッツ工科大学(MIT)にプログラミングコースが開講した年だそうだが、DECはそのMITにPDP-1を寄贈。コンピュータプログラミングに熱中する学生(元祖ハッカー)を生み出し、その後のソフトウェア開発の発展とも深く関わっていくことになる。価格も12万ドルと破格に安かった。さらに'65年発売の12bitミニコン「PDP-8」を18,000ドルで売り出すと世界中で大ヒット。IBMに次ぐ世界第2位のコンピュータメーカーの地位を確実なものにした。写真にはグラフィックディスプレイやライトペンも見られる |
DECのミニコンはインタラクティブなプログラミング環境を備えていたため、教育機関や研究機関でさまざまなプログラムが開発された。その中にはAT&Tのベル研究所が「PDP-7」上に実装したUNIXもある。そのUNIXを記述するために作られたのがC言語で、'70年の16bitミニコン「PDP-11」上に実装された。写真はPDP-11のプロセッサモジュール。動作速度は1.25MHzとのこと |
 |
 |
| DECの偉大な仕事として、もう1つ忘れてはならないの、32bitの仮想メモリをサポートしたPDPシリーズの次世代機「VAX-11」だろう。写真は'78年発売の初代モデル「VAX-11/780」。この製品も大ヒットし、後にMicroVAXと呼ばれるマイクロプロセッサにまでなっている。この上で動作したのがVMS(Virtual Memory System)というOSだ。VMSの開発プロジェクトリーダを担当したのは「闘うプログラマー」でも有名なデビッド・カトラー。カトラーはその後、マイクロソフトに移籍してVMSの経験を生かした新しいOS、Windows NT 3.1を開発する。Windows XPはその後継バージョンだ |
ユニークなデザインで知られるクレイリサーチのスーパーコンピュータ「CRAY-1」。'76年の製品だ。まるでベンチのように見えるが、実際にそこに女性が腰掛けた写真がこのころ、雑誌に良く掲載された。このC字を描く放射状の筐体は、放熱を考えたものだと当時、読んだ記憶がある。猛烈な計算速度を実現するには相応の電力も必要で、消費電力は0.5MW(!)にも達したからだ。大量のデータ処理が中心だった当時のメインフレームに比べると演算速度は圧倒的で整数演算でメインフレーム最新機の25倍程度と博物館の資料には記載されている。理論スループットは150MIPS、80MFLOPS |
 |
 |
| こちらはCRAY-1の次の次に作られた「CRAY-2」。不活性炭化フッ素による液浸冷却方式により、熱を効率的に逃がすことで小型化を図っているそうで、写真にあるように液冷のためのユニットが別途用意されている。演算用プロセッサを4個、制御用プロセッサを1個搭載し、CRAY-1の6~12倍の性能を引き出した |
 |
 |
| '87年に発売された「CRAY-3」のプロセッサモジュール。GaAs(ガリウム砒素)をプロセッサ用の素子として利用。69枚の電子回路層と4枚のガリウム砒素層が積層化されており、レンガのような形になっている。CRAY-2のさらに5~10倍の性能を発揮した。ガリウム砒素はシリコンよりも高速かつ消費電力が低いという特長がある反面、高価で加工しにくい。ちなみにこのモジュールの消費電力は9万W。かなりの省電力化が図られていることがわかる。15GFLOPSで3千万ドルというシステム価格が付けられていた。ちなみにENIACでは67年かかる演算を、CRAY-3はわずかに1秒でこなしてしまうという |
こちらはマイクロプロセッサと高密度のDRAMなど。Intel製プロセッサはもちろん、ZiLOGのZ80、Motorolaの68000、DECのAlpha、SunのSPARC、MIPSのMIPSプロセッサなど懐かしいプロセッサが並ぶ。やっと今で言う“プロセッサ”のサイズになってきた |
●縮小と高速化の歴史
こうして振り返って見ると、高性能化と小型化が、いかにすさまじいペースで進んできたかがよくわかるだろう。軍用のシステムから企業向けのメインフレームへ、そしてミニコン、そしてワークステーションやパーソナルコンピュータへと、ユーザーに近付くにつれてプログラミングが一般的になり、一般消費者からはるか遠くにあったコンピュータが、どんどん近くなってくる。
ソフトウェアの面を見ると、特に業務という呪縛にとらわれない学生が、手軽にインタラクティブなプログラミングを行なえるようになったPDPミニコンの時代は、現在のソフトウェア文化を生み出す人材を育てた点で興味深い。より多くの人間が、コンピュータとプログラミングに触れる事で触発され、新しい何かを作り出していった時代だ。
現在のPC業界が、やや停滞気味に感じるのも、もしかするとコンピュータのプログラミングに直接触れるユーザーの割合が減ったからなのかな、と思ったりもする。現在のソフトウェア開発は、ハードウェアからかなり離れたところで行なわれており、コンピュータを直接動かすプログラムを作るプログラマは少なくなっている。
既存の開発フレームワークの中だけしか知らない開発者が多くなっているわけで、自由な発想が阻害されている面もあるのかもしれない。とはいえ、モノを作り出す産業としては、開発の効率化を図る上でそれらが重要な事なのだから、悪いとは言えないのだが。
ハードウェアに目を向けると、猛烈な小型化、高集積化、高集積化に伴うシステムの複雑化などが進んできた事がわかる。今の学生が、昔のミニコンを見て、ミニコンピュータなどという名前を想像することはないだろう。
博物館の展示は、さらにワークステーションからパーソナルコンピュータ、そしてポータブルコンピュータ、ラップトップ、ノートPCへとつながっていく。現在、我々が持ち歩いて使うことができているコンピュータ。その小型化の歴史はまだまだ続く。コンピュータが“モビリティ”を求め始めるのは'80年代からだ。
□米Computer History Museumのホームページ(英文)
http://www.computerhistory.org/
□関連記事
【2004年7月16日】「テレビゲームとデジタル科学展」7月17日から開催
~ENIACからゲームボーイまで一斉に展示
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/2004/0716/tvgame.htm
【2001年3月13日】写真で見る歴史的なコンピュータ
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/article/20010313/ipsj.htm
□バックナンバー
(2005年3月2日)
[Text by 本田雅一]
PC Watch編集部
pc-watch-info@impress.co.jp
個別にご回答することはいたしかねます。
Copyright (c) 2005 Impress Corporation All rights reserved.
|