 |


■笠原一輝のユビキタス情報局■RCAやスマートアンテナは何をもたらすのか |
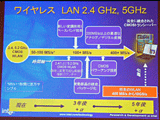 |
| IntelのCMOS実装ロードマップ |
一昨日、Intelは都内のホテルにおいて記者説明会を開催し、同社が現在取り組んでいる無線技術のうち、CMOS無線技術、RCA(Reconfigurable Communication Architecture、再構成可能な通信技術)、スマートアンテナと呼ばれる3つの技術に関する説明会を開催した。
その概要に関しては、別記事を参照して頂きたいが、ここではIntelが(そしてIntel以外の会社も)、なぜこうした技術を開発しているのか、その背景を探っていきたい。
●現在の無線データ通信が抱えるいくつかの問題点
現在、あらゆるデジタル機器に利用されている無線によるデータ通信は、いくつかの問題を抱えている。特に、ポータブル機器(携帯電話やノートPC)などに話しを限れば、以下の3つが問題になる。
(1) 複数の無線技術をシームレスに切り替えるのが難しいこと
(2) 各国の法令に合わせて技術ローカライズしていく必要があること
(3) 複数の規格が存在するため、それに対応する必要があること
例えば、現在のノートPCでもAir H"を内蔵している製品があるが、こうした製品では有線LAN、無線LAN、PHSの各アクセス方法を切り替えてデータ通信が可能だ。しかし、現在の技術では、これらの無線を切り替えるたびに、IPアドレスは割り当て直しとなり、それまで行なっていたデータ通信は一度とぎれてしまう。
例えば、サーバーからストリーミング配信で動画の再生を行なっていた場合、アクセス方法を切り替えると、再度サーバーに接続し直してやる必要がある。こうした問題に関しては、現在各社が研究しているMobile IPで、ある程度は解決することができるようになる。
●各国の法令により利用できる帯域が異なるという現実
そして2番目の問題だが、無線の利用方法は、基本的に各国の政府が利用割り当てを行なっており、その割り当ては各国の事情により異なっている。例えば、ノートPCユーザーに最も関係する話としては、5GHz帯の無線LANに関する無線の割り当てがある。
この話は以前の記事でも触れたが、現在販売されているIEEE 802.11aに準拠した無線LANのシステムは、同じ11aの製品であっても、日本向けの11a機器を米国で利用することはできない。なぜ、こういうことが起きているかと言えば、日本の電波法が規定する無線LANの5GHzの帯域と、米国のFCCが規定する無線LANの帯域が微妙に異なっているからだ。
以下の図は、日本と米国における11a機器向けの帯域を示したものだが、日本では5.16GHzから20MHz刻みで4チャネル確保されているのに対して、米国では5.17GHzから20MHz刻みで8チャネルとなっており、10MHzほど利用できる帯域がずれているのだ。
かつ、5.25GHz~5.35GHzは気象レーダーに割り当てられており、この周波数は利用できない。この結果、何が起きているかと言えば、日本の11a機器が利用できるチャネルは34、38、42、46なのに対して、米国の11a機器は36、40、44、48、52、56、60、64となり、チャネルが微妙にずれているので、相互に通信できないのだ。
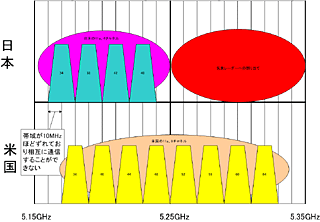 |
| 日本の11aと米国の11aの違い |
ただ、実際には日本の11aでも、米国の11aでも同じ論理層と物理層のチップを利用しているので、実際のところ違いはファームウェアだけであり、例えばファームウェアを書き換えることで、米国で発売されている11aの機器を、日本の11aの機器とすることは技術的には可能だ。
さらに言うならば、ソフトウェアで米国と日本を切り替える、という設計にすることも技術的には不可能ではないようだ。
しかし、日本で無線機器を発売するためにはテレックが行なっている認定を通す必要があり、米国の11aのチャネルに接続できるように設計することはできないし、仮にそれで認定を通ったとしても、どこかに(日本では)違法な米国の11aアクセスポイントが立っていたとして、ユーザーがそれを知らずに接続してしまった場合でも電波法違反となってしまう。
このため、ベンダは日本でも、米国でも利用できる11aのPCカードや、米国でも利用できる11aを内蔵したノートPCというものを販売することはできないのだ。
●複数の無線規格が並立する現状ではそれに対応していく必要がある
また、複数の無線の規格が存在しており、かつそれが並立しているという現状もある。
例えば、次世代携帯電話はNTTドコモとJ-PHONEが導入しているW-CDMAと、auが導入しているCDMA2000がある。W-CDMAの電話機で、CDMA2000のネットワークに接続することはできないし、その逆も不可だ。
また、日本で従来導入されていたPDCのネットワークにも当然接続することはできない。3Gは一昨年から導入が始まったばかりで、PDCに比べるとエリアのカバー率は低く、PDCでは接続できるのに、3Gでは接続できないというところが続出してくる。
となると、当然考えたくなるのが、3GとPDCのデュアル端末だが、現時点では3GとPDCのデュアルを行なうためには、それぞれ別のチップを用意する必要があり、コストが高くなり、端末のサイズも大きくなってしまう。
実際、筆者はJ-PHONEのW-CDMAとGSMのデュアル端末、NTTドコモのW-CDMAとPDCのデュアル端末を所有しているが、いずれも一般的な携帯電話よりはやや大きめで重くなってしまっている。
今後は、携帯電話であっても無線LANをサポートしたり、逆にPCに携帯電話のチップを内蔵し、データ通信を行なうなどの製品が続々登場することになると言われている。例えば、IEEE 802.11委員会の議長であるスチュアート・ケリー氏(Philips Semiconductors divisionのワイヤレスビジネス開発担当取締役)は、「現在いくつかの携帯機器ベンダが無線LANチップを内蔵した携帯電話を開発している」と述べるなど、携帯電話ベンダが無線LAN内蔵の携帯電話を開発していることは業界関係者であれば常識となりつつあり、複数の無線に対応できる半導体のニーズは加速度的に高まっていく可能性が高い。
●RCAを利用することですべての無線技術に対応した携帯電話やノートPCが実現可能に
だが、各国の法令に対応し、複数の無線の規格に対応するデバイスを作る上でいくつかの障害もある。先ほど述べたように、無線機器は、利用する国でそれぞれ認定を取る必要があるが、11aの例のように各国で法令が異なっている場合があり、それに対してどのように対処していくのかということが1つ。もう1つは、複数の無線規格に対応するため複数のチップを搭載することになるが、チップ数に合わせて増大する消費電力に何らかの解決策を探さなければいけないということだ。
それらを解決する技術の1つがRCAとスマートアンテナだ。例えば、Intelがこれからリリースする11aと11bのデュアルバンドをサポートするコードネーム:Calexico(Intel Pro/Wireless 2100A)は、MAC+11aのベースバンド、11bのベースバンド、11aの物理層、11bの物理層という4つのチップから構成されている。
現在の11bのみの無線LANモジュールは、多くがMAC+11bベースバンドと11b物理層という2つのチップから構成されていることを考えると、チップ数も多く、その分消費電力も増大する(つまりは、熱量も増える)。
今年の末までに登場する11a/b/gをサポートしたCalexico2では、2チップ構成になり徐々にチップは減っていく傾向にあるが、複数の規格をサポートしようとするとCalexicoのようにチップが増えてしまう。また、将来、無線LANとW-CDMAの両方をPCに搭載しようということになると、無線LANの物理層、W-CDMAの物理層はそれぞれ別のチップになりチップ数は増えてしまう。
そこで、将来はDSPのような汎用チップを利用し、ソフトウェアなどを組み合わせることで、複数の無線技術に対応させようというのがRCAだ。極端な話、RCAが現実になれば、ベースバンドと物理層の2つのチップがあれば、すべての無線技術に対応させることも不可能ではなくなる。
実際、Intelの説明会においてケビン・カーン氏(Intelフェロー)は「最終的な製品でどうなるかはまだ未知数だが、我々の予測では3つの無線チップを搭載する場合に比べれば、RCAは消費電力で有利だろう」と説明しており、RCAが実現されれば、W-CDMA、PDC、無線LAN、UWB……のすべてに対応した携帯電話や、ノートPCなどを実現することも不可能ではなくなる。つまり、状況に応じて最適な無線技術で、常に通信するという夢のようなストーリーが現実となるわけだ。
●認定の問題は徐々にクリアにしていく
もう1つの各国の法令に対応してという問題も、RCAにより解決が可能になる可能性がある。「将来的にはRCAを利用することで、別の国に移動した時にはそれを認識して、自動でその国の法令に準拠した無線に切り替えるなども可能になる」(カーン氏)との通り、それも技術的に乗り越えられることが可能になる。
ただ、実際には“認定”という法令上の壁は依然として存在しており、たとえRCAにより各国の切り替えができるようになっても、そもそも切り替えできる装置が“認定”をパスできるのかという問題をクリアする必要がある。
「RCAのような柔軟なシステムの導入には、規制当局は不安に感じるかもしれない」とカーン氏自身もその問題は懸念しているようだ。
ただ、すでに米国のFCCとは話しを進めているようで「FCCとRCAに対してどのように対処していくべきか、対話している。現実的に考えれば、規制当局との対話には時間がかかると思うが、最初はわずかな柔軟性を認定してもらい、徐々にフルの柔軟性を認めてもらえるような方向性を探っていきたい」(カーン氏)と、段階的にRCAのフレキシビリティを高めていくことで、認定の壁を突破していきたいという方向性を探っていくようだ。
●すべては“Radio Free Intel”へとつながる道
Intelが、こうした無線技術を開発し、目指している方向性は明白だと思う。それは、言うまでもなく無線技術のCPUへの統合というビジョンの実現だろう。
以前からIntelは「Radio Free Intel」という、すべてのシリコンに無線技術を統合するというビジョンを明らかにしており、RCAやスマートアンテナなどはその要素技術であると考えることができる。
Intelは今後、無線LANのCMOS化を進めていき、RCA、スマートアンテナなどの開発を待って、最終的にCPUないしはチップセットに無線機能(それは無線LANにとどまらず、3Gや他の無線技術も含まれるだろう)を内蔵させていく、それが長期的なビジョンであると推測される。
ただし、これは数年先とかそういうレベルではないと思う。現在Intelは、Baniasの後継としてDothan、さらにその後継として2004年末にJonah、2005年末にMerom、2006年末にGiloというパイプラインでモバイルプロセッサを開発しているが、おそらく無線技術が搭載されるのは、早くてもGilo以降、現実的にはもっと後になる可能性も高い。
Intelが、この無線技術入りのCPUやチップセットで戦おうとしている相手は、AMDやTransmetaではないと思う。そのライバルは、ノキアなどの携帯電話機ベンダにチップを供給している半導体ベンダだろう。
長い目で見れば、それらのキャリアや携帯電話ベンダが、より大きなLCDを搭載したPCライクなモバイル機器をリリースしてくる可能性が高いことは、以前Centrinoの短期連載でも述べた(逆にPCも小型化していき、携帯電話の大きさに近づいていく)。
仮に、そうなればノートPCとそうしたモバイル機器の差は、ウィンテルであるか、非ウィンテルであるかの差だけになる。
すでに携帯電話の側は、アプリケーションプロセッサの搭載などにより、“無線”だけでなく、コンピューティングパワーを備えつつあるし、それは今後も強化されていくだろう。そうした中で、モバイルにおいてウィンテルが生き残るためには、ウィンテルの側も無線で武装する必要がある。
Intelが開発している無線技術は、この競争が本格化した時のための強力な“弾”であり、Centrinoはその第一歩にすぎないのだ。
□関連記事
【6月9日】インテル、CMOS無線技術などへの取り組みを紹介
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/2003/0609/intel.htm
【5月02日】【笠原】IEEE 802.11g対応製品がこんなに早く立ち上がった本当の理由
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/2003/0502/ubiq3.htm
□Pentium M/Centrino関連リンク集
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/2003/link/centrino.htm
(2003年6月12日)
[Reported by 笠原一輝]
【PC Watchホームページ】
PC Watch編集部 pc-watch-info@impress.co.jp 個別にご回答することはいたしかねます。
Copyright (c) 2003 Impress Corporation All rights reserved.