 |


■森山和道の「ヒトと機械の境界面」■ユビキタス環境実験室「STONEルーム」が目指すもの |
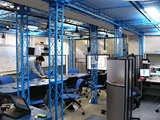 |
| STONEルーム |
東京大学にほど近い本郷三丁目からすぐの場所に、東京大学大学院 情報理工系研究科電子情報学専攻・青山 森川 研究室( http://www.mlab.t.u-tokyo.ac.jp/ )のユビキタス環境実験システムのためのデモルームがある。名前は「STONEルーム」。STONEとは「Service Synthesizer on the Net」の略だ。直訳すれば、サービス合成システムである。
ネットワークに接続されたデバイスがますます世の中に満ちていったとき、すなわちユビキタス時代が到来したとき、どんな新しいサービスを提供することができるか、どんなサービスが必要とされるだろうか。そのためにはどんな技術が必要だろう。青山研究室では「遍在、連携、融合」という3つのキーワードで研究を行なっている。その実証のためのデモルームがSTONEルームであり、STONEはサービス提供のためのミドルウェアである。
マンションの一室である室内に入ると、まずブルーのフレームが目に入る。天井には超音波センサーが取り付けられている。サービス提供のために必要な、ユーザー個人の位置情報を検出するためのものだ。
まずはSTONEルームのインフラと、見せてもらったデモンストレーションを紹介しよう。
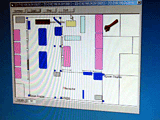 |
 |
| 天井にはユーザー位置検出用の超音波受信機が付けられている(写真右) | |
STONEルームのレイアウト(写真左)。下方にあるNavigatorという赤丸がユーザー位置。ユーザーは超音波発信器を持ち、超音波到達の時間差を使って自分の位置を部屋に検出させる。誤差はプラスマイナス5cm程度。将来は微弱無線や携帯電話、PDAなど常に電波を出しているデバイスを利用した位置検出を行ないたいという。
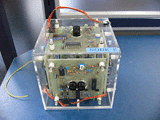 |
超音波位置検出器バージョン2。将来、ユビキタス社会が来るのであれば、いちいち部屋の中全体の位置座標を測るのではなく、適当にDIYショップで買ってきたデバイスを部屋に撒いただけで位置検出ができるような簡便デバイスが必要になる。そういった環境を目指した研究用デバイス。基準ノードは必要だが、その周囲の検出器は新しく決まったノード位置から自分の位置を自動で決めていく。当然、精度は少し悪くなるが、いまのところ15cmくらいのズレで収まっているという。四畳半程度の部屋でならば、十分に使える精度だ。
 |
携帯電話に送られてきた写真を手近なディスプレイで見る。ユーザーはワンクリックするだけで、手近なディスプレイで拡大画像を見ることができる。右手に持っているのが位置情報検出のための超音波発信器。そのデータを元にユーザーが特に意識して命令を出さなくてもSTONEが「手近な位置にあるディスプレイ」がどれか判断して画像を映す。フォーマットもSTONEが自動変換するので気にする必要はない。なお、このデモでは実データは携帯の中にあるのではなく、ネットワークの中にある。
 |
同じくネットワークに繋がったプリンタからファイルを印刷する。写真データはJPEG、印刷するプリンタはPostScriptだが、その変換もSTONEルームが勝手に行なう。ユーザーはファイルフォーマットを意識する必要がない。
 |
スマートバトン。レーザーポインタでテレビを指すと、各人用にカスタマイズされたテレビリモコンがPDAに送られてくる。つまりPDAを用途ごとにカスタマイズされつつも万能リモコン化するアプリケーション。そのあとのチャンネル操作は無線LAN経由で行なう。個々人にカスタマイズされたリモコン環境をPDAに送ることができる。たとえば、子ども向けには有害チャンネルをシャットアウトしたり、老人向けには大きなボタンのインタフェースなどにすることができる。
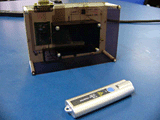 |
太陽電池改造の受光器とレーザーポインタ。レーザーそのものに物理的にPDAのIPアドレスとかポート番号等ユーザー情報がエンコードされている。赤外線と違ってどれを指さしているかユーザーにも明示できるが、受光器にピタッとあてにくいのが難点。
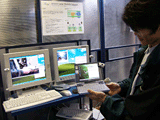 |
セッションレベルのモビリティサポート。たとえば、ビデオチャットをしていたとする。ビデオチャットを継続しながら、そのまま別のPCを持って移動することができる。つまりデバイスに依存した形でサービスを提供するのではなく、ネットワークや端末をシームレスに切り替えることでデバイス透過的に、セッションレベルでユーザーサービスを提供するアプリケーション。モビリティのサポートはエンドホストで行なう。たとえば、携帯電話から固定電話へ(いったん接続を切ることなく)シームレスに通話を継続するといった用途が目標。
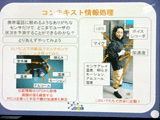 |
ユビキタス環境でのサービスにおいては、ユーザーのコンテキスト推定も重要な技術。携帯電話や秋葉原で売っているような簡単なセンサだけでどの程度ユーザーの行動を推定できるか、センサを身につけ、背中に処理用のPCをしょった状態で渋谷を1日歩かせてみた。もともと博報堂との共同研究で、様々な広告やコンテンツをユーザーのシチュエーションに応じて配信するための基礎研究。ヒマそうな時は暇つぶしコンテンツを、忙しそうなときは仕事コンテンツを配信するほうがコンテンツ提供側としては効率的だ。
 |
 |
実際に身につけていたセンサー。アルコール検知機能なども
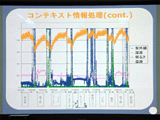 |
実際に取れたデータの一例。紫外線の量が変われば屋外だと分かるし、加速時センサから足を動かさず腕だけを動かしていると食事中だと見当がつく。また書店で立ち読みしているときと駅内で歩いているときとでは、全く違う物理量が取れたそうだ。詳細は現在、解析中
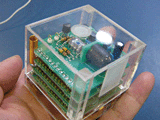 |
 |
室内の湿度や温度など物理的データを取るための汎用センサ・ノード。このセンサーを組み合わせることでセンサーのネットワークを作る。データはノードからノードへと伝送されていく。使用周波数帯は免許のいらない300MHz帯、PICを使い、CPUはMAC制御用とOS用にそれぞれ1つずつ搭載、ボード単位で機能を交換することもできる。PCとはIrDAで通信する。用途はこれから思案中だが、たとえば人体の検知などにも使える。
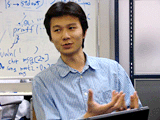 |
| デモと説明をしてくれた川原圭博氏 |
「いま、PC 1つとっても、マイクや出力など色んな機能を持っていますね。それらネットワーク中にある多様な機能を分解して、必要な機能だけを組み合わせれば新しいサービスが実現できるんじゃないか。そういう発想にもとづいているミドルウェアがSTONEです」
デモと説明をしてくれたドクターコースの川原氏は、こう説明してくれた。
【「ネーミング」と「透過性」】
STONEにおけるキーワードが「ネーミング」だ。STONEではネットワークにある全ての機能を、IPアドレス等を使うのではなく、入力と出力だけで記述してやる。たとえば、PCとディスプレイがあるとしよう。これまでの考え方だと、それぞれアドレスを振ることになる。
「STONEではそうじゃなくて、入力タイプ=JPEG、出力タイプ=光とかディスプレイとか、とにかくあいつに対してJPEGを送りつければ表示できるんだ、という『機能に応じた名前付け』をしてやるんです。DNSに足りない部分を補ってやるような感じですね」(川原氏)
STONE上ではデバイスを「どのようなデータを受け付けるか」と「どのようにアウトプットするか」という2種類の機能で分類・認識する。別にIPアドレスがなくなるのではい。ユーザーがアドレスを意識する必要がなくなるのだ。
ネーミングでたとえば何ができるのか。カメラはモノを撮影してMPEG-2に変換するとする。そしてMPEGしか受け付けないディスプレイがあったとする。従来だと、この間にPCが入って仲立ちしてどうこう、という作業が必要になる。
だがSTONEというミドルウェアを使えば、自動的にネットワーク中から画像を変換してくれる機能を、もともとのネットワークの仕組みとして発見してきて、自動的にはさんでくれるのである。仮に変換機能を持つものがなくても、2つの機能を組み合わせることで何とかしてくれる。それによって、従来なら繋がらなかったものを繋がるようにしてくれるといったこともできるという。
また、JPEGを受け付けるディスプレイが何台もあった場合、1台が壊れていたとする。だがユーザーがとにかく画像を出してくれという信号を出しつづけると、他のディスプレイに出力してくれる。つまり障害に対するロバスト性も高くなる。
言い換えれば、ユーザーが、いちいち知らない情報を調べる必要がなくなるのである。「とにかく俺はこれをやりたいんだ」と意志を示すだけでいい。青山研究室ではこれを「透過性」と呼んでいる。ユーザーがサービスを受けるにあたって、デバイスや場所そのほかを意識する必要がなくなり、どこでもいつでも「透過的に」サービスを受けることができるようになるという。
IPアドレスではわかりにくいし、覚えにくい。だからDNSという人が覚えやすいシステムが作られた。だがデバイスの機能やデータの形式などは、まだ人が覚えておく必要がある。STONEならそれすら意識する必要がなくなる。STONEは既存のネットワークの上に覆い被さる「オーバーレイネットワーク」であり、デバイスや場所、プロトコルそのほかを気にせずにネットワークサービスの恩恵を受けるための、縁の下の力持ち的な技術である。その可能性の1つがSTONEだと言えばいいだろうか。
【ユビキタス・サービスはどこから普及するのか?】
 |
| 青山友紀教授。以前はNTTでネットワークの研究を行なっていた |
さて、問題はこれらの技術が、今後どうやって普及していくのか、ということだ。STONEは一見、普通の家庭に入れていくことを目指しているように見える。実際、川原氏らも、たとえば壁紙をあとから買ってきて壁に貼るだけで部屋のモデリングや位置計測ができるような「スマートマテリアル」技術が重要になるという。
だが青山教授は、家庭への導入はコストの面でハードルが高いと見ている。介護のようにやむを得ない場合か、大規模なインフラコストを投資しても、その回収が見込めるような場所、つまりオフィスのようなところから入っていくのかもしれない。
現実的には、初期のアプリにも投資する人はやはりPC好きの人たちだろう。すなわち本誌読者、すなわちあなたならば、どういうモノにならお金を払うか、ということになる。青山教授も「若い彼らに聞くのが一番」と笑う。
 |
| 金子晋丈氏 |
川原氏は「お金を払うか払わないかは使用感があるかどうかだと思います。携帯の場合は使用感がありますよね。だからいかに使用感のあるサービスを考えられるかが課題です。あからさまに便利になる、ないと生きていけないようなものじゃないと。『あればいいな』ではダメでしょうね」という。
同様にデモを見せてくれた金子氏は、現在の社会は「ユーザーにフィードバックされてない情報化社会」だという。どういう意味だろうか。
「いまの段階だと、まだまだだなと思うんです。なんでこんなに不便なんだと思うくらい、現状は不便です。たとえば電車に乗りますね。あ、今日はガス消したかなと思う。でも、もう帰れない。でもガスメーターは最近は電子化されていたりする。でも、それがユーザーに反映されてないんです。各社各様に電子化はしている。なのにそれが結局ユーザーに返ってこないのが現状だと思います。ですからこれからは横の連携が必要になると思います。先ほどの『使用感』という話も横の連携だと思うんですよね。もっと相互に情報がやりとりできるようになって、ユーザーにフィードバックされれば、情報化社会はこういうふうに便利になっていくんだともっと実感されるようになると思うんですよね。今ある情報だけでも、もっと有効活用できるはずです」
 |
| お遊びで作ったという無線LAN経由でコントロールするラジコン。普通に面白い。どこかで商品化して欲しい |
これからは一人一人にカスタマイズされたサービスがいかに実現できるか、たとえばサービスを必要としている人間の置かれている状況を推察して、その人に応じたコンテンツを配信するといった技術が重要になる。だが、そのような社会が来るためには、まだ様々なハードルがある。
取りあえず、色んなモノがインテリジェントになっていくことだけは間違いない。それを取りあえず繋げられるようにすること。それがネットワークの研究室としてはファーストステップだ。現在の目標は「ユビキタス社会実現」だ。だが、研究者は「常に5年くらい先のことを妄想し続ける」ことが重要だ。今年起きることも楽しみだが、5年後はさらに楽しみである。
(2003年6月12日)
[Reported by 森山和道]
【PC Watchホームページ】
PC Watch編集部 pc-watch-info@impress.co.jp 個別にご回答することはいたしかねます。
Copyright (c) 2003 Impress Corporation All rights reserved.