特集
Windowsでストレージの空きが足りなくなったときに試すこと
2017年8月23日 06:00
タブレットやスマートフォンであれば、ストレージの容量が32GB程度であっても、Web閲覧や写真撮影、音楽を聴くといった通常用途でなら大きな障害になることはまずない。しかし、ことPCにいたってはモバイル向けのOSと違って、OS自体のサイズが大きいだけに問題になりやすい。
PC Watchでは、各社の低価格ノートPCを比較したクロスレビュー記事「2017年夏の激安ノートパソコンおすすめを探る」を掲載しているが、ここで紹介した製品にも、eMMC/SSDが32GBしかないモデルが登場しており、空き領域を適切に保ちながら運用していくには多少の工夫が必要だ。
ここでは、このクロスレビューの補足として、低容量ストレージモデルを使用する場合の空き領域の確保方法について、簡単に紹介したい。
初期状態でストレージの空き領域は残りわずか、Windowsの大型アップデートも一苦労
低容量モデルのPCをはじめて起動してみると、機種によってはすでにストレージ容量の半分近くを埋めてしまっている場合もある。上述の記事のなかで登場するASUSの11.6型ノートPC「VivoBook E203NA」はストレージがeMMC 32GBだが、OSやらほかのアプリなどがインストールされている関係で、初期状態では空き容量が14GB程度しかなかった(※試用機のため実際とは容量が異なる場合がある)。これではOfficeアプリなどを入れるだけで、すぐにストレージがいっぱいいっぱいになってしまうだろう。
また、MicrosoftはWindows 10において、Anniversary UpdateやCreators Updateといった大型アップデートを年に2回ほど提供しており、低容量ストレージの場合だと空き領域が足りずにアップデートできなかったり、アップデートできたとしても空き領域が数GB程度まで減っていたりと問題が起きがちである。
実際にVivoBook E203NAでCreators Updateを適用してみると、アップデートはできたものの、空き領域が6GBほどまでに減ってしまっていた。ストレージの空き領域を増やす方法として、これから以下に挙げる方法を試し、十分な容量を確保できるか確認してほしい。
ディスク クリーンアップを実行する
Windowsにはストレージ内の不要なファイルを削除する「ディスク クリーンアップ」を標準で搭載しているので、ストレージの空き容量を増やしたい場合はまずこちらを利用したい。とくにWindows 10の大型アップデートを行なった場合、アップデート前のWindowsが「以前のWindowsのインストール」として残されており、ASUS VivoBook E203NAの場合は、17.9GBもの容量となっていた。
ディスク クリーンアップは、スタートボタンの横にある検索窓から「ディスク クリーンアップ」を検索して、アプリ名が出てきたら選択して実行すればいい。
ディスク クリーンアップが立ち上がると、インターネットの一時ファイルなど削除してもシステムの動作に影響を与えない対象候補が一覧表示される。ただし、このままではWindowsアップデートで使用した以前のバージョンのWindowsファイルが表示されない。以下の画像の下部にある「システム ファイルのクリーンアップ」を選択する必要がある。
「システム ファイルのクリーンアップ」を選択すると、「以前のWindowsのインストール」が見つかるはずだ。注意したいのは、このWindowsファイルを削除した場合、以前のバージョンのOSに戻せなくなる点。最新版のOSにしたあとしばらく使用し、とくに動作で問題が起きていないことを確認できていれば削除してしまってもいいだろう。
なお、このほかに表示されている候補については、数百MB程度なのであれば無理に消す必要はない。というのもインターネットの一時ファイルなど、キャッシュとなっているファイルを消してしまうと、Webページ表示の高速化といった恩恵を受けられなくなる可能性があるからだ。
ディスク クリーンアップでは、各候補にカーソルを合わせると説明が表示されるので、消す必要があるかどうか一度確認してから削除するようにしたい。
クラウド上にローカルドライブのファイルを逃がす
ファイルの整理などをせずにPCを使い続けていると、保存しているファイルの量が増え、ストレージをどんどん圧迫していく。とくにもともとのストレージ容量が少ないPCだと限界の訪れは早いし、デスクトップPCのように容易に拡張ができないノートPCなどでは使用頻度が低かったり、まったく使っていないファイルを外部に逃がして空き領域を確保する必要がある。
USB HDDなどの外部ストレージを使って、複数のドライブで運用する手段もあるが、出先でノートPCを使うさいに外部ストレージに置いたデータが必要な場合もあるだろう。大きなサイズのファイルに頻繁にアクセスしないのであれば、クラウドストレージに配置し、必要なときにダウンロードするという方法を活用したい。
クラウドストレージには「OneDrive」、「Google Drive」、「Dropbox」などがあり、OneDriveなら無料で5GB、Google Driveは無料で15GB、Dropboxは無料で2GB利用可能だ。これらのサービスはWindows用アプリでも提供されているが、アプリではローカルドライブとクラウドの同期させるという方法を採るため、ローカルドライブの容量が削られてしまう。
同期するフォルダは個別に選択して、ローカルドライブの容量を節約できはするが、今回のように少しでもストレージの空き領域を増やしたい場合は、アプリは利用せずWebブラウザを使ってクラウドにアクセスするようにしたい。アプリを使う場合については後述する。
なお、OneDriveは今秋登場予定の大型アップデート“Fall Creators Update”で、オンデマンド機能を実装予定となっており、ユーザーはクラウド上にのみあるファイルを、ローカルドライブにあるかのように扱えるようになる。ローカルドライブにダウンロードしておくか、ダウンロードせずにクラウドに置くかはユーザーが任意に選べる。実装されれば、低容量PCに有益な機能となるだろう。
SDカードや超小型USBメモリを常設ストレージに。OneDriveの同期先にも利用可能
音楽ファイルや写真、動画などといった趣味的なコンテンツはファイル数が増えがちで、ファイルサイズもそれなりに大きい。こういったものまでクラウド上にすべて逃がすのは無理がある。
とはいえ、それらのファイルをつねに手元に置いて、いつでも利用できるようにしたいという人もいるはずだ。USB HDD/SSDを使えば、ストレージの少なさをカバーできるが、ノートPCを持ち運ぶことを考えると使い勝手が悪くなってしまう。そこで、容量はHDDほど多くはないものの、SDカードや超小型のUSBメモリを常設のストレージとして利用してみるのはどうだろうか。
また、OneDriveやGoogle DriveはSDカードやUSBメモリを同期先として選ぶこともできるので、内蔵ドライブの容量を消費せずに保存、バックアップできる。この方法ならストレージの容量が少なくても安心だ。ただし、OS動作中に取り外したり、PC起動時に装着されていなかったりするとアプリの動作に支障を来たすので注意する必要がある。
以下に、OneDriveをSDカード上に配置する手順を紹介しているが、注意点としてOneDriveはファイルシステムがFAT系のストレージ上で使えないことを知っておきたい。そのため、SDカード/USBメモリはNTFS形式でのフォーマットが必要だ(OneDriveがNTFS上でのみの動作に変更か? FAT32/ReFSには配置不可に参照)。
ドキュメント/ピクチャなどの標準フォルダをSDカード/USBメモリに移動
上述したOneDriveの保存先をSDカード/USBメモリに変更する対策と同様に、ドキュメント/ピクチャ/ビデオ/ミュージック/ダウンロード/デスクトップといった、ユーザーフォルダの配下に作られている標準フォルダをメインドライブ以外のドライブに移動させることで空き領域を増やすこともできる。
なかでもドキュメントフォルダは、ユーザーが意識してファイルを置いていなくても、さまざまなアプリがデータの置き場所として使っていることもあり、データ量が増えがちだ。
以下の手順ではSDカードのドライブレターである「Dドライブ」にドキュメントフォルダを移動させている。なお、OneDriveの場所をSDカードに移動させたときと同様に、OS動作中に取り外したり、PC起動時に未装着の状態だと該当フォルダにアクセスできないので注意したい。











![【Amazon.co.jp限定】 伊藤園 磨かれて、澄みきった日本の水 2L 8本 ラベルレス [ ケース ] [ 水 ] [ 軟水 ] [ ペットボトル ] [ 箱買い ] [ ストック ] [ 水分補給 ] 製品画像:2位](https://m.media-amazon.com/images/I/41n0o65dSkL._SL160_.jpg)
![[Amazon限定ブランド]CCL い・ろ・は・すラベルレス 2LPET ×8本 ミネラルウォーター 無味 製品画像:3位](https://m.media-amazon.com/images/I/41h0MHfvhkL._SL160_.jpg)



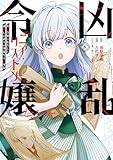































![太郎 DON’T ESCAPE!【特典ペーパー付】【電子書籍】[ mememe ] 製品画像:30位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rakutenkobo-ebooks/cabinet/2467/2000019272467.jpg?_ex=128x128)


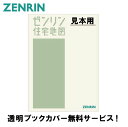


![角川まんが学習シリーズ 日本の歴史 5大特典つき全16巻+別巻5冊セット [ 山本 博文 ] 製品画像:24位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/3680/9784041153680_1_17.jpg?_ex=128x128)
![生きる言葉 (新潮新書) [ 俵 万智 ] 製品画像:23位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/0832/9784106110832_1_22.jpg?_ex=128x128)
![MARQUEE Vol.161 [ マーキー編集部 ] 製品画像:22位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/2520/9784434372520.jpg?_ex=128x128)
![女友達は頼めば意外とヤらせてくれる(4)【電子限定特典付き】【電子書籍】[ ろくろ ] 製品画像:21位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rakutenkobo-ebooks/cabinet/5228/2000019615228.jpg?_ex=128x128)