
![]()
 |
|
鈴木直美の |
|
PC用MDLP対応MDデッキ「MDS-PC3」レビュー~ かなり使える2倍録音「LP2モード」 ~ |
■PCとデジタルでつながるMDLP対応デッキ「MDS-PC3」
「PCに繋がるものは、とりあえず何でも繋げてみたい」と思うユーザーは、結構多いのではないだろうか。筆者もそんな1人で、ソニーの初代PC用(?)MDデッキ「MDS-PC1」の発売時には、速攻で購入した。パソコンと接続できるMDデッキは、ほとんどの機能をPCから制御でき、面倒なタイトル入力もPC上で行なえるというのが大きなポイントで、その後もPC対応のMDデッキやミニコンポが次々に発売された(表1参照)。
| MDデッキ | MDS-S50 | 39,000円 |
|---|---|---|
| MDS-PC3 | 49,000円 | |
| MDS-JE640 | 49,000円 | |
| MDS-JB940 | 69,000円 | |
| MDS-JA333ES | 100,000円 | |
| MD/CDデッキ | MXD-D5C | 79,000円 |
| ミニコンポ | CMT-PX3 | 68,000円 |
| CMT-PX5S,PX5W | 73,000円 | |
| CMT-PX5LTD | 80,000円 | |
| CMT-PX7 | 124,000円 |
現在、ソニーがラインナップしたMDLP対応のMDデッキとミニコンポは、全機種PC接続対応になっており、リンクキット「PCLK-MN10」(15,000円)を使って接続する。ただし、PC接続を前提としたMDS-PC3のみ、このリンクキットが同梱されており、実質的には最もリーズナブルな製品となっている。
サイズ的にも、ほぼハーフハイトの5インチベイサイズなので、スペースの無いデスクトップに置くには、たいへん都合が良い(ドライブベイに収納できればもっと面白かったかもしれないが)。しかし、その反面、他のデッキと違って本体の操作パネルはかなり簡略化されており、デジタル/アナログの入出力も各1系統のみ。コントロールA1端子もサポートされていないので、既存のコンポに組み込むつもりだと使い勝手は悪くなってしまう。もちろんPC無しでも利用できるのだが、二代目のMDS-PC2と同様、あくまでPCと連携させることが主体の製品となっている。
 |
 |
 |
【参考】
□MDLP
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/article/20000824/key132.htm#MDLP
■新しいリンクキットはデジタル出力をサポート
今回の接続キットの大きな変更点は、PCとの接続が従来のシリアルからUSBに変更されたこと。デッキやミニコンポの方も、CDデッキとMDデッキを連携させたり、1つのリモコンでシステムをコントロールする用途に使われていたコントロールA1やA1IIではなく、PC接続専用のPC LINK端子に繋ぐ仕様に改められている。
 |
 |
 |
| 【接続キット】 | ||
シリアルポートが消えいく現在、USB化はもはや避けられない選択であり、より広帯域のUSB接続を利用することによって、新しいリンクキットには光デジタル出力という新たな機能も追加された。このデジタル出力は、汎用のUSBオーディオデバイスなので、WAVE系のオーディオ(ソフトシンセなども含む)やCD-ROMドライブのデジタル再生をそのまま出力することができる。付属ソフトの「M-crew」では、このデジタル出力を使って(別のデジタル出力やアナログ出力でも構わないが)PC上の音楽ファイルやCDをMDに録音する機能をサポート。他の機器と連携できないMDS-PC3の場合には、PCから制御できる唯一のソースデバイスがPC(PCオーディオ、CDなど)ということになる。
機能的には、従来の制御専門の接続キットに、カノープスのDAPortのような製品がドッキングしたもの。しかし、入力がサポートされていない中途半端なところもあり、この辺は少々使い勝手が悪い。PC → MDへの録音は、CDやMedia Playerの再生をデジタル出力するという趣向で、リンクキットのUSBオーディオ出力を「優先するデバイス」に設定することになる。しかし、この設定を行なうと、PCの出力が全てUSBオーディオで出力されてしまうので、サウンドカードの出力が利用できなくなってしまう。
モニタ出力できるのは、MDデッキかリンクキットになるわけだが、デッキは録音スタンバイ状態にしておかないと入力がモニタできないので不便なことこの上ない。リンクキットなら、PC側の音は全てモニタできるのだが、今度はMDの再生出力がモニタできなくなってしまう。
結局は、MDの出力をサウンドカードのLINE INに返しておき、普段はサウンドカードを使用。MDに録音する際に切り換えるというのが一般的な使い方になってしまう(外部にセレクタやミキサなどを用意できれば解決するのだが)。
また、「優先するデバイス」をM-crew上で操作できればまだよいのだが、いちいちコントロールパネルを開いて設定を変更しなければならず、この辺がちょっと面倒なところである。さらに、他の作業のバックグラウンドでファイルを再生すれば、音が途切れたりノイズが入ったりということも起こるし、CD-ROMがCDのデジタル再生に対応していない場合には、USBオーディオ経由では録音できないということも認識しておかなければいけない。
■コントロールソフト「M-Crew」の使い心地
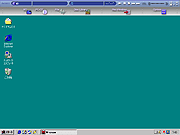 M-crewは、基本的に従来の「MD Editor」を踏襲したもので、デスクトップにコントロールバーを配したデザインや、マウスが無いとお手上げという操作体系もそのまま継承されている。ただ、今回の製品からリンクキットが統一され、同じソフトでMDデッキからミニコンポまで幅広くサポートするようになった。試用した製品は単体のMDデッキなので、操作できるのは「MD」と「PC-CD」、「File」だけになっているが、CD/MDデッキやミニコンポを接続すれば、CDやチューナー、録音予約のタイマーなどのファンクションがパネルに追加される。
M-crewは、基本的に従来の「MD Editor」を踏襲したもので、デスクトップにコントロールバーを配したデザインや、マウスが無いとお手上げという操作体系もそのまま継承されている。ただ、今回の製品からリンクキットが統一され、同じソフトでMDデッキからミニコンポまで幅広くサポートするようになった。試用した製品は単体のMDデッキなので、操作できるのは「MD」と「PC-CD」、「File」だけになっているが、CD/MDデッキやミニコンポを接続すれば、CDやチューナー、録音予約のタイマーなどのファンクションがパネルに追加される。
 このM-crewのバーにある「PC-CD」はPCに搭載されたCD-ROMドライブの制御とCDのライブラリ化を、「File」はMedia Playerを使った再生とオーディオファイルのライブラリ化を行なう。曲名入力は、PCでやったら二度とリモコンではできない――というより、筆者の場合は最初からリモコン入力をやる気になれず、ほとんどこのためだけにMDS-PC1を買ったようなもの。しかし、今となっては、CDDBなどのCDデータベースから曲名を取りこむ機能が提供されていないのが惜しまれる。新しいリンクキットも、残念ながら未対応のままとなっている(VAIO MXのソフトは同種の機能をサポートしている)。ファイルの方は、ID3タグなどに対応しているので、タグ付きのファイルを追加すれば曲名が自動的にライブラリに登録される(暗号化されたWMAファイルのタイトル情報は取得できない)。
このM-crewのバーにある「PC-CD」はPCに搭載されたCD-ROMドライブの制御とCDのライブラリ化を、「File」はMedia Playerを使った再生とオーディオファイルのライブラリ化を行なう。曲名入力は、PCでやったら二度とリモコンではできない――というより、筆者の場合は最初からリモコン入力をやる気になれず、ほとんどこのためだけにMDS-PC1を買ったようなもの。しかし、今となっては、CDDBなどのCDデータベースから曲名を取りこむ機能が提供されていないのが惜しまれる。新しいリンクキットも、残念ながら未対応のままとなっている(VAIO MXのソフトは同種の機能をサポートしている)。ファイルの方は、ID3タグなどに対応しているので、タグ付きのファイルを追加すれば曲名が自動的にライブラリに登録される(暗号化されたWMAファイルのタイトル情報は取得できない)。
 「RecWindow」は、これらソースをMDに録音する機能で、ソース側の曲をMD側にドロップし「REC」ボタンを押すと、MDの録音/停止を繰り返しながらドロップされたソースを順に再生して自動的に録音を完了する。PC上のソースがコピー感覚で録音できるのだが、ファイルやリッピングしたデータをUSB経由で転送するのではなく、あくまでリアルタイム再生したものを録音する仕組みなので、昔ながらの等速コピーとなる。CD/MDデッキやミニコンポでは、2倍速/4倍速コピーが主流となりつつある昨今、この辺にも物足りなさを感じる。ちなみにUSBのデジタル出力は、常に「1回だけデジタルコピー可」として出力されるので、デジタル経由でMDにコピーしたものから、さらにデジタルでコピーすることは出来ない。
「RecWindow」は、これらソースをMDに録音する機能で、ソース側の曲をMD側にドロップし「REC」ボタンを押すと、MDの録音/停止を繰り返しながらドロップされたソースを順に再生して自動的に録音を完了する。PC上のソースがコピー感覚で録音できるのだが、ファイルやリッピングしたデータをUSB経由で転送するのではなく、あくまでリアルタイム再生したものを録音する仕組みなので、昔ながらの等速コピーとなる。CD/MDデッキやミニコンポでは、2倍速/4倍速コピーが主流となりつつある昨今、この辺にも物足りなさを感じる。ちなみにUSBのデジタル出力は、常に「1回だけデジタルコピー可」として出力されるので、デジタル経由でMDにコピーしたものから、さらにデジタルでコピーすることは出来ない。
M-crewからは、MDS-PC3の機能が一通りコントロールできるようになっており、入力の切り換えや入力レベルの設定、録音モード、スマートスペースとオートトラックマーキングの制御、SFエディットやフェードイン/フェードアウトなどの機能も全て操作することができる。
スマートスペースは、設定されたレベル(出荷時は-50dB)以下の部分を無音と認識し、自動的に切り詰める機能。オートトラックマーキングは、音頭を新しいトラックとして自動的にマーキングしていく機能で、これらをシンクロ録音と合わせて使うと、いちいち録音/停止を操作しなくても、曲を適当に再生していくだけでMD上にはきれいに収録される。

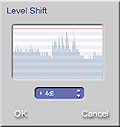 SFエディットというのは、録音済みのトラックの音量を変える機能なのだが、「伸長→レベル変更→再圧縮」という著しく音質が劣化するやり方ではなく、圧縮記録されているデータのスケールファクタ(Scale Factor)を変更するところから、この名が付けられている。
SFエディットというのは、録音済みのトラックの音量を変える機能なのだが、「伸長→レベル変更→再圧縮」という著しく音質が劣化するやり方ではなく、圧縮記録されているデータのスケールファクタ(Scale Factor)を変更するところから、この名が付けられている。
CDなどに使われている無圧縮のPCMデータは、音の振幅を常に16bitのスケールで量子化している。しかし、MP3やATRACでは、より効率よく量子化できるように、振幅の大小に合わせて割り当てるビット数を変え、量子化データとそれを元の振幅に戻すための倍率という形で記録している(PCMが時間軸であるのに対し、周波数軸のデータとして扱うという根本的な違いはある)。この倍率をスケールファクタといい、SFエディットはこれを書き換えて不揃いな録音レベルを後から再調整(±12dB)できるようになっている。
【参考】
□CDDB
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/article/990708/key83.htm#CDDB
□WMA
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/article/991125/key99.htm#WMA
□ID3タグ
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/article/990909/key90.htm#ID3
□ATRAC3
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/article/991119/key98.htm#atrac
■かなり使えるLP2モード
| 【MDS-PC3の主な仕様】 | |
|---|---|
 |
入力端子:光デジタル×1、アナログライン×1 出力端子:光デジタル×1、アナログライン×1、ヘッドホン×1 サイズ(幅×奥行き×高さ):152×255×52mm 付属品:PCリンクキット(PCLK-MN10同等)、カード型ワイヤレスリモコン、光デジタルケーブル、電源アダプタ |
'94年にはより高圧縮のATRAC2が、'96年には4倍密度のMDメディアが発表され、オーディオMDへの採用が期待されていた。昨年になってようやく、ATRAC2はATRAC3に、4倍密度MDはMD DATA2となって登場(※1)。今回、圧縮技術のATRAC3の方がMDに搭載され、LP2/LP4という2つの長時間ステレオ録音モードが実現されたのである。
ビットレートは、2倍モードのLP2で132kbps(LP4は66kbps)と、圧縮率の上では半分を若干下回っている。これは、従来のSPモードとの互換性を保つために、ダミーデータが挿入しているからで、LPモードを再生できない既存のプレーヤーは、これを半分の時間のトラックとして認識。「LP」というタイトルが付いた無音のトラックが再生される。
気になる音質だが、LP2モードは、SPモードよりも若干奥行き感が減りざらついた感じになるものの、ほとんど変わらないレベル(MDっぽさが少し増すといったら良いのだろうか)。ごく普通のヘッドホンを使い、生活に支障の無い音量で聴いている限りでは気にならない範囲なので、SPモードやMP3の音が許容できる多くのユーザーにとっては、全く問題無いレベルだろう。それよりも、80分メディアに160分入るメリットの方がはるかに大きい。
LP4になると、音を出した瞬間に誰でもわかるほど違いが歴然としてくる。これを許容できるかどうかは、録音時間との兼ね合いもあり意見の分かれるところだと思うが、圧縮サウンド特有のステレオ感と耳に付くイヤな感じがぐっと増してくることは確かだ。それでも、賑やか系の音楽はまだ良い方なのだが、曲によっては1台の楽器が分離してしまい(帯域で異なる位置に定位してしまう)、聴くに耐えないものもある。まだ、ソースや再生環境、ユーザーをかなり選ぶレベルといっていいだろう。
なお、SPモードにあったモノラル長時間録音モードは、LPモードではサポートしていない(LP4に関しては、ステレオ信号の左右の相関性を利用して圧縮効率を高めるJoint Stereoを用いているので、モノラルにしても録音時間はあまり伸びないと思う)。また、SFエディットやフェードイン・フェードアウトの機能も、現行機ではSPモードのみの対応で、LPモードでは利用できない。
(※1)ATRAC2は、73kbps/chと36.5kbps/chのビットレートのものがMD DATA向けにライセンスされたそうだが、対応製品に関しては不明。MD DATA2の方は、現在MD DISCAMに採用されている。
【参考】
□MD-DATA
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/article/981203/key57.htm#MD_DATA
□ソニーのホームページ
http://www.sony.co.jp/
□「MDS-PC3」の製品情報
http://www.sony.co.jp/sd/ProductsPark/Models/New/MDS-PC3_J_1/index.html
□Sony Music Network(PC接続対応機器のサイト)
http://www.geton.smoj.sony.co.jp/products/musicnetwork/index.html
□関連記事
【8月31日】ソニー、PCから操作や、デジタル録音できる2/4倍長対応MDデッキ
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/article/20000831/sony.htm
[Reported by 鈴木直美]